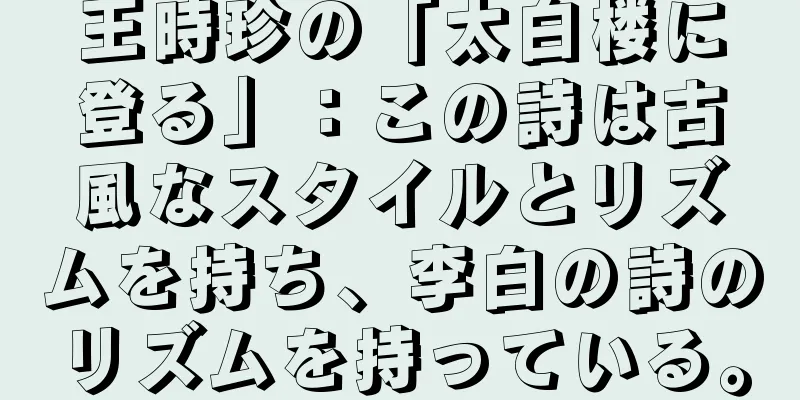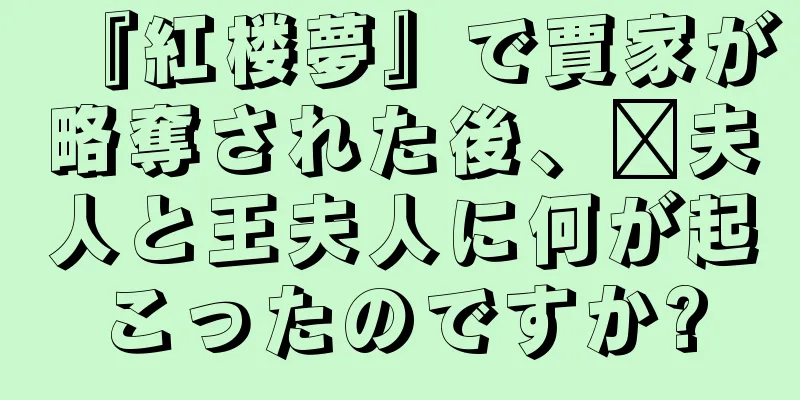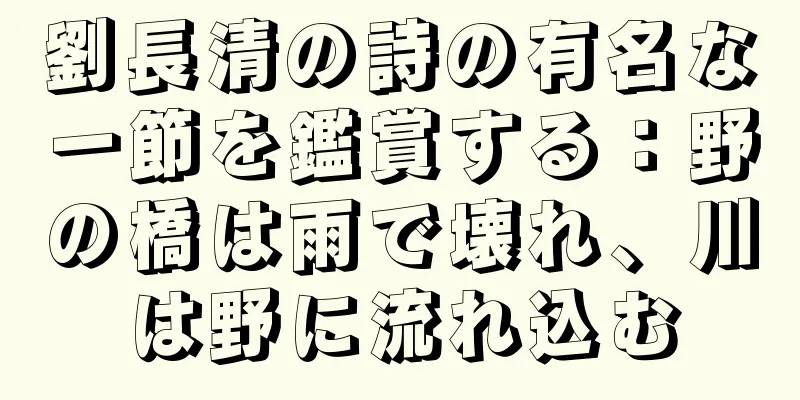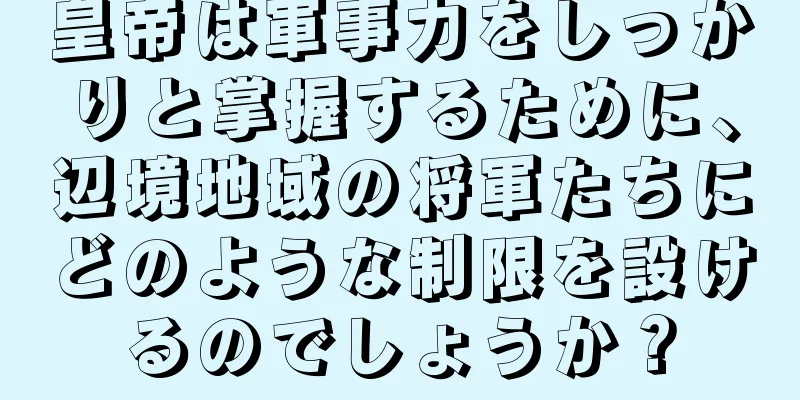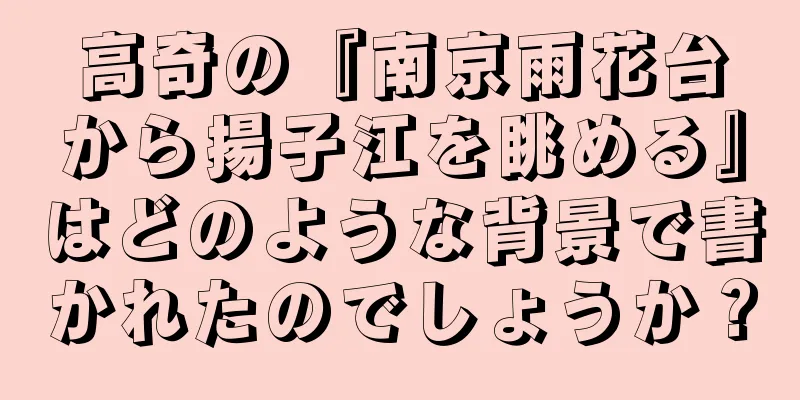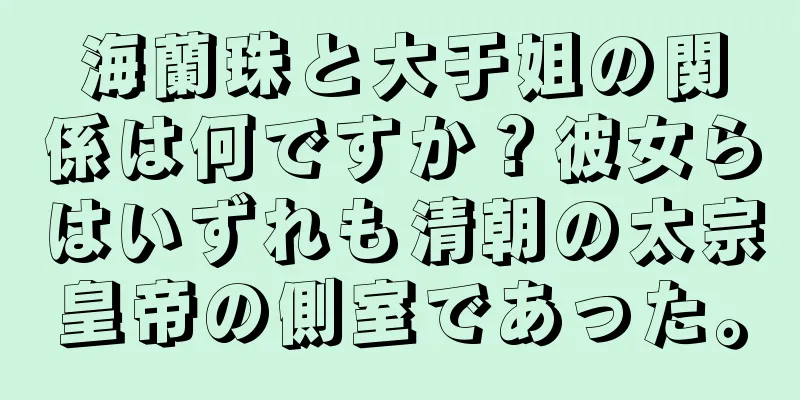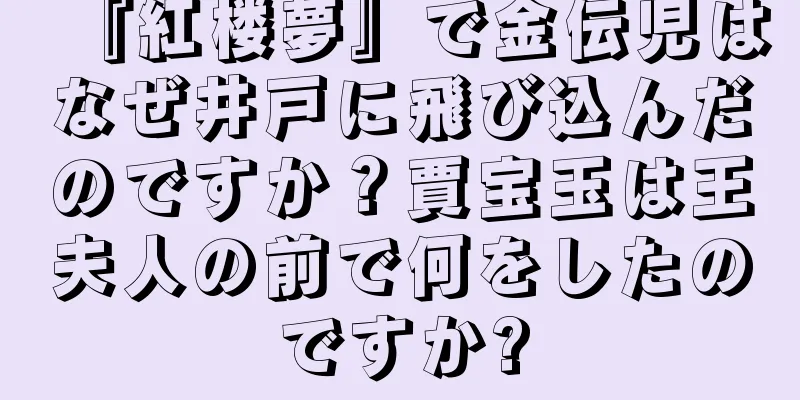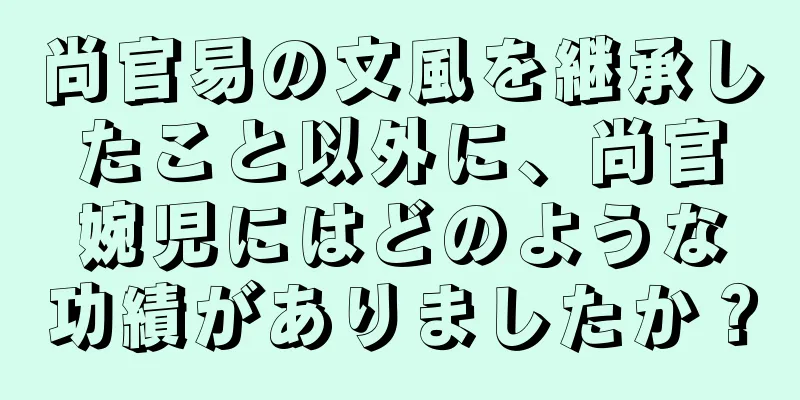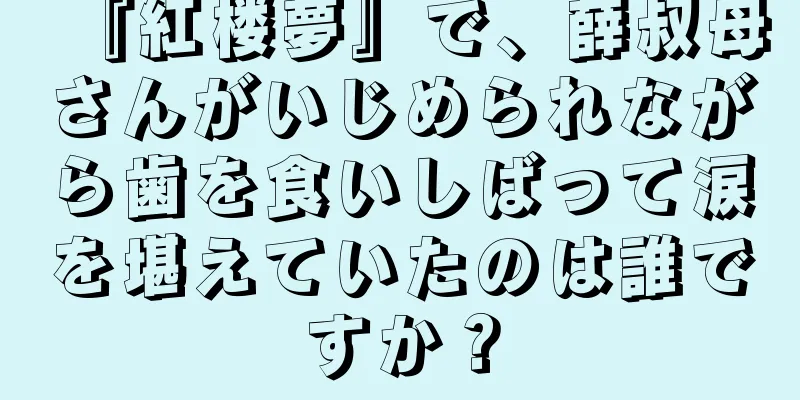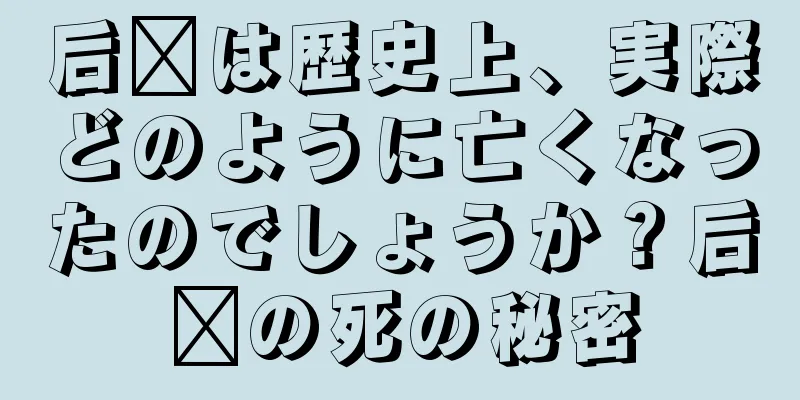纏足はなぜ「金蓮華」と呼ばれるのでしょうか?三寸金蓮華の起源
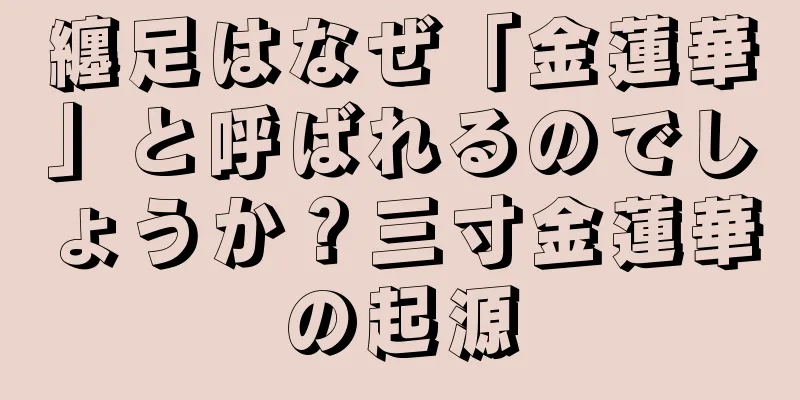
|
「三寸金蓮華」といえば、なぜ女性の足は纏足によって「金蓮華」と呼ばれるのかと疑問に思わざるを得ません。長い間、人々はこの疑問に非常に興味を持っていましたが、満足のいく答えはありませんでした。 纏足が金蓮華と呼ばれる理由は、仏教文化における蓮華の観点から検討する必要がある。蓮は泥の中から生えても汚れがなく、仏教では清浄さと高貴さの象徴とされています。仏教が中国に伝わった後、蓮は清浄と縁起の象徴として中国に伝わり、中国の人々に受け入れられました。これは、蓮が中国の縁起の良い言葉や縁起の良い図柄の中でかなりの位置を占めているという事実からも明らかです。したがって、女性の足を「蓮」と呼ぶのは褒め言葉であるのは理解できます。さらに、仏教美術では菩薩が蓮の花の上に裸足で立っている姿で描かれることが多く、これも蓮の花と女性の纏足を関連付ける重要な理由であると考えられます。しかし、なぜ「蓮」の前に「金」という言葉を付けるのでしょうか? これは、中国人の伝統的な言語習慣によるものです。中国人は貴重なものや美しいものを表現するのに「金」という言葉を好んで使います。纏足の時代には、小足が大切にされ、小足を「金蓮華」と呼ぶのも、その貴重さを表す美しい呼び名でした。その後、纏足のファンは、その大きさによって、さらに高貴な足と卑しい足、美しい足と醜い足に分けることが多くなり、3インチ以内のものは金蓮華、4インチ以内のものは銀蓮華、4インチを超えるものは鉄蓮華と名付けられました。ですから、金蓮華といえば、それは3インチでなければなりません。いわゆる3インチの金蓮華です。 別の説では、金蓮花は、南斉の東勲公の側室である潘公主が歩くたびに蓮の花を生むという物語にちなんで名付けられたと言われています。董勲侯は蕭宝娟、蕭鸞の息子である。彼は王位に就いたときわずか16歳であった。この暴君中の暴君は、極めて放蕩で軽薄であった。彼の後宮には数万人の美女がいたが、特に潘妃を寵愛していた。潘妃は非常に魅力的で、肌は雪のように白かったので、小宝娟は彼女を「玉児」と呼んでいました。潘貴妃もまた、春の竹の子のような形をした、繊細で骨のない一対の足を持っていました。蕭宝娟は彼女のために、秀玉首、神仙、仙花という三つの宮殿を特別に建てました。これら三つの宮殿は色彩豊かな彫刻が施され、壁は芳香があり、錦や真珠のカーテンで飾られており、非常に豪華でした。彼らはまた、星光塔を緑色のペンキで塗り、「青楼」と名付けました。これは後世、売春宿の同義語になりました。彼はまた地面から蓮を彫り、それをピンク色の翡翠で飾りました。潘玉兒は裸足で優雅に歩き、花は彼女の歩みに合わせて揺れ、彼女の歩みは花のように美しかった。そこで小宝娟は叫んだ。「仙女が地上に降りてきて、彼女が歩くたびに蓮の花が咲いている。」 この時までに、国は混乱状態に陥り、政府は混乱状態にありました。蕭延は反乱を起こしてすぐに、軍隊を率いて建康を攻撃した。城が陥落した夜、蕭宝娟は漢徳殿で笛を吹き歌を歌っていたが、蕭炎の部下の一人の剣に刺されて殺された。蕭炎は死後、彼に東勲侯の称号を授けた。 |
<<: 北宋の哲宗皇帝の昭懐皇后と元復皇后、劉皇后の生涯について簡単に紹介します。
推薦する
「于美人:まばらな柵と曲がりくねった小道のある小さな農家」の原文は何ですか?これをどう理解すべきでしょうか?
ポピー:まばらな柵と曲がりくねった小道のある小さな農家周邦厳(宋代)小さな農地にはまばらに柵があり、...
『紅楼夢』で黛玉の死後、宝玉はなぜ僧侶になることを選んだのですか?
『紅楼夢』には賈家の人物がたくさん登場しますが、その中でも特にユニークなのは宝玉と黛玉の2人です。多...
『紅楼夢』で王夫人は黛玉の何を嫌っているのでしょうか?理由は何でしょう
王夫人は『紅楼夢』の主人公の一人です。次は『おもしろ歴史』編集者が歴史物語をお届けします。見てみまし...
韓愈が書いた『修禅師室碑文』の原文は何ですか?どのように翻訳しますか?
皆さんご存知の通り、韓愈は唐宋の八大師の一人です。では、彼の「秀禅師室碑文」の何がそんなに素晴らしい...
潮州八景とは何ですか? 潮州八景とはどのようなところですか?
潮州の8つの名所とは何でしょうか?次の興味深い歴史編集者が詳しく紹介しますので、見てみましょう! 1...
劉備が息子を諸葛亮に託したのは理解できるが、なぜ李厳も大臣に含めたのだろうか?
東漢末期、世が乱れていた頃、劉備が畳織りと靴売りから荊州、益州、漢中を治める蜀漢の君主になるまでは、...
東晋時代の有名な僧侶、道安の生涯とはどのようなものですか?
石道安は東晋の時代に常山の伏流地区に生まれ、仏教に大きな功績を残した有名な僧侶、翻訳家であった。石道...
斉の人々はなぜ刀銭を好んだのでしょうか?それは武術の伝統によるものでしょうか?
わが国の秦以前の時代、古代の貨幣制度には、刀銭、布銭、円銭、貝銭の4つの主要な系統がありました。他の...
陳衛松の代表作は何ですか?そこにはどんな感情が込められているのでしょうか?
陳衛松は、愛称は白文としても知られ、中国の清朝末期の有名な詩人でした。彼の詩は才能にあふれ、作品は広...
古代の斬首はなぜいつも野菜市場で行われていたのでしょうか?
古代の斬首はなぜいつも野菜市場で行われていたのでしょうか。これは、古代の科学が未発達だったため、人々...
人類の起源の謎 人類の起源に関する中国の神話
人類の起源に関する中国の神話1. マカクザルが人間を産んだ人類の起源に関しては、チベット地方ではマカ...
歴史上「五代十国」の時代にはどの国が存在したのでしょうか? 「五代」と「十国」をどう区別するか?
歴史上「五代十国」の時代にはどんな国が存在したのでしょうか?「五代」と「十国」はどのように区別するの...
曹操は船から矢を借りたとき、なぜロケットを発射しなかったのですか?主な理由は何ですか?
三国志演義に詳しい人なら誰でも、この小説には非常に有名な軍師が登場することをご存じでしょう。その人物...
昔と今の不思議 第14巻 宋金浪と壊れたフェルト帽との再会(後編)
『今昔奇談』は、明代の鮑翁老人によって書かれた、中国語の俗語による短編小説集です。馮夢龍の『三語』と...
薛安福の「清東園・西高亭」は停滞感や堅苦しさを感じさせず一気に完成した
薛昊甫(1267-1359)は元代の紀書家であった。ウイグル人。彼の本名は薛超武であり、彼は自分の名...