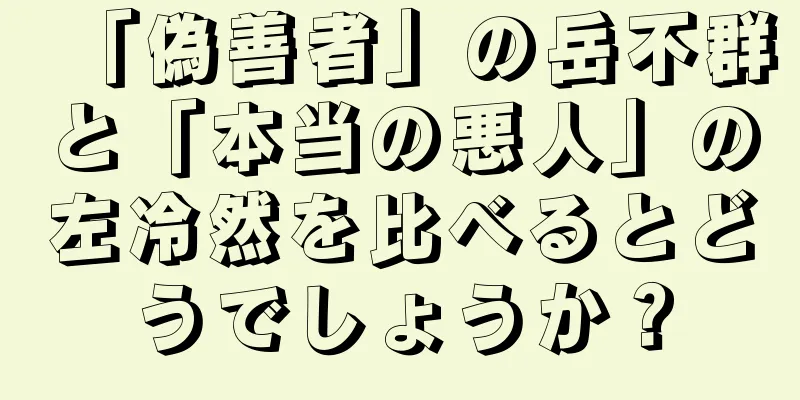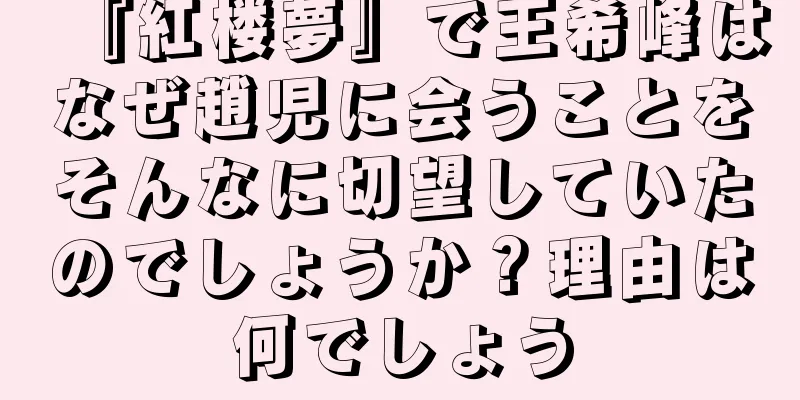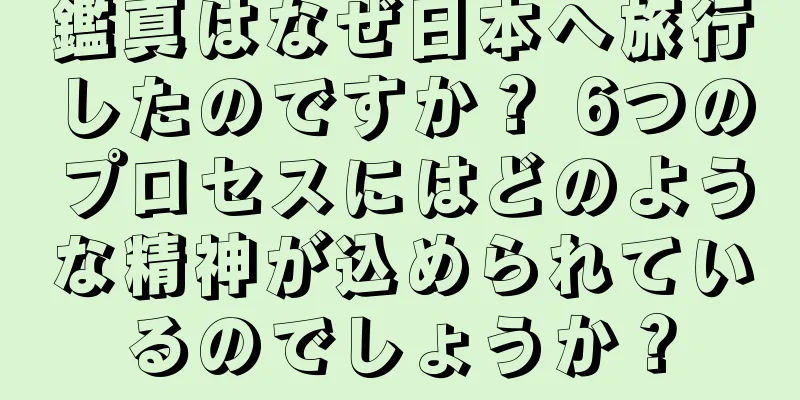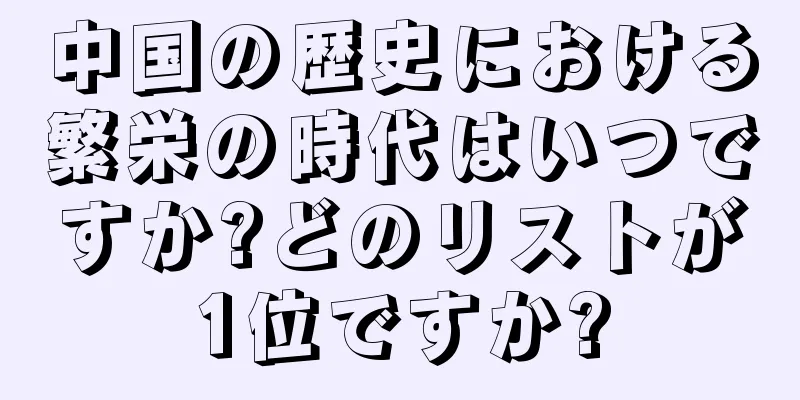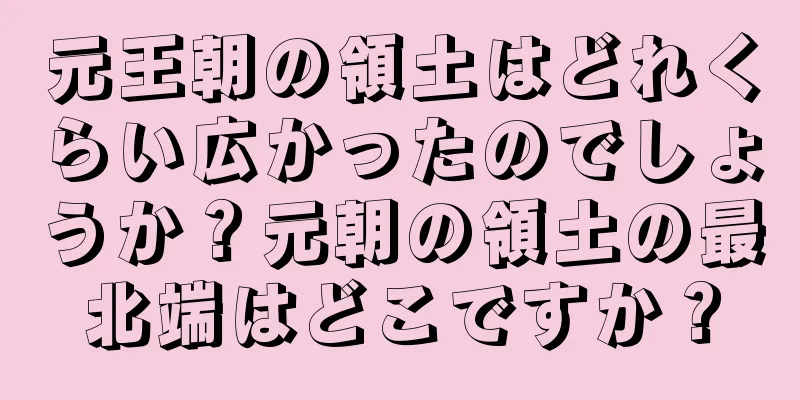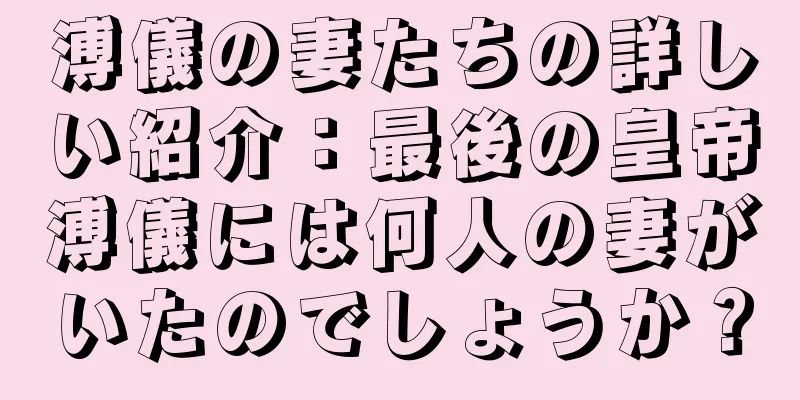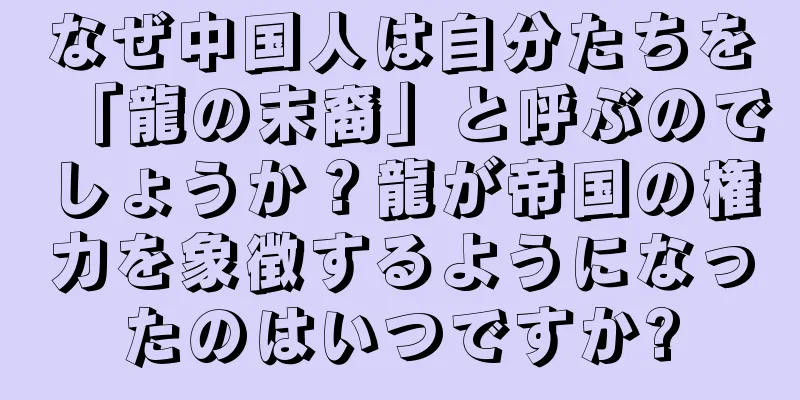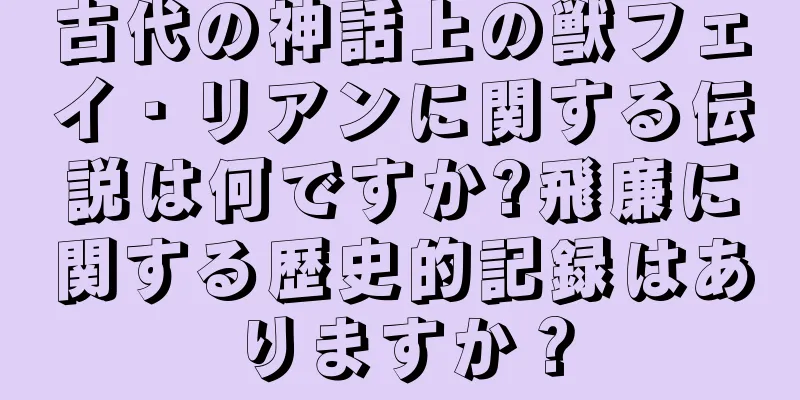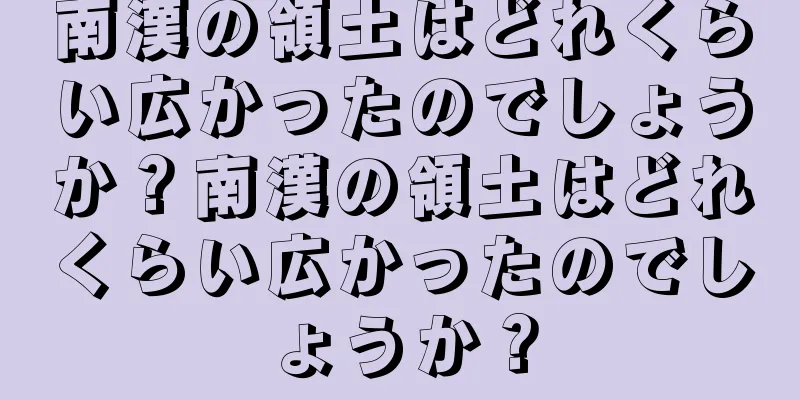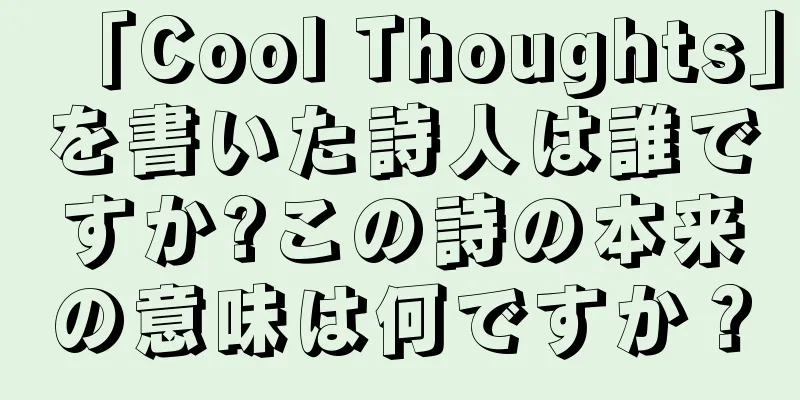趙と秦は互角だったのに、なぜ趙は秦の攻撃を止められなかったのか?
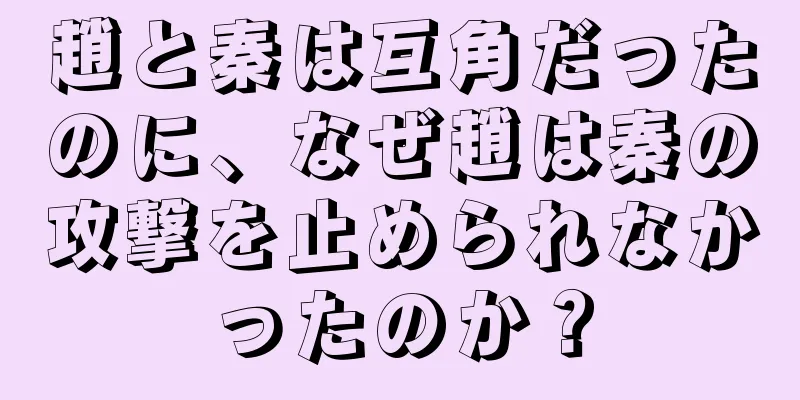
|
戦国時代には、様々な属国の間で戦争が絶えず起こり、数え切れないほどの武将や文官が輩出されました。その中でも特に有名なのは、戦国時代後期の四大将軍、白起、王翦、廉頗、李牧です。この4人の名将、白起と王翦は秦の出身、廉頗と李牧は趙の出身で、それぞれ軍事的才能に長けていました。 「軍隊を得るのは簡単だが、将軍を得るのは難しい」ということわざがあります。将軍の面では秦と同等に優れていた趙が、なぜ秦の攻撃を阻止できなかったのでしょうか。次の興味深い歴史編集者が詳しく紹介しますので、見てみましょう! 「料理が上手な人も、米がなければ料理はできない」。国の物力と軍事力は、まず将軍たちが才能を十分に発揮できるかどうかに直接影響します。秦と趙の物質的豊かさを比較してもいいでしょう。 戦国時代は戦争の時代であると同時に、各国にとって改革の時代でもありました。魏の李逵の改革から秦の商阳の改革まで、覇権争いでは変化を求める者が優位に立つことが多い。戦国時代末期、他国の改革は次々と失敗に終わり、秦は商鞅の改革によって徐々に強くなっていった。趙の武陵王は胡装と乗馬を奨励し、戦国時代末期に秦に対抗できる唯一の属国となった。改革後、趙の騎兵は無敵となり、北方の遊牧民との対決でも不利にならなかった。そして、現在の考古学的発見から、当時の趙国は既に他の国にはなかった相当数の鉄兵器を保有していたことが分かります。ある見方をすれば、秦の東進を遅らせたのは趙の存在だった。 しかし、秦と趙の改革を注意深く調べると、趙の改革には秦の改革に比べて多くの欠陥があったことがわかります。趙の武陵王の改革は比較的一方的であり、胡服を着用し、馬に乗って射撃するという政策を除いて、他の面については具体的には扱われなかった。秦の商鞅の改革では、国家の経済制度から家族人口構造に至るまで、あらゆることに関して明確な規則と規制が設けられ、改革は比較的徹底したものであった。商鞅の改革後、秦国は経済力と軍事力の両面で各国のトップに躍り出た。最も単純かつ明確な例は、秦と魏の戦争です。改革以前、魏の呉起はわずか1万人の兵で50万人の秦軍を打ち破りました。しかし、紀元前341年以降、魏は秦の河西地方への度重なる攻撃に反撃することができず、最終的に河西地方全体を失いました。さらに、商阳の重要な改革の一つは、戦国時代後期の要求に合致した井田制度の廃止と土地の私有化であった。しかし、趙国には依然として貴族の土地制度が残っており、それが経済発展に深刻な影響を与えた。時間が経つにつれて、秦の経済は自国の軍事消費に十分耐えられるようになり、趙は必然的に引きずり下ろされることになる。 物質的な豊かさという点では、秦はすでに趙よりも優れており、趙の地理的な位置も理想的ではありませんでした。戦国時代の七大国のうち、趙はその中に位置し、七国間の戦争は多かれ少なかれ趙に影響を与えていました。秦国は西に位置していたため、軍事力を東に集中させるだけでよかったのです。秦の昭王は樊於を宰相に任命した後、遠国を友好国とし近隣諸国を攻撃するという戦略を採用し、東方六国の「縦の同盟」を破壊し、趙を四方八方から攻撃させ、秦と戦うために兵力を十分に集中できなくした。 秦趙国の客観的な理由を分析した後、4人の有名な将軍から理由を探ってみましょう。一人目は「四大将軍」のリーダーである白起です。白起に対する大多数の人々の印象は、長平の戦いで趙の降伏兵40万人を殺したことであり、趙括は白起の神格化の背景板にもなった。しかし、上記の分析によれば、長平の戦いでの趙の惨敗は必然だった。たとえ趙括がいなかったとしても、銭括、孫括、李括が責任を負ったであろう。たとえ廉頗が将軍であったとしても、秦と趙の間では昌平の戦いのような戦争が必ず起こり、結果は変わらないだろう。白起が秦の軍隊に与えた最も重要な影響は、彼の優れた軍事的功績だけでなく、彼の軍事思想にもある。白起は戦争において、殲滅戦を得意とする特徴を持っていた。殲滅戦は敵の兵力を徹底的に消耗させ、その後の作戦に保証を与えることができる。白起が趙の降伏兵を殺害したのは、彼の戦闘スタイルに関係していた。また、白起は戦国時代には前例のないほど、戦う際に城塞を築くことを非常に重視していました。この高度な戦闘思考に頼って、秦軍は野戦で優位に立った。白起は後に秦王によって処刑されたが、彼の軍事思想は受け継がれ、その後の秦軍の東方作戦に大きな影響を与えた。 秦の将軍である王翦も賢い人物でした。東方の六つの国のうち、漢を除く残りの五つは王翦とその息子が率いる軍隊によって滅ぼされました。このような軍事的功績にもかかわらず、王翦は秦王に疑われず、結局無傷で逃げ延びた。王翦は楚を攻撃する前に、秦王に「美しい田畑、家、庭園、池」を繰り返し求め、自分が欲しているのは金だけであり軍事力には興味がないことを王に示した。趙国への攻撃中、王翦と李牧は直接戦闘を行った。李牧は防御に優れ、防御を攻撃の前提としていたため、王翦は長い間彼を倒すことができませんでした。王建は、膠着状態に陥ると、再び狡猾さを発揮し、趙王の寵臣である郭凱に多額の賄賂を贈り、李牧の反乱の知らせを広めた。趙王は罠にかかり、ついには密かに李牧を殺す罠を仕掛けた。王翦はわずか3ヶ月で邯鄲を攻撃し続け、趙国は滅亡した。諺にあるように、「城を攻めるのは心を攻めるより劣る」。 「四大将軍」の武術を順位付けするとしたら、おそらく誰も明確な答えを出すことはできないだろうが、戦略を順位付けするとしたら、王建は間違いなく一位になるだろう。 廉頗と李牧は趙国最後の希望として、後世に「毗牧」と総称された。「毗牧」は名将の同義語ともいわれる。しかし、二人の人生における最大の敵は秦軍ではなく君主だったようです。廉頗は君主に疑われ、趙括に交代させられたが、趙は昌平で惨敗した。李牧も君主に疑われ、軍権の譲渡を拒否し、趙王に殺され、最終的に趙は滅亡した。しかし、どちらにも欠点はあります。廉頗は勇敢だが柔軟性に欠け、李牧は防御に優れ、しばらくは身を守ることができたが、趙と秦が長期戦を始めると、趙の経済的予備資源は必然的に秦に劣ることになる。白起の軍事思想と王翦の戦略に比べれば、白牧はしばらくの間しか趙を守れなかった。二人が亡くなったり、評価されなくなったりすれば、趙は秦と戦う力がなくなるだろう。 後世の「戦国四大将軍」の評価は、白起と王翦に対して偏見を持つ傾向があった。結局のところ、白起が降伏した者を殺害したことや、王建が策略で李牧を殺害したことは、古代に唱えられた仁義や道徳に沿うものではなかった。しかし、ここは戦場であり、結果はあなたが死ぬか私が生きるかのどちらかであることを知っておく必要があります。最終的な結果は趙ではなく秦の統一でした。もし白起と王翦がしばらくの間慈悲深かったら、秦の統一に何か変化があったかどうかは誰にもわかりません。 秦と趙の祖先は商王朝の有名な将軍である費廉であり、この二つの国はもともと同じ一族であった。戦国時代後期の秦と趙の覇権争いは、別の意味での兄弟間の争いのようでした。最終的な勝利者は兄の秦国でした。 「戦国四大将軍」秦と趙の対決は、両国間の闘争のほんの一端に過ぎず、両国間の優位と不利は、一人や二人の将軍によって覆されるものではない。これには多くの理由がある。同様に、秦が六国を統一できたのも、数世代にわたる王たちの努力の結果であり、単なる「時代の流れ」では説明できない。 |
<<: 王安石の改革の際、新政策を担当していた傅弼と韓奇はなぜ反対の立場に立ったのでしょうか。
>>: 雍正帝が初めて帝位に就いたとき、なぜ異母兄弟の殷貞を皇帝陵の守護に処したのでしょうか?
推薦する
イスマイール派宗教:タジク民族の独特な信仰
歴史的に、タジク人はゾロアスター教や仏教を含むさまざまな宗教を信じてきました。これら二つの宗教文化は...
『リトル・ピーチ・レッド・客船の夜の会合』の作者は誰ですか?この歌の本来の意味は何ですか?
【オリジナル】澄んだ湾をゆっくりと緑の雲が覆い、香りが東岸と西岸に広がります。今年の公式コースは90...
古代の人々の寿命が短かったのは、彼らが食べていた食べ物と関係があるのでしょうか?
ご存知のとおり、古代人の平均寿命は非常に短かったです。では、それは彼らが食べていた食べ物と直接関係し...
「何心浪:茅家十二番目の兄弟に別れを告げる」鑑賞。当時、詩人の心其基は千山に住んでいた。
辛其基(1140年5月28日 - 1207年10月3日)、元の字は譚復、後に幽安と改め、中年になって...
古代では、結婚前に妊娠した女性は殴り殺されたのでしょうか?
古代では、男性と女性の境界は非常に明確で、決して越えられることはありませんでした。では、古代の女性は...
于吉の『松風図』は平易な文体で書かれており、自然の傑作と言える。
于吉(1272年3月21日 - 1348年6月20日)、号は伯勝、号は道元、通称は少安氏。彼の先祖の...
『紅楼夢』のタンチュンはどれほど野心的なのか?ろくでなしの地位から脱却するために、
『紅楼夢』のタンチュンはどれほど野心的なのか?彼女は側室の地位から脱却するために本当に努力した。大観...
秦国は初期には弱かった。なぜ他の大国に併合されなかったのか?
秦は初期は弱かった。なぜ他の大国に併合されなかったのか? Interesting History の...
清代古散文の鑑賞:河中石獣。この古散文にはどんな真実が込められているのでしょうか?
清代の江中石獣、季雲については、次の興味深い歴史編集者が詳しく紹介しますので、見てみましょう!滄州南...
「丁鋒博墨易能格联盟」の原文は何ですか?これをどう理解すべきでしょうか?
丁鳳波:莫毅は歌いながらしかめっ面もできる周邦厳(宋代)歌ったり顔をしかめたりする能力に頼らないでく...
明代の人々は何を食べていたのでしょうか?明王朝時代の食生活の特徴は何ですか?
明朝は華麗で華やかな文化を生み出しました。その際立った特徴の一つは、都市経済と都市文化の繁栄でした。...
白居易の「南湖早春」:詩人は長江南部の春の風景を心から愛している
白居易(772-846)は、字を楽天といい、別名を向山居士、随隠仙生とも呼ばれた。祖先は山西省太原に...
『紅楼夢』で、王希峰が幽二潔を賈邸に連れて来たとき、賈おばあさんはなぜ反対しなかったのですか?
賈祖母は、石夫人としても知られ、賈家で最も権力のある人物です。次はInteresting Histo...
王平は曹操、劉備、諸葛亮から高い評価を受けるに値するほどの功績と能力を持っていたのでしょうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
『紅楼夢』では、禿頭の僧侶が岱玉を改宗させたが、薛宝才は改宗させなかった。なぜ彼はそうしたのか?
禿げ頭の僧侶と足の不自由な道士は、このテキスト全体に登場します。以下の記事は、Interesting...