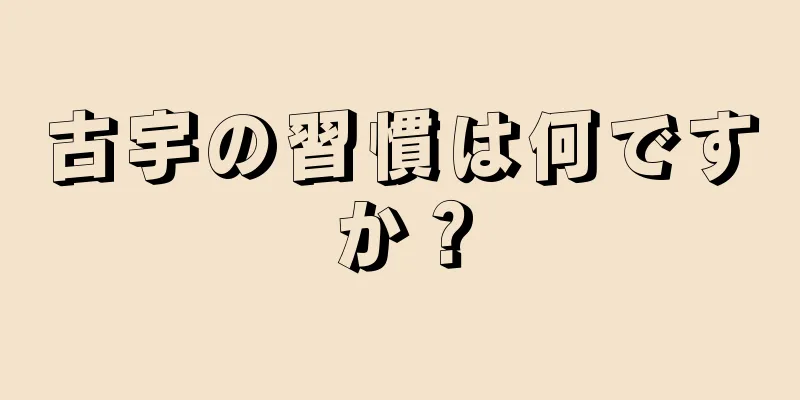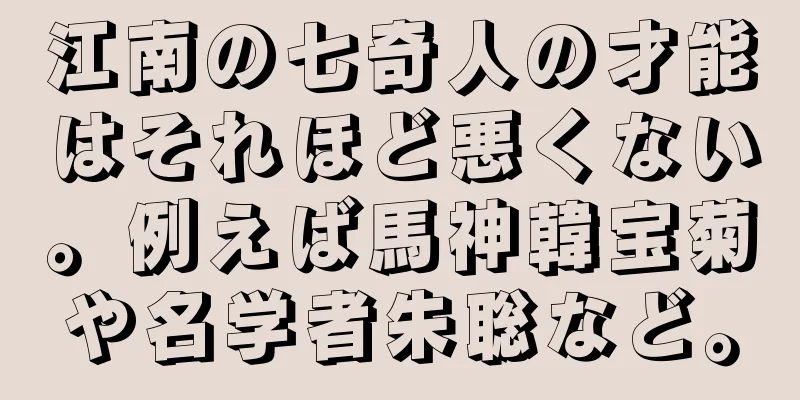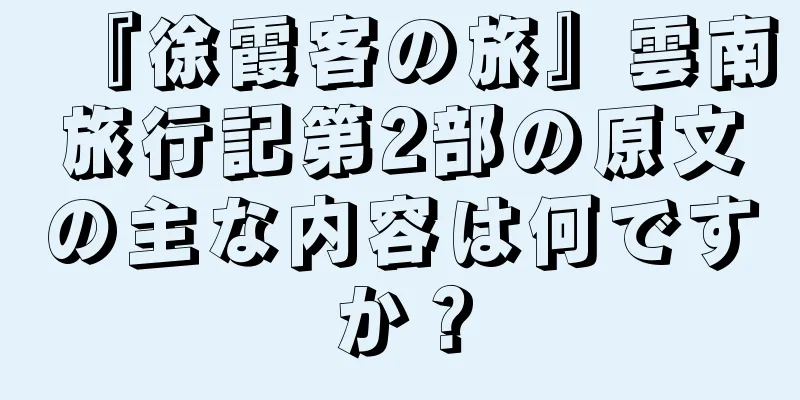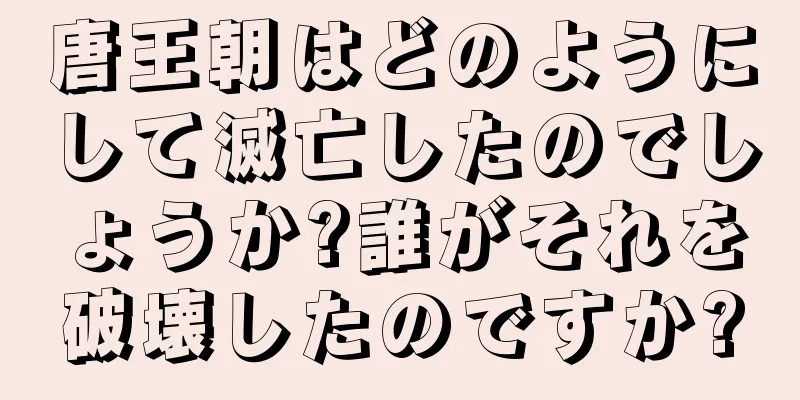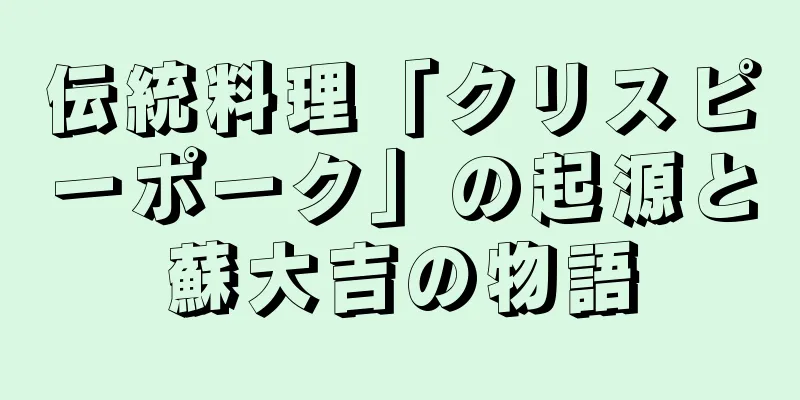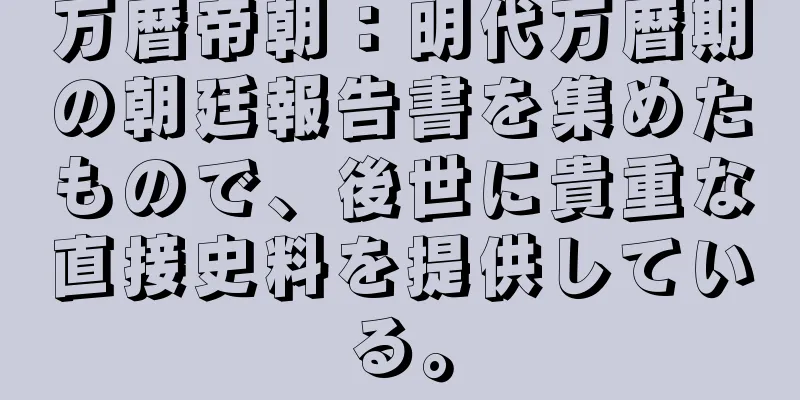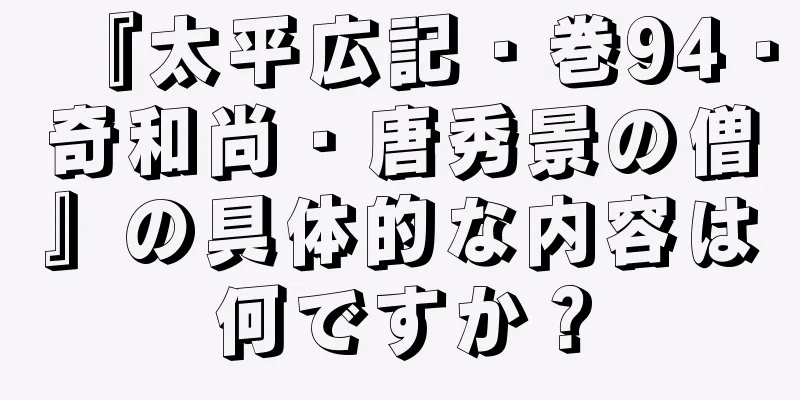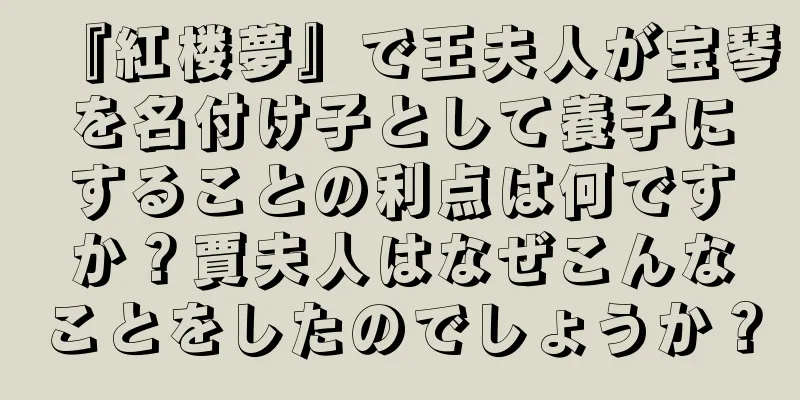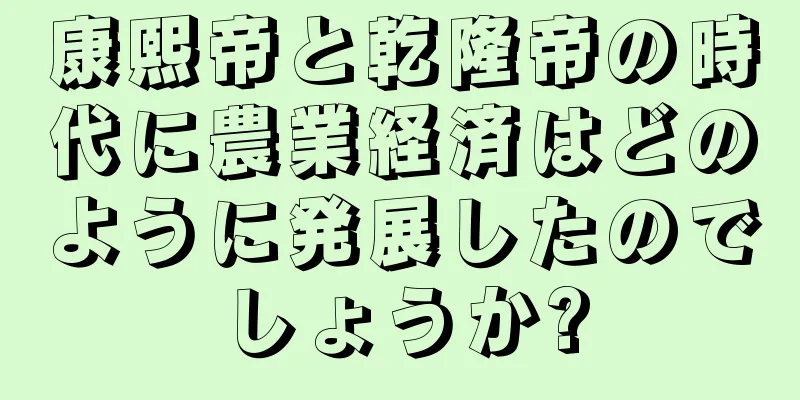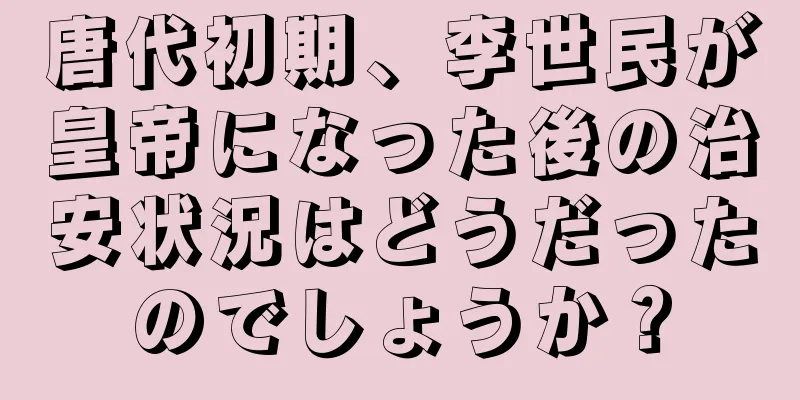漢王朝の死後救済制度とは何でしたか?漢代の死者救済制度の詳細な説明
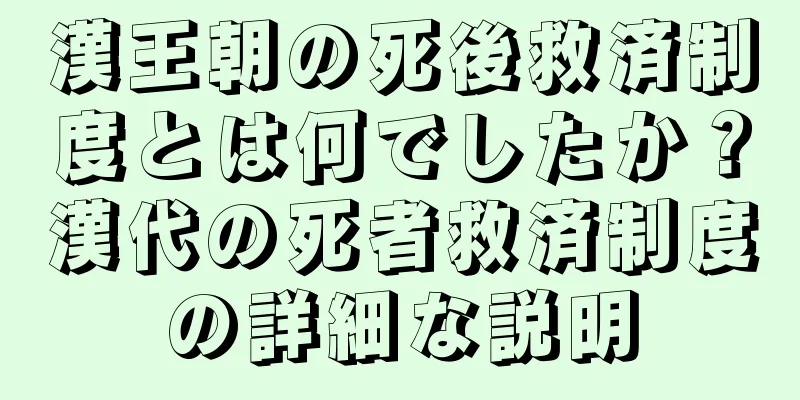
|
漢代の死罪救済制度とは何ですか?漢代の死罪救済制度の実施をより明確に提示することができます。特定の社会状況の影響を受けて、漢代の死罪救済制度は発展と変化を続けました。次に、興味深い歴史の編集者が関連するコンテンツの紹介をお届けします。興味のある友人は、ぜひ見に来てください。 1. 張家山漢籍竹簡に描かれた「死の贖罪」 張家山漢簡には「死罪救済」について明確に言及している記録が計6件あり、「二年法」の「全法」「盗人法」「報告法」に分配されている。 「二年法」の死償還条項は、文言を研究すると、「法による死償還」と「命令による死償還」の2つに分けられる。 1. 法による死の償い 法律による死の償還とは、法律文が初めて公布され施行される際に、法律文の形式で規定される死の償還を指します。これは一般的な法的規定であり、償還の各レベルに対応する身代金について具体的な規定を定めています。 そこには「死の身代金は、金二斤八オンス」と規定されている。他の身代金水準と比較すると、金二斤八オンスは最も高い身代金水準であり、他の各水準との差は金四オンスである。 死罪の償いと成丹崇、桂心百辛の低級の償いの差は1キロもあり、死罪の償いが償い制度の中で最高かつ最も重い刑罰であることを改めて証明している。 法律自体から判断すると、規定されている償いの性質を判断することは困難です。しかし、漢の武帝の治世中の淮南王の反乱の事例と結び付けると、その性質は明らかになります。 この謀反事件では、淮南王の側近たちは「官位を剥奪され、兵士に降格」されただけだった。したがって、官職に就いていない「非官」に対する処罰はより軽いものであるべきであり、死刑ではなく直接死刑を宣告し、その後他の刑罰に置き換えた。 2. 命令に従った死の償い 死の贖罪とは、元々の法律文には規定がなかったが、後に皇帝が死の贖罪の勅令を出したことをいう。漢代の法律によれば、喧嘩中に誰かが負傷し、その負傷者が保釈期間内に死亡した場合、加害者は殺人罪で起訴される。 しかし、第5法と第6法には2つの例外が規定されている。1つは、親が年長者として子供や身分の低い奴隷を殴打し、仮釈放期間中に死亡させること。もう1つは、成丹刑や桂心百監に服役する囚人を、役人が職務を遂行する過程で殴打や鞭打ちを行い、仮釈放期間中に死亡させることである。 以前の償還条項と比較すると、これら 2 つの条項には非常に明らかな特徴があり、それは「償還」の前に「命令」という言葉があることです。古代の立法技術の限界により、当初制定された法律はすべての刑事事件を網羅することはできなかったため、皇帝が補足として「命令」を発令することが特に重要でした。 一般的に、命令は法律の一時的な改正ですが、一時的な効力しか持たない命令が「命令として書かれた」場合、法律と同様の長期的な効力を持ちます。 法第5条および第6条に規定する事情は、本来は死刑に処されるべきであったが、皇帝の「命令」により、死刑が救済に置き換えられ、補助的救済の性格を満たしている。 しかし、それが「命令として公布」されると、政府は直接その判決を援用して死刑を執行することができるようになり、このとき、それは補助的な援用刑罰から独立した援用刑罰へと変化した。 3.償還の実行方法 張家山漢簡には、死罪の処刑方法についての記録はあまり残っていない。二年目の法令では、人の死を償うためには金二斤八オンスの支払いが必要であると明確に規定されていました。したがって、死刑を償う好ましい方法は金を支払うことであるはずです。 しかし、金は貴金属であり、人々の間で流通している主要な通貨ではありません。そのため、「黄金法典」では、人の死を償うために金を支払うことに加えて、同じ価値のお金を支払うことでも人の死を償うことができると規定されています。 「泥棒法」は、称号で罪を償う方法である。息子が両親を殺したり、傷つけたり、殴ったり、叱ったり、あるいは殺害を企てたりした場合、妻も罪に問われ、称号で罪を償うなどの刑罰を軽減することはできないと規定されている。 また、『邢班書』の「溧陽県令回が郡米を盗んだ」事件では、「盗んだ役人は処罰され、その爵位は減免または償還されない」という法令がある。 この二つの法律は、どちらも「いかなる爵位も人を贖うために使うことはできない」という状況を規定しているが、その逆から、貴族の爵位を使って人の死を贖うなど、貴族の爵位を使って人の刑を贖うことができる状況が当時もあったと推測することもできる。これは以下の分析で確認できます。 Ⅱ. 史記と漢書における死後救済制度 1. 前漢初期の「死の贖罪」 伝承文献における死罪救済制度の最も古い記録は『漢書会賽記』にあり、「人民が罪を犯した場合、30級以上の爵位を購入すれば死刑を免除される」とある。これも、前述の爵位で死罪を救済する処刑方法が実際に存在したことを裏付けている。 死罪救済制度は漢代初期に存在したが、あまり普及せず、代々伝わる文書の中に記録が一つだけ残っているだけである。これは当時の不況という社会背景と切り離せないもので、当時は「米一石が一万銭」という時代で、「人が互いに食べ合う」という光景さえありました。 民衆は飢えに苦しみ、衣食住という最も基本的な問題さえ解決できないのに、罪を償うためのお金はどうやって手に入れられるのだろうか。そこで高祖は「法律を制定し、禁制を緩和し、地代を減らし、税金を15分の1に減らし、役人の給料を測り、官費を見積もって民衆に課税した」。恵帝と呂后の治世になってようやく状況は改善し、「衣食住が豊かになった」。 2. 文靖時代の「死の贖罪」 文帝の治世中、趙匡は碑文の中で、穀物を納めることで罪を償うことができると述べているが、文帝は最終的に「穀物を納めれば爵位が与えられる」という考えだけを採用した。恵帝の治世中に行われた罪を償うための金銭の支払い政策も、文帝によって廃止された可能性がある。 文帝の治世中、彼は農業の発展を非常に重視しました。趙匡の「穀物を納めて爵位を授かり、罪を償う」という考えは、文帝の「農業を重視する」という考えと一致していました。 しかし、それでも文帝は「罪を償うために穀物を支払う」という提案を採用しなかった。そのため、文帝が恵帝の治世中に罪を償うために金銭を支払って爵位を授与するという政策を継続する理由はさらに少なかった。実際、『史記』や『漢書』には関連する記録がない。 このことから、文帝の時代には、補助的な贖罪刑はなかった可能性があり、龔毓の言ったことは不合理ではないと推測できます。景帝の治世中、尚鈞の西方で干ばつが起こったため、「売爵令」が復活し、「囚人が仕事に復帰すれば、郡役人に穀物を支払って刑を免除してもらえる」という命令まで出された。 しかし、このとき、穀物税を納めて罪を免れるのは「再懲役」に限られ、死刑には適用されなかった。したがって、文帝と景帝の治世中には、死を贖うという勅令は存在しなかった可能性がある。 3. 武帝の治世中の「死の贖罪」 武帝の治世中に、贖罪の方法が徐々に実行されました。当初、文帝と景帝の時代に蓄積されたため、国庫は十分であり、贖罪法を実施する必要はなかった。そのため、武帝の時代に贖罪の記録が出現したのは、基本的に武帝が「海外の四夷を処分し、国内の軍事功績を奨励し、人件費を増やした」後のことである。 武帝は海外で戦争をしていたため、軍法に違反した将軍に死刑を宣告する例が多かった。 武帝の治世中の軍事戦争は長期化し、莫大な軍事費を費やしたため、全国で贖罪の法の施行が促進された。 元碩6年、漢王朝は戦争に赴いた兵士に報いるために「軍功称号」を制定した。富裕層は兵士から称号を買うことができ、買った称号のレベルに応じて罪が2段階軽減された。兵士は称号をお金と交換することもできた。褒賞を受けた一般兵士や称号を買った人が死刑に値する罪を犯した場合、その刑罰は称号のレベルに応じて軽減されることができました。 このとき、軍法に違反した将軍のみに適用されていた死罪救済制度は、一般兵士、さらには民間人にも拡大された。匈奴や周辺の少数民族との戦争はすでに漢王朝にかなりの財政的圧力をかけていたが、軍事費もそれに加えて増加した。 西南易路の開拓や碩放城の建設、さらには武帝自身の出費などにより、漢王朝の財政は大きな問題を抱えることとなった。 そこで、元豊元年、大臣の桑鴻陽は武帝に「官吏は昇進するために穀物を支払うことを許可し、犯罪者は罪を償うことを認めるべきだ」と提案した。この頃、武帝の時代に、粟を使って死を贖う制度が生まれました。その後、天漢4年、太史2年に武帝は「身代金50万元を支払えば、死刑を一等死刑に減刑できる」という勅令を出し、当時の財政難が露呈した。 称号による死の償いから穀物による死の償い、そして金銭による死の償いへと、この非標準的な死の償いの方法は、基本的に武帝の治世の全期間を通じて存在していました。 4. 昭帝から前漢末期までの「死の贖罪」 武帝の後に死を贖う記録は多くありませんが、「馬で死を贖う」や「領地で死を贖う」などの記録があり、方法はより柔軟になりました。昭帝の治世中、尚官桀皇后の祖父には崇国という名の寵愛された宮廷医師がいた。崇国は許可なく宮殿に侵入したため、法律によれば死刑に処されるべきであった。 昭帝の長姉である夷公主は「罪を償うために皇帝に馬20頭を捧げたため、死刑を免れた」。宣帝の治世中、大臣の劉翔が銅貨に鉛や鉄などを混ぜて「偽金」を鋳造した。法律によれば彼は死刑に処されるべきであったが、彼の兄弟は「五百世帯」で劉翔の罪を償った。 この時期には民間人に対する死罪救済令は発布されていなかったことから、この時期の死罪救済制度は主に特権階級に適用されていたと推測される。 後漢書における死後救済制度 『後漢書』は、東漢の光武帝の建武元年から、漢の献帝の建安25年までの約200年の歴史を記録した書物で、東漢時代の死の救済に関する記録が数多く含まれています。西漢とは異なり、東漢の勅令における償還金の額は絶えず変化していたものの、東漢全土を通じて存在していた。 光武帝の建武29年以来、歴代の皇帝は即位後、必ず斃死の贖いの勅を発布した。この勅は大きく分けて、絹で斃死を贖うものと、国境を守備して斃死を贖うものの2つに分けられる。 絹は織物の一種ですが、すでに前漢末期に通貨として使われ始め、東漢で最も普及しました。当時、報酬や給料は絹で支払われることが多かったです。後漢書には、絹を使って人の死を償うことができると明記された14の勅令がありました。 同様の法令は10件あります。 計24の勅令を分析すると、絹による死の贖罪の主な対象は「逃亡者」、つまり犯罪により逃亡した人々であることが分かる。逃亡者は死に至るまで何であっても贖罪できる。 漢の何帝の治世中に、絹による死刑の償いの対象範囲が「囚人」(刑務所に拘留されている囚人)と逃亡者にまで拡大されました。しかし漢の霊帝の治世までは、絹による贖罪の主な受取人は逃亡者であり、捕虜を贖う主な方法は、後述するように国境の守備兵として働くことであった。 漢の霊帝の時代には、享楽にふけり、宦官を優遇し、官職や爵位を売却し、絹による罪の償いの適用範囲を未決犯罪者にまで拡大したが、これはより合法的に金儲けをするためであったと推測するのが妥当である。 国境を守りながら死者を救済することは、東漢時代に死者を救済するもう一つの主要な方法でした。 東漢の時代、漢王朝は南匈奴、五桓、一部の羌族を相次いで奪還し、北匈奴を駆逐し、鮮卑と友好関係を樹立した。降伏した少数民族に対する統制を強化し、服従しない勢力との共同抵抗を防ぐために、東漢は国境地帯に軍隊を駐留させる必要があった。国境警備の死者を償還する制度は、国境の兵力不足の問題を解決することができる。 東漢時代には、上記の2つの主な死の償いの方法の他に、武功で死を償う、官位で死を償う、金銭で死を償うといった方法もありました。 前漢の時代に爵位によって死を贖う習慣があったのと同様に、東漢の時代の官吏は降格によって罪を贖うことができ、つまり官位や給与によって罪を贖うことができた。実際には、『後漢書』には、官吏が官位と俸給を支払って罪を償ったという直接的な記録はない。しかし、漢の明帝、漢の安帝、漢の舜帝の治世中には、官吏に「官位を回復し、罪を償う」という勅令があった。 官吏の死を償うために官位を降格したり、俸給を減額したりしたという正確な記録はないが、当時出された逃亡者や囚人の死を償う勅令を考慮すると、官吏は官位と俸給で死を償うことができたはずである。漢の舜帝や桓帝の時代に庶民が金銭で罪を償ったという記録があるが、これは当時の役人による「集金」の手段であり、皇帝の勅令によって全国的に実施された償いの方法ではなかった。 |
<<: 古代において、蚕の飼育場所はどのように変化したのでしょうか?
>>: 漢王朝の死後救済制度は社会にどのような影響を与えたのでしょうか?
推薦する
漢民族のドラゴンボート祭りは何を記念するものですか?
端午節の起源の伝説端午の節句は、中国の春秋戦国時代に始まり、2000年以上の歴史を持つ古代の伝統的な...
中高年はどうやって健康を維持すればいいのでしょうか?中高年が健康を維持するためにはどのような食品を摂取すべきでしょうか?
中高年は健康を維持するために適切な食品を選ぶ必要があります。健康を維持するために、以下の食品を摂取す...
董卓はなぜ漢の紹帝を廃位しようとしたのでしょうか?漢の献帝は若く、統制しやすかった。
董卓は三国時代の偉大な英雄でしたが、彼の残酷さのために世界中の人々から嫌われ、最後に笑うことはありま...
「紅楼夢」のシレンは本当に危険なのか?彼女は実際はそんなに悪い人ではない。
多くの人は『紅楼夢』の雪人を嫌い、彼女はとても裏切り者だと思っているが、彼女は本当にそんなに悪いのだ...
「丁鳳波:春が来ると悲しい緑と悲しい赤」の内容は何ですか?丁鳳波の詩「春以来、緑は悲しく、赤は悲しい」の鑑賞
本日は、Interesting History の編集者が「丁鳳波・春が来ると緑は悲しく、赤は悲しく...
中国古典文学の原典の鑑賞:『論語』集成第16章
季舒は舒羽を攻撃しようとしていた。然有と季陸は孔子に会い、「季師は桓于で任務を果たすでしょう」と言っ...
「国内で類を見ない」とはどういう意味ですか?史上唯一「国内無双」と呼べる人物!
「国内無比」とはどういう意味でしょうか?歴史上「国内無比」と呼べる人物は誰でしょうか?以下、Inte...
雍正帝廟はいつ発掘されましたか?なぜ尾行霊廟は略奪されなかったのか?
泰陵は清代初期の陵墓であり、地下宮殿は陵墓全体の中で最も中心的かつ神秘的な場所です。陵墓研究にとって...
『紅楼夢』で、王夫人はなぜ賈正が側室を迎えることに同意したのですか?
『紅楼夢』の中で、なぜ王夫人は賈正が趙おばさんを側室として結婚することに同意したのでしょうか? これ...
漢民族の祭り 漢民族の伝統的な祭り 冬至の習慣とは
何千年にもわたる発展を経て、冬至は独特の祭りの食文化を形成してきました。ワンタン、餃子、もち米団子、...
孫子の兵法を分析すると、漢の武帝はフン族に対してどのように反撃したのでしょうか?
漢の武帝といえば、何を思い浮かべますか?次のInteresting History編集者が、関連する...
宋代の首都は「汪梁」ではなく「汪京」であった。
2007年5月、CCTVは「龍里旗杯第12回CCTVヤングシンガーグランプリ」を生放送しました。知識...
蘇軾はなぜ黄州に降格されたのか?もっと深い理由は何でしょうか?
蘇軾が黄州に左遷された直接的な理由は「五台詩事件」であったが、より深い理由は王安石の改革における新旧...
龐統の一連の計画の主な内容は何ですか?
龐統(179-214)は、字は世源、号は鳳初で、漢代の荊州襄陽(現在の湖北省襄陽市)の人である。三国...
『筆孟于宋礼周』の原文は何ですか?どのように鑑賞すればよいでしょうか?
夕闇の雨の中、李周に別れを告げる魏英武(唐代)楚河の霧雨の中、建業の晩鐘が鳴る。帆は重くのしかかり、...