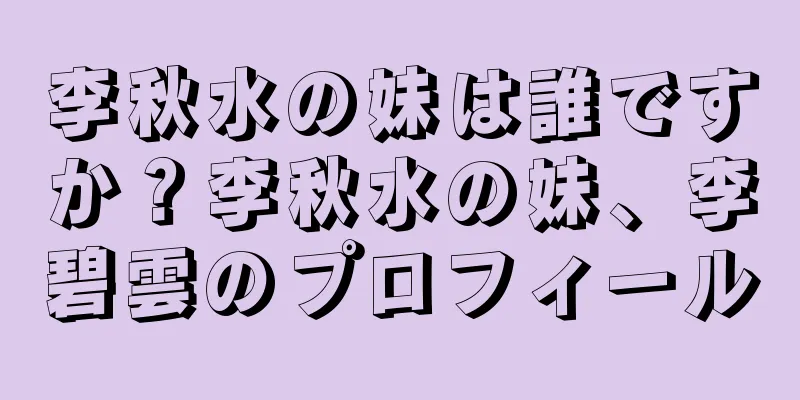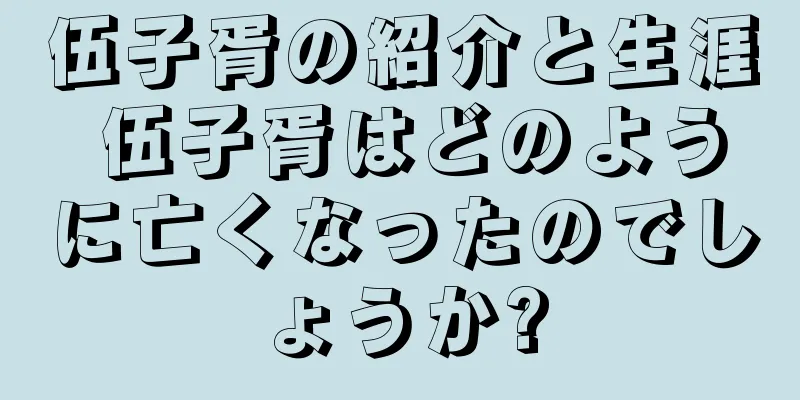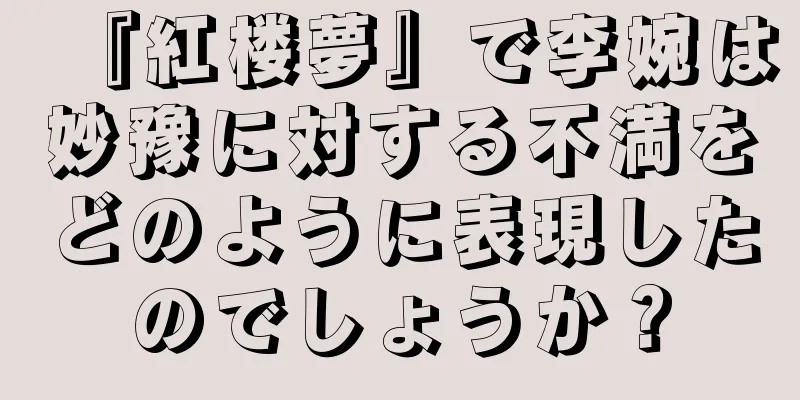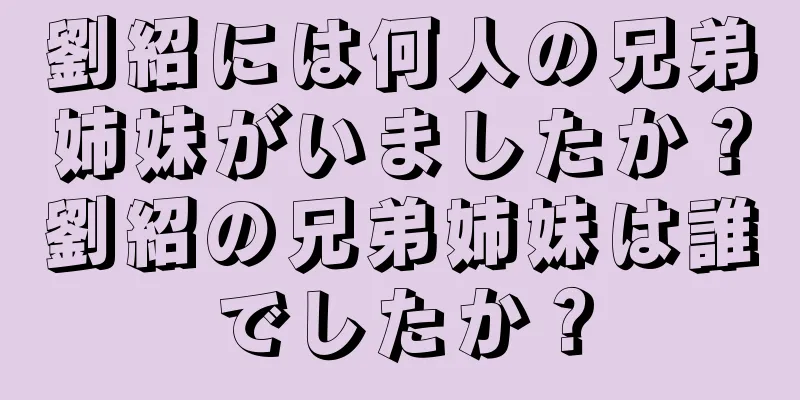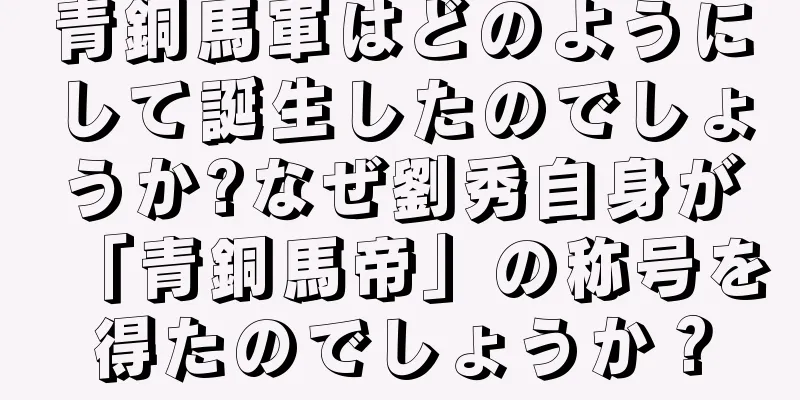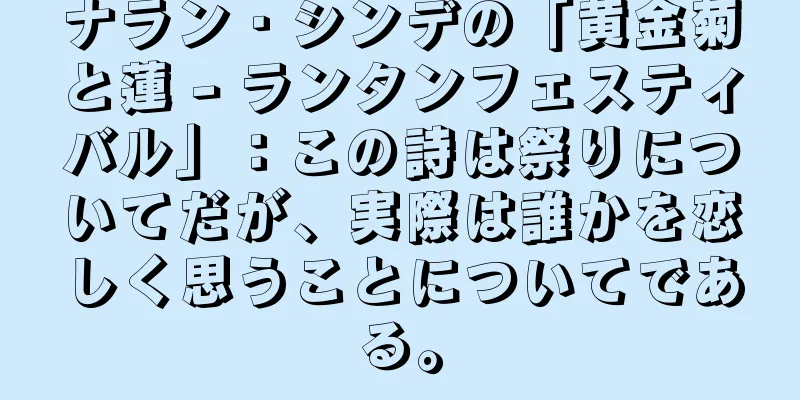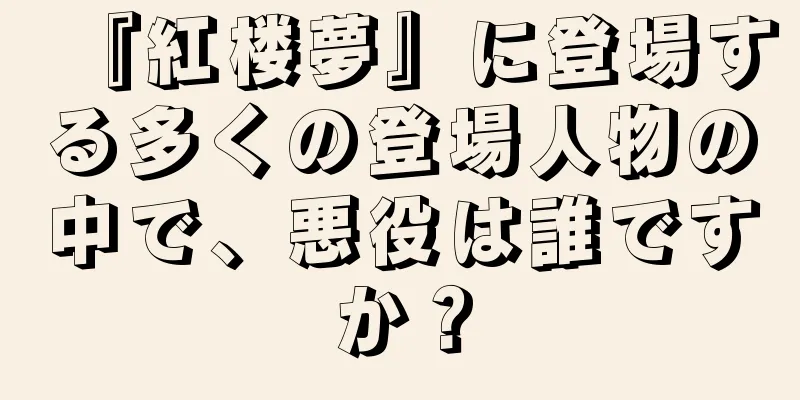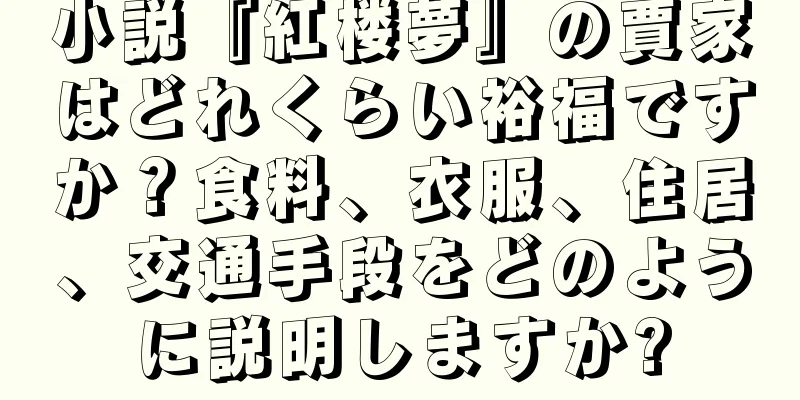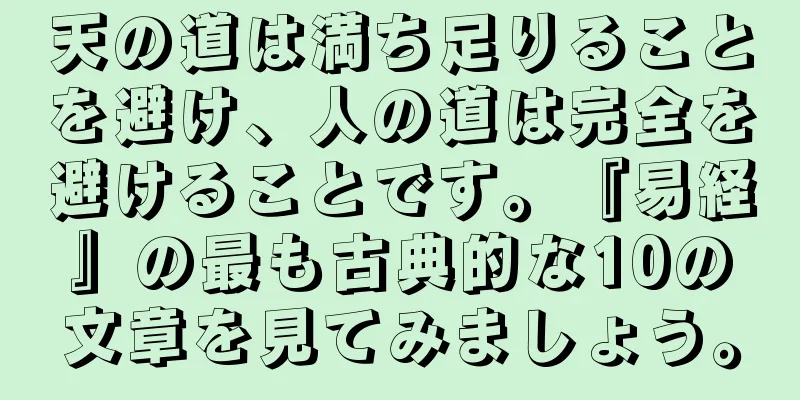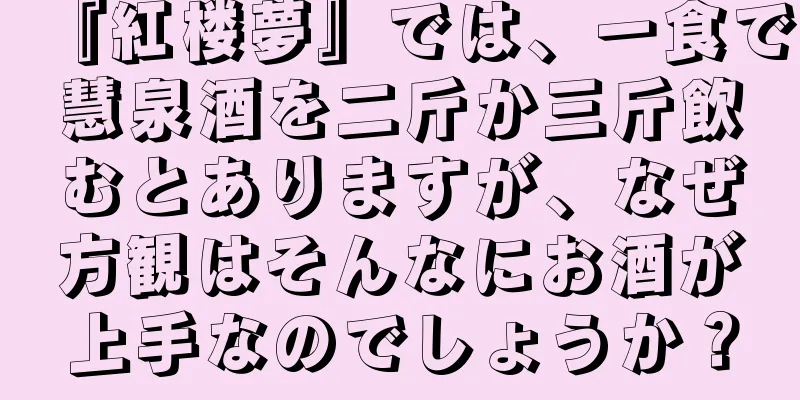諸葛亮と司馬懿の戦いで、死んだ諸葛亮はどうやって生きている鍾大を追い払ったのでしょうか?
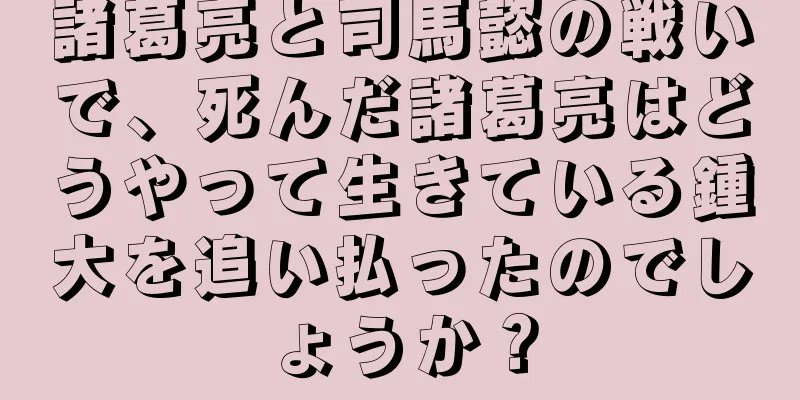
|
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代です。この時期には曹魏、蜀漢、東呉という3つの大政権が相次いで誕生した。それでは、次の興味深い歴史編集者が、司馬懿が諸葛亮を恐れた理由について詳しく紹介します。見てみましょう! 諸葛亮の第四次北伐から、諸葛亮は生涯最後の敵である司馬懿と出会う。諸葛亮と司馬懿の戦いの際、「死んだ諸葛亮が生きている鍾大を追い払った」という伝説が残されました。人々はこの物語を諸葛亮と司馬懿の軍事的才能を判断するためによく使います。それで、この事件はどうなったのでしょうか? 1. 死んだ諸葛亮は生きている仲達を追い払った。 この物語は諸葛亮の最後の北伐の時代に起こります。諸葛亮は最後の北伐で最大の努力を払った。この戦いの前に、食糧と飼料の不足問題を解決するために、諸葛亮は特別に3年分の食糧と飼料を蓄え、漢中に輸送しました。輸送と物資の問題を解決するために、彼は木製の牛と流し馬を輸送に使用し、機械の力の助けを借りて問題を解決しました。 軍事面では、諸葛亮は蜀漢最大の軍勢を展開した。蜀軍の総兵力は約12万人。過去の北伐では、諸葛亮は通常、兵力の3分の2だけを連れて行き、残りの3分の1は念のため国内に留まっていた。しかし、このとき諸葛亮は10万人の軍勢を率いており、蜀軍の限界に達したとも言える。同時に、諸葛亮は東呉に合同で軍を派遣するよう要請し、曹魏に対して東西に進軍する状況を作り出した。 戦闘指揮においては、諸葛亮はそれまでの冷静で安定したスタイルを変え、柔軟で変化に富んだ戦術を採用した。彼は魏軍の防御の抜け穴を探し続け、先手を打って攻撃を仕掛け、魏軍を動揺させ疲れさせた。これらすべてが曹魏に不安を引き起こし、また司馬懿にも考えさせました。 一方で、司馬懿はわざと大言壮語し、諸葛亮の軍事的才能と戦闘指揮力を軽視した。一方で、彼は戦況を安定させ、諸葛亮の進出を阻止するためにあらゆる手段を講じた。結局、司馬懿の努力により、諸葛亮は戦いで突破口を開くことができず、司馬懿と対決しなければならなくなった。諸葛亮は司馬懿との決戦を企てて何度も司馬懿に戦いを挑んだが、司馬懿は戦争前に曹叡と練った戦略を固守した。つまり、戦わずに陣地を守り、諸葛亮が食糧や草が尽きて退却するのを待ってから追撃するのです。そのため、司馬懿は自分の立場を守り、出ることを拒否した。 何度も敵に挑戦して失敗した後、諸葛亮は敵を挑発する手段に頼りました。彼は使者を派遣して司馬懿に女性の衣服や宝石を与え、司馬懿が女性のように臆病だと嘲笑した。しかし、狡猾な司馬懿はそれを無視し、自らの謎の答えを見つけるために蜀軍の使者をもてなした。 司馬懿は諸葛亮が食べるものも少なく、いろいろと悩んでいると知り、諸葛亮の体調を理解した。諸葛亮は自身の体調不良のため、あらゆる手段を講じて魏軍との決戦を試みようとした。このため、司馬懿は決意を固め、曹叡に軍監を派遣して部下を鎮圧し、諸葛亮と対決し続けるよう要請した。 諸葛亮は司馬懿の意図を見抜き、その状況を利用して軍を率いてその場で土地を耕作した。この戦争は諸葛亮と司馬懿の意志の争いとなった。ここで鍵となるのは時間であり、諸葛亮の体調と曹魏の軍隊の忍耐力のどちらが長く続くかを見ることです。結局、諸葛亮の体は最後まで持ちこたえられず、後悔の念を抱きながら五丈原の蜀軍陣地で亡くなりました。 司馬懿は現地の人から諸葛亮が軍を撤退させたという報告を受け、定められた戦略に従って軍を派遣し蜀軍を追撃した。しかし、司馬懿が蜀軍に追いついたとき、蜀軍は慌てる様子を見せなかった。逆に蜀軍は厳重な陣形を敷き、魏軍に対して攻勢的な姿勢をとった。司馬懿はこれを見て、すぐに軍を撤退させ、陣地に戻って持ちこたえました。蜀軍は司馬懿を脅かし、静かに退却した。 司馬懿は蜀軍が撤退したことを知り、蜀軍が残した軍営を視察して諸葛亮が死んだと確信した。しかし、このとき司馬懿が軍を派遣して蜀軍を追撃したが、もはや追いつくことができなかった。こうして、「死んだ諸葛亮が生きている中大を追い払った」という物語が残された。司馬懿はこの話を聞いても怒らず、自嘲的に「生を予言することはできるが、死を予言することはできない」と言った。 2. 司馬懿はなぜ諸葛亮を恐れたのですか? 司馬懿が諸葛亮を恐れたのは、諸葛亮の第五次北伐に由来するものではないと一般に考えられている。諸葛亮が開始した第四次北伐の際、司馬懿は諸葛亮に対する戦術のせいで部下から批判された。これらの部下の中で、最も強く反応したのは張郃でした。 司馬懿が魏軍を率いて諸葛亮の蜀軍と戦ったとき、彼が採用した戦術は諸葛亮の蜀軍を追跡し、遠くからそれを封じ込めることだった。諸葛亮が司馬懿と戦おうとしたときはいつでも、司馬懿は兵舎を守り、反撃しませんでした。このような戦いが何度も続いた後、司馬懿の兵士たちは耐えられなくなり、戦いに出ることを要請した。司馬懿は諸葛亮を虎のように恐れていたとさえ言われ、世間は彼を嘲笑した。司馬懿は戦争に赴くしかなかったが、呂城の戦いで惨敗を喫した。 結局、食糧と草が枯渇したため諸葛亮は軍隊を撤退させざるを得なかった。このとき、司馬懿は戦わずに抑える戦略に変更した。彼は戦う意志のない張郃を諸葛亮の追撃に派遣した。その結果、張郃は木門路で諸葛亮に待ち伏せされ、射殺された。この事件は司馬懿に深い教訓を与え、彼に精神的トラウマを残した。 実際、諸葛亮の戦術の多くは蜀軍独特のものでした。これらの戦術は劉備の時代から受け継がれ、戦争でテストされ、効果的であることが証明されています。例えば、退却中に敵を反撃するというこの戦術は、諸葛亮が駆け出しの頃、博旺坡で劉備が諸葛亮に実演したものです。当時、曹操は夏侯惇を率いて劉備を攻撃させ、両者はしばらく対峙していた。そこで劉備は陣営を焼き払い、撤退するふりをした。夏侯惇が軍を率いて劉備を追撃したとき、突然劉備に攻撃され敗北した。 これらすべては、当時駆け出しの諸葛亮に深い印象を残したに違いありません。彼は北方遠征の際にもこの戦術を適用し、毎回成功しました。諸葛亮は第二次北伐の際、食料が尽き、敵の援軍が到着しようとしていたため陳倉を占領できず、軍を率いて撤退した。魏軍の猛将、王爽は軍を率いて諸葛亮を追撃したが、諸葛亮に敗れて殺された。諸葛亮の第四次北伐の際、彼はこの戦術を使って有名な将軍張郃を殺害した。 諸葛亮がこの戦術を完璧に使いこなしたと想像できます。張郃は曹操の五大将軍の一人として、長い間戦場にいて、戦場の地形を非常に注意深く観察していました。こうしたベテランを捕らえるのは容易なことではない。この待ち伏せ攻撃で諸葛亮が使った創意工夫は想像に難くない。司馬懿が最も恐れていたのは、諸葛亮の退却と反撃の戦術を全く知らなかったからである。 3. 死んだ諸葛亮が生きている中大を怖がらせた理由の真実。 実際、諸葛亮の第四次北伐の時期には、彼の軍事思想は成熟し、また、司馬懿が諸葛亮をよく知るようになった時期でもありました。諸葛亮は管仲や岳毅と自分を比べていましたが、文武両道の才能に恵まれた人物でした。しかし、劉備は配下に多くの軍事的才能を持っていたものの、国を統治する才能が欠けていた。そのため、劉備の時代には、十分な食料と兵士を確保するために諸葛亮の国家統治能力にさらに頼り、地方を統治させました。 劉備が死ぬまで、北伐における蜀漢の二大勢力は、度重なる悲惨な敗北によりほぼ完全に失われていた。この時、劉備は諸葛亮を近衛警視に任命し、軍事力を掌握し始めた。白帝城の孤児の信頼を受け入れた諸葛亮は、期待に応えて新たな蜀軍を育成した。諸葛亮はこの軍を率いて中国南部と中央部を征服し、北部の曹魏を攻撃し、軍事的キャリアをスタートさせた。 諸葛亮は高い軍事的資質を備えていたが、理論はまだ実践されていない。諸葛亮の最初の3回の北伐では多くの挫折を経験しましたが、それによって彼の戦闘能力も向上しました。第四次北伐以降、諸葛亮の軍事力は質的に飛躍し、成熟し始めた。司馬懿が諸葛亮と出会ったのはこの頃であった。 司馬懿は諸葛亮の第四次北伐に抵抗していたとき、諸葛亮の軍風を観察し、それに基づいて独自の戦略を構築していました。洛城の戦いの後、彼は諸葛亮の軍隊の戦闘力を目の当たりにし、諸葛亮と正面から戦わないことを決意した。諸葛亮が食糧不足で軍を撤退させた後、彼は諸葛亮の兵站上の困難を利用して、諸葛亮と補給消耗戦を行う戦略を決定した。諸葛亮が軍を撤退させているとき、司馬懿は、軍を撤退させている間に諸葛亮を追撃するという自身の最後の戦略を実証するために、張郃に軍を率いて追撃するよう強く主張した。 こうして、諸葛亮の第四次北伐との対決後、司馬懿は諸葛亮の第五次北伐に対抗するための戦略を立てた。それは「堅固な守りで城を守り、相手の攻勢を鈍らせる。前進できなければ、食糧が尽き、略奪しても何も得られないので、必ず逃げる。逃げたら追撃する。これが完全な勝利への道である」というものだった。司馬懿は諸葛亮の第五次北伐に抵抗する際にこの戦略を忠実に実行し、最終的な勝利を収めたことがわかります。彼は自分の立場を守り、出撃を拒否したが、諸葛亮が亡くなり、蜀軍は撤退を余儀なくされた。 しかし、この戦略において、司馬懿は他の部分については完全に自信を持っていた。唯一確信が持てなかったのは、最後の点、つまり逃げて追撃することだけだった。諸葛亮率いる蜀軍の独特な退却・反撃戦術が、彼にとって理解しがたいものだったからだ。張郃の死という代償を払っても、司馬懿は追撃すれば蜀軍は騙されるだろうという情報を得ただけで、それ以上は何も得られなかった。こうなると、司馬懿のいわゆる完全勝利は達成しにくいだろう。 このため、司馬懿は蜀軍を追撃する際に非常に不安を感じていた。慌てて軍を派遣したため、蜀軍が残した陣地を偵察することができなかった。これにより、蜀軍の撤退に疑念を抱くようになった。諸葛亮が本当に病気で亡くなったのなら、それはそれでいいのですが、もし諸葛亮が昔の悪行を繰り返したなら、夏侯惇、王爽、張郃のような結末を迎えることになるでしょう。 まさにこの精神があったからこそ、司馬懿が蜀軍に追いついたとき、蜀軍の厳重な陣形を見て、諸葛亮の死についても全く慌てなかったのです。司馬懿の最初の結論は、諸葛亮に騙されたということだった。司馬懿は予期せぬ損失を避けるため、すぐに軍を撤退させ、安全な陣地に戻った。 結論: 諸葛亮の5回目にして最後の北伐の際、彼は司馬懿と長い戦いを繰り広げた。両者は戦場で競い合うだけでなく、意志を貫いて戦いました。結局、諸葛亮が五丈原で病死したため、蜀軍は撤退を余儀なくされ、司馬懿が勝利した。 しかし、司馬懿は完全な勝利を収めることはおろか、蜀軍を追撃するという任務を達成することもできなかった。これは蜀軍の撤退と反撃の戦術を恐れ、攻撃を受けることを恐れたためである。しかし、最大のライバルである諸葛亮の死は彼に安堵感も与えた。蜀軍の最大の攻勢はここで終わり、曹魏は最大の脅威から解放された。このような気分だったので、司馬懿は「死んだ諸葛亮が生きている中道を追い払った」という他人の嘲笑に直面しても冷静さを保つことができた。 |
<<: 孫尚香と劉備の結婚生活は短かったのに、なぜ子供が残らなかったのでしょうか?
>>: 荊州が東呉に占領されたのは本当に関羽の不注意によるものだったのだろうか?
推薦する
『徐州を通過』の著者は誰ですか?どのように鑑賞すればよいでしょうか?
徐州を通過沈徳謙(清朝)池や沼は至る所に水で満たされ、何百マイルにもわたって平原は枝垂れ柳で覆われて...
文廷雲の『南湖』:詩は平易で斬新であり、文体は優雅で美しい
文廷雲は、本名は斉、雅号は飛清で、太原斉県(現在の山西省)の出身である。唐代の詩人、作詞家。彼の詩は...
「良いことがやってくる:ペンコウから船を戻そう」の原文は何ですか?これをどう理解すべきでしょうか?
良いことが起きる。船は彭口から解放される陸游(宋代)我々は潭口から出航して帰国し、夕暮れ時に三花州に...
北宋時代の程浩が書いた「春日折詩」は詩人の内なる誇りと喜びを表現している。
程昊は、号を伯春、号を明道といい、通称は明道氏。北宋代に朱子学を創始した。弟の程毅とともに「二人の程...
2月2日の漢民族の祭りの起源について簡単に紹介します
2月2日は古代では中和節と呼ばれ、一般的には龍が頭を上げる節句として知られています。民間伝承によると...
なぜテナガザルは単純ではないのでしょうか?真実とは何でしょうか?
『西遊記』では、花果山は東勝神地の奥来国にあります。花果山は多くの種類の猿を生んだ仙人の山であり、そ...
林黛玉の父、林如海の正体とは?
林黛玉の父、林如海の正体とは?興味深い歴史編集者が関連コンテンツをお届けします。興味のある方はぜひご...
ミャオ族の詩文化の紹介 ミャオ族の詩のスタイルとは?
ミャオ族の詩は、一般的には親しい親戚や友人に挨拶したり見送ったり、男女の愛情を表現したり、さらには仲...
麩は昔からとても人気がありました。では、有名な麩と呼べるものは何でしょうか?
中華民族には約5000年の文化があり、その中には優れた詩歌が数多く存在します。特に『中国古詩八大名詩...
「南京鳳凰塔登頂」は李白によって書かれた文学史上珍しい鳳凰歌である。
李白(701年 - 762年12月)は、太白、清廉居士、流罪仙とも呼ばれ、唐代の偉大な浪漫詩人です。...
林黛玉は苦味に欠けることはないが、なぜ最も金銭の匂いが欠けているのだろうか?
『紅楼夢』は、中国古代の章立て形式の長編小説で、中国四大古典小説の一つです。普及版は全部で120章か...
西魏の恭帝袁括の妻は誰?袁括の妻と数人の王妃の紹介
西魏の恭帝拓跋括(537年 - 557年)は鮮卑人。中国名は袁括。西魏の文帝袁宝舒の4男で、西魏の非...
陳良の『典江口・梅月頌』は「一言も言わずともその優雅さが表現されている」傑作
陳良(1143年10月16日 - 1194年)は、本名は陳汝能で、同府、龍川とも呼ばれ、学者たちは彼...
夜鹿紅基の紹介 夜鹿紅基と小鋒の関係とは
耶律洪基は遼王朝の第8代皇帝であり、号は聶林であった。彼は46年間統治し、裏切り者の大臣を任命し、女...
『紅楼夢』の『葦と雪』の詩の競争で、王希峰はどのような詩を語ったのですか?
王希峰は『紅楼夢』の登場人物であり、金陵十二美女の一人です。今日は『おもしろ歴史』編集者が新たな解釈...