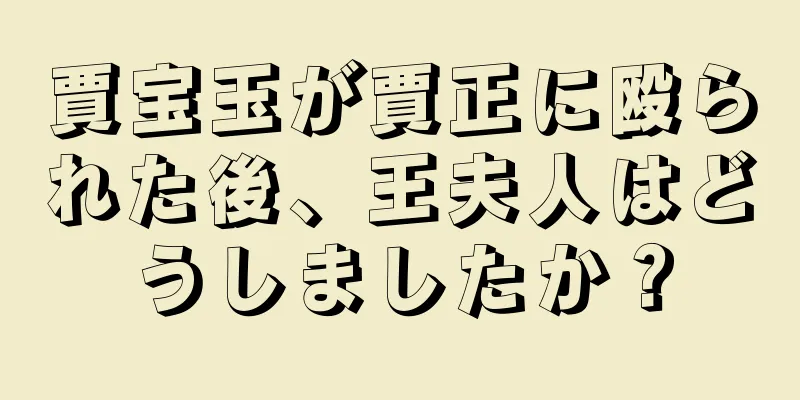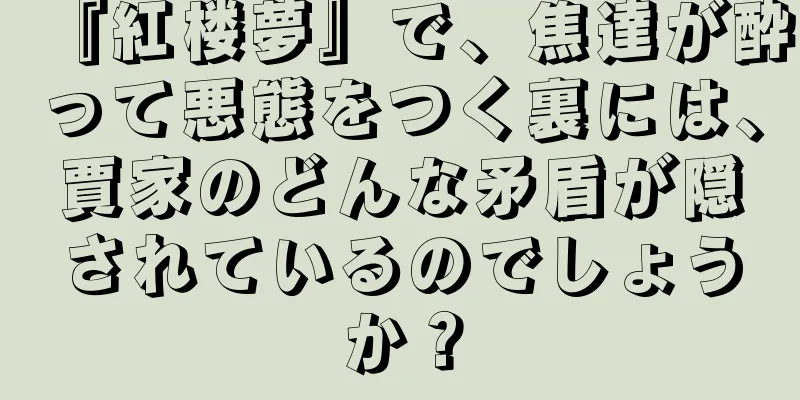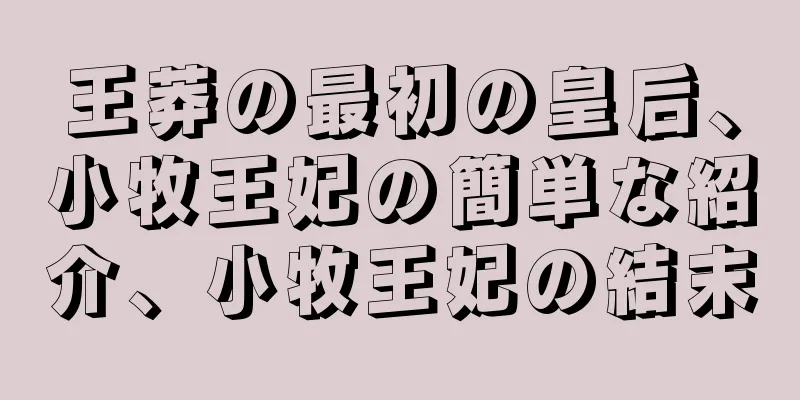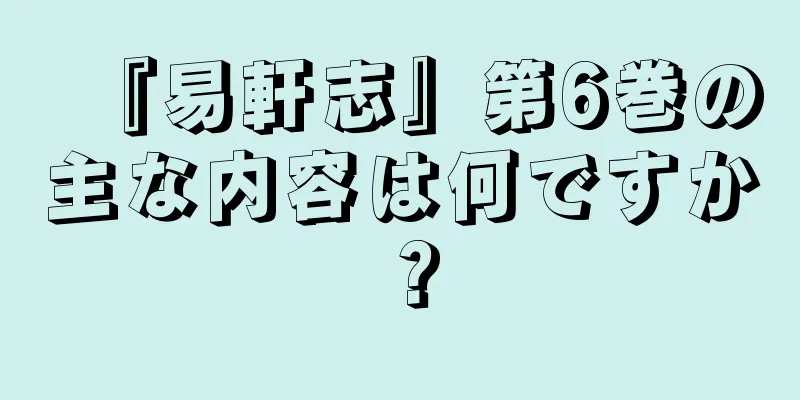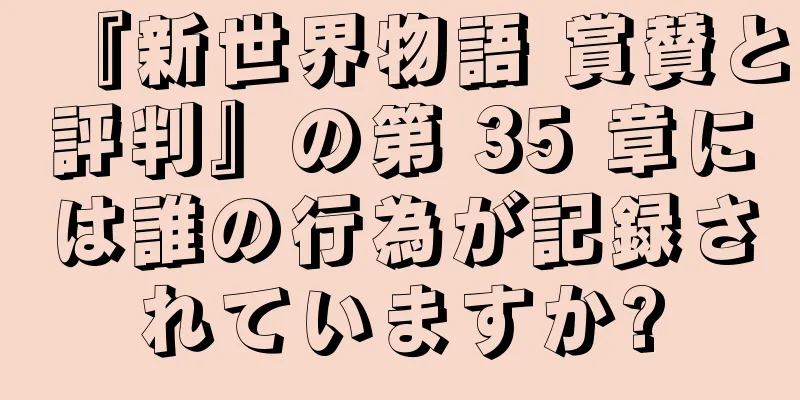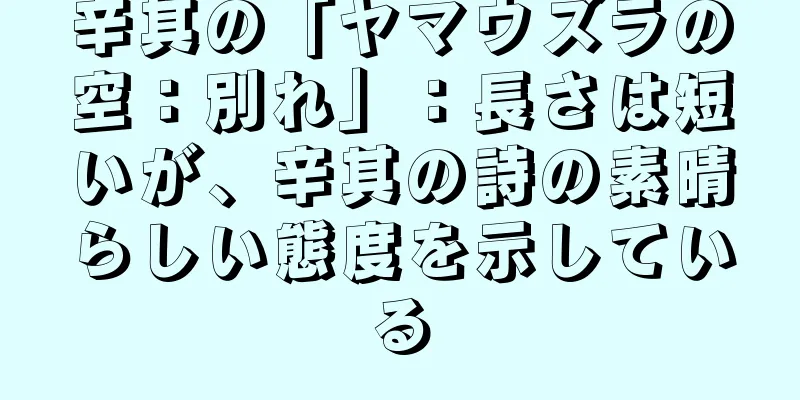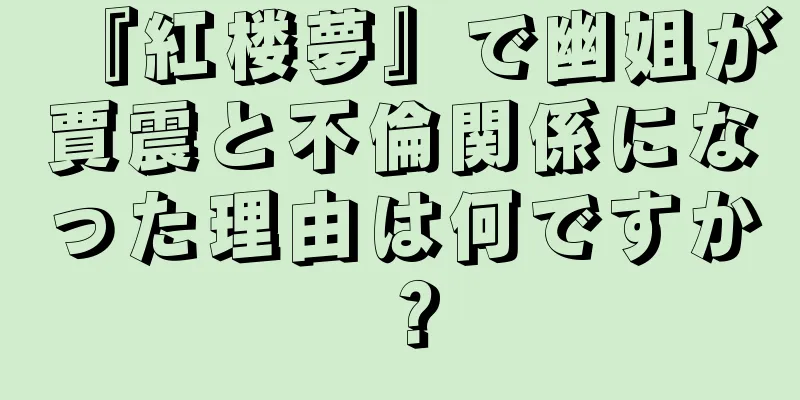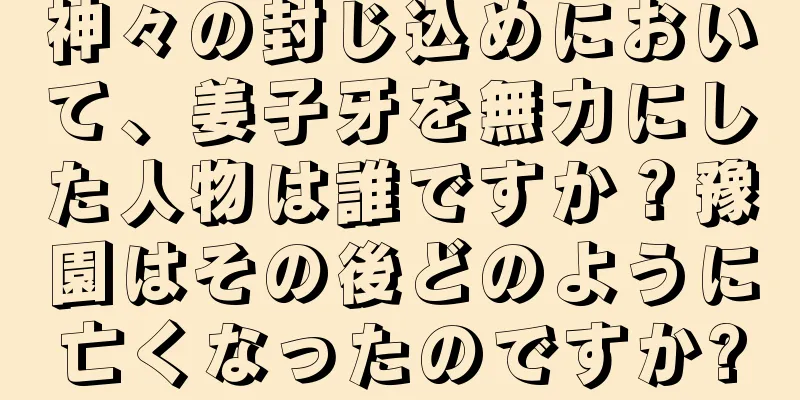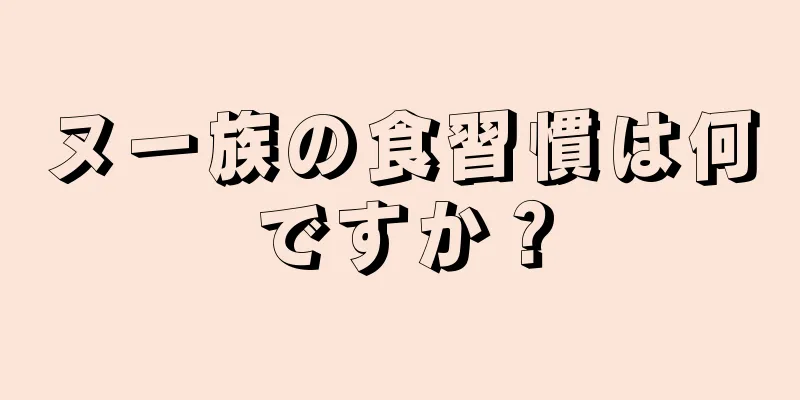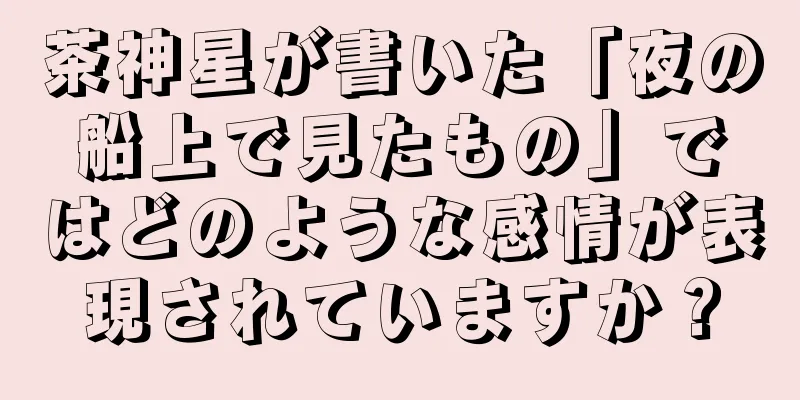歴史上の古代人はなぜ「歩く」ことができなかったのでしょうか?
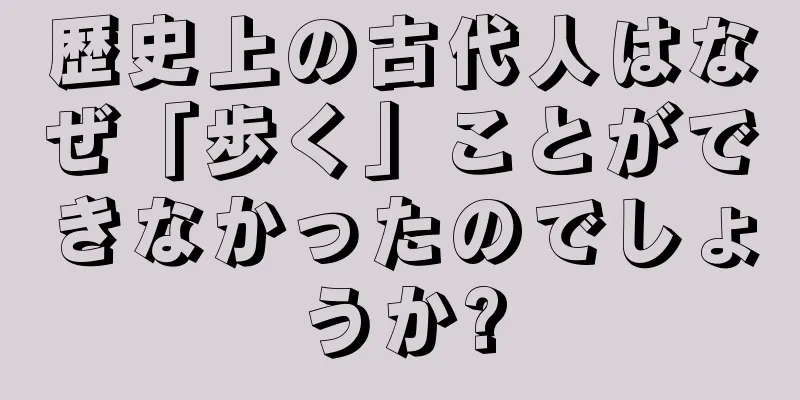
|
今日のタイトルはちょっとパーティーっぽいですね、ハハ、わざとミステリアスにしてるんです。古代人は歩けなかったので、皆足が不自由になったり麻痺したりしたのではないでしょうか。 「歩く」ことができないというのは、古代の人々が「歩く」という言葉に出会ったとき、それを「走る」に変えたという意味です。 「舒文」には「歩くことは急ぐことである」とある。「越える」とは「走る」という意味である。 『孟子・梁徽王尚』:「武器がぶつかったとき、彼らは鎧と武器を捨てて逃げた。」 『山海経・海外北経』:「卯弗は太陽を追いかけた。」 『韓非子・五蟲』:「ウサギが走って切り株にぶつかり、首を折って死んだ。」 杜甫の『世浩暦』:「老人は壁を乗り越えて逃げ、老婆は見物に出かけた。」 など。ここでの「走」は「走る」または「逃げる」を意味します。 「ゾウ」は甲骨文字で、人が腕を振りながら走り出す様子を象った象形文字です。銅銘「走」は上部は甲骨文字と同じで、下部に「止」という文字が追加されている。「止」は足を意味し、足で走ることを強調し、象形文字的要素を加えている。小篆字の形は銅銘と全く同じであるが、楷書体になった際に上部が「土」と誤認され、本来の象形文字の意味を失ってしまった。しかし、「走」はやはり「跑」を意味しており、そうでなければ「走马观花」の「走」は説明できません。 古代では「走」は「跑」を意味していましたが、古代では「走」の代わりに何が使われていたのでしょうか。 「ステップ」に置き換えられます。古代では、「歩く」は名詞ではなく、「歩く」という意味の動詞でした。 『朔文街子』には「歩む」とある。『礼記 供犠』には「小さな一歩を忘れずに歩くのが親孝行である」とある。『戦国策 斉の四策』には「遅く食べるのは肉の代わりに、ゆっくり歩くのは車に乗る代わりに」とある。『左伝 相公二十六年』には「私は婦人の馬と足を見た」とある。また「落ち着いて歩く」「徒歩で歩く」「歩兵」「人の足跡をたどる」「立ち止まる」「警戒を固める」など、現在でも使われている表現もある。ここでの「歩」はすべて「歩く」という意味である。 宋代にはすでに「zou」は「歩く」という意味を持っていました。例えば、蘇東坡の『小篆般若心経讃』には「突然大篆と小篆を書けと言われ、まるで壁に向かって歩いているようだった。たとえ大まかに覚えたとしても、筆を上げて探したいほどだった」とある。元代の李星道の『灰壁記』には「彼はかなり前から私の家の周りをうろついていた。私の娘に好意を抱き、しばしば妾として結婚したいと望んでいた」とある。『二科派安経記』巻17には「お嬢様は男装をしているが、二人の男と一緒に歩くのは非常に不便だ」とある。これらの「走」には「跑」の意味はないが、「走る」が「歩く」として広く使われるようになったのは明代からであると思われる。 明代以降、「走る」は「歩く」という意味だけでなく、より広い意味を持つようになりました。例えば、『西遊記』では「古い諺が広まったのではなく、一体何が起こっているのか!」とあります。『沈農書』では「溝は深すぎると肥料が流れて行かなくなる」とあります。ここでの「失う」という言葉は「漏れる」または「失う」という意味です。また、現在では「親戚を訪ねる」「母の家を訪ねる」「移動する」といった言葉も使われるようになり、誰かが亡くなったときには「去る」といった言い方もされるようになりました。こうした「歩く」という言葉は、長い間「走る」という意味を少しも失っています。つまり、「走る」という言葉の出現によって、何千年もの間「走る」ことであった「歩く」という言葉に、本当の目的地が与えられたのです。 |
<<: 三国志演義ではなぜ五虎将軍の子孫として張飛の息子である張宝が重視されているのでしょうか?
>>: 関羽は呂布に会ったときなぜそれほど控えめで、敬意を込めて呂布を「呂将軍」と呼んだのでしょうか?
推薦する
中国のスパイス文化には長い歴史があります。体に塗る以外にどんな用途があるのでしょうか?
私の国のスパイス文化には長い歴史があります。スパイスは体に塗る以外にどんな用途があるかご存知ですか?...
音とリズム入門第4巻:ハオの原文の鑑賞と注釈
剣がナイフと対になっているように、琴はハープと対になっています。空に比べて地球は広大で高い。高い帽子...
三国時代の魏の将軍、胡尊の簡単な紹介。胡尊の功績と死に様
胡尊は、漢代建安11年(206年)に冰申(ひんしん)に生まれ、安定臨井(現在の甘粛省鎮遠南部)の人で...
『漢江に浮かぶ』は王維によって書かれたもので、詩人が絵画技法を詩に融合させた傑作と言える。
王維(701-761)、字は墨傑、字は墨傑居士。彼は河東省蒲州市(現在の山西省永済市)に生まれ、祖先...
もし清朝が存在しなかったら、中国にはこれらの 3 つの場所があったかもしれません。それはどの3つですか?
今日は、Interesting Historyの編集者が、もし清朝が存在しなかったら中国はどうなって...
「紅楼夢」で賈一家は皇帝の疑いを避けるために何をすべきでしょうか?
『紅楼夢』では、賈一族の没落が一連の悲劇を引き起こした。賈一族の没落により、金陵十二美女の人生は基本...
『西遊記』の火焔山はどのようにして生まれたのでしょうか?なぜ孫悟空はそれを消滅させたかったのでしょうか?
孫悟空は魔法の石から変身し、並外れた才能に恵まれました。彼は四大古典の一つである『西遊記』に登場しま...
宋江が居易殿を中義殿に改めたことの意味は何ですか?
『水滸伝』は主に北宋末期に宋江率いる108人の英雄たちが山東省の涼山湖に集まる物語を描いています。ま...
『西遊記』の小さなワニの起源は何ですか?彼の最終的な結末はどうだったのでしょうか?
『西遊記』のブラックウォーター川には、リトルアリゲーターという魔法の生き物がいます。本日は、Inte...
唐代の僧侶、宜興師:天文暦アルゴリズムの達人
歴史上、宜興師について紹介されているものは非常に多いです。記録によれば、宜興法師は683年に生まれ、...
古典文学の名作『夜船』:仏教の九宗(1)全文
『夜船』は、明代末期から清代初期の作家・歴史家である張岱が著した百科事典である。この本は、あらゆる職...
カラハン朝:我が国の極西にある分離主義政権
カラ・ハン朝(カラ・ハン朝)は、古代イランの最西部に存在した地方の分離主義政権であった。全盛期には、...
関羽はたった1ラウンドで華雄を倒した。なぜこんなに差が大きかったのか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
東漢時代に宦官集団はどのようにして出現したのでしょうか?姻族と宮廷関係者の間ではどのような役割を果たすのでしょうか?
東漢時代に宦官集団はどのようにして台頭したのでしょうか。次の Interesting History...
宋代の女性はなぜ「河東獅子」になることを敢えてしたのでしょうか?河東ライオンとは何ですか?
宋代の女性は実に幸運でした。何らかの技能を身につければ職場の人気者になることができました。これは、差...