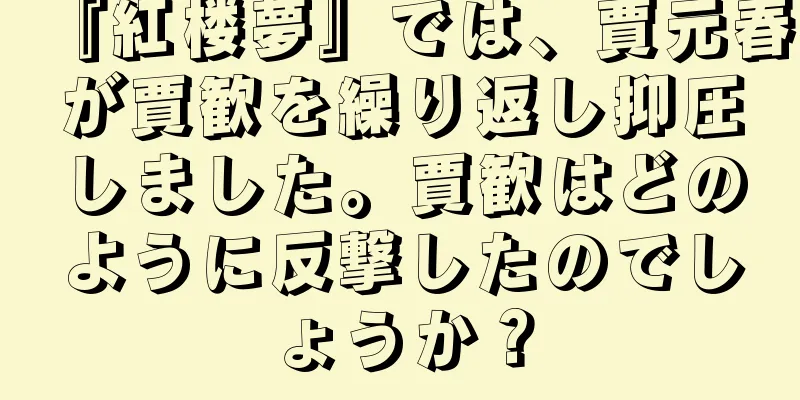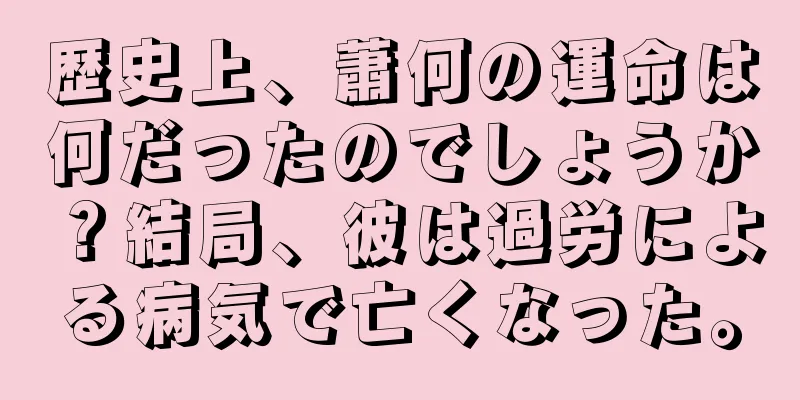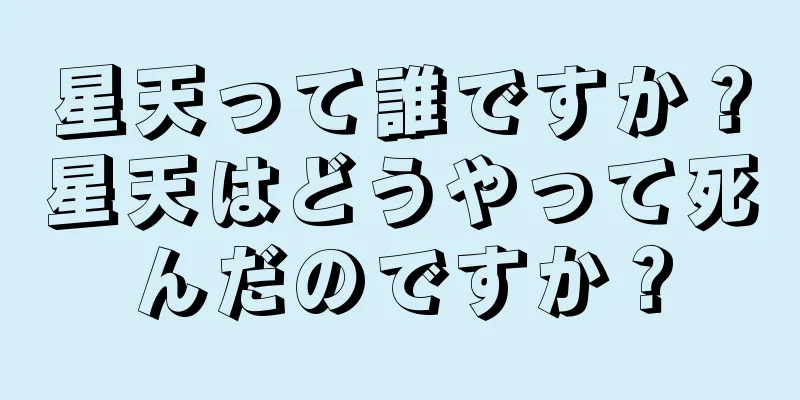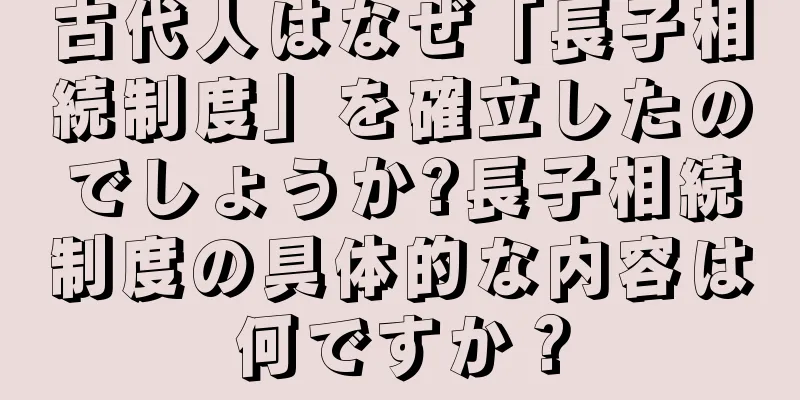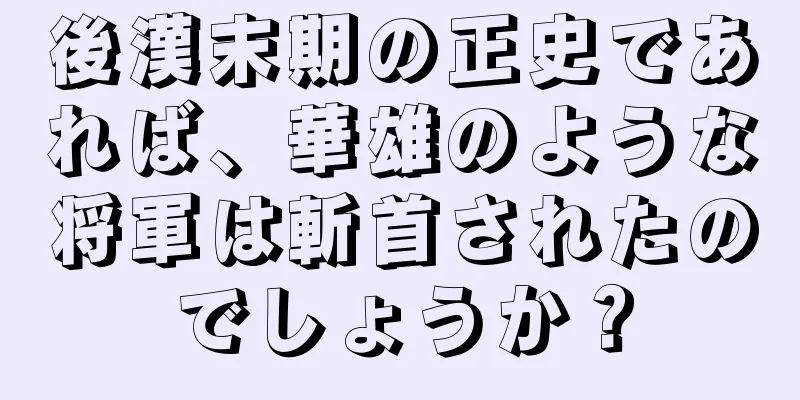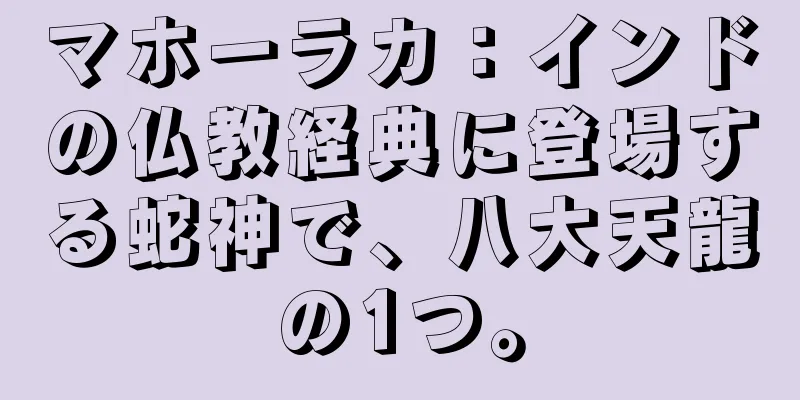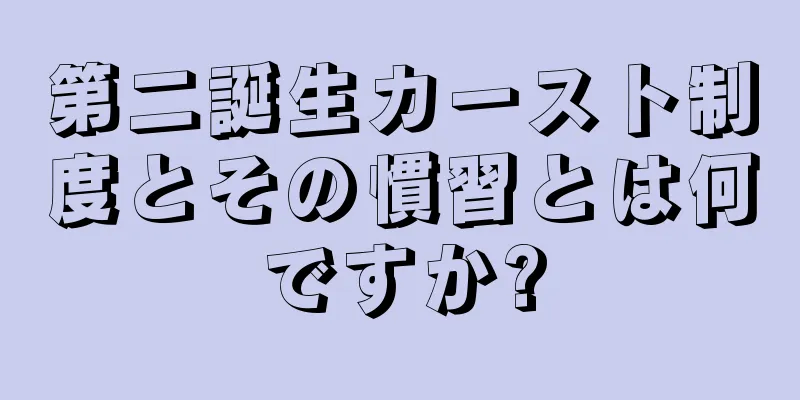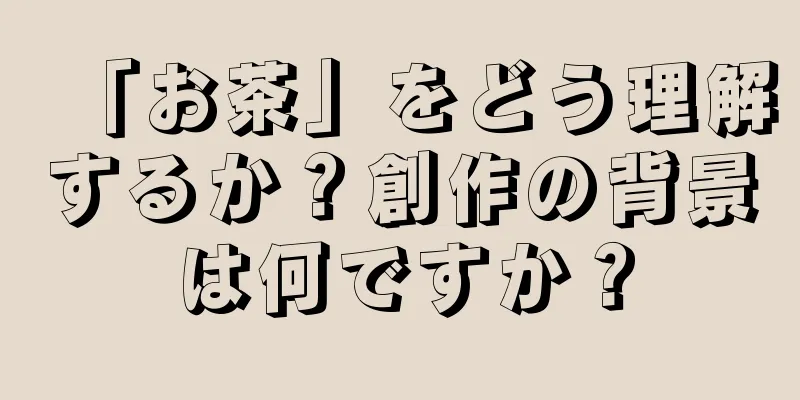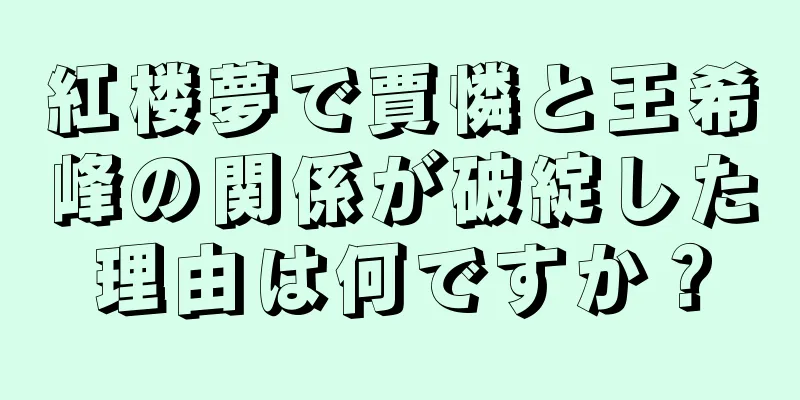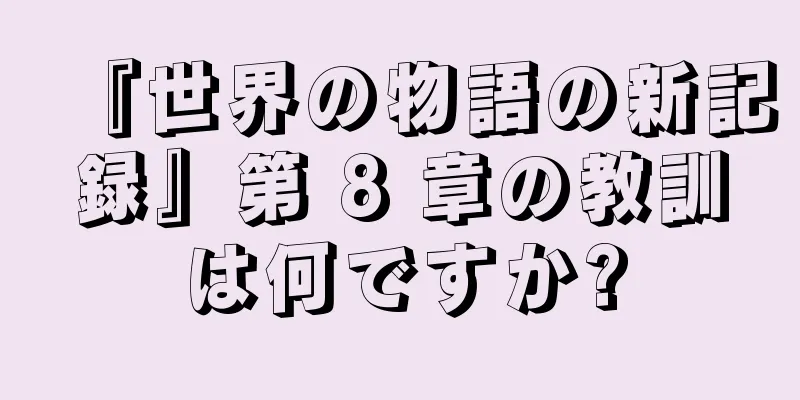ブイダンスの特徴は何ですか?
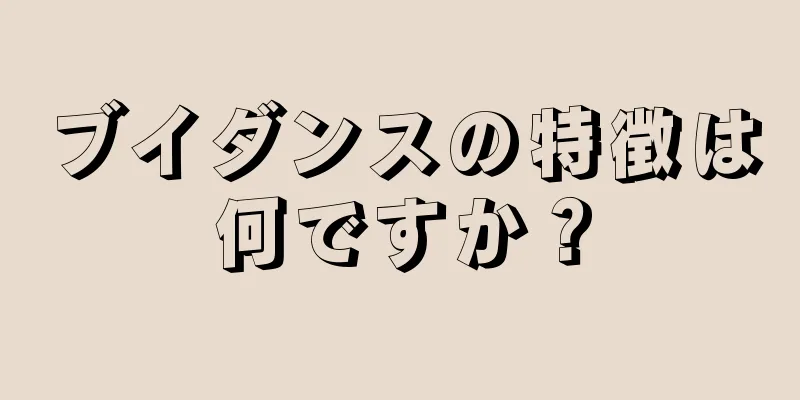
|
歌と踊りが得意なブイ族は、色彩豊かなブイ文化を創り上げてきました。ブイ族の人々は、畑仕事をしているときでも日常生活の中でも、歌ったり踊ったりして自分の気持ちを表現するのが好きです。ブイ族には、移行ダンスという非常に重要なダンスがあります。 遷移ダンスには深い歴史的ルーツがあり、その文化的遺産は計り知れません。それでは、編集者と一緒に、民族色の強いブイ遷移ダンスを見てみましょう。 ブイ族の移行ダンスは、ブイ語で「レウ」と呼ばれ、貴州省ツェヘン県のブイ族の村で人気のある伝統的なダンスです。毎年旧暦1月13日から15日まで、ブイ族の村々の老若男女が最高の衣装を身にまとい、村の天日干し場に集まって輪舞を披露します。伝統的なパフォーマンスプログラムの観点から見ると、犠牲、教師のオープニング招待、状況パフォーマンス、シーンの移行という 4 つの側面が含まれます。移行ダンスには今日まで受け継がれてきた 8 つの伝統的な動きがあります。 伝説によると、清朝の康熙帝の治世中、臥衡潘村の村長であった王宝才は村人を率いて侵略者を撃退し、村長となったが、その後、民衆を頻繁に抑圧し、彼らの生活を不可能にした。康熙帝の治世48年の真冬、皆が憎しみから村長の家を焼き払った。彼らはとても幸せで、手をつなぎ、火の周りで歌ったり踊ったりしていました。その後、彼らは踊りを始める前にまずバオサイ王に供物を捧げるようになりました。300年にわたる進化の過程で、いつからかは不明ですが、この踊りは徐々にチェヘンゲのブイ族の村に広まっていきました。 移行ダンスは、トゥシ制度下のブイ族の村々の闘争から生まれたダンスです。このダンスは情熱的で自由奔放であり、緊張とリラックスのバランスが良く、パフォーマンスの可能性も高いです。春の耕作が近づくと、ブイ族の人々は畑の踊りを披露して縁起の良い儀式を行い、神々に祈りを捧げ、翌年の農作業の順調さと豊作を祈ります。ブイ族の人々は、ダンスを披露することで、自分たちの歴史、文化、習慣、習慣を楽しく学び、感謝、尊敬、団結についての教育を受けることができます。 遷移舞踊には、ブイ族の信仰、社会礼儀、生活態度、道徳観念、教育方法などの多くの要素が含まれており、ブイ族の歴史と文化、民俗、民族、舞踊などの分野にとって重要な研究価値があります。遷移舞踊を保護し継承することは、地元のブイ族の民族的自尊心、自信、誇りを確立し、調和のとれた社会を構築する上で大きな意義があります。 現在、ブイ族の転換舞踊は儀式舞踊から徐々にブイ族に親しまれている美的娯楽舞踊へと変化し、県内の16の小中学校でブイ族の転換舞踊が継承・保護されており、「1万人ブイ族転換舞踊」を主催して「上海世界ギネス記録」を樹立するなど、ブイ族地域に大きな影響力を持っています。しかし、全体的な環境の影響により、現在では後継者不足や絶滅の危機に直面しています。 |
<<: 旧頤和園の碧通書院はどこにありますか?具体的な用途は何ですか?
>>: 旧頤和園の慈雲普虎はどこにありますか?具体的な用途は何ですか?
推薦する
「結婚」という言葉はどこから来たのでしょうか?古代のさまざまな時代の結婚制度はどのようなものだったのでしょうか?
「結婚」という言葉はどのようにして生まれたのでしょうか?古代のさまざまな時代の結婚制度はどのようなも...
南北朝時代の衣服:古代中国の衣服史における大きな変化の時代
南北朝時代は古代中国の服装史において大きな変化があった時期であり、この時期に大量の胡人が中原に移住し...
白露節気中には何を食べたらよいでしょうか?関連する詩は何ですか?
白鹿は二十四節気のうち15番目の節気であり、自然界の寒気が増すことを反映する重要な節気です。次の I...
冬至の時期の北と南の食習慣の違いは何ですか?これらの食べ物にはどんな意味があるのでしょうか?
中国文化は広く奥深いと言われています。数千年にわたる歴史的発展を経て、北と南の伝統的な文化の違いもか...
西梁の孝逵皇帝には何人の息子がいましたか?孝逵の子供は誰でしたか?
蕭逵(542-585)、愛称は仁元、西涼の宣帝蕭昭の三男であり、南北朝時代の分離独立政権である西涼の...
『紅楼夢』で秦克清の葬儀に向かう途中に現れた農家にはどんな意味があるのでしょうか?
『紅楼夢』は、中国古代の章立ての長編小説で、中国古典四大傑作の一つです。多くの読者が気になる問題です...
「蝉」は李尚胤が書いた詩です。表面的には蝉についての詩ですが、実際は李尚胤自身についての詩です。
李尚鑫(813年頃 - 858年頃)は、字を易山、号を毓曦生といい、淮州河内(現在の河南省沁陽市)の...
水滸伝の涼山における胡三娘の順位は何位ですか?彼女の人生はどうだったのでしょうか?
胡三娘は『水滸伝』の登場人物で、涼山の三人の女将軍の一人である。次に、『Interesting Hi...
明朝の万暦帝の治世中に起こった三大軍事作戦は何でしたか?
万暦三大遠征は、明代、万暦帝の治世中に起こった。この戦いにより中国の領土は強化され、明王朝の東アジア...
孫尚香と劉備の関係はどのようなものですか?それは小説に書かれているほど深い意味があるのでしょうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
『紅楼夢』では、ジェン・シーインのジャ・ユークンへの投資は価値がある
「紅楼夢」では、甄世銀と賈玉村が出会ったのは、賈玉村がまだ無名だった頃です。甄世銀は賈玉村に投資しま...
明代末期の随筆集『生因為』第4巻、御蔵『詩韻』全文
『聖陰余』は、明代末期の著名な学者陸坤(1536-1618)が書いた引用や格言の形式の短いエッセイ集...
唐代の春の田園詩をどう鑑賞するか?王維はどのような感情を表現したのでしょうか?
唐代春田園画 王維、次の興味深い歴史編集者が詳細な紹介をお届けしますので、見てみましょう!屋根の上で...
封建制度には多くの欠点があったのに、なぜ周王朝の封建制度は800年もの間その基盤を維持できたのでしょうか。
封建制度には多くの欠点がありました。前漢の七王の乱、西晋の八王の乱がありました。ではなぜ周の封建制度...
魏索制度はなぜ明朝の繁栄の基盤を築いたとも、明朝を滅ぼしたとも言われているのでしょうか。
魏索の概念を最初に提唱したのは、元代の歳入大臣である張昌であった。明の洪武17年(1384年)、全国...