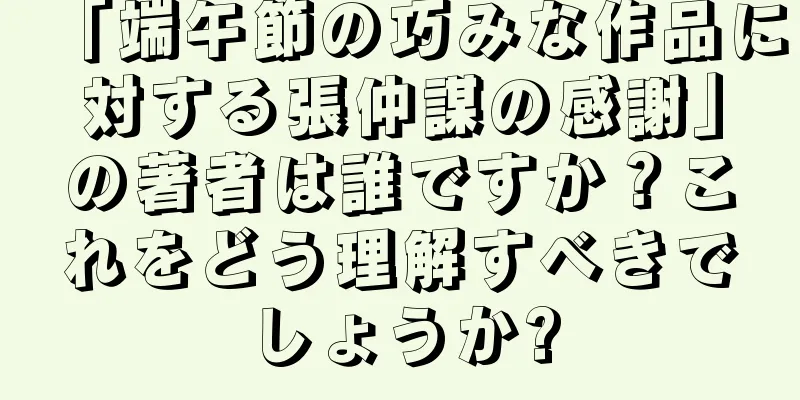白居易の『曲江秋二詩』の本来の意味を鑑賞する

|
古詩「曲江の秋の詩二首」 時代: 唐代 著者: 白居易 元和二年秋、私は三十七歳でした。長慶二年の秋、私は五十一歳でした。 その間の14年間のうち、彼は6年間追放されていました。富と貧困、名誉と不名誉はすべて外部要因に依存します。 そこで先生は、湘江で再び屈原を弔うために遠くの廬山へ行きました。夜には悲しげな竹の音を聞き、秋の波が消えていくのを眺めましょう。 私は最近巴県の印璽を辞任し、現在は宮廷での仕事に戻っています。遅れて会う意味があるのか?私の白い髪が赤い帯に映っている。 古い精神を取り除き、古い外見を変えます。秋の曲江だけは、風も煙も以前と同じです。 南岸の草はまばらで、木々は西風にざわめいている。秋が来るとすぐに、セミがまた鳴き始めます。 草は平らで緑で、蓮は露で覆われています。今日外を見ると、例年通りの秋の気配を感じます。 池の水はそのままで、街の上の山々もそのままです。以前は黒かったこめかみの毛だけが白くなりました。 名誉と名声は朝と夕のように違う。運命が来ようとしたとき、年齢も容姿もすでに消え去っている。 春に幸せでなければ、年をとったときに失敗にショックを受けるでしょう。そこで私は自分の気持ちを表現した詩を作り、それを曲江路に刻みました。 |
<<: 白居易の詩「霊公南荘の花柳は満開。まずは盗んで鑑賞したい、詩を二首送る」の本来の意味を鑑賞する
>>: 白居易の詩「新豊の腕折れ老人 国境問題に対する警告」の本来の意味を理解する
推薦する
なぜ唐代が最も開放的だったと言われるのでしょうか?唐の時代はどのような開拓だったのでしょうか?
なぜ唐王朝は最も開かれた王朝なのでしょうか?次の興味深い歴史編集者が詳しく紹介しますので、見てみまし...
清朝の歴史を見ると、なぜ長男のほとんどが王位を継承できなかったのでしょうか?
清朝は中国史上最後の封建王朝であり、皇帝は全部で12人おり、その統治者は満州族の愛新覚羅氏族であった...
白居易の詩「江楼から夕を眺めて客を招く」は杭州郊外の繁栄した風景を描写している。
白居易は、字を楽天といい、別名を向山居士、随音献生とも呼ばれた。写実主義の詩人で、唐代の三大詩人の一...
「旅を偲ぶ三つの詩」をどう理解するか?創作の背景は何ですか?
過去の旅についての3つの詩杜牧(唐代)私は10年間、支配の輪の外で暮らしてきましたが、私自身のワイン...
爆竹の起源:私の国で爆竹を鳴らす習慣はどこから来たのでしょうか?
爆竹の起源:私たち中国人は、春節になると昔から通りや路地で爆竹を鳴らす習慣がありました。大都市の繁華...
李和の有名な詩の一節を鑑賞する:孤独で寂しい人に一杯の酒を、主人は客に長寿を与える
李和(790-816)、雅号は昌吉とも呼ばれる。彼は河南省富昌県長谷郷(現在の河南省益陽県)に生まれ...
潘熙白の「大有・舞台前」:この詩は作者が重陽の節句に秋の悲しみを表現するために書いたものです。
潘熙白は、雅号を懐古、号を玉荘といい、永嘉(現在の浙江省温州市)の出身である。南宋礼宗の宝有元年(1...
馮延思の「鶏連花:窓の外は寒く、夜明けは近づいている」:夫を恋しがる若い女性の苦しみを描写
馮延嗣(903-960)は、正忠、仲潔とも呼ばれ、南唐の丞相馮霊懿の長男であった。彼の先祖は彭城出身...
荘園経済とは何ですか?東漢の成立と滅亡の原因!
今日は、Interesting History の編集者が荘園経済とは何かをお伝えします。興味のある...
『紅楼夢』では、于世が率先して責任を取ったのに、李婉はなぜ責任を回避したのでしょうか?
『紅楼夢』は、中国古代の章立て形式の長編小説で、中国四大古典小説の一つであり、一般に使われているバー...
孫権が荊州を劉備に貸与することを望んだ主な理由は何でしたか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
哲学の名著『荘子』内篇 皇帝に答える(2)原文と口語訳
『荘子』は『南華経』とも呼ばれ、戦国時代後期に荘子とその弟子たちが著した道教の教義をまとめた書物です...
隋唐代史第49章:叔宝が景徳の肖像画を汚す
『隋唐代志』は、元代末期から明代初期にかけて羅貫中が書いた章立ての小説である。 『隋唐書紀』は瓦岡寨...
ジンポ族の結婚習慣の紹介
雲南省龍川県は、景坡族の主な居住地です。ここでは恋人同士が手紙を書くのではなく、物を使ってコミュニケ...
『鄭正君に贈る』の執筆背景は何ですか?これをどう理解すべきでしょうか?
「鄭正君に贈る」 文廷雲私は蘭の櫂を捨てて、ツバメや雁を追いかけました。かつて私は川や湖で謝公に会っ...