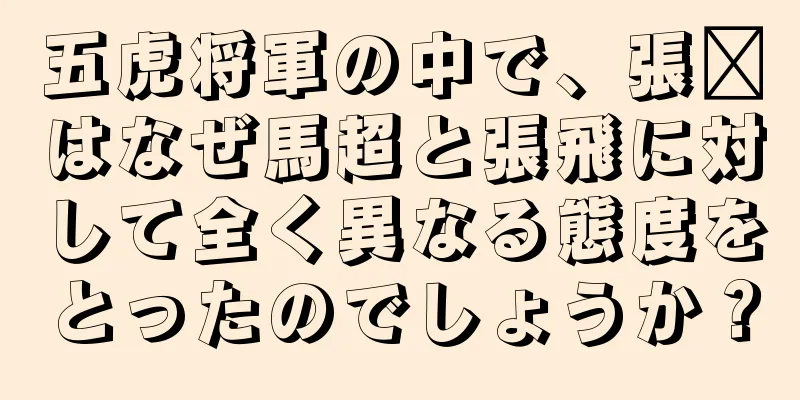孟子:梁慧王書第七章(上)原文、翻訳、注釈

|
『孟子』は儒教の古典で、戦国時代中期に孟子とその弟子の万璋、公孫周らによって著された。『大学』『中庸』『論語』とともに「四書」と呼ばれ、四書の中で最も長く、最後の書である。清代末期まで科挙の必修科目であった。 『孟子』は全部で7章から成り、孟子と他の学派との論争、弟子への教え、君主への働きかけなどが記録されている。彼の教義の要点は、性善説と老人の保護と道徳的統治である。 孟子、梁恵王第一章第七節 【オリジナル】 斉の宣王は「斉桓と金文の事について聞かせてもらえますか?」と尋ねた。孟子は答えた。「仲尼の弟子は桓と文の事について語らなかったため、後世の記録に残っていない。私は聞いたことがない。もし方法がない場合は、王が何と言ったのか教えてくれないか?」 彼は「どのような徳があれば王になれるのか」と尋ねました。彼は「民を守る者こそが王であり、誰も彼を止めることはできない」と答えました。 彼は言いました。「私のような人間が国民を守れるのか?」彼は言いました。「はい。」彼は言いました。「どうして私が守れるとわかるのですか?」 彼は言いました。「胡和6から聞いたのですが、王様が広間に座っていると、誰かが牛を広間の前に連れて来ていました。王様はそれを見て、『牛はどこへ行くのですか』と尋ねました。7 答えは、『私たちはそれを犠牲として使うつもりです』でした。8 王様は言いました、『放っておけ! まるで罪のない牛が死んでしまうかのように、恐怖で震えているのを見るのは耐えられない。10』 答えは、『では、犠牲を廃止すべきか』でした。彼は言いました、『なぜ廃止しなければならないのか? 羊に置き換えろ!』 - そんなものがあるのかは知りませんが。11 彼は言いました、『はい』。 彼は言いました。「このような心は王にとって十分です。民は皆王を愛しています。王がそれに耐えられないことはわかっています。」王は言いました。「確かに民はいます。斉は小さな国ですが、なぜ牛を愛さなければならないのですか?牛が無実で死んでしまうかのように震えているのを見るのは耐えられません。だから羊と交換します。」 彼は言いました。「あなたはあなたを愛している人々と何ら変わりません。あなたが小さなものを大きなものと交換したとしても、どうして彼らはそれを知ることができましょうか。あなたが自分の無実を隠して彼を死なせてしまったら、牛と羊のどちらを選ぶべきでしょうか。」王は笑って言いました。「あなたはどのような心を持っているのですか。私は彼の富を愛しているのではなく、それを羊と交換しているのです。人々が私が彼を愛していると言うのは当然です。」 彼は言いました。「傷つけないことは慈悲深い方法である。羊ではなく牛を見るのと同じだ。君子は動物が生きているのを見ても、それが死ぬのを見るのに耐えられない。その鳴き声を聞いても、その肉を食べるのに耐えられない。だから君子は台所から離れているのだ。」 【翻訳】 斉の宣王は孟子に尋ねた。「斉の桓公と晋の文公の事績について教えてください。」孟子は答えた。「孔子の弟子たちは斉の桓公と晋の文公の事績について語らなかったため、後世に伝わっておらず、私も聞いたことがありません。どうしても語るのであれば、『王道』について語ってください。」 宣王は「王の道を修めるには、どれほど高い道徳基準が必要ですか?」と尋ねました。孟子は「民を守ることで王の道を修めるなら、誰もそれを止めることはできない」と言いました。 宣王は尋ねた。「私のような男が民を守ることができるか?」孟子は答えた。宣王は尋ねた。「どうして私がそれができるとわかるのか?」 孟子は言った。「胡和から聞いた話では、王が宮殿に座っていて、誰かが牛を宮殿の前に連れて行っていました。王はそれを見て、『牛をどこに連れて行くのですか』と尋ねました。男は『牛を殺して鐘にするつもりです』と答えました。王は『放してあげなさい。罪のない人が処刑場に連れて行かれるように震えているのを見るのは、本当に耐えられません』と言いました。男は『では、鐘の代わりにならないのですか』と言いました。王は再び『どうして捨てられるでしょうか。代わりに羊を使おう』と言いました。本当ですか?」宣王は「はい」と言いました。 メンシウスは、「そのような考えを持っていることは王様のやり方を練習するのに十分です。王はそれを手放すことに消極的であると考えていますが、王は心がないことを知っていました。 ep。「王はそれを手放すことに消極的であると考えています牛を羊に置き換えるお金で、あなたが言っているので、私はそれを手放すことに消極的であると人々が言うのは自然です。 孟子は言った。「そんなことは問題ではない。このような情けは仁である。王は牛の哀れみしか見なかったが、羊の哀れみは見なかった。君子は鳥や獣が生きているときにその愛らしさを見るので、それらが死ぬのを見る心はもうない。それらの鳴き声を聞くと、それらの肉を食べる心はもうない。君子がいつも台所から離れているのはそのためである。」 【注意事項】 (1)斉の宣王:衛王の息子、名は畢江。 (2)斉の桓公と晋の文公:斉の桓公は小白と名付けられ、晋の文公は崇禮と名付けられ、春秋時代に相次いで天下を制覇し、「五大覇者」の第一と第二であった。 (3)私はこれについて聞いたことがありません。当時の言語では、否定文の場合、目的語としての代名詞は述語動詞の前に置かれるのが一般的でした。他の章の「見たことがない」「学んだことがない」「使い果たしたことがない」「知られていない」などについても同様でした。 (4)無益:選択の余地がない。易は「易」と同じ。 (5)バオ:安全。 (6)龁:「hé」と発音する。 (7)之:行く。 (8)神:新しい物や祖先の神殿への供物として生き物を屠る供儀の名称。 (9)觳觫:「hú sù」と発音し、恐怖で震えることを意味する。 (10) 彼が恐怖で震えているのを見るのは耐えられない。まるで彼が無実であるのに今にも死にそうだ。: 馮斌は、伝統的な句読点は「彼が恐怖で震えているのを見るのは耐えられない。まるで彼が無実であるのに今にも死にそうだ。」であると指摘している。于悦の『孟子平易』では、「若」の後で文が区切られています。 「觳觫若」は「恐れて震えている表情」を意味します。楊樹大氏の『古書文解』は于氏の本と同じである。しかし、孟子は「~の様子」を表現するために、「若」の代わりに「然」を使用しています。秦以前の文献の中では、『詩経』だけが「若」を「…の出現」の意味で時折使用していました。鄭子玉は、呉長英と王殷之の意見によれば、「若」を「其」と解釈して「牛」を指すのは意味がないと考えている。代名詞「其」と似た意味を持つ「若」は、「其」と同様に主語の位置ではなく、連体の位置にあるからです。この文では、「若」は当然「のように」または「あたかも」を意味します。なぜ伝統的な読み方を否定する必要があるのでしょうか。牛は無罪であると考える人が多いため、なぜ「若」という言葉を使うのでしょうか。また、楊伯俊氏が「無罪」を「罪之人」と翻訳したと考える人もいます。これは「経典を解釈するために言葉を加える」ということです。実際、孟子が書かれた時代の言語では、「有罪」や「無罪」は「国」などの人々や社会単位の人々を指すはずなので、「無実の人々」と翻訳されるべきであり、これは決して「経典を解釈するために言葉を加える」という問題ではありません。 「無邪気」は牛ではなく人を指すので、「若」という言葉が使われます。詳細は楊鳳斌著『孟子新訳』を参照。 (11)诸:「知乎」と「朱」という漢字を組み合わせたもの。 (12)愛:けちで、手放すことを嫌がる。 (13)褊:「biǎn」と発音し、「小さい」を意味する。 (14)异:驚くべき、奇妙な。 (15)陰:慈悲。 (16)遠く:…から遠ざける |
<<: 孟子:梁恵王章句集(上) - 第6節、原文、翻訳および注釈
推薦する
徐晃は顔良を倒せなかったのに、なぜ樊城に救援に向かったのではなく、関羽を倒したのでしょうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
『紅楼夢』では、奴隷である林志暁の家族はなぜバスに乗って仕事に行くことができたのでしょうか?
周知のように、封建社会には厳格な階級制度があります。それでは、奴隷である林志暁の家族は、どのようにし...
『秘話』に登場する無視された女性、チー・ファンは、リン・シュアンホアよりもさらに不幸な人物だ。
小説『秘められた物語』の闇は、登場人物たちが権力と富への欲望に駆られて、父と娘の愛、師匠と弟子の忠誠...
『紅楼夢』で宝玉のベッドの頭のところに鏡が置かれているのはなぜですか?
賈宝玉は中国の古典小説『紅楼夢』の主人公です。今日は、おもしろ歴史編集長が皆さんに詳しく解説します〜...
律法主義の代表的人物は誰ですか?律法主義の創始者は誰ですか?
韓非は伝統的に法家の代表として認識されています。実際、法家の思想は彼の師である荀子(清)の時代から存...
「パートリッジ・スカイ:名声と富について語る、青春時代の出来事を回想して書かれた劇」のオリジナル翻訳と鑑賞
パートリッジ・スカイ:ゲストは名声と富について非常に感情的に語り、若い頃の出来事を思い出してこれを冗...
北宋の皇帝たちは春節をどのように祝ったのでしょうか?あなたはすべての役人の崇拝を受け入れたいですか?
1000年前の中国は北宋の時代で、都は開封、汴梁でした。春節は「正月」と呼ばれ、一年の始まりを告げる...
龍が頭を上げているのはどういう意味ですか? 2月2日に龍が頭を上げる由来
伝説によると、武則天は唐王朝を廃し、周王朝を皇帝として建国しましたが、玉皇大帝はこれに怒り、3年間地...
水滸伝 第16話 花の僧が独り二龍山を攻撃し、緑面獣が宝珠寺を占拠
『水滸伝』は、元代末期から明代初期にかけて書かれた章立ての小説である。作者あるいは編者は、一般に施乃...
『紅楼夢』で黛玉は青文の死を知った後、なぜ少しも悲しまなかったのですか?
『紅楼夢』のヒロイン、黛玉。金陵十二美女本編の二人の名の中の一人。これと聞いて何を思い浮かべますか?...
礼儀が第一、勝利は第二?春秋時代の戦争はどのように行われましたか?
礼儀が第一、勝ち負けは二の次?春秋戦国時代の戦いはどのように行われたのか?次のInteresting...
Wutongzouyin の創設者は誰ですか?黒銅を銀に変えるプロセスは何ですか?
五通象印の創始者は誰ですか?五通象印の職人技とは?興味深い歴史の編集者が詳細な関連コンテンツを提供し...
『後漢民義録』第32章の主な内容は何ですか?
劉昌を殺害した罪を恐れ、彼は主人に智寿を逮捕するよう頼み、不当に死んだ。しかし、章帝は即位して13年...
上官婉児墓の考古学的発掘で詳細が明らかに、3つの謎が歴史の真実に近づく
概要:唐代初の女性官僚として知られる、武則天の寵愛を受けた尚官婉児の墓が咸陽で発見されました。最近、...
趙雲は劉禅を無事に救出したのに、なぜ劉備の二人の娘を救出しなかったのでしょうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...