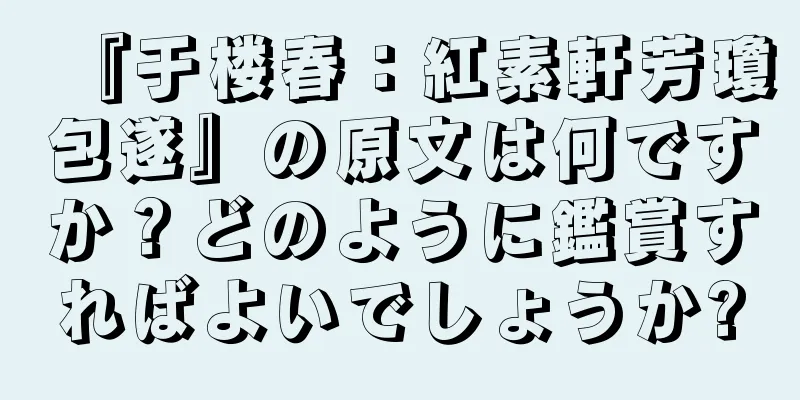大師、大導師、大護衛、大宰相、大司令官の正式な役職は何ですか?

|
古代の官職について言えば、その数は非常に多く、同じ官職でも王朝によって責任が異なり、誰もが少し混乱します。 「Tai」という単語を含む次の公式称号を例にとると、違いも多数あります。 グランドマスター: 太子とは二つの官職を指します。まず、古代では太子、太夫、太保は「三公」(西周)と呼ばれ、後には主に高官に与えられた称号で、寵愛は示したものの実際の地位はなかった。第二に、古代では太子の太子、太夫、太保はいずれも太子の師匠であり、「東宮の三師」とも呼ばれた。太子は太子太子の略称で、後に次第に尊称となった。 泰風: 大夫天皇から賜った大夫額は、君主を補佐し、重要な大臣として政治に参加し、国の軍事力や政治力を司る官吏です。周の時代に皇帝を補佐するために設立されました。漢代に太子に次いで再建された。歴代の王朝で維持されてきたもので、主に実際の職務を持たない高官に称号を付与するために使用され、皇太子を指導する東宮の役人です。この制度は非常に早くから確立され、西漢の時代から太子の師範と呼ばれていました。後に名誉称号としても用いられるようになった。彼は最高位の三官のうちの一人であり、独裁君主の中核をなす人物である。 太宝: 古代の三公爵の一人で、王子の助言者であった王子の家庭教師を指すこともある。西周時代に設立されました。君主を護衛し補佐する役人。武王が亡くなった後、成王はまだ幼かったので、邵公は太傅に任命され、長老として王の保護に当たった。周公は東征に勝利し、東の都を成州に建てた。成王が成州に到着すると、自ら政務を取り仕切り、邵公は周公に長い講義をした。その後、陝西省は境界線として使われました。「陝西省の西は趙公主が統治し、陝西省の東は周公主が統治した。」その後、趙公主の子孫は太保を姓とし、太保、太子、太夫は総称して「三公」と呼ばれました。 太子大師範、太子大師範、太子大守護は総称して「東宮三師範」と呼ばれています。 『官記第四巻第一』には「太子太師、太師、太守はそれぞれ一位であり、太子を指導する責任がある」とある。 太宰: 『周書』に登場する六官の長。伝説によれば、殷王朝は太宰を建国した。周の時代、宗宰は天官の長と呼ばれ、国王の国政を補佐して国造りの六大原則を担当していました。春秋時代には多くの国で太宰という役職が設けられましたが、その職務と権限はまったく同じではありませんでした。秦、漢、魏にはこの制度はありませんでした。晋は司馬師の禁忌を避けるため、太史に代わる三代の食糧担当官として太宰を設置した。明・清の時代、人事大臣は一般に太宰と呼ばれていた。なお、殷代には太史は太宰とも呼ばれていた。 一般的な: 秦・漢の時代、中央政府で軍事を担当した最高官僚。秦の時代、「宰相」「太元帥」「太監」は総称して「三公」と呼ばれていた。その後、徐々に名誉称号や追加の公職として扱われるようになりました。西漢初期、太衛の職は軍事とはほとんど関係がなかったため、宰相や検閲長などの他の職とは異なり、名目上の役職であった。武帝の治世には、貴族の親族が太元帥に任命され、彼らは宰相と同等の地位にあった。光武帝の建武27年、太元帥が太守に改められた。東漢の時代、三公は太衛、司徒、司空でした。太衛は軍事を担当し、司徒は民政を担当し、司空は監督を担当し、それぞれ独自の政府と職員を持っていました。その後、曹操は三大臣制度を廃止し、自らを宰相に任命した。曹丕の治世中に短期間復活したが、後に廃止された。隋代に官職とその補佐官が廃止されて以来、寵愛を受けた宰相、君主、使節に官称を追加して自由に与える制度が徐々に確立されていった。元王朝は永続的に確立されたわけではありません。明代に廃止された。 読者の中には宦官について言及する人もいると思います。宦官の仕事は誰もが知っているので、詳しく説明はしません。 |
推薦する
「剣は近い・夜の雨」の原文は何ですか?どのように鑑賞すればよいでしょうか?
剣術:夜の雨袁曲華(宋代)夜は雨が降った。莱千徳、東風が吹く。クラブアップルの木は魅力的です。そして...
辛其記の『木蘭花人:興遠の張中谷元帥との別れ』:詩人は熱烈な愛国心を持っている
辛其基(1140年5月28日 - 1207年10月3日)、元の字は譚復、後に幽安と改め、中年になって...
邵勇の「村詩」:詩人の自然への愛と賛美を表現している
邵雍(1011年12月25日 - 1077年7月5日)、号は堯夫、諱は康潔、北宋代の儒学者、数学者、...
酔った武松が江門神を殴った話の簡単な紹介
武松が酒に酔って蒋門神を殴打した話は、元代末期から明代初期にかけて史乃安が著した『水滸伝』第29章「...
西洋記録第41章:天主は一連の戦闘陣で火の母を倒す。火の母はトリックを使って火の竜を借りる
『西遊記』は、正式名称を『三宝西遊記』といい、『三宝西遊記』、『三宝西遊記』とも呼ばれ、明代の羅茂登...
岑申の古詩「梁遜城中高居碑」の本来の意味を鑑賞する
古代詩「梁洵の城中高居について」時代: 唐代著者: セン・シェン何千もの家族が見える、最も高い場所に...
武則天は皇帝になる前の李世民の治世中に全く寵愛されなかったのはなぜですか?
武則天は歴史上唯一の女性皇帝ではなかったが、歴史家によって唯一の正統派女性皇帝として常に認識されてき...
戦国時代後期の作品『韓非子』:全文と翻訳・注釈
『韓非子』は、戦国時代後期の朝鮮法家の巨匠、韓非の著作です。この本には55章が現存しており、合計約1...
春秋戦国時代の領土:国の興亡、領土の拡大と縮小
春秋戦国地図と戦国地図の類似点と相違点は、国の興亡、領土の拡大と縮小にあります。春秋戦国時代の情勢図...
『江城子・易茂正月二十日夜夢記』の原文は何ですか?どのように理解すればよいのでしょうか?
江城子:沛年正月二十日夜の夢蘇軾(宋代) 10年間の生と死はあまりにも曖昧で、考えなくても忘れること...
なぜ趙匡胤は「一杯の酒のために武力を放棄する」という大胆な行動に出たのか?彼は勇敢な将軍たちが反乱を起こすことを恐れていないのでしょうか?
趙匡胤は陳橋の乱を経て宋王朝を建国したので、当然軍事力の重要性を理解しており、即位後は属国の勢力を弱...
呂蒙と関羽が同じ年に亡くなったという事実について、歴史上の3つの説は何ですか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
項子珍の『秦楼月・方飛詩』:長さは短いが、感情の容量は小さくない
項子珍(1085-1152)は、法名は伯公、自称は項林居師で、臨江(現在の江西省)出身の宋代の詩人で...
無限の感情に満ちた秋を描いた宋代の詩8編を振り返る
宋代には秋を題材にした詩が数多くありました。Interesting History の次の編集者が、...
『紅楼夢』の4大家の一つである賈邸の収入源は何ですか?
曹雪芹の『紅楼夢』に登場する賈家はもともと貴族の家系であり、その家系は隆盛を極めていた。今日は、In...