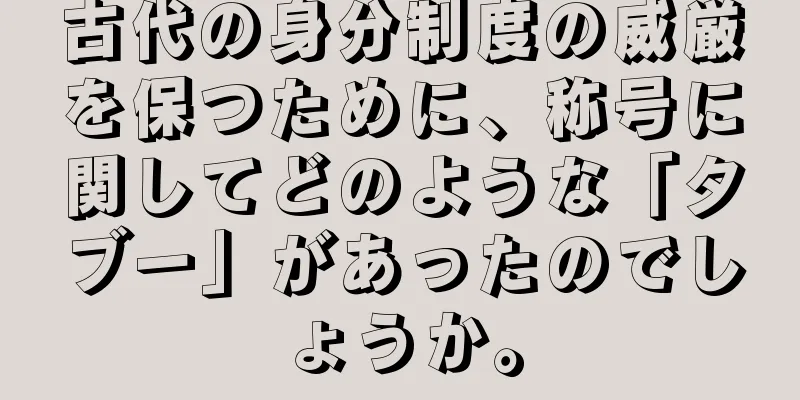歴史上「モンゴルの世紀」はいつだったのでしょうか?なぜその時代はそのように呼ばれるのでしょうか?

|
歴史上「モンゴル世紀」とはいつのことでしょうか?なぜその時代はこう呼ばれたのでしょうか?興味のある方はぜひ見に来てください! 絶えず発展し進歩してきた人類文明の歴史において、戦争は常に存在してきました。歴史発展の軌跡を世界史の観点から見ると、戦争は災害をもたらす一方で、かつては孤立した島のような大陸をゆっくりと近づけていくことも分かります。 このような前提のもとで、13 世紀は世界に記憶される運命にあるのです。その理由は、この 100 年間に、モンゴル軍の征服が当時知られていた土地のほとんどをカバーしたからです。そしてまさにこのために、13 世紀に世界史上最大の帝国、モンゴル帝国が誕生したのです。現代のヨーロッパの学者が東アジア文明とヨーロッパ文明の衝突について語るとき、彼らは必ず何百年も前の冷兵器時代のモンゴル人の疾走について言及する。そのため、中国や海外の歴史家の多くは、13 世紀を「モンゴルの世紀」と呼んでいます。なぜでしょうか? 13 世紀の 100 年間が歴史上「モンゴルの世紀」と呼ばれた根本的な理由は、モンゴル帝国や四汗国の広大な領土のためではありません。むしろ、13 世紀がモンゴルと非常に密接な関係を築くことができたのは、モンゴルがユーラシアを征服した際に歴史に与えた影響によるところが大きいのです。そして、13 世紀に世界を支配したモンゴル人が東洋と西洋の文明に与えた影響。この二つの側面から見れば、「モンゴルの世紀」の歴史的真実を深く掘り下げることができます。 まず、チンギス・ハーンの治世中にモンゴル諸部族が統一された後、彼らは将来、遊牧民として極めて強力な戦闘力を発揮することが運命づけられていました。歴史上、モンゴル人は3回にわたって大規模な西征を行った。この3回の遠征はモンゴル人の世界覇権確立を可能にしただけでなく、その覇権の背後にある世界史全体にも影響を与えた。東ヨーロッパのロシアを例に挙げてみましょう。モンゴル人が世界覇権を確立した後、彼らは何百年もの間モンゴル人の支配下に置かれました。過去数百年にわたる変化は、その後のロシアの文化の発展に大きな影響を与えたと言えます。 同時に、モンゴル人の世界征服の過程で、新興のホラズムや、長く衰退していたアラブ帝国のアッバース朝などの国家が次々と滅亡した。これらの王朝は滅ぼされましたが、この100年間に他の多くの王朝が徐々に成長し、発展することができました。例えば、歴史上エジプトのマムルーク朝は、モンゴルの西征の大きな恩恵を受けた国であると言えます。さらに、モンゴルの西方侵攻は、その後のオスマン帝国の台頭にも良い条件を作り出した。 もちろん、「モンゴルの世紀」は、ヨーロッパとアジアの多くの王朝の興亡の歴史だけで要約できるものではありません。実際、「モンゴルの世紀」は東洋文明と西洋文明の衝突にも反映されています。大規模な軍事遠征は人口の移動と技術の普及も促進したことに注目すべきである。最も単純な例を挙げると、モンゴル軍の西征の際、中国発祥の兵器技術である火薬もヨーロッパや中東に流入した。火薬の導入は近代ヨーロッパの台頭に重要な役割を果たした。 このことから、13世紀の歴史は単に軍隊同士が戦うだけの時代ではなかったことがわかります。両者の闘争の中で、技術も広まり、革新も起こりました。特にモンゴル軍が征服に向かうときには、必ず大勢の職人が従っていました。彼らは、アジア発祥の多くの技術をヨーロッパや中東にもたらしただけでなく、遠く離れた東アジアに、反対側の重要な技術も持ち帰ったのです。もちろん、軍事技術の交流は、東洋と西洋の文明の衝突の氷山の一角に過ぎません。この世紀の交流には、文化、教育、さらには病気や馬の品種など、さまざまな側面が関わっていました。 13 世紀が「モンゴルの世紀」と呼ばれるのには理由があることがわかります。 13世紀は人類史上最も重い時代であったと言えるでしょう。モンゴル軍の拡大の陰で数え切れないほどの命が失われたからです。この「モンゴルの世紀」は人類社会の発展における新たな章でもあります。なぜなら、この100年を経て、かつては孤立した島々のようだったいくつかの大陸が密接につながり始めたからです。特に、さまざまな技術や文化の交流は、世界の歴史全体の発展に大きな影響を与えてきました。 |
<<: 中原文明の始まりはいつですか?周王朝の前に商王朝は存在していましたか?
>>: 軍の将軍はどのように訓練されるのでしょうか?三国志の正史では兵士と将軍の違いはどれくらい大きいのでしょうか?
推薦する
清朝末期の二人の実業家の争いを解明
清朝末期の二人の実業家の争いウー・ゴウ胡雪岩は安徽省鶏西の人(浙江省杭州出身とも言われる)で、道光三...
陳子龍の「年女嬌」:この詩は深い感情に満ち、優雅で荒涼としている。
陳子龍(1608-1647)は、明代後期の官僚、作家であった。初名は傑、号は臥子、茂忠、仁忠、号は大...
西洋史第39章:張天石の連続魔法、王神谷が誤って数珠を掛ける
『西遊記』は、正式名称を『三宝西遊記』といい、『三宝西遊記』、『三宝西遊記』とも呼ばれ、明代の羅茂登...
張吉の『成都曲』:詩人の成都への愛が表れる
張季(766年頃 - 830年頃)、号は文昌、唐代の詩人。賀州呉江(現在の安徽省賀県呉江鎮)の出身。...
宋代の朝廷会議制度はどのようなものだったのでしょうか?裁判停止制度はいつから施行されるのでしょうか?
今日は、おもしろ歴史編集長が宋代の朝廷会議制度がどのようなものであったかをお伝えします。皆さんのお役...
荀攸は曹魏の五人の顧問の一人でもありました。彼は曹魏にどのような大きな貢献をしたのでしょうか?
曹魏の五人の補佐官とは荀攸、荀攸、賈詡、程毓、郭嘉のことである。この5人は曹魏の権力の確立と強化に多...
欧陽冲の『南湘子図舟漕止図』:絹と絹の香りを洗い流した後、風景を描写し、風俗を記録する
欧陽瓊(896年 - 971年)は、宜州華陽(現在の四川省成都)出身で、五代十国時代の後蜀の詩人であ...
Pan Jinlian と Sun Erniang の違いは何ですか?武松の物語にはなぜ似たような女性が二人いるのでしょうか?
今日は、Interesting History の編集者が水滸伝の解説をお届けします。興味のある読者...
大喬と小喬はそれぞれ誰と結婚したのですか?
大喬は小君孫策と結婚した。二喬の父は喬玄である。世間の混乱により妻を失った喬玄は、朝廷での官職を辞し...
南宋時代の詩人程蓋の作品「水龍隠」鑑賞
程蓋の『水龍隠・夜来風雨』を鑑賞し、興味のある読者と『Interesting History』編集者...
『紅楼夢』で香玲と秦克清が似ているのはなぜですか?意味は何ですか
「紅楼夢」は優雅な気質と優れた才能を持つ女性たちを描いた作品です。本日はInteresting Hi...
中国の歴史王朝の歌の複数のバージョンは、中国のさまざまな王朝の発展の歴史をより迅速かつ簡単に覚えるのに役立ちます。
王朝歌は主に中国の歴史上の王朝の名前を覚えやすくするために使われるバラードです。それらのほとんどは、...
晋史第70巻第40伝の原文
◎ 英戦甘卓 鄧千扁旭(従兄弟の敦劉超仲雅)英戦は、名を思源といい、汝南の南墩の出身で、魏の丞相であ...
明朝初期の封建制度はどのような役割を果たしたのでしょうか?朱元璋もため息をつくしかなかった
洪武3年(1370年)、朱元璋は歴代の封建制度を基礎として、明の封建制度を独創的に確立した。洪武3年...
後世の人々は曹申をどのように記念したのでしょうか?曹申の漢墓はどこにありますか?
曹深(発音:cān、紀元前190年頃)、愛称は荊伯、漢族の沛の出身。西漢の建国の英雄、名将、蕭何に次...