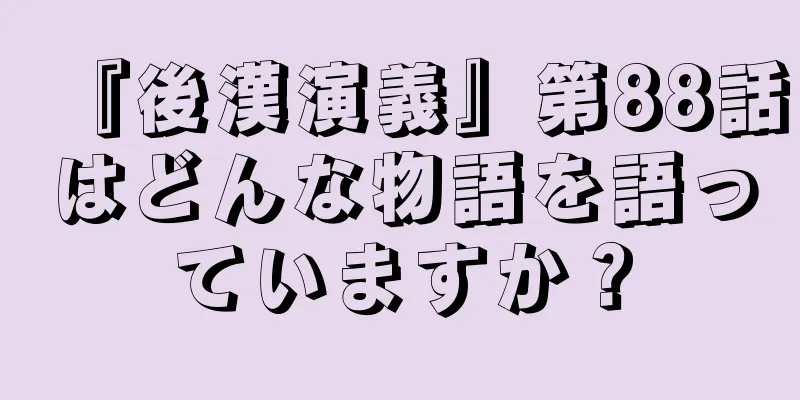古代の人々はスイカを食べていたのでしょうか?スイカはいつ、どのようにして中国に伝わったのでしょうか?

|
古代の人々はスイカを食べていたのでしょうか?スイカはいつ、どのようにして中国に伝わったのでしょうか?今日は関連するコンテンツを皆さんにシェアしたいと思います。 中国は今や世界最大のスイカ消費国となっている。毎年夏になると、スイカはどの家庭にも欠かせない涼しい果物となっているようだ。しかし、スイカはもともと中国では生産されていなかったため、古代人は長い間スイカを食べることができませんでした。では、古代にスイカはどのようにして中国に伝わったのでしょうか?初期には西域から中原に伝わったと言われていますが、スイカの起源についてはさまざまな意見があります。幸いなことに、スイカの栽培に必要な環境はそれほど厳しくないため、輸入に頼らざるを得ない果物とは異なり、中原ではスイカを自力で栽培することができます。 名前から、スイカは中原で生産されているのではなく、西部から来ていることがわかります。もちろん、「スイカ」という名前は古代のある時期には他のメロンも指していましたが、それは私たちが話しているスイカとはまったく異なるので、ここでは説明しません。 スイカの起源は現在ではアフリカであると一般的に信じられています。現代の学者の研究によれば、北アフリカのスーダンには、今でも自生する野生のスイカが広大な地域で生育しており、ここがスイカの原産地であると考えられています。 その後、古代エジプト人がスイカの栽培を始め、地中海沿岸から北ヨーロッパ、中東、そして西方地域から中国へと徐々に伝わり、スイカという名前が付けられました。 中国で「スイカ」という言葉が初めて登場したのは、五代胡喬が著した『捕虜記』という書物です。胡喬はもともと宣武軍の太守蕭寒の秘書で、蕭寒に従って契丹に入りました。その後、蕭寒が殺害され、胡喬は帰国できず捕虜になりました。彼は7年間契丹に滞在した後、中原に戻りました。帰国後、彼は契丹での経験に基づいて『捕虜記』という書物を執筆しました。書物には次のように記されています。「そして彼らは平原に入り、そこには多くの草木があり、スイカを食べ始めました。」契丹族がウイグル族を倒したときにこの種を手に入れたと言われている。彼らは牛糞を敷いた小屋にこの種を植えた。中国の冬瓜ほどの大きさで、味は甘かった。 この本に記されている契丹族のウイグル族の敗北は、時代的にも一致している。924年、遼の太祖皇帝は西域の高昌ウイグル族に遠征し、「富途城と西部国境地帯のすべての部族を占領した」。これは歴史上「契丹族のウイグル族の敗北」として知られている。 胡橋が中原に戻った953年当時、スイカは契丹に導入されてから30年以上が経っていた。 しかし、胡橋が契丹でスイカを食べたという事実は、五代の間にスイカが中国に伝わったことを意味するものではない。五代から北宋にかけて、各種の歴史書にはスイカに関する記録が残っていません。宋代は経済が発達していたので、その頃にスイカが伝来し、植えられていたなら、書物に記録されているはずです。 スイカは、スイカを初めて食べた胡橋の時代から約200年後の南宋時代に、中原に初めて導入され、大規模に栽培されました。 北方の女真族が蜂起し、遼朝を滅ぼして金朝を建国した。南宋の官吏洪昊は使節として金朝に派遣されたが、金朝に15年間拘留され、紹興13年(1143年)まで帰国を許されなかった。洪昊は帰国後、スイカの種を持ち帰り、中原や杭州などに植え始めた。洪昊はその後の著作『松墨紀文』の中で、次のようにはっきりと書いている。「スイカは平たいガマのような形をしていますが、丸く、色は緑色です。数年経つと黄色に変わります。メロンに似ていて、甘くてシャキシャキした味がします。…私はそれを家に持ち帰りました。」洪昊が中原に戻った後、スイカ栽培に関する記録文書が現れ始め、これも洪昊の主張を裏付けた。 もちろん、民族的な観点から言えば、契丹族は現在では漢民族に同化され、歴史から姿を消しています。彼が建てた遼王朝は、現在も中国の一部です。このように考えると、スイカが栽培用に導入されたのは五代時代だと言うのも納得できます。 もう少し範囲を広げて考えてみると、例えば唐代はかつて西域を長く支配し、行政軍事組織である護国府を設置していました。そして唐代中期から後期にかけて、スイカが中国に伝わったと言えます。しかし、当時はスイカを食べることができたのは辺境地域だけで、中原の漢民族はスイカを楽しむことができませんでした。 |
<<: 皇帝の芸術とは何ですか? 「天皇の芸術」の真髄を3つの文章にまとめました!
>>: 古代の交通手段は何でしたか?金持ちはどのように旅行するのでしょうか?
推薦する
『紅楼夢』で薛家がいつも賈家の屋敷に泊まったのはなぜですか?
『紅楼夢』に登場する四大家はいずれも親密な関係にある。次の『Interesting History』...
「ミスター・サイプレスのコテージ」を鑑賞するには?著者は誰ですか?
メイスター・バイのコテージ杜甫(唐代)学者のビシャンは銀の魚を燃やし、白い馬は深い洞窟に住むようにな...
古代において潼関はどれほど重要だったのでしょうか?なぜそれがそんなに重要なのでしょうか?
古代において潼関はどれほど重要だったのでしょうか?なぜそれほど重要だったのでしょうか?これは多くの読...
九霊元勝の師匠は誰ですか?本当の体とは何ですか?
神々の世界では、九霊元生は単なる乗り物であるにもかかわらず、すべての神は彼に面目を与えなければなりま...
「舒通」の原文は何ですか?どのように鑑賞すればよいでしょうか?
桐の花李尚閔(唐代)玉城の高い桐の木が玉縄に擦れていますが、その下には霧も氷もありません。紫の鳳凰は...
兵馬俑の職人技はどれほど複雑なのでしょうか?陶芸馬術入門
兵馬坑の陶馬には、戦車馬と騎馬馬の2種類があります。これらの陶馬の職人技はどれほど複雑なのでしょうか...
秀雲閣第37章:龍王が宴会を開き、道士たちを解任し、役人を停職させる
『秀雲歌』は清代の魏文忠が書いた神と悪魔を扱った長編民俗小説である。 「秀雲仙閣」とも呼ばれる。この...
宋代の古詩『成天寺夜遊』を鑑賞する、この古詩にはどんな真実が含まれているのか?
宋代の蘇軾が城天寺の夜遊びを記録し、次の興味深い歴史編集者が詳細な紹介をお届けします。見てみましょう...
漢の元帝が西漢王朝の衰退を引き起こしたのであれば、漢の成帝はどのような影響を与えたのでしょうか?
漢の元帝が西漢の繁栄を衰退させたとすれば、漢の成帝は西漢の衰退の過程に重圧を加え、西漢を滅亡の瀬戸際...
東晋の葛洪著『包朴子』内篇全文と翻訳:兌詢
『包朴子』は晋の葛洪によって書かれた。包埔([bào pǔ])は道教の用語です。その由来は『老子』の...
『散る梅の花 心の中のこと』の執筆背景を教えてください。どのように理解すればいいのでしょうか?
【オリジナル】あなたが考えていることを彼に伝えてください。早めに言ったほうがいいですよ。 「pa」と...
現代人は住宅価格を非常に気にしていますが、宋代にはそのような問題があったのでしょうか?
古代から現代に至るまで、家と土地は常に人々にとって最も関心の高い問題でした。今日、経済発展に伴い、貧...
桓公9年の儒教古典『春秋古梁伝』の原文は何ですか?
顧良池が著した儒教の著作『春秋古梁伝』は、君主の権威は尊重しなければならないが、王権を制限してはなら...
斉孝鸞の皇帝高宗には何人の息子がいましたか? 孝鸞の息子は誰でしたか?
蕭鸞(452年 - 498年9月1日)は、景斉とも呼ばれ、通称は玄都で、南蘭嶺(現在の江蘇省常州の北...
「狼涛沙・東風に酒を飲む」を鑑賞し、詩人の欧陽秀と友人の梅耀塵が故地を再び訪れた
欧陽秀(おうようしゅう、1007年8月1日 - 1072年9月22日)、字は永叔、晩年は随翁、劉義居...