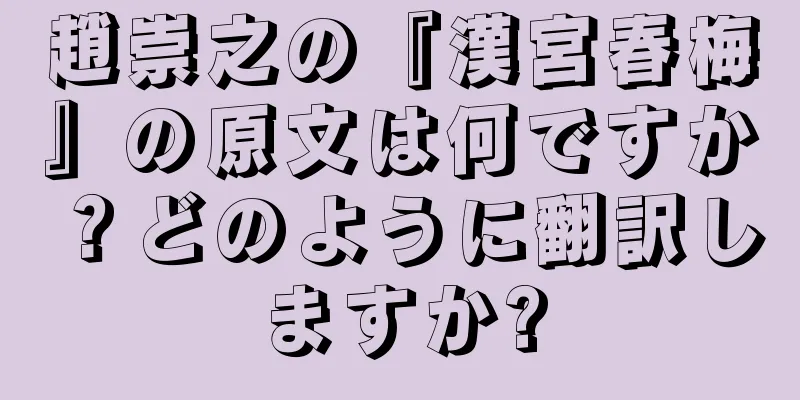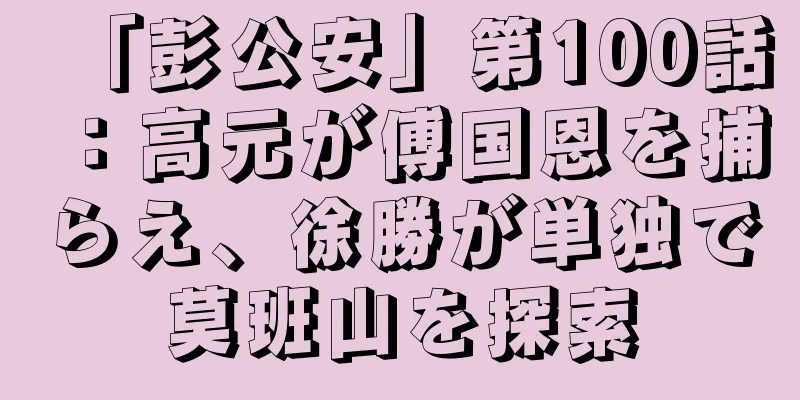敦煌壁画「伏羲女媧図」の芸術的素晴らしさはどのようなところですか?

|
敦煌壁画の「伏羲女媧図」の芸術的素晴らしさとは何でしょうか?それは主に仏教が中国の地方文化と融合し始め、多くの中国文化の内容を吸収したことに反映されています。今日は、興味深い歴史の編集者が詳しく紹介します。読み続けましょう〜 莫高窟第285洞窟の天井には伏羲と女媧の像が描かれている。この洞窟には、西魏大同4年と5年(西暦538年と539年)に建てられたことがはっきりと刻まれています。この洞窟の天井画のスタイルは洞窟 249 のものと多少似ており、どちらも色とりどりの雲が舞い、さまざまな伝説の神や怪物が描かれています。東側の七宝焼きの中央には、大きな蓮の花が咲いた蓮の茎と蓮の中にマニの宝石を持っている2人の力持ちの男性が描かれています。マニ珠の両面には、それぞれ上半身が人間、下半身が動物の伏羲と女媧の像が描かれています。左側は伏羲で、片手に定規を持ち、もう片方の手に硯を持っています。伏羲の体には円輪があり、その中には太陽を象徴する金色のカラスがいます。右側は女媧で、手にコンパスを持っています。女媧の体には円輪があり、その中には月を象徴するヒキガエルがいます。定規、定規、墨壺などの道具は大工の道具で、それぞれ円、四角、直線を描くのに使われます。古代人は「天は丸く、地は四角い」と信じていました。ここでの円と四角は天と地を象徴し、伏羲と女媧が世界を創造した神であることを暗示しています。伏羲と女媧の下には、悟りを開いた獣と仙人が描かれている。同じ洞窟の天井の南、西、北の側面には、風、雨、雷、稲妻の四神と飛廉と有翼人が描かれている。これらの神々のイメージは、249洞窟の天井に描かれたものとほぼ一致している。 世界を創造した神である伏羲と女媧は、秦以前の時代から文書に記録されています。漢代になると、伏羲と女媧を描いた絵画がますます増えた。王延寿の『魯陵光宮譜』には、宮廷壁画に描かれた伏羲、女媧などのさまざまな神話について、「天地創造の初め、太古の初めには、翼を持った五頭の龍が並んでおり、人間の皇帝には九つの頭があり、伏羲は鱗の体を持ち、女媧は蛇の体を持っていた」と記されている。呂陵光殿は現存していないが、現代の考古学的発見により、洛陽の漢の墓から北西部の嘉峪関の魏と金の墓まで、伏羲と女媧の像が発見されている。通常、伏羲は手に羅針盤を持ち、その体には太陽を象徴する金色のカラスが乗った丸い車輪が付いています。女媧は手に羅針盤を持ち、その体には月を象徴するヒキガエルが乗った丸い車輪が付いています。上半身は人間の形で、下半身は蛇の形をしています。伏羲と女媧の蛇のような下半身が絡み合うこともあります。 249窟と285窟はどちらも西魏時代の洞窟です。この時代、東王、西王母、伏羲、女媧など中国の伝統的な神話の内容が仏教洞窟に大規模に現れ、仏教壁画の内容と完璧に融合しました。絵画技法の面では、アーティストは飛んでいる雲や模様を利用して動きの感覚を誇張し、壁一面に飛んでいるような効果を生み出しています。これは仏教と中国文化の親和性、そして外来仏教と中国本土の文化の融合を反映しており、この時期に中原からもたらされた新しい芸術様式が敦煌壁画に強い影響を与えたことが見て取れる。 北魏から西魏にかけて、孝文帝の改革により、鮮卑人は統治者として漢民族の先進的な文化を本格的に学び始め、政治体制から言語、衣服などに至るまで一連の改革を行った。特に洛陽に遷都されてからは中国化が加速し、南方の芸術も北方に多大な影響を与えた。一方では、仏教思想は比較的開放的で、中国の伝統的な神仙思想を仏教石窟に取り入れました。他方では、芸術スタイルは南方の影響を吸収し、249洞窟、285洞窟、288洞窟などの洞窟に代表されています。仏像や菩薩像は、どれもほっそりとしていて、目は明るく、笑顔は優しいです。彼らは皆、袖の広い衣を着て、豊かなリボンを飾り、裾はひらひらと舞い、神々しい印象を与えます。これは、当時の南方絵画で流行した「精緻な骨格と鮮明な像」と「幅広の衣服と帯」の特徴です。 |
推薦する
三国志演義の七星灯籠は何を意味しているのでしょうか?諸葛亮はなぜ七星灯を使って寿命を延ばしたのでしょうか?
今日は、Interesting Historyの編集者が諸葛亮についての記事をお届けします。ぜひお読...
「帰ってきた鳳凰は鳳凰を捜すが、もうその音沙汰はない」という有名なセリフはどこから来たのでしょうか?
「帰ってきた鳳凰は鳳凰を捜すが、もう声は聞こえない」という有名な詩はどこから来たのでしょうか?実は、...
文学と歴史に関する興味深い逸話:皇帝の婿はなぜフー・マーと呼ばれるのか?
「傅馬」とは古代中国における皇帝の婿の称号です。皇帝の婿、主君の婿、国家の婿などとも呼ばれます。では...
西涼政権の君主、李勲とはどのような人物だったのでしょうか?歴史は李勲をどのように評価しているのでしょうか?
李勲(?-421)は、隴西省城邑(現在の甘粛省秦安市)の出身で、西涼の武昭王李昊の息子であり、西涼最...
子供たちの英雄的英雄第2章:穆皇帝の恩寵により河川労働者が司令官に任命されるが、彼は知事に従わず、不当に郡刑務所に投獄される
清代の作家文康が書いた『家中英雄』は、主に清代の康熙・雍正年間の公的な事件を描いたものです。主人公は...
商王朝の青銅製三脚は何に使われたのでしょうか?三脚の本来の目的
中国語の教科書には、「丁」に関連する慣用句やことわざが数多く挙げられます。「一語一句が三脚のごとく」...
古典文学の傑作『太平記』:布絹部第7巻全文
『太平百科事典』は宋代の有名な百科事典で、北宋の李芳、李牧、徐玄などの学者が皇帝の命を受けて編纂した...
慕容衛の発音は?慕容衛の生涯の簡単な紹介。慕容衛はどのようにして亡くなったのか?
慕容惟(350年 - 384年)、号は景茂、鮮卑族の一人。昌黎郡吉城(現在の遼寧省宜県)の人。前燕の...
「女仙人の非公式歴史」第19章:女元帥が王を守るために立ち上がり、正義の男たちは全員団結して敵を殺す
『女仙秘史』は、清代に陸雄が書いた中国語の長編歴史小説です。『石魂』や『明代女仙史』とも呼ばれていま...
太平広記·巻41·仙人·劉武明をどのように翻訳しますか?原文の内容は何ですか?
『太平広記』は、漢文で書かれた中国古代の記録小説集で、全500巻、目録10巻から成り、漢代から宋代初...
諸葛亮の岐山への6回の遠征と姜維の中原への9回の遠征の違いは何ですか?
夷陵の戦いで蜀が東呉に敗れた後、劉備は病死し、後の皇帝劉禅が帝位を継承し、宰相の諸葛亮が政権を補佐し...
関興と張宝は義兄弟になったとき、なぜ劉備の息子である劉禅を連れてこなかったのでしょうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
『詩経・国風・書玉田』の原文は何ですか?どうやって鑑賞すればいいのでしょうか?
舒玉田(不明)(先秦時代)玉田おじさん、この路地には誰も住んでいません。ここには誰も住んでいないので...
さまざまな王朝における澄んだ霜を描写した詩は何ですか?詩人はどんな場面を描写しているのでしょうか?
歴代の王朝には、冬の澄んだ霜を描写した詩が数多くあります。Interesting History の...
『西遊記』の黒熊鬼には背景がなかったのに、なぜ殺されずに神に戴冠されたのでしょうか?
ご存知の通り、『西遊記』はファンタジー小説ですが、その本質は社会の現実を暴くことです。西遊記に登場す...