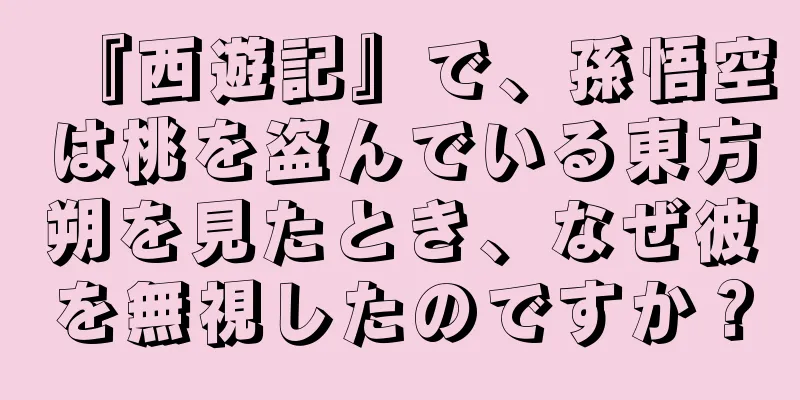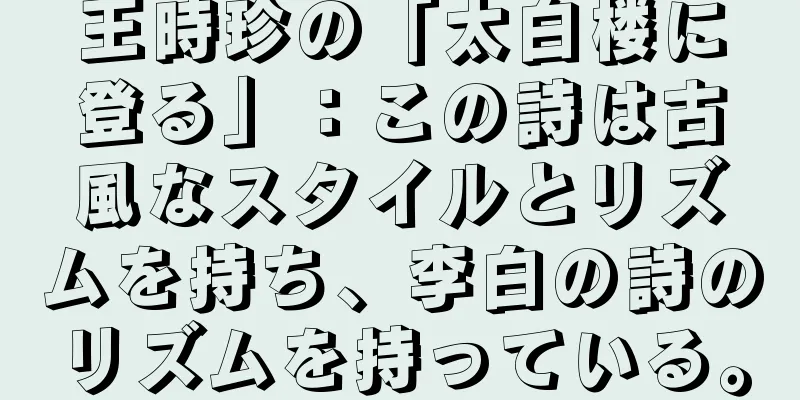古代の側室はなぜ自分の子供を育てることができなかったのでしょうか?歴史上、自分の子供を育てる栄誉に恵まれた人は誰でしょうか?

|
今日は、Interesting History の編集者が、古代の側室が出産後に自分の子供を育てることができなかった理由をお話しします。興味のある読者は編集者をフォローしてご覧ください。 古代中国では、男尊女卑の状況が長く続いていたため、特に3つの宮殿と6つの中庭を持つ王室では一夫多妻制が非常に一般的でした。皇帝は後宮に数百人、多いときには千人の側室を抱えていました。後宮にこれほど多くの側室がいると、たとえ皇帝が毎晩1人の側室を訪ねたとしても、1年ですべての側室の面倒を見ることはできないかもしれません。また、王室の側室は常に固定されているわけではありません。皇帝は毎年、決まった場所から美女を選び、寵愛を受けなかったこれらの側室は、皇帝が寵愛を受けた時から老齢になるまで、皇帝に会うことがなかったかもしれません。彼女らは皇帝の過ちに抵抗しながらも、寒い宮殿での生活を送っていました。 しかし、皇帝が毎年選ぶ側室の中には、唐代の楊貴妃のように容姿が抜群な女性も多くいます。彼女たちは見事な容姿を頼りに皇帝の寵愛を受け、子供を産んだ後も寵愛を受けています。清代の魏英洛は王子を産んだ後も乾隆帝に寝るように仕えなければなりませんでした。皇帝に寵愛される側室の栄誉が非常に高いことがわかります。王子を無事に産んだ後、魏英洛は皇帝からさらに寵愛を受けました。 そのため、宮中に入った女性の多くは皇帝の寵愛を受け、王族の男児や女児を産み、息子を産むごとに母親としての地位も高まっていきました。しかし、王子を身籠った多くの側室は出産後、ほんの一瞬だけ見られるだけだったことにお気づきでしょうか。助産婦でさえ、側室に自分の子供を見せませんでした。子供は乳母に連れ去られ、授乳されました。母子が会えるのは、王子が成長して分別がついたときだけでした。映画やテレビドラマに出てくる王子のほとんどは、乳母と非常に良い関係を築いています。たとえば、最後の皇帝である溥儀は、紫禁城から退去した後も乳母を連れてくるのを忘れませんでした。では、なぜ皇室は側室に皇子の授乳を許可せず、代わりに乳母に任せたのでしょうか。実は、それは皇帝の利己的な動機からでした。 側室が王子を出産した後、母性本能から、側室と王子の関係が近すぎることを心配し、皇帝への奉仕がよりおざなりになりました。さらに重要なのは、息子が皇帝になることを望まない側室はいないため、皇帝は側室が王子を惑わすのではないかと心配しました。側室が王子を誘惑し、悪い考えを植え付け、欺くことを防ぐために、そして将来の朝廷の秩序の混乱を防ぐために、側室が自分の王子から引き離される現在の状況が発生しました。 そういえば、古代の皇帝も玉座を守るために多大な労力を費やしており、これもまた古代封建制による覇権国家の覇権を示すものであり、したがって、これは王族が川上で自らを守る手段でもあった。 |
<<: 長子相続制度を発明したのは誰ですか?なぜこの規則は春秋時代以降に破られたのでしょうか?
>>: 昔は、このようなものがあれば、まず実行して後で報告することができました。 「皇剣」以外に何を知っていますか?
推薦する
荘族の民謡にはいくつの形式がありますか?
チワン族の民謡は、楽声歌、白歌、三歌などの3つの形式に分けられます。詩歌は壮族の詩の自由な形式であり...
秋を表現した詩にはどんなものがありますか?秋の風景を描いた有名な詩
秋の風景を描いた有名な詩は何ですか?秋風は荒々しく、波はうねる。「海を眺める」 3ヶ月目に葉が落ち、...
曹植の『七雑詩第四』は、自分の才能が認められていないことに対する詩人の苛立ちを表現している。
曹植は、字を子堅といい、曹操の息子で、魏の文帝曹丕の弟である。三国時代の有名な作家であり、建安文学の...
三国志演義第91章:呂河に犠牲を捧げ、漢の宰相が中原を攻撃するために戻り、呉侯が記念碑を贈呈
しかし孔明が帰国すると、孟獲は大小の洞窟の長老たちや他の部族を率いて丁重に孔明を見送った。先鋒軍が盧...
フビライ・カーンの統治時代、中国の領土はどれくらい広かったのでしょうか?
ボルジギン姓を持つクビライ・ハーン(1215-1294)はモンゴル人であり、チンギス・ハーンの孫であ...
内務省は宋代の宦官の総本山でした。宦官の職名はどのようなものでしたか。
内務省は、天皇の側近として宮廷の内政を管理する官庁の名称です。北斉の初めに中時中州と昌丘寺が設立され...
春の始まりを祝う中国の伝統的な習慣は何ですか?
立春の風習についてどれくらいご存知ですか?私の国には伝統的な祭りがたくさんあるので、伝統的な習慣もた...
三国時代、魏、蜀、呉は対立していましたが、異民族とはどのような交流があったのでしょうか?
三国時代、魏、蜀、呉は対立していたものの、孤立することはなく、外国の民族との交流も行われていました。...
漢の万里の長城はどこから始まるのでしょうか?漢の万里の長城の終わりはどこですか?
漢の万里の長城は外長城とも呼ばれています。安渓には150キロメートルの漢の長城、70の烽火塔、3つの...
ランタンフェスティバルのランタンはどこから来たのでしょうか?ランタンフェスティバルでランタンを灯す意味は何ですか?
元宵節の提灯にはさまざまな種類があり、龍提灯、虎提灯、兎提灯など物を模して作られた像提灯や、牛飼いと...
Yelu Yanの叔父は誰ですか?イェルヤンの叔父、陸無双のプロフィール
呂無双は金庸の小説『射雁英雄の帰還』の登場人物である。彼女はもともと江南の陸家荘の娘でした。幼い頃、...
『荀陽夜景廬山』の原文は何ですか?それをどう理解すればいいのでしょうか?
夜は浚陽に泊まり、廬山を眺める孟浩然(唐代)私は何千マイルも旅しましたが、有名な山々を一度も見たこと...
賈憐が関係を持った数人の女性を見て、なぜ彼は彼女たちに特別な好意を抱いたのだろうか?
『紅楼夢』は、中国古代の章立て形式の長編小説で、中国四大古典小説の一つです。普及版は全部で120章か...
漢碑は李尚閔によって書かれ、李尚閔は漢碑の優雅さと価値を高く評価しました。
李尚鑫(813年頃 - 858年頃)は、字を易山、号を毓曦生といい、淮州河内(現在の河南省沁陽市)の...
古典文学の傑作「太平天国」:食品飲料第24巻全文
『太平百科事典』は宋代の有名な百科事典で、北宋の李芳、李牧、徐玄などの学者が皇帝の命を受けて編纂した...