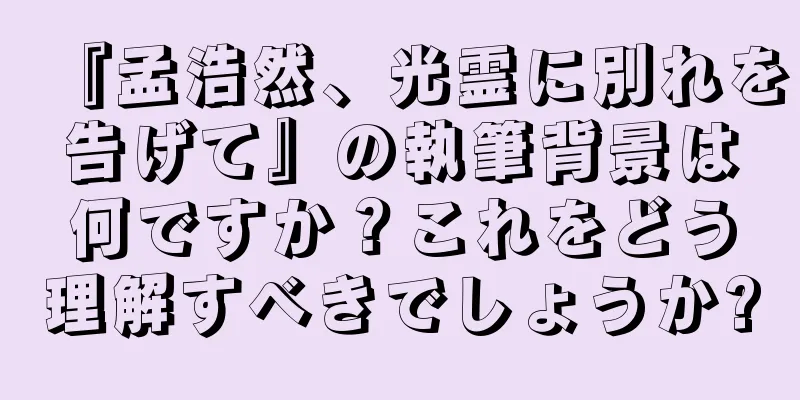「裏切り者」という称号の裏で、曹操はなぜ皇帝を人質に取ろうとしたのか?

|
歴史上、曹操は貧しい家庭の出身で、名家の出身ではなく、軍事力も持っていませんでした。彼は十代の頃、清廉潔白な官吏として選ばれたが、その高潔な性格ゆえに常に上司の怒りを買い、結局は失業者となって家に残された。若き曹操は、官僚制度を改革し、さらには漢王朝を支える責任を自ら負うことを望み、何度も朝廷に手紙を書いた。董卓が入京するまで、曹操は財産をすべて使い果たし、弱い軍事力に頼って董卓と戦っていた。皇帝を人質にすることのデメリットがメリットを上回るのであれば、曹操が生涯戦い続けた動機は実は漢王朝を支えるためだったということなのだろうか?これらは、今日私たちが知らない「裏切り者」の背後にいる曹操です。次は興味深い歴史エディターが詳しく紹介しますので、見てみましょう! 『三国志』によると、何進は董卓を都に招き入れ、宦官を滅ぼそうとしたが、予想外に宦官に滅ぼされた。董卓は混乱に乗じて漢王朝を奪い、元の皇帝である少帝劉弁を廃位し、劉協を擁立した。劉協は後に漢の献帝となった。漢の献帝、劉協は、何皇后の息子ではなかったので、論理的には皇帝になることはできないはずだったが、皇帝になる運命にあった。漢の霊帝は劉協を大変気に入り、密かに皇太子を劉協に交代させる計画を立てました。彼は宦官の簡碩にその任務を与えました。残念ながら、皇太子が交代される前に献帝は亡くなりました。何皇后は当然、息子である漢の紹帝を即位させた。何進と宦官たちの戦いが董卓の登場を招き、若き皇帝が廃位の運命から逃れられず、漢の献帝が歴史の舞台に登場するとは、誰が想像しただろうか。 実際、劉懿の皇帝としての統治はいくぶん異例なものでした。劉協は長子相続の規定に当てはまらず、董卓が立てた皇帝であったため、漢の献帝の地位を認めるつもりのない者が多かった。後に皇帝が人質にされたとき、袁紹らが漢の献帝を奪いに来なかったのは、彼らが心から献帝の権威を認めていなかったからである。たとえ本当に皇帝が必要だったとしても、彼に代わる王族の血を引く別の人物を見つけることができた。董卓は都に入り、かつては漢王朝を簒奪しようとした。その後、王允などの老臣が董卓を殺害しようと企んだ。董卓を滅ぼせば、天下は平和になるかと思われた。しかし、予想外に董卓の古い部下である李傅と郭汜が再び反乱を起こした。献帝は狼の穴から脱出したばかりだったが、再び虎の穴に落ちた。 では、なぜ彼は皇帝を人質に取ろうとしたのでしょうか? これは曹操の野心から始まります。 『三国志演義』の記録によれば、曹操は貧しい家庭の出身だった。彼らは貧しい家に生まれたが、官僚の家系でもあった。しかし、袁紹の「四代三官」には遠く及ばなかった。曹操は若い頃から非常に才能があり、成功のほとんどは彼自身の能力によって達成されました。曹操は、家族の支援を受けられず、10代の頃に中等官に抜擢されたが、あまりに高潔な性格であったため宦官たちの反感を買い、すぐに解任された。 『三国志』の『魏武物語』には、この時期の曹操の心の旅についての独白が記録されている。建安15年吉海日に出した勅旨には、郡守だった頃の心境が記されており、自分の評判が悪いために当時の人から蔑まれるのを恐れ、その時は良い郡守になりたいと願っていたと記されている。実際、彼は誠実に職務を遂行していたが、後漢末期には宦官が権力を握り、人々の心は以前とは異なり、道徳というものは存在しなかったため、彼の野望は空しくなってしまった。この時点でほとんどの人は諦めていたでしょうが、曹操は諦めなかったようです。董卓と戦うために財産を売り払ったことからもそれがわかります。 『三国志演義』に描かれていても、『三国志演義』に記録されていても、董卓は暴君です。彼の軍隊は道中、焼き討ち、殺戮、略奪を繰り返し、彼自身も非常に寛容であった。そのようなチームはオオカミやトラのように獰猛に見えるかもしれないが、無敵ではない。悲しいことに、当時の人々は皆、自分勝手な欲望を抱いていました。諸侯は自らの権力を拡大する機会を得たいと考え、董卓と戦うために軍隊を送ることを望まなかったし、そうするのには理由もありました。危機的な瞬間に最初に立ち上がったのは曹操だった。曹操はわずか数千人の傭兵しか持っていなかったが、董卓と戦う勇気を持っていた。この戦うだけの正義感は偽りのものではない。もし曹操が当時漢王朝を簒奪する意図を持っていた、あるいは機会を利用して何かを奪取しようとしていたとしたら、彼は劉表や袁紹など力を蓄えた者たちに比べるとはるかに賢くなかった。したがって、曹操が若い頃に挫折したとしても、董卓と戦うために軍隊を編成したとしても、彼の本来の意図は漢王朝を支援することであった。後世の人々が彼の評価に基づいて批判するのは、彼にとって非常に不公平だ。曹操は皇帝を人質にしていたにもかかわらず、生涯を通じて自らを皇帝と称することはなかった。曹操の死後、他の者たちも自らを皇帝と称した。実際、曹操は漢王朝の忠実な救世主であった。 |
<<: 永宣は嘉慶帝の年長者に過ぎなかったが、なぜ太子の称号を与えられたのだろうか?
>>: 李世民はこれほど大きな貢献をしたのに、なぜ李淵は彼に王位を譲ることを望まなかったのでしょうか?
推薦する
水滸伝で王瑾はなぜ涼山に行ったのですか?彼の最終的な結末はどうだったのでしょうか?
王瑾は『水滸伝』の登場人物で、北宋時代の東京に駐屯していた80万人の近衛兵の指導者である。これについ...
明らかに:西遊記の弥勒仏の起源は何ですか?
弥勒仏といえば、皆さんもよくご存知だと思います。弥勒仏は多くの神話ドラマ、特に西遊記に登場してい...
『紅楼夢』で賈夫人が西人(シーレン)を嫌っていたのはなぜですか?王夫人と関係がありますか?
中国の古典小説『紅楼夢』に登場する希仁は、賈宝玉に仕える四人の侍女の一人です。『Interestin...
モンゴル料理 モンゴルの名物料理は何ですか?
食べ物に関しては、人それぞれに考えがあります。辛い食べ物が好きだったり、他の国の特別な食べ物が好きだ...
古代中国ではなぜ銃に赤い房が付けられていたのでしょうか? Hongyingの機能は何ですか?
おもしろ歴史編集部が、赤房槍の由来をまとめて、みなさんに詳しく解説しています。ぜひご覧ください。 2...
「秦鄂を偲んで 笛の音」は李白が書いた短い歌で、詩人の世間に対する慈悲を表現している。
李白は、雅号を太白、雅号を青連居士としても知られ、屈原に続くもう一人の偉大なロマン派詩人で、後に「詩...
徐霞客の旅行記:白岳山旅行記の原文
冰塵の年(1618年)旧暦1月26日、私は叔父の荀陽とともに衛之秀寧へ行きました。西門から出てくださ...
頤和園の40景の一つである蓬島瑶台はどんな感じでしょうか?
ご存知の通り、頤和園は清朝の皇室庭園で、雄大で壮麗です。では、四十景の一つである蓬島瑶台はどのような...
肖宝音の発音は?肖宝音の生涯の簡単な紹介。肖宝音はどのようにして亡くなったのか?
蕭宝印(485年または486年 - 530年)は、蕭宝印とも呼ばれ、字は智良で、南北朝時代の北魏の将...
徐有の最大の弱点は何ですか?なぜ彼は曹操に殺されたのですか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
「水龍音・南江双渓塔を通過」鑑賞、詩人辛其基は当時流刑となり南江県を通過した
辛其基(1140年5月28日 - 1207年10月3日)、元の字は譚復、後に幽安と改め、中年になって...
劉備が荊州太守の劉表のもとに避難したとき、なぜ劉表は劉備を受け入れたのでしょうか? ?
劉備は誰もが知っている人物です。彼は優れた才能と戦略の持ち主でしたが、庶民の家に生まれ、生涯を放浪し...
「半神半悪魔:天山の子供のようなおばあちゃん」における呉星雲の紹介
ヒロインのウーは、1994年の映画「天山童話おばあちゃん」の登場人物で、コン・リーが演じた。天山通老...
厳吉道の「皇街を歩く:春には南の緑の木々が花を咲かせている」:これは報われない愛についての詩です
顔継道(1038年5月29日 - 1110年)は北宋時代の有名な詩人である。名は書源、号は蕭山。福州...
元代に本当に殷之平は存在したのでしょうか?元王朝に関する10の興味深い事実をチェックしましょう!
元代には本当に殷志平がいたのでしょうか?元代に関するあまり知られていない興味深い事実を10個ご紹介し...