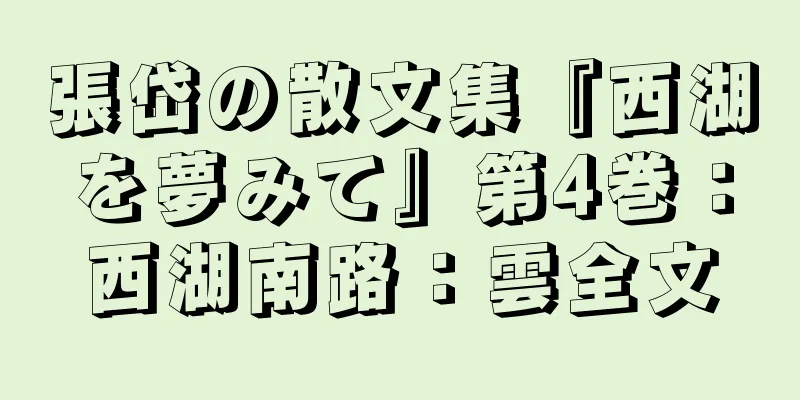清朝皇帝の一日はどんな感じだったのでしょうか?午前4時に起きる

|
「皇帝の野望を語り笑うのは、人生で酒に酔うのに劣る」ということわざがあるように、清朝の皇帝にとって一日はどんなものだったのでしょうか。今日は、Interesting History の編集者が関連コンテンツをお届けします。興味のある方は、ぜひご覧ください。 乾隆帝の起床時間は殷始、つまり午前4時頃でした。彼がまだ王子だった頃、彼はこの時間に起きて読書をし、書道を練習し、武術を練習しなければなりませんでした。彼は皇帝になってからもこの習慣を続けました。 乾隆帝は午前4時に起きて何をしたのでしょうか? まず、皇帝はいくつかの記念碑を拝見し、それから宮廷の侍女たちが皇帝に朝廷に参列するときに着る宮廷服を着るのを手伝った。これは皇帝が個人的な権威を誇示したかったからだけではなく、宮廷服は皇帝の威厳を反映するようにデザインされていたからだ。宮廷服は非常に複雑で重く、基本的に一人では着ることができなかった。重い宮廷冠も一人では着るのが難しかった。 朝の5時になると、乾隆帝は朝廷に出席するために和殿に行かなければならず、これが彼の公務の開始であった。通常、この時間には大臣たちは到着しておらず、乾隆帝は待っている間に朝食をとることさえあった。 清末の『北京郷愁』の斉汝山氏の記録によると、仕事中毒の雍正帝は午前3時に仕事を始めた。最初に出勤した軍部の大臣たちは、このために彼に「交奇」という名前を特別に与えた。 法廷の時間は、時には非常に短く、時には非常に長かった。この過程で、皇帝は主に大臣たちの報告を聞き、彼らの議論や口論を見守り、最終的に決断を下すか、「後で話しましょう」と言って法廷の閉会を宣言した。その後、皇帝は西園や東暖閣に移動したが、これでその日の皇帝の仕事が終わったわけではなく、ここで引き続き記念碑の視察やさまざまな政務をこなさなければならなかった。 正午、つまり午後1時頃、乾隆帝はようやく昼食をとることができた。通常、乾隆帝は一人で、海と陸の珍味が並んだ数個のテーブルを前にしていた。これが満漢の宴会だった。しかし、皇帝は特定の料理を食べることに集中することができませんでした。たとえ彼が特に好きな料理であっても、通常は3口以上食べることはできませんでした。一方では中毒を防ぐためであり、他方では彼は家臣に彼の好みが見られることを恐れていました。彼はほとんどの料理に触れませんでした。 昼食後、公務や軍事上の用事があれば、乾隆帝は太政官に赴いて仕事をした。仕事がすべて終わっていれば、乾隆帝はオペラを聴いたり、娯楽活動に参加したりする自由時間があった。しかし、このような自由時間は通常非常に短く、基本的にはさまざまな大臣との会談に費やされた。 乾隆帝は夜7時に夕食をとります。基本的には昼食と同じです。夕食後、自分の宮殿に戻り、政務を執ります。終わった後、「カードをめくる」と、ランダムに側室の宮殿に行き、そこで休みます。翌日の朝4時に起きて、また新しい繰り返しの生活が始まります。 |
<<: 董卓に対抗する連合軍では、関羽以外に華雄を殺す者がいなかったというのは本当ですか?
>>: 清朝の龍のローブは黄色でしたが、他の王朝ではどうでしょうか?
推薦する
康熙辞典:清朝の康熙帝の治世中に編纂された中国語の辞書。
『康熙字典』は清代の康熙帝の時代に出版された書物で、張毓書、陳廷静らが執筆した。明代の梅英左の『子会...
雲南省のハニ族の人たちは新年に何をするのでしょうか?習慣は何ですか?
ハニ族の新年の習慣:彼らは年に2回新年を祝います。一つは十月祭、もう一つは六月祭です。ハニ暦では10...
モンゴルの結婚式の習慣の特別なところは何ですか?
モンゴル人は中国の少数民族の一つであり、主に東アジアに分布する伝統的な遊牧民です。長期にわたる遊牧生...
「君子には三つの喜びがある」ということわざにある三つの喜びとは何でしょうか?歴史的な暗示はありますか?
こんにちは、またお会いしました。今日は、Interesting History の編集者が「紳士には...
「狼煙と狼火」という用語はどこから来たのでしょうか? 「狼煙」はなぜ「狼煙」と呼ばれるのでしょうか?
「狼煙と狼火」という用語はどこから来たのでしょうか? 「狼煙」はなぜ「狼火」と呼ばれるのでしょうか?...
ミャオ族の祖先はどのようにしてミャオ族の医療文化を創り上げたのでしょうか?
ミャオ族は中国の歴史上最も古い民族の一つです。 5000年前、長江中下流と黄河下流に住んでいた蚩尤が...
後漢書第28巻の桓・譚・馮燕の伝記原文
桓譚(読み方:ジュンシャン)は、沛国の宰相であった。父成帝の治世中、彼は楽相を務めた。譚は父の任命に...
『紅楼夢』の賈家と江南の甄家との関係は何ですか?
『紅楼夢』では、甄家と賈家は古くからの友人であり、親戚でもあります。 Interesting His...
『紅楼夢』における李婉の判決は何ですか?彼女と王希峰との関係は?
李婉は古典小説『紅楼夢』の登場人物であり、金陵十二美女の一人である。今日は、Interesting ...
『彭公安』第29章:費天宝が酒を注ぎ英雄を語る;楊祥武が九龍杯を盗む
『彭公安』は、譚孟道士が書いた清代末期の長編事件小説である。 「彭氏」とは、清朝の康熙帝の治世中の誠...
三勇五勇士第92章:若い英雄はお金を使いすぎて、お酒を飲みすぎて酔っ払います。老ゲはキジを盗もうとして怪我をします。
清朝の貴族の弟子、石宇坤が書いた『三勇五勇士』は、中国古典文学における長編騎士道小説である。中国武侠...
李山昌は二度も死から救ってくれる金メダルを持っていたのに、なぜ朱元璋に殺されたのでしょうか?
皇帝が一人で王朝を建てるだけでは十分ではありません。文武両道の多くの有能な人々の協力が必要です。朱元...
『紅楼夢』で、周睿佳が王希峰に宮廷の花を贈ったとき、平児は何をしていたのですか?
平児は王希峰の持参金係であり、賈廉の側室であった。本日は、Interesting History編集...
肉の脂身と新鮮さを保つために、唐代にはどのような調理法がよく使われていましたか?
「国は民で成り立ち、食べ物は民の天国である」と言われています。軍事、経済、文化がかつてないほど繁栄し...
八橋ってどんな橋ですか?八橋で何が起こったのですか?
八橋とはどんな橋ですか?八橋で何が起こったのですか?次の興味深い歴史編集者が詳しく紹介しますので、読...