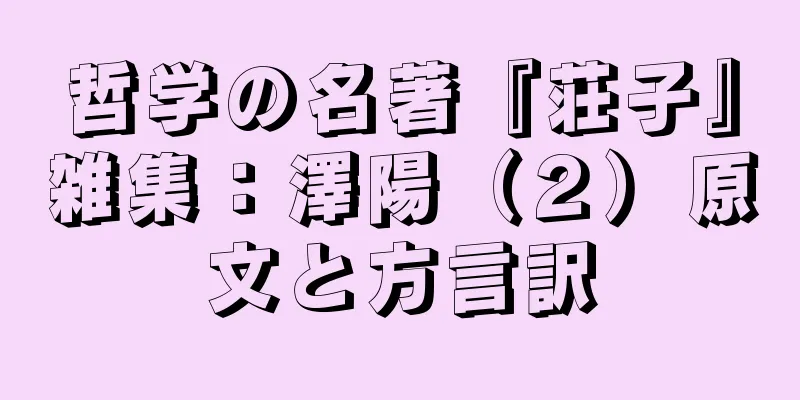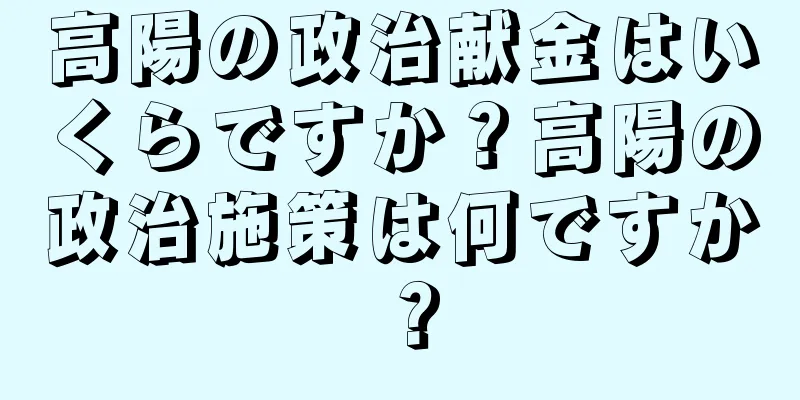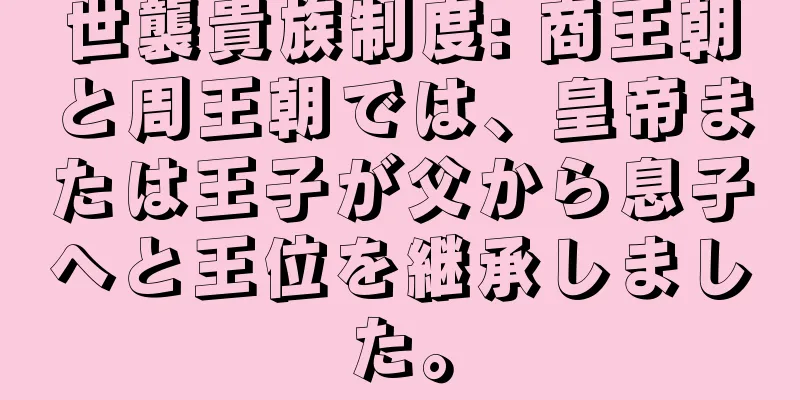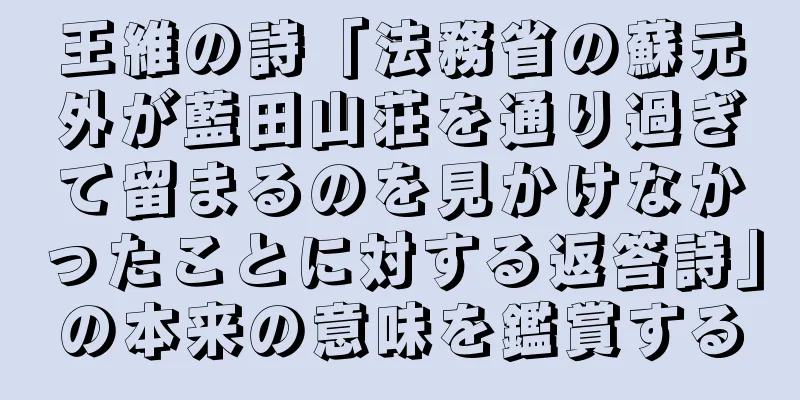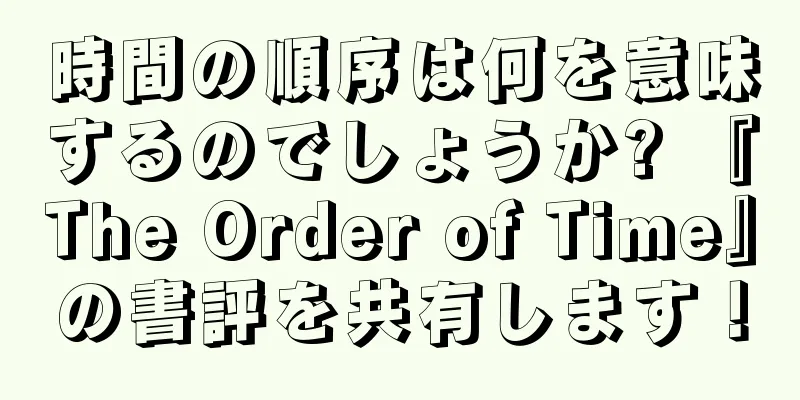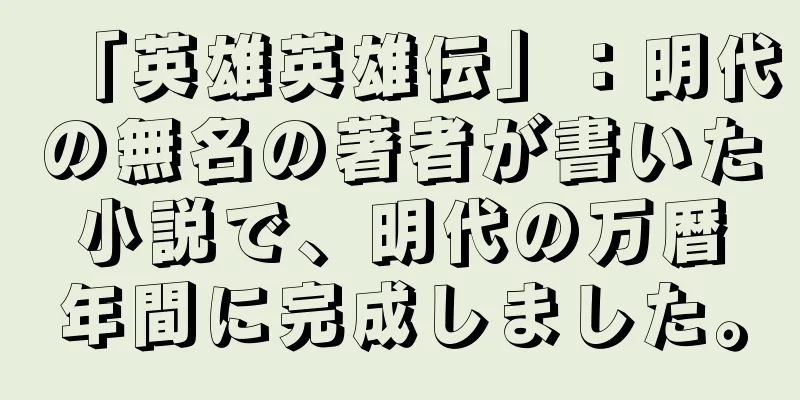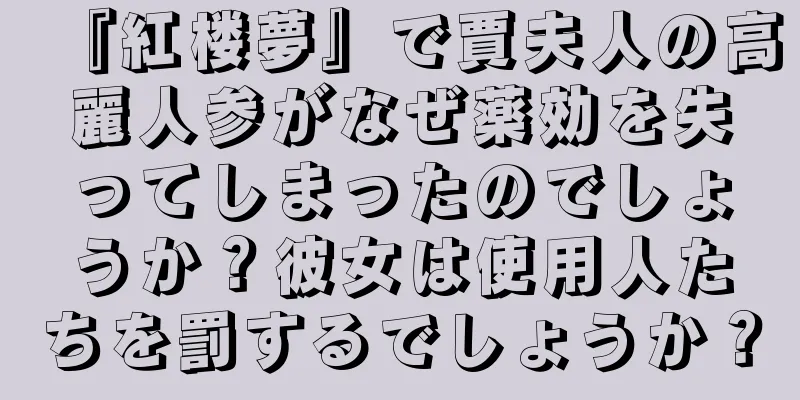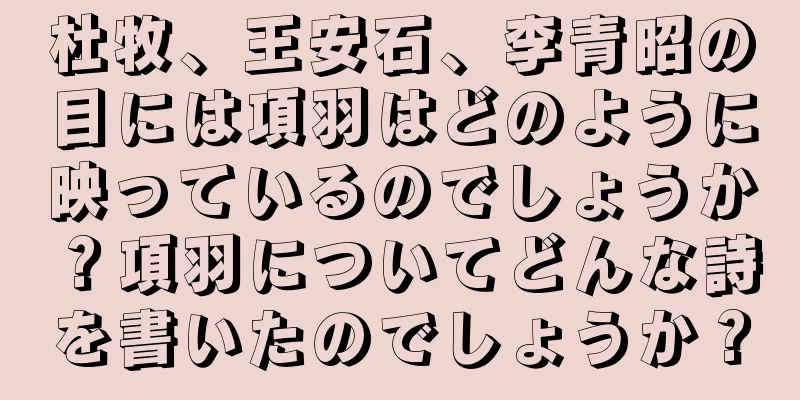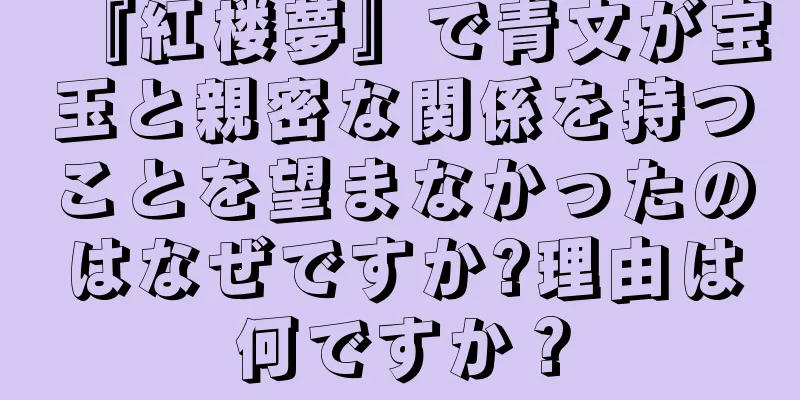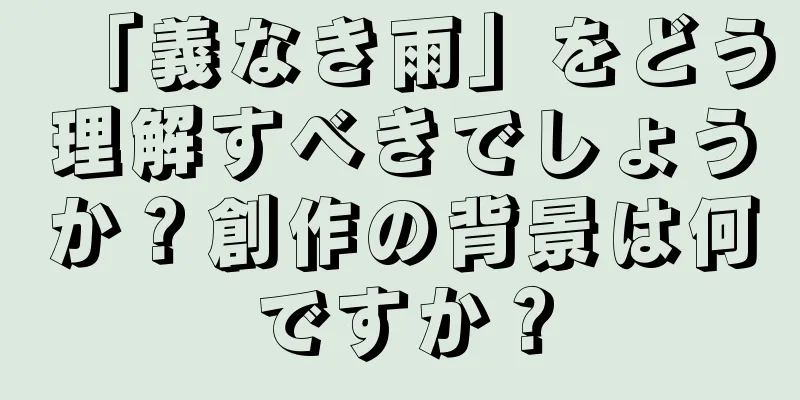李清昭は梅の花を好む、その本当の理由を明かす
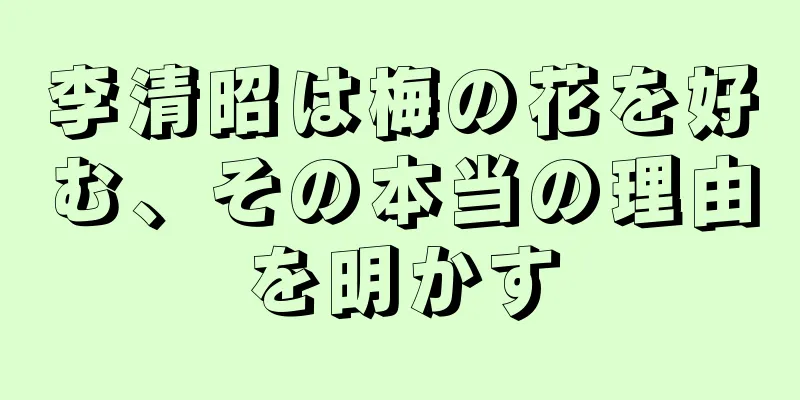
|
体は鈍い緑と黄色で、性質は柔らかく、感情は遠く、香りだけが残ります。なぜ薄緑や濃い赤である必要があるのでしょうか? 花の中ではそれが最高なのです。梅は嫉妬し、菊は恥じるに違いない。中秋節を表す絵が描かれた手すり。あの詩人は本当に無慈悲だ、なぜあの時報酬をもらえなかったのか?梅の花を題材にした悲しい詩からは、李清照の優美で憂鬱な感情が伝わってきます。李清昭の文章では、梅の花は違った感じがするようです。では、李清昭はなぜ梅の花をそれほど愛したのでしょうか?興味のある読者と『Interesting History』編集者は一緒に調べてみましょう! 梅の花を自分自身の比喩として使う 李清昭さんの文章からは、彼女が本当に梅の花に特別な愛着を持っていることが感じられます。彼女は他の花はすべて愛でていましたが、菊について書くときは梅の花について堂々と書きましたが、実際は自分自身について書いていたのです。その変わらない清らかさと強さは梅の花を引き立て、李青昭自身も梅の花のように高貴で誇り高い生活を送っていた。 李清昭が残した詩をよく読むと、梅の花が全体の3分の1を占めていることがわかります。李青昭の人生は喜びと幸せ、純真さとロマンスに満ちていた。彼女はその困難な人生を通して、多くの苦難、悲しみ、悲嘆を経験しました。彼女は梅の花と切っても切れない絆で結ばれているようで、梅の花の気高く優雅な精神と彼女のこの世のものとは思えない魂がぶつかり合っているようでした。 悲劇的な幼少時代 李青昭さんは幼い頃に母親を亡くしたため、心の中に多くの悩みを抱えていました。それで彼女は自分を梅の花に例えました。彼女は吐き出す場所のない感情を梅の花に溶かします。梅の花は彼女であり、彼女は梅の花です。運命が変わるにつれ、彼女の靴の梅の花は少女から若い女性へ、そして最後には人生の浮き沈みに満ちた老婆へと変化しました。 中年の憂鬱 李青昭さんは少女時代には悩みを分かち合える人がいなかったが、夫と結婚してからは当初は生活が順調だった。しかし、政府の悲劇的な死後、彼女自身は梅の花を鑑賞する楽しみを失ってしまった。こうして、李青昭さんの生活は次第に夫を恋しく思う気持ちでいっぱいになり、毎日涙を流しながら過ごすようになった。 孤独な老後 晩年、李青昭の国は荒廃し、彼女の家族は没落し、夫はすでに亡くなっていた。彼女は毎日、さまよいながら惨めな思いをしていた。もうそんなことはできなくなり、梅の花を鑑賞することに集中しました。それ以降、梅の花について書くことはありませんでした。 要約する 自分を梅の花に例えるのは、李青昭の人生を忠実に表現している。彼女は幼い頃に母親を亡くしており、その想いを梅の花に託して多くの梅の詩を書いた。彼女は若い頃に結婚した後、梅の花の詩の中で結婚生活について書きました。しかし、中年から老年にかけて、李清昭は梅の花について書くことをやめたようだ。しかし、梅の花は彼女の人生において非常に重要な役割を果たしました。それで、李青昭は梅の花が好きです。 |
<<: 「古代月の歌」の執筆背景は何ですか?これをどう理解すべきでしょうか?
>>: 「深夜の呉歌・秋の歌」の原文は何ですか?どうやって鑑賞すればいいのでしょうか?
推薦する
『菩薩人 黄雲三千里紫峠』の著者は誰ですか?どのように評価したらいいのでしょうか?
菩薩男 - 黄雲紫三千里那蘭興徳(清朝)黄色い雲と紫色の境界線が三千里を覆い、女壁の西側ではカラスが...
古代詩の鑑賞:「詩集:黄色くない草は何か」
『詩経』は中国古代詩の始まりであり、最古の詩集である。西周初期から春秋中期(紀元前11世紀から6世紀...
初期の自然崇拝によって形成されたタジク人の「鷲文化」
イーグルダンスは、中国の民族舞踊の中でも非常に特徴的な伝統的な舞踊形式で、高い芸術的価値を持っていま...
明代志農(選集):明治部列子全文と翻訳
『シンクタンク全集』は、明の天啓6年(1626年)に初めて編纂された。この本には、秦以前の時代から明...
秦強の鞭掃き灯籠花とは何ですか?この技術はどれくらい難しいのでしょうか?
秦強の鞭掃き灯花とは何なのか知りたいですか?その技法はどれほど難しいのでしょうか?実は、鞭掃き灯花は...
『残雪が冷たい絵画のスクリーンに輝く』の著者は誰ですか?どのように評価したらいいのでしょうか?
環西沙:冷たい絵画のスクリーンに残る雪が光る那蘭興徳(清朝)冷たい絵のスクリーンに残雪が明るく輝き、...
戦国時代後期の楚の国、屈原の詩「橙頌」の鑑賞と創作背景
「オレンジへの頌歌」は物についての抒情詩です。前半は感情と物体の表現についてであり、描写的な要素が主...
唐の玄宗皇帝の娘、宋公主の紹介。宋公主の夫は誰だったのでしょうか?
宋公主(?-?)、唐の玄宗皇帝李龍基の娘。母親は不明。彼女は最初、平昌公主と名付けられました。天宝5...
張岱散文集『西湖を夢みて』:第1巻・西湖北路・六聖寺全文
『西湖夢想』は、明代末期から清代初期の作家、張岱が書いた散文集で、全5巻72章から成り、杭州周辺の重...
『紅楼夢』の王夫人はなぜ金伝児を追い払ったのですか?
王夫人が金川を追い出そうとした最も直接的な理由は、賈宝玉のためであった。宝玉の名誉のためであり、また...
坤申の「文公講堂」の本来の意味を鑑賞する
古代詩「文公講堂」時代: 唐代著者: セン・シェン文公は姿が見えなかったので、蜀の民にその旨を伝えさ...
呉璋の「金鹿曲・玉玉虎天説」:この詩は作者が23歳くらいの頃の心の声を表現している。
呉璋(1799-1862)は、清朝の有名な女性作詞家、作詞家である。彼女の芸名は萍祥、号は玉允子。彼...
済公第184章:王三虎が大悲院の秘密を明かし、空中で雷鳴を響かせて鉄面仏を捕らえる
『済公全伝』は清代の学者郭暁廷が書いた神と悪魔についての長編小説である。主に済公僧侶が世界中を旅しな...
『続・英雄物語』が制作された背景は何でしょうか?主人公は誰ですか?
『続英雄譚』は、明代の無名の作者(紀真倫という説もある)によって書かれた長編小説で、明代の万暦年間に...
『紅楼夢』で劉おばあさんは大観園を訪れたとき、なぜ一宏院に行ったのですか?その後何が起こりましたか?
『紅楼夢』の中で、劉おばあさんが大観園を訪れた場面は、この本の中で最も古典的な章の一つと言えます。次...