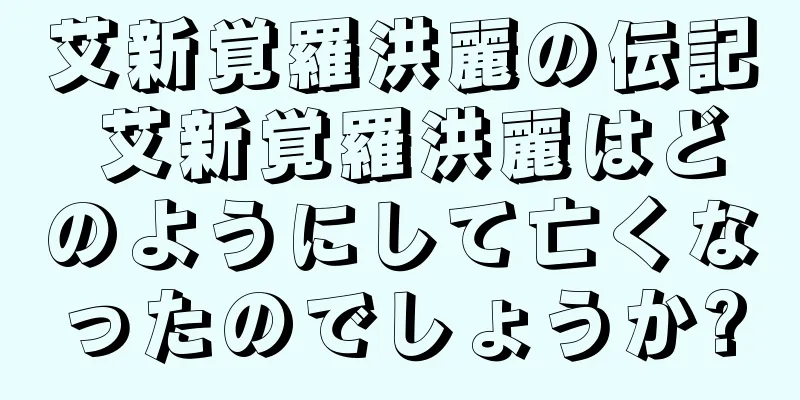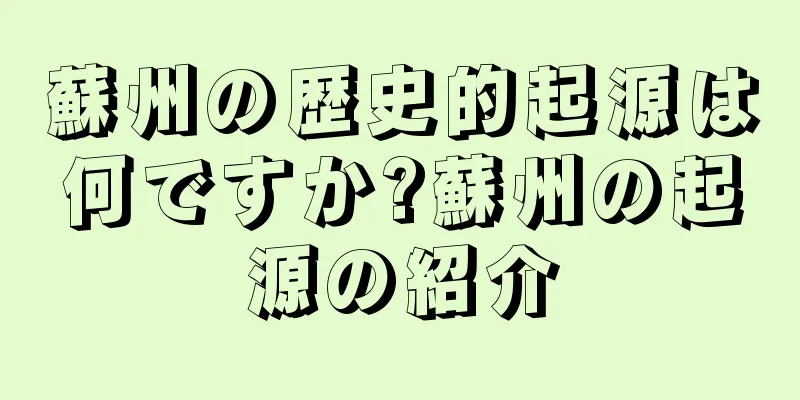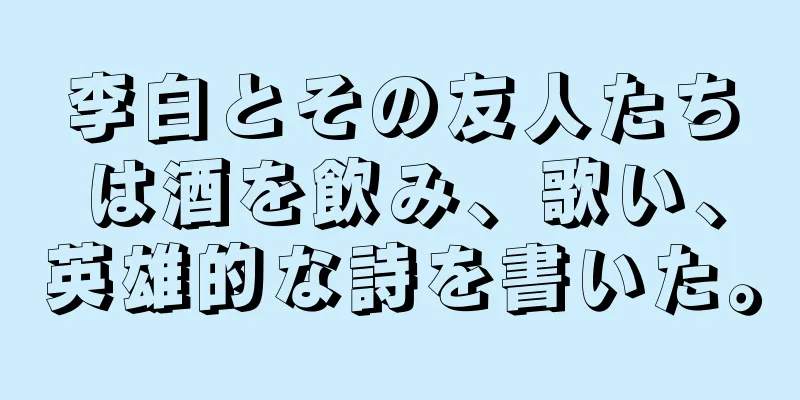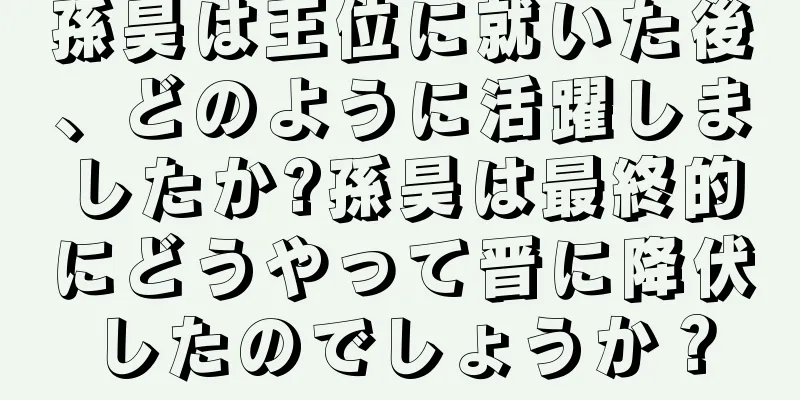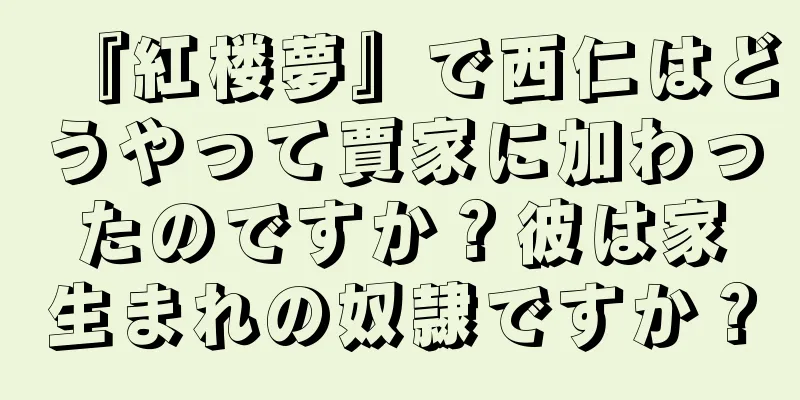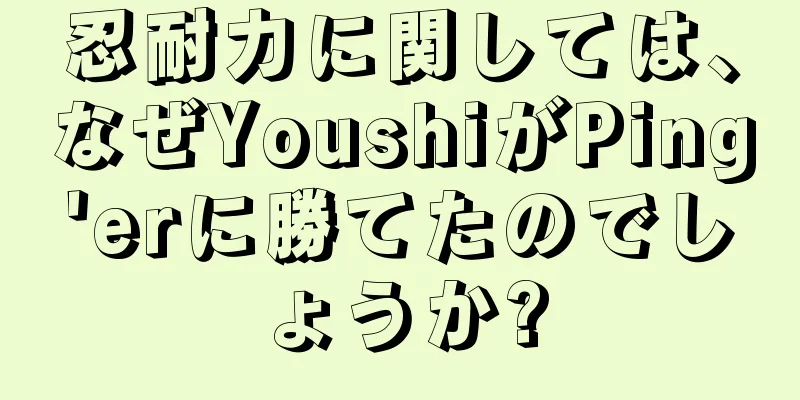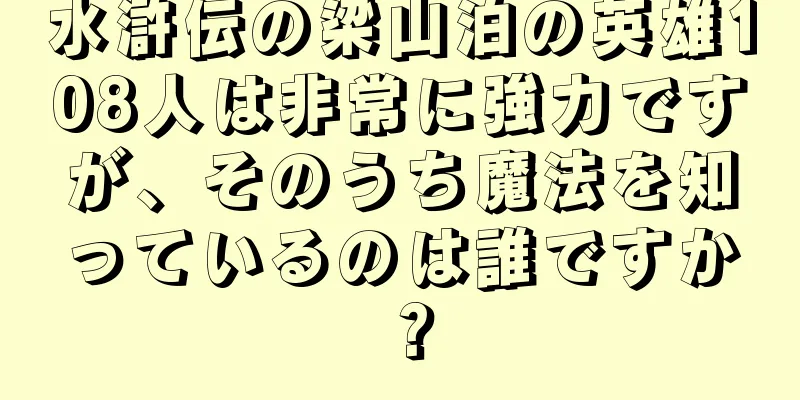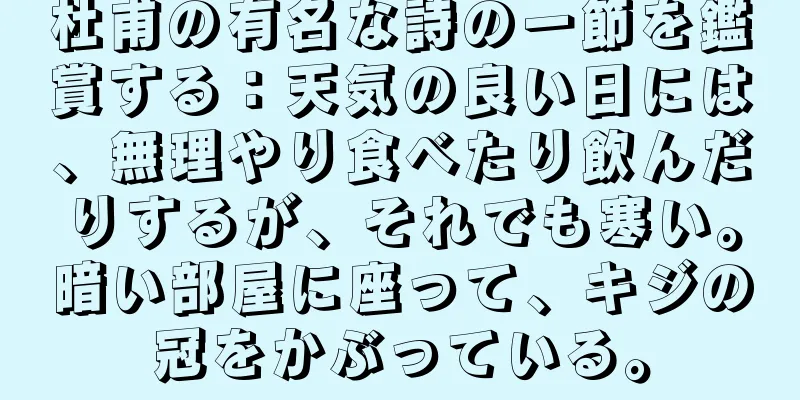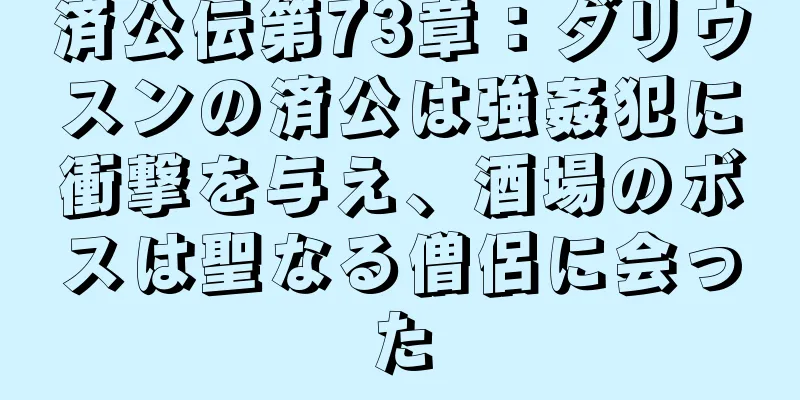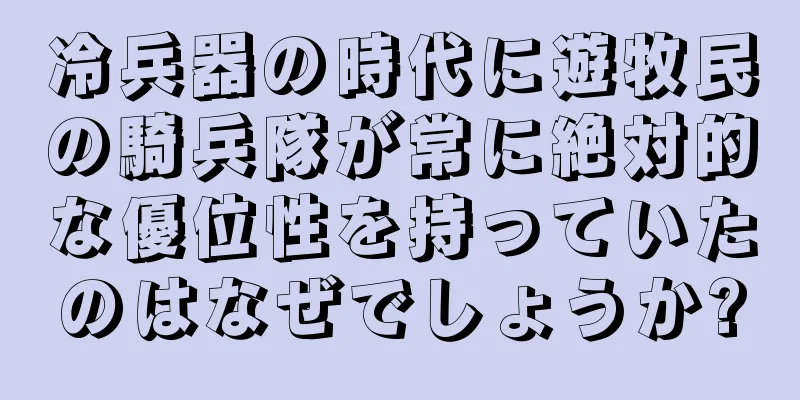趙の孝成王はなぜ秦に宣戦布告したのですか?戦国時代を舞台にした3つの戦略決戦!
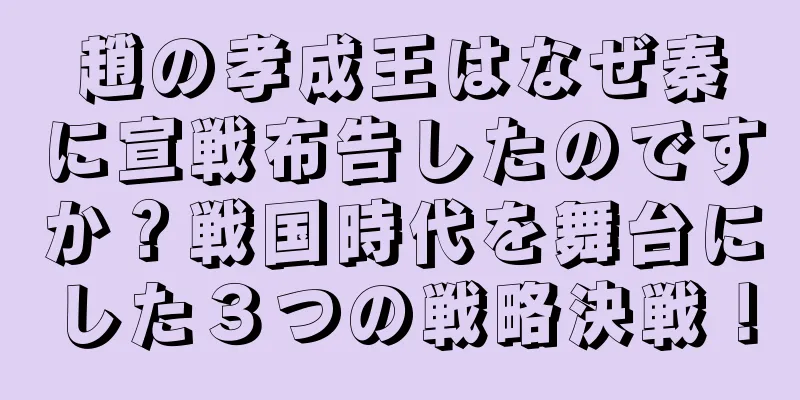
|
今日は、おもしろ歴史編集長が、戦国時代の戦略決戦を3つご紹介します!皆さんのお役に立てれば幸いです。 趙孝成王は趙国の第8代君主でした。若く精力的な趙孝成王は、治世の初年に斉国と同盟を結び、秦国の攻撃を撃退しました。当時、趙国は胡服と乗馬を何年も推進した結果、七大国から首尾よく昇格し、当時秦国に対抗できる唯一の国となった。紀元前262年、漢は上当県を趙国に与えた。その目的は秦国の注意をそらすことだった。趙の孝成王が上当県を受け入れると、秦国は間違いなく趙国に注意を向けるだろう。趙の国力は大きく向上したものの、秦よりはわずかに弱かった。残念なことに、自信にあふれた趙の孝成王はこれをはっきりと理解せず、秦を攻撃することに熱心だった。その結果、彼自身の軍隊は大きな損失を被り、二度と回復することはなかった。 「昌平の戦い」について、誰もが知っているわけではないかもしれません。しかし、「紙の話」となると、ほとんど誰もがそれを知っています。 ああ、書類上で議論されていた戦いは昌平の戦いだったことが判明しました。 まず、「紙上で戦争を語る」というのは、昌平の戦いにおけるいくつかの状況を指しているのかもしれないが、その発言自体は明らかに後世の捏造である。つまり、昌平の戦いは実際には「紙の上で戦争を語る」という慣用句の起源ではないのです。 理由は簡単です。当時は「紙」というものがまだ発明されていなかったからです。 「昌平の戦い」を知る人ならば、40万人の捕虜を「生き埋め」する残虐行為で有名な戦いだったことも知っているだろう。それは歴史の教科書にも記載されている、「秦の統一」を加速させた重要な戦いでもありました。 この血なまぐさい戦いは、間違いなく戦国時代全体で最も重要な戦略的戦いであったと著者は言いたい。 戦略決戦! (白奇) 1. 「戦略的決戦」とは何か? 「決戦」というと、当然「最後の」とか「最後の戦い」を思い浮かべるようです。 必ずしもそうではありません。 中国や海外の歴史上、一回の戦闘で戦争全体が勝利した少数の例を除けば、実際の「戦略決戦」のほとんどは「最後の戦い」ではありません。 それに比べて、「最後の戦い」は「最後の一撃」だった。 例えば、「解放戦争」。よく知られている「三大戦闘」は「終結」ではなく、間違いなく「戦略的決戦」でした。 戦略は「戦術」に対応し、「戦争の傾向」、すなわち強弱、積極的と消極的、攻撃と防御、これらの要素が「終局」に関係し、その発展と傾向の変化を指します。大規模戦争、特に長期にわたる大規模戦争では、戦略が決定的な役割を果たします。戦略の正確さと、正確さに向けての戦略のタイムリーで効果的な調整は、最終的な勝利の基本条件です。 名前が示すように、決戦とは、強さ、攻防、生き残りを決めることを目的とした、交戦当事者(通常は 2 つの当事者ですが、複数の当事者の場合もあります)間の「究極の戦い」を指します。規模は大きくないかもしれませんが、通常は最後まで戦い、ある状態や傾向を「決定」したに違いありません。 戦略にかなう決戦は戦略的な決戦である。 戦略を伴う決戦は、通常、規模が大きくなります。実際、多くの場合、それは単一の戦闘ではなく、戦略的に相互にリンクされたグループまたは複数の戦闘です。 (秦の昭襄王と白起) (II)戦国時代の三つの戦略決戦 戦国時代は私の国の歴史において非常に特別な時代でした。この時期、現在の我が国の領土の約3分の1に相当する地域に分布していた数十の属国が戦争を手段に拡大し、大魚が小魚を食い尽くすという状況が続きました。最終的に、属国の一つである秦国が武力で他のすべての属国を滅ぼし、「大統一」の政情を形成しました。 戦国時代の始まりと終わりの時期(年)については、「止」が終わりであるというのが最も明確ですが、「始まり」である「起」の年については学界でもさまざまな意見があります。主流なものは3つあります: 一つは、孔子の指導のもと『春秋』の編纂が完了した後であったということである。この見解は古代において高く評価されていました。 2つ目は、現代でより広く受け入れられている「三家が晋を分裂させた」という説で、つまり、かつての属国であった「晋」が、その支配下にある「韓」「魏」「趙」の3つの分裂勢力によって分割された。そして、分割勢力は、当時の名目上の「天下の共同統治者」であった周の皇帝によって承認され、新たな属国として列聖された(いわゆる「三金が皆称号を得た」)。 春秋時代と戦国時代を分ける境界線は「郭堅が呉を滅ぼした」時であるという比較的新しい説もあります。これは、個人的にはあまり意味がないと思います。しかし、それは間違いなく学界が抱いている見解なので、とりあえず列挙しておきましょう。 上記の 3 つの記述は、具体的な年に関しては実は非常に近いもので、いずれも紀元前 5 世紀半ばのものです。したがって、そういったことを勉強しない一般人としては、戦国時代の始まりは紀元前5世紀中頃であると想定するのが一般的です。 紀元前3世紀後半(紀元前221年)に秦が中国を統一するまで、戦国時代という特別な歴史的時代は約220年から230年続きました。 この二百年の間に、大小さまざまな戦争が数え切れないほど起こり、その多くは大規模で広範囲に及び、血なまぐさいものでした。しかし、私の浅い歴史知識に基づくと、本当に「戦略的決戦」と呼べる事例は3つしかありません。発生順に古いものから新しいものまで並べると、次のようになります。 最初の出来事は、紀元前4世紀後半(秦の昭襄王の初期、秦の宣太后が権力を握っていた時代)に起こった孟嘗公による秦への攻撃でした。 攻撃側は斉王の縁戚で「孟嘗君」の称号を持つ有力貴族の田文が率いる「連合軍」で、斉、趙、魏を中核として大小十数ヶ国の属国から構成されていた。攻撃を受ける側は秦であった。これは秦国に対する「縦横無尽」戦略の最も成功した戦いであり、200年以上にわたる戦国時代の数回の「秦国縦横無尽の攻勢」の中で、秦国の東側にある「要塞」である漢谷関を突破した唯一の戦いでもあった。軍隊は秦の首都、咸陽へと直行した。その結果、秦は平和と引き換えに領土を譲渡した。 2つ目は、紀元前3世紀前半(秦の昭襄王の末期)に起こった秦と趙の間の昌平の戦いです。 主に秦と趙の二つの属国のみが関与しています。結果は秦が勝利した。 3つ目は、紀元前3世紀中期から後半にかけて秦が五国を征服した戦争です。 攻撃側は秦国で、当時は「秦の正王」として知られ、歴史上は「秦の始皇帝」として知られる嬴政が統治していました。攻撃の標的は、漢、魏、燕、趙、楚の 5 大属国でした。これらの戦争の中で最大かつ最も決定的だったのは秦楚戦争で、ほぼ 3 年間続き、双方合わせて 100 万人以上の軍隊が参加しました。そのため、「秦楚の戦い」とも呼ばれています。なんと言っても、これは戦国時代の「最終決戦」だ! 結果は秦が韓・魏・燕・趙・楚の五国を制圧し、斉を降伏させた。秦を除く「戦国七国」は壊滅し、「六王は皆罪を認め、天下は平定」した! この3つのうち、秦と趙の間の長平の戦いは規模が最大ではなく、主な戦闘過程には2つの属国しか関与していなかったため、「影響」は十分に広がらなかったようです。しかし、軍事戦略の観点からは、「攻守の状況が変わった」という点で画期的な意義がある。 3. 昌平の戦いの戦略的意義 前述のように、秦と趙の長平の戦いとその結果は、「攻防の局面が変わった」という点で、戦国時代の「大局」において画期的な意義を持っていました。著者は、この意義が「世界の大局」に及ぼす影響は、秦末の「天下を平定する」ための「最後の決戦」をも凌ぐものであると信じている。 武力で成し遂げた「大統一」が「果実」ならば、六国を征服する最後の決戦は「収穫」であり、数十年前の秦と趙の長平の戦いは「種まき」である。 乱暴な類推はさておき、昌平の戦いの戦略的意義をもう少し明確に語るには、まず当時の「大勢」、つまり「基本情勢」と「基本パターン」を簡単に整理する必要がある。 戦国時代の七国、楚、魏、斉、趙、燕、韓、秦(戦国時代初期の各国の総合力による順位)は、多くの人が知っています。また、戦国時代にはこの7つの属国しか存在しなかったと誤解している人も多いようです。実際、秦が統一する少し前まで、当時「天下」と呼ばれていた地域には、まだ数十の小さな属国が存在していました。 戦国時代初期には、「西」の遠く離れた場所にあった秦国は、総力としては最も弱かったはずである。状況はひどく、他の「七王国」の六つの国によって分割されそうになったほどでした。中国は、軍国主義的で好戦的な「国民性」と比較的「高水準」の「個人戦闘能力」を除けば、他のあらゆる面で他の「大国」と比較することはできず、その総合的な軍事力は言及する価値すらない。 商閻の改革と遠国との友好と近国の攻撃という二つの戦略的突破を経て、「貧学生」だった秦は、70~80年(商閻の改革20年以上、恵文王20年以上、宣太后が政局を支配した40年近く)で「優秀な学生」に躍進したが、まだ「頂点」やナンバーワンのレベルには達していない。 (秦の昭襄王) この70年から80年の期間の中期または前期、「徽文君」の時代(英思王は在位28年、14年に即位。史料によれば、以前は「徽文君」と呼ばれ、後に「徽文王」と呼ばれた。宣太后の米は妾のお気に入りだった)には、他の属国を併合するという「究極の国策」が基本的に確立された。外交官の張儀が秦の宰相になった後、この戦略はほぼ完全に確実なものとなった。 しかし、当時の秦の力は、この「大目標」にはまだ程遠いものであったため、対外的には「遠国を友好に結び、近国を攻撃する」戦略を採用し、国内的には軍事力の強化に注力した。 昭襄王(英嗣と宣太后の長男、英済、在位56年)の中期から後期、つまり宣太后が権力を放棄して亡くなった後、秦の総合的な国力と軍事力は大きく進歩し、世界を併合するという「壮大な目標」ははるかに近づきましたが、依然として「強大な敵に囲まれている」状態でした。 当時、秦の「進軍」と「狼の目を持つ山東」、秦によって著しく弱体化された韓と魏、燕と趙の親密な関係、斉と楚の勢力の増大、貴族の拡大、垂直同盟の傾向の台頭など、多くの複雑で相互作用する要因により、秦は政治的にかなり孤立し、外交戦略の役割はますます弱くなっていました。 魏の樊儒に代表される「新客」の影響を受けて、母親の宣太后の強力な支援を失い、彼女の巨大な「政治的影」からも解放された秦の昭襄王は、外交政策を「遠国を友にして近国を攻める」から「近国を友にして遠国を攻める」へと大きく調整しました。 当時、「七国」の「ボス」は楚国であり、最大の領土、最も豊富な資源、最大の人口、最強の総合経済力を有し、「理想の議会」の前提の下で最強の「理論上の」軍事力も持っていた。 「国力」という点では、楚に次いで斉は間違いなく「二番目の兄弟」であり、秦はせいぜい「二位タイ」である。軍事力の面では、斉と秦は互角である。 楚国はあまりにも大きく、政治体制は緩く、軍事力の大部分は「再封された」貴族の「私兵」で構成されていました。戦争の極めて深刻な脅威の下でのみ、国全体が真に「団結」することができました。そして、それはただ、たぶん。 (リアン・ポー) したがって、軍事的に言えば、「生き残りの最終段階」まで、チューの「ボス」としての地位は空虚なものとみなすことができます。 戦闘、特に正面からの戦闘において最強の勢力は趙国であり、胡の服を着て馬に乗って矢を射、北方の遊牧民と長く戦い、寛大で悲劇的な人物が多かった。軍事力に基づいて建国された国である秦は、これまで趙との規模の異なる多くの戦いで勝ちよりも負けが多かった。 しかし、趙の全体的な国力は比較的弱く、楚、斉、秦ほど優れていませんでした。 地理的に見ると、秦と楚は隣接しており、秦と斉は最も離れており、秦と趙は隣接していないものの、それぞれの勢力の「伸張」が「ライバル」の傾向となっている。 秦国から見れば、楚国との戦争が小規模であれば、問題は解決しない。大規模であれば、「短く、平らかに、速く」できなければ、たとえ他国がその状況を利用して略奪しても、単に時間を浪費する余裕はない。 武力で国を建て、武力で国を安定させ、武力で天下を取ろうとする「強国秦」は、「近くを友とし、遠くを攻める」という全体戦略の下、将来主導権を握りたいなら、軍事行動は「戦略決戦」の姿勢と規模をとるべきだ。効果から言えば、強い相手を選ぶべきだ……このように、「戦略決戦」の相手には斉と趙の2つの選択肢がある。 どちらかを選んで勝てば、「全体的な状況」は必然的に劇的に変化します。 そこで、昌平の戦いが起こりました。 この戦いの後、最も強大な趙国は「翼を折った」ため、遠く離れた燕国と斉国は恐怖に陥った。長い間「心配」がなかった強大な秦国は、自信を持って隣国の韓と魏を大胆に虐殺することができ、さらに自信を持って牙をむき出しにして大ボスの楚国に見せつけた。このように、「近くの国を友にして遠くの国を攻める」ことは大きな利益をもたらし、秦に対する連合軍の抵抗はさらに困難になり、後の賢人が述べた「秦への買収」は比較的「安定した状態」を形成しました... 昌平の戦いの勝利がなければ、その後の「大統一」はなかったと敢えて言うつもりはありませんが、その「最終的な勝利」はずっと後になってから、はるかに困難なものになることは基本的に確実です。 (趙括) 4. 「偶然の」戦いや結末はほとんどない 前述のように、当時の秦国には「戦略的決戦」を挑むことのできる「潜在的な」敵、つまり斉国と趙国が存在した。 しかし、これは「理論上」のことです。 実際には、状況を少し理解していれば、この多肢選択式の質問に答えることは難しくありません。 答えは、趙国に違いありません。 趙は斉よりも戦闘が得意です。趙に勝てば斉は恐れるでしょう。逆に、趙に勝てない可能性もあります。 趙国は比較的接近しており、より接近した「非陸」戦闘を選択する可能性があり、「技術」レベルから見ると、手配は簡単です。 趙の国力は斉や秦ほど強くない。本当に「焦る」気になれば、秦なら余裕だ! 理論上、斉を攻めれば趙が助けに来る可能性が高いので、一対二の戦いとなり、勝つ可能性は低い。しかし、趙を攻める場合、地理的な位置が正しければ、斉の助けの可能性は大幅に減少する。 これらはすべて「歴史上運命づけられている」。この「戦略決戦」の相手は趙国であるべきであり、そうでなければならないし、そうであり得るのは趙国だけである。 後世の歴史、軍事、政治の専門家、追随者、愛好家の多くは、昌平の戦いの発生からその過程、そして結末に至るまで、そこには「偶然の」要素があったと信じていました。しかし、当時の「一般的な傾向」と戦争の地域的な「微気候」を組み合わせ、さらに注意深く考えてみると、これらすべての偶然はほとんど必然であったことがわかるでしょう。この点について、著者は「大秦」について執筆する際に非常に注意深く研究しました。 「戦略決戦」を選択し、対戦相手に趙を選ぶことは以前にも言及されています。 特にこの戦争自体について言えば、あらゆる要素、あらゆる段階が「必然性」に満ちている。 まず第一に、これは趙を「誘い出して」秦に対する「決戦」を開始させるための戦争でした。 平原君趙勝は趙国の大貴族で、王族の近親者であり、歴史上の「四君子」の一人であり、「縦連して秦を攻める」派の比較的頑固な支持者であった。彼は軍事に関してある程度の知識があり、朝敵の力は「優勢」であった。彼は趙国の「自強」を主張し、軍事拡大の「急速な道」を進む傾向があった。当時の趙国最高指導部に彼が多大な影響力を持っていたこともあって、戦闘力で第1位だった趙国は、強大な秦国の挑発に直面すれば、基本的にいつ爆発してもおかしくない火薬庫となっていた。 戦争の火種となった上当県の帰属問題も避けられない選択だった。 上当県は漢国の「非地域」であり、漢国の中心地からは遠く離れていましたが、趙国には比較的近かったです。韓国は秦に最もいじめられた国であり、また秦への賄賂に最も熱心だった国でもある。秦は「非領土」を奪取したかったが、抵抗する勇気も力もなかった。強大な秦がこの地を欲しがっていたとき、韓国の基本的な態度は絶対的な寛容さでした。このような状況では、秦に対する抵抗を主張する地方官僚がいたかどうか、あるいは地方民衆の中に「秦を支持しない」という世論があったかどうかは、強大な秦に対して「剣を抜く」という趙国の決断に影響を与えなかった。なぜなら、趙国は昔からこの地に目を付けており、自国のものだとすら考えていたからだ。ひとたび「秦に負け」れば、資源と国家の名誉の問題になるだけでなく、玄関先で攻撃されるという現実の安全保障上の危機にもなるでしょう。 そのため、秦の「領土占領」というほぼ「フェイント」の試みに直面して、趙が急いで上当県を「占領」したのは「条件反射」の行動でした! 秦軍の圧倒的な力に直面して、強い兵馬、戦績、優れた将軍(世界で唯一、白起を必ず倒すと大胆に言った将軍、廉頗)を擁する趙は、簡単に「状況を利用して」大戦闘を開始する決断を下すことができました。 中国の地図を手に取って、趙国(現在の河北省中南部、河南省北東部、山西省東部)、斉国(現在の山東省の大部分、河南省北西部、山西省西部)、秦国(現在の陝西省の大部分、河南省北西部、山西省西部)の位置を見れば、山西省の北中部に位置する「上当」(現在も同じ地名)で戦っていたことが容易に分かる。交戦中の秦と趙の「補給線」は長さに差はあるものの、特に大きな差ではなかった。そして、趙を援助できる唯一の力を持つ斉が本当に援助するとしたら、戦線が長すぎるだろう。 さあ、ここにあります!ここにあります!この戦場は「偶然」ではなく「選ばれた」ものです! 具体的な戦闘過程において、廉頗を陥れ、趙王と平原君の関係を挑発し、趙国の有力官僚を買収するなどの「秘密戦争」が後世の歴史書や権威ある文書に記録されているが、これは偶然ではなく、土壇場での指揮官交代や、戦争に対する姿勢、戦略、勝敗予測に関する趙の高級官僚の意見の相違をもたらした。戦いの前に将軍を変えるのは軍事戦略上のタブーである。言うまでもなく、戦いが正式に始まる前に、趙国はすでに戦いの半分を失っていた。理論上、上級リーダー間の意見の不一致は、実際には残りの半分を失うことに等しい。 さらに、秦は趙の軍事力を根本的に弱体化、あるいは破壊することも考えていた。 まず、若い将軍と中年の将軍を使って趙に敵を過小評価させ、大量の兵を派遣して戦い、強敵の主力を誘い出すという戦略目的を達成します。 秦の昭襄王は自ら戦場に赴き、兵士たちを励まし、慰め、勝利への決意を固めました。 「人殺し」として知られる猛将、白起の密かな到着は、彼の「大量殺戮」の意図を示していた。 それはすべて意図的なものです! すべては最初に計画されます! それはすべて「避けられない」ことだ! もし「偶然」だったとすれば、おそらく理由は二つしかない。第一に、趙国の新しい司令官は経験不足で成功を渇望していた趙括であったこと、第二に、趙国の死傷者数と趙国の捕虜数の差が大きすぎ、捕虜が多すぎたことである。 武器を渡しただけで基本的に無傷で、中には組織を維持している者もいる40万人の若くて強い捕虜を前に、白起は11語でこう言った。「趙の兵士たちは欺瞞に満ちている。全員殺さなければ、混乱が起きるかもしれない。」 それはかなり残酷で、収支の範囲を超えているように聞こえます。 しかし、もう一度考えてみると、それはまた、捕虜が多すぎるという「偶然の」状況に対処するための「避けられない選択」でもあった。もしこれらの人々が解放されれば、趙国は数分のうちに彼らを武装させ、強力な軍隊にすることができるのだ。そうすると、この勝利は意味を失ってしまいます。 40万人! 今日の国力と人口基盤を考慮しても、そのような大規模な軍隊を編成し訓練するには少なくとも3年から5年はかかるでしょう。 事実が証明しているように、趙国は45万人の精鋭部隊を「失った」後も、非常に強力な「邯鄲の戦い」を組織し、圧倒的な軍事力でますます強くなっていた強大な秦を「最後の一里」で止めさせた。その後間もなく、甚大な被害を受けた趙国は、秦軍の壊滅に対して依然として非常に粘り強い抵抗を見せた。 したがって、秦国の観点からすると、40万人の捕虜は殺されなければならなかったのです。 昌平の戦いの後、秦は基本的に外交を放棄し、純粋に軍事的手段によって「国際関係を処理する」段階に入った。秦にとって脅威となった唯一の抵抗は、魏の武忌王(辛霊公)が率いる連合軍の攻勢であった。 おそらく、昌平の戦いでの悲惨な敗北がなければ、共同攻勢は起こらなかっただろう。 しかし一方で、もし長平の戦いや大規模な捕虜殺害がなかったら、この協調攻勢が本当に後から組織されていたら、趙の参加によって秦への圧力は大きく高まっていただろう。その場合、たとえ秦が最終的に勝利したとしても、大きな損失を被ることは間違いない。その「最終決戦」は、大幅に「遅れる」だけでなく、それほど決定的で鋭いものにはならない可能性が高い。 【著者プロフィール】劉紅宇、通称毛穎、景紅。才能ある小説家、ベテラン脚本家、北京作家協会会員、「夏燕杯優秀映画脚本賞」受賞者。彼は『Is It Your Business?』、『Red Moon』、『King Wu Conquers King Zhou』、『Deep Water Blasting』など、多くの小説を執筆しています。 |
<<: 黄鶴楼はいつ建てられたのですか?宋代以前の黄鶴楼はどのような様子だったのでしょうか?
>>: 崇禎帝が絞首刑にされた「曲がった木」は今も大丈夫でしょうか?清朝はなぜこの木を残したのでしょうか?
推薦する
四聖心 出典:第一巻 天と人の解釈:澱伝全文
『四聖心源』は、1753年に清朝の黄元宇によって書かれた医学書で、『医聖心源』としても知られています...
『啓東夜話』第8巻第8章の主な内容は何ですか?
○張衛公について2つのこと高宗皇帝は張衛公を守備隊長に、楊和王を宮廷前部の責任者に任命して南京の軍隊...
「楚科派安静記」シリーズ第1話第2巻:姚迪珠は恥を避け恥をかかせ、程月娥は恥を最大限に利用する
『楚科派安経記』は、明代末期に凌孟初が編纂した俗語小説集である。この本は、一般大衆に人気のある「疑似...
歴史上、大規模な移民の時代はいくつありましたか?なぜ移民が五代十国の形成を促進したと言われるのでしょうか?
なぜ移民が五代十国の形成を早めたと言われるのか? 興味深い歴史の編集者が、関連する内容を詳しく紹介し...
『奇民耀書』ってどんな本ですか? 『奇民耀書』は誰が書いたのですか?
『奇民耀書』とはどんな本でしょうか?『奇民耀書』を書いたのは誰でしょうか?次の『Interestin...
黄金の婿の物語とは?このことわざは誰の作品に最初に登場したのでしょうか?
古代人は、高貴な身分の婿を「金亀婿」と呼んでいました。このことわざは、李商胤の『衛有』に初めて登場し...
宋代の統治者は、自らの支配的地位を固めるためにどのような政治体制を確立したのでしょうか。
宋代の統治者は、分裂政権の再発や大臣、皇帝の親族、皇后、王族、宦官による権力の濫用を防ぎ、労働者人民...
「龍頭音」を鑑賞するには?著者は誰ですか?
ロントゥイン王維(唐代)長安の若い遍歴の騎士が、夜の太白山を見るために望楼に登りました。龍頭峠の明る...
『鹿と釜』で最も役割が少ない曾柔の重要性は何ですか?
曾柔は7人の女性の中で最も注目されていない人物だと言えますが、非常に特別な人物でもあります。特別なの...
ワインの神とワインの祖先は誰ですか?ワインを作ったのは誰ですか?
今日は、Interesting History の編集者が「ワイン」を作ったのは誰かを教えてくれます...
チベット人はチベット人の主な民族経済とは何かを紹介します。
チベットの国家経済チベット人は主にチベット自治区と青海省の海北、海南、黄南、ゴログ、玉樹のチベット族...
歴史を語る: 水滸伝の、思いもよらなかった最高のものをすべて振り返る
最も賢いメイド、ジンエル。金児は林冲の妻、張振娘の侍女であった。しかし、この侍女は非常に賢く、高艶内...
張岱の散文集『西湖を夢みて』第3巻・西湖中路・呂玄宮全文
『西湖夢想』は、明代末期から清代初期の作家、張岱が書いた散文集で、全5巻72章から成り、杭州周辺の重...
『紅楼夢』で賈玉村が官吏に復帰した後、最初に担当した事件は何ですか?
賈玉村は『紅楼夢』のかなり早い段階で登場し、物語全体をつなぐ役割を果たしている。よく分からない読者は...
「恋慕・慈愛の梅」を鑑賞、詩人劉克荘の「慈愛」という言葉が骨身に染み入る
劉克荘(1187年9月3日 - 1269年3月3日)は、原名は卓、字は千福、号は后村で、福建省莆田県...