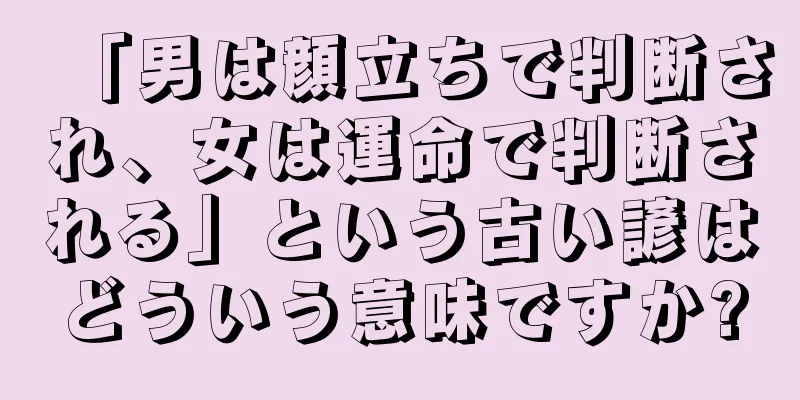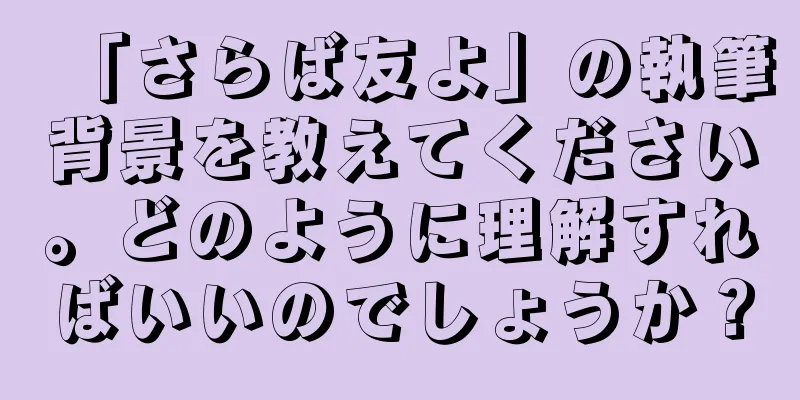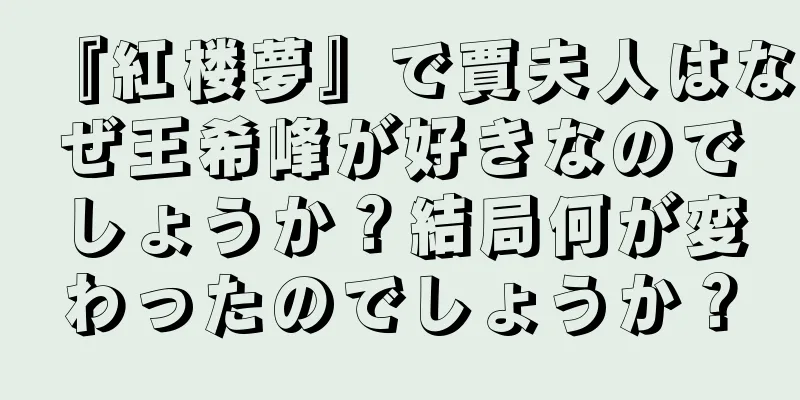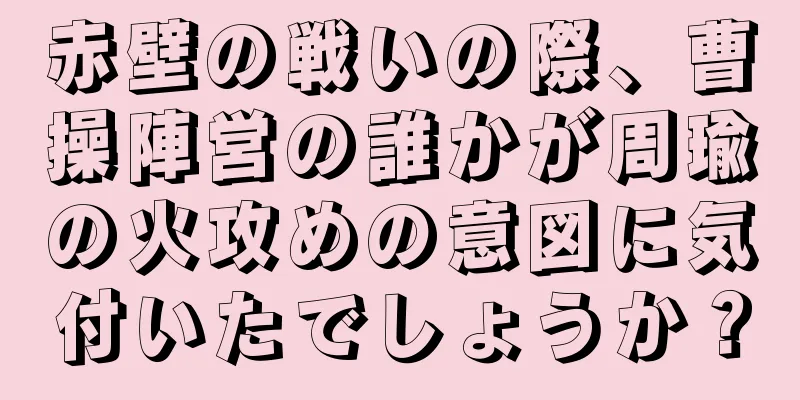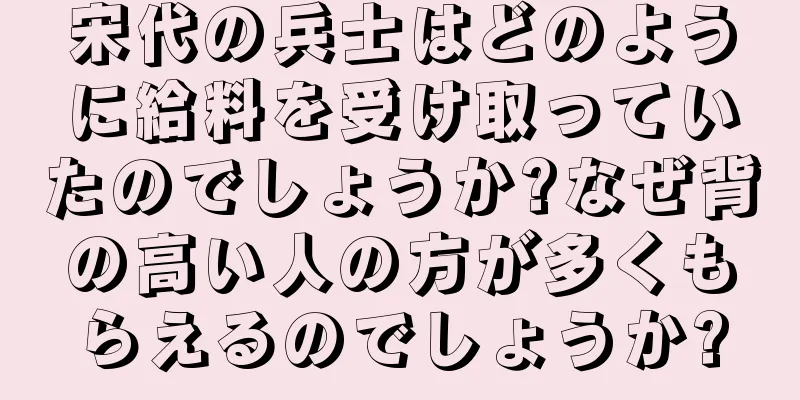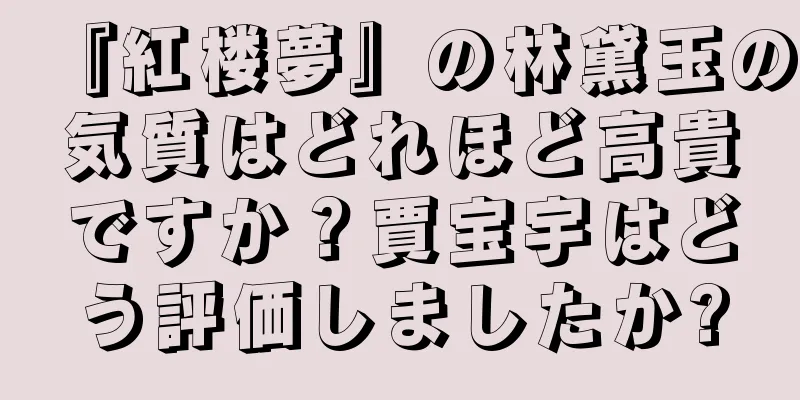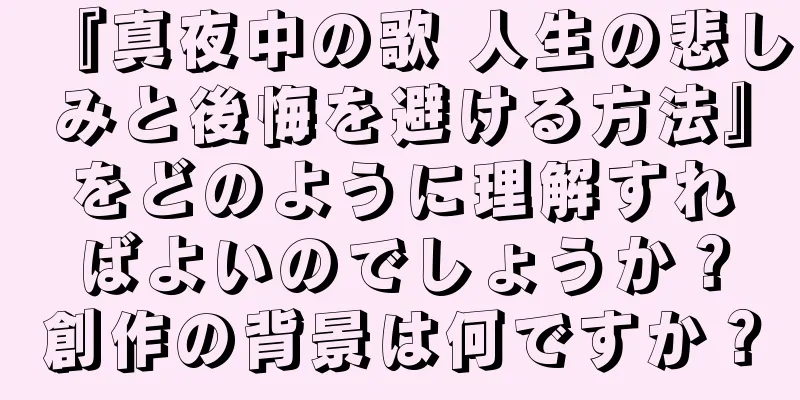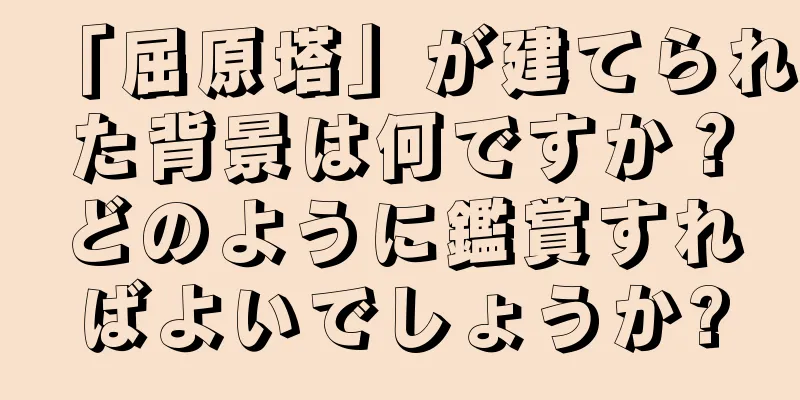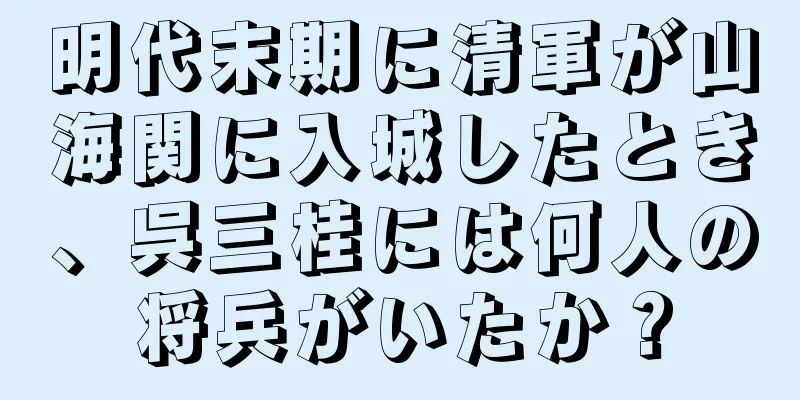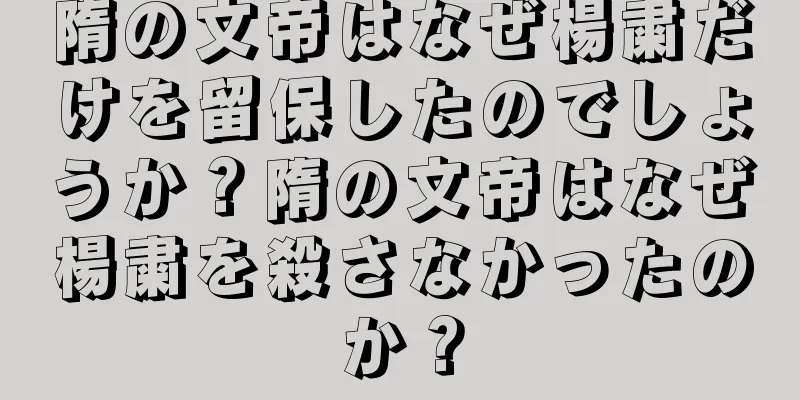中国の皇帝、王子、側室の称号の完全なリスト
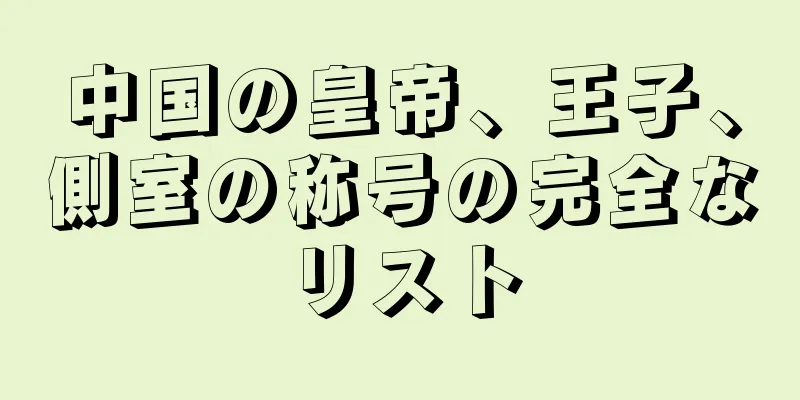
|
古代中国の皇帝には、「王」、「皇帝」、「諡号」、「寺号」、「治世名」と呼ばれるほかにも、いくつかの古典に散在する他の称号もありました。普段は読んで集めています。参考までにいくつかを下記に挙げておきます。 1. 皇帝: 王に対する敬意を表す称号。「大王」と同じ。雅歌集に載っています。素晴らしい優雅さ。 『文王に声あり』:「四方を統一し、皇帝は王、皇帝は王。」朱熹の『評論集』:「皇帝は天下の称号であり、武王を指す。」 2. 皇祖:天皇の祖先。明朝では、朝廷が祖廟に供物を捧げる際、大祖より上の祖先はすべて皇祖と呼ばれると規定されていました。 3. 黄帝:皇帝の別名。 「隋書」。王紹伝:「黄皮楚、黄は偉大な意味、皮は君主を意味する。偉大な君主楚は、最高の統治者が勅命を受けて皇帝になることを意味するのだろう。」 4. 君主: 君主の古代の呼び名。 「尚君の書」 「君主と大臣」:「国家はよく統治され、領土は広大で、軍隊は強く、君主は尊敬されている。」 5. 君主: 臣下が君主に呼びかけるときに使用する称号。 『紫禁同鑑』第214巻で、李林甫はこう言っている。「これは師匠の家庭の問題です。なぜ外部の人に聞くのですか?」 6. 君主: 臣下が君主に呼びかけるときに使用する称号。 「三国志演義」。蜀の歴史。法正の伝記:「ある人が諸葛亮に言った。『法正は蜀県で傲慢すぎる。将軍、主君に彼の権力を抑えるよう頼むべきだ。』」 7. 君主: 君主の別名。 「墨子」。 「桂毅」:「そして、主は唐の教えを聞いたことがあるか?」 8. ジュン: 君主、皇帝。 「歴史の本」大禹の教え:「私は四つの海を所有し、世界の支配者である。」 9. 王: 皇帝の称号。 「マンダリン」呉宇:「今、王は注意を払わず、激怒して越国を攻撃しようとしています。」 10. 人間の支配者: 人民の支配者、君主を指します。商王の書。神法:「いかなる君主も国民を永遠に統治することはできない。そして混乱のない国など存在しない。」 11. 淳連:天皇を指します。商王の書。 「神法」(慎重の法):「君主が注意深く観察しなければ、君主は君主を侵略するか、民衆を略奪することになる。」 12. 先帝: 現在の皇帝の亡き父。諸葛亮の『遠征序文』:「先帝は生涯の半分を終える前に亡くなった。」 13. 先代皇帝: 古代皇帝が先代皇帝を指すために使用した称号。 「詩集」。イェフェン。 「ヤンヤン」:「先祖の優しさが私を励ましてくれました。」 14. 献卓:歴代の王の称号。 「漢書」。魏仙の伝記:「この階段を登った後、私は祖先が登ってきた昔の階段を振り返り、私の心は懐かしさで満たされました。」 顔時固の注釈:「「最初と最後」という言葉は祖先を指します。」 15. 献正: 先代の統治者、亡くなった皇帝。 「儀式の書」黒服は失われた詩を引用した。「昔、私には先人がいた。その言葉は明瞭で明快だった。」鄭玄の注釈:「先人は年長者である。」 16. 先帝:前の皇帝の称号。唐代、杜甫の「昔を懐かしむ」の詩:「先帝が北方を巡視し、何千もの戦車と馬を率いて咸陽に入った昔を思い出す。」 17. 仙璽:建国者の称号。 『三国志演義』に『始皇帝伝』が収録されている。 18. 祖先: 皇帝や王子の祖先に対する敬意を表す称号。 「マンダリン」 『陸羽尚』には「君主は王の祖先と祖先に供物を捧げる」とある。魏昭の注釈には「祖先は君主の祖先である」とある。 19. 古代の聖王: 古代の賢明で慈悲深い君主。 「呂氏春秋」人間について: 「古代の賢者や王たちはこのように人間を知っていた。」 20. 大甲: 宮殿の側近や側室が皇帝に呼ぶ名前。 『新唐書』李福国の伝記:「代宗皇帝が権力を握ると、福国らは決断力に優れているため、ますます傲慢になった。彼らは皇帝にこうさえ言った。『あなた方は宮殿に座り、対外関係は老奴隷の私に任せてください』」 21. 大王: 皇帝に対する敬意を表す称号。 「旧唐書」玄宗記(第1巻):「まず、陛下に申し上げましょう」と言う者もいる。 22. マハラジャ: 古代の皇帝の別名。宋代。范仲厳:「六官府」:「六官部は、さまざまな政治事務を管理し、偉大な君主を補佐するために設立されました。」 23. 大皇:皇帝に対する敬称。 「昭明選集」ジン。呂季。 「偉大な皇帝の死去について」:「偉大な皇帝が亡くなった後、若い君主が王位を継承しました。」 24. 大廷:古代皇帝の伝説上の名前。 「荘子」。 「謝謝」:「昔、栄成氏、達磨氏、神農氏の統治時代には、人々は結び目のある縄を使って縄を作り、使用していました。」 25. 先帝または故帝: 新しく亡くなった皇帝の婉曲表現。 『後漢書』 『安帝紀』:「先帝は長く生きられなかった。」 26. 聖者、聖なる主、聖なる賢明なる主、陛下、聖なる君主、聖なる賢明なる、賢明なるはすべて皇帝に対する敬称です。班固:「東都頌歌」:「そして皇帝はすべての民の喜びを味わい、神々の恵みに浸った。」 27. 上: 上にいる人。特に君主や皇帝を指すこともあります。 「儀式の書」 「王政」:「皇帝を敬い、上位者に近づき、学問を推進する。」 28. 現在の天皇:当時の天皇の称号。現在とも呼ばれることがあります。 「偉大な歴史家の記録」 『太史公序』:「漢代五代、建元帝の治世は栄えていた。夷狄を駆逐し、法規を定め、鳳山の祭を執り行い、暦を改め、衣服を改めた。『今帝紀』第十二章が書かれた。」 29. 皇帝:古代の皇帝。鄭玄:「詩集序文」:「至高帝の治世中、詩は栄えなかった。」 30. 王:秦王朝以前の皇帝の称号。 「荀子」。 「王と覇権」:「百王のやり方はそれぞれ違う。」 31. 祖下:戦国時代前後の大臣が君主に対して使う敬称。伝説によると、春秋時代に晋の文公が桀子推を恋しがったことに由来する。 「戦国の戦略」ヤン・イー:「閣下が満足しているとお考えなら、私は閣下に仕えるつもりはありません。」 32. 「万歳」は古代の臣民が王や王子に贈る祝辞であり、秦漢の時代以降は皇帝に対する敬称として定着した。 33. 陛下: 秦の時代以降、皇帝は陛下と呼ばれるようになりました。 34. 孤児、未亡人、孤児、未亡人、不十分: 古代の王や王子が自分自身を指すために使用した謙虚な言葉。 『老子』:「高貴なるものは卑しきものの上に成り立ち、高きものは卑しきものの上に成り立つ。それゆえ、君主や王は自らを孤独、未亡人、不十分と称する。」 『左伝』 西貢23年:「楚王は彼を歓待して言った。「もし君主が晋に反逆したら、その不十分さをどう償うのか?」」 35. 閣下: 大臣が他国の君主を指すときに使う謙虚な言葉。 「左伝」羲公四年:斉公は言った。「これは不孤のすることではないか。これは先代の友情の継続だ。不孤と友人になるのはいかがか?」彼は答えた。「陛下は国と私の貧しい町の人々に祝福をもたらし、あなたの奉仕で私に名誉を与えました。これが私の願いです。」 36. 王: 君主または皇帝の称号。最高の称号でもあります。漢代から明代にかけて使われてきました。 37. 君主:君主、王。 「アンソロジー」李凌「蘇武への返事」:「それで、前回の手紙で言ったように、王の恩に報いたいのです。」 38. 皇帝と王: 古代の君主の称号。例えば、三皇五帝など。 39. 侯王:古代の君主の称号。 「荀子」。 「不埒」(不注意):「天地の始まりは今日であり、百王の道は未来の王である。」未来の王:現在の王。 40. 蘇王:古代の皇帝の称号。道教徒は、皇帝の徳を持ちながら必ずしも皇帝の地位に就くわけではない人々を蘇王と呼びます。儒教では孔子を蘇王と呼びます。 41. 世界の支配者:君主。 42. 若き皇帝。 『新唐語』第11巻:「高宗皇帝が重病になったとき、彼は裴延に若い皇帝を助けるように命じた。」 43. 国家と国の君主: 君主の愛称。 『新唐語』第1巻:「宋景昌は言った。『太子は世に多大な貢献をし、国の真の主人である。どうして異議を唱えるのか?』」 44. 袁皇后:皇帝または君主の称号。後世の人々は皇帝の正妻を「袁皇后」とも呼んだ。 45. シェジュン:若いマスターの称号。 46. 国家元首:君主。 47. 元君:優しい君主。 48. 皇帝の後継者、君主の後継者、聖人の後継者、王の後継者:王位を継承する皇帝。 「儀式の書」 『礼記』第2部:「皇帝が即位し、祭祀に臨むとき、内政に関しては皇帝は孝王何某と呼ばれ、外政に関しては皇帝は皇太子何某と呼ばれる。」 49. 賈、大賈、車賈、于賈、盛賈、尊賈:もともとは皇帝の乗り物の総称であったが、後に皇帝の愛称としてよく使われるようになった。 「旧唐書」宦官の伝記:「皇帝の頻繁な転居により、朝廷は徐々に弱体化しました。この災難の原因は宦官から始まりました。」 50. 万成:皇帝の愛称。 「孟子」 『梁恵王記 上』には、「一万台の戦車を持つ国で、君主を殺した者は必ず一千台の戦車を持つ一族を持つ」とある。周の制度によれば、皇帝は一千里の領土を持ち、一万台の戦車を送り出すことができた。君主は百里の領土を持ち、一千台の戦車を送り出すことができた。そのため、皇帝は一万台の戦車を持っていることから天子と呼ばれています。 51. 成宇:皇帝の乗り物。後に皇帝とも呼ばれる。 『後漢書』 『耿厳伝』には、「皇帝の馬車が到着すると、大臣たちは牛を叩き、官吏をもてなすために酒を用意すべきである」と書かれている。 52. 黄玉:皇帝の乗り物。後に皇帝とも呼ばれる。屈原の「李襲」:「私は自分の体に起こる災難を恐れないが、皇帝の馬車の失敗を恐れる。」 53. アッラー: 皇帝、いわゆる真の皇帝の別名。 『後漢書』王昌の伝記:「張大武は言った。『王莽は王位を奪い、国を殺し、民を残酷に抑圧した。民は漢王朝を懐かしみ、英雄たちが立ち上がった。今や劉家が再興し、彼らこそが真の王者だ』」 54. 真人:皇帝の別名。 「偉大な歴史家の記録」 『秦の始皇帝紀』:「35年、始皇帝は言った。『私は真の男を尊敬し、私は真の男と呼ぶが、私ではない。』」 55. 天子:君主。 「儀式の書」 「世界の支配者は天子と呼ばれる」(李)。 56. 天王: 殷と周の時代、皇帝は単に王と呼ばれていました。春秋時代以降、楚や呉などの君主が相次いで王を名乗り、周の王は敬称として天王と呼ばれた。後には封建時代の皇帝を指すことが多くなった。杜甫の詩「懐古」には、「蛮族はまっすぐにやって来て皇帝のベッドに座り、官僚は皆裸足で王に従った」とある。 57. 天顔:皇帝の顔、皇帝の愛称。 58. 天丘:皇帝に対する蔑称。張炳麟の『康有為の革命論の反駁』には、「この貧しい囚人を漢民族の長にすることは、刑務所から犯罪者を連れ出して大王にすることと何ら変わらない」とある。 59. スオティアン: 皇帝の別名。昔は、父親や夫を指すこともありました。 『後漢書』 「梁朔の伝記」:「(竇)仙の兄弟は罪を償い、国は平和になり、誰もが当然の報いを受けました。私は休息し、涙を拭うことができました。そして今、ためらうことなく私の物語をあなたに伝えようと思います。」 60. 孝同:周の皇帝が喪に服しているときに自らを呼んだ名前。左伝、羲公、9年目:「喪に服して、王は息子を孝童と呼び、公侯は息子を孝童と呼ぶ。」 61. 崇仁:若い皇帝が自らを称えるために使う謙虚な言葉。 62. 太祖・高祖:初代皇帝の尊称。主に寺院名として使われます。例えば、漢の高祖、唐の高祖、宋の太祖、明の太祖など。 63. 静(しず):初代天皇に対する敬称。主に寺院名として使われます。元の時代の聖祖帝や清の時代の聖祖帝など。 57. 天顔:皇帝の顔、皇帝の愛称。 58. 天丘:皇帝に対する蔑称。張炳麟の『康有為の革命論の反駁』には、「この貧しい囚人を漢民族の長にすることは、刑務所から犯罪者を連れ出して大王にすることと何ら変わらない」とある。 59. スオティアン: 皇帝の別名。昔は、父親や夫を指すこともありました。 『後漢書』 「梁朔の伝記」:「(竇)仙の兄弟は罪を償い、国は平和になり、誰もが当然の報いを受けました。私は休息し、涙を拭うことができました。そして今、ためらうことなく私の物語をあなたに伝えようと思います。」 60. 孝同:周の皇帝が喪に服しているときに自らを呼んだ名前。左伝、羲公、9年目:「喪に服して、王は息子を孝童と呼び、公侯は息子を孝童と呼ぶ。」 61. 崇仁:若い皇帝が自らを称えるために使う謙虚な言葉。 62. 太祖・高祖:初代皇帝の尊称。主に寺院名として使われます。例えば、漢の高祖、唐の高祖、宋の太祖、明の太祖など。 63. 静(しず):初代天皇に対する敬称。主に寺院名として使われます。元の時代の聖祖帝や清の時代の聖祖帝など。 64. 黄瓜:もともとは人の名前。 (元寿は太原知事の回顧を生み、顧は平原知事の烈を生み、烈は寧原将軍の禎を生み、禎は黄高忠を生んだ。)清朝では現皇帝の亡き父を指すことが多い。 65. 大興:亡くなったばかりで、寺号や戒名のない皇帝を指します。 66 太上:もともと古代皇帝の時代を指します。 「儀式の書」 『礼記』にはこうある。「至高の者は徳を重んじる。」 解釈:「至高の者は三帝五帝の時代を指す。」 後世の人々は敬意を込めて皇帝を至高の者と呼んだ。 67. 太宗: 建国王朝の2代目皇帝に対する敬称。 68. カーン:古代の鮮卑、柔然、突厥、ウイグル、モンゴルなどの民族における最高統治者の称号。 3世紀に鮮卑族によって初めて使用されました。 69. チャンユ: 漢王朝時代、匈奴はリーダーをチャンユと呼んでいました。 70. 連武:君主の別名。人々を統治する人々。 「孟子」 『梁恵王 第一部』:「今や、世界のすべての君主の中で、人を殺すことを好まない者は一人もいない。」 71. 九荘:もともとは皇帝の住居である宮殿を指します。 「楚辞」 「九つの論証」:「王の門は九つの層になっている。」後に皇帝を指すために使われた。 「旧唐書」宦官の伝記:「彼はすべての事柄を自らの意志で決定し、皇帝の廃位と即位も決定する。」 72. 朝廷:本来は皇帝が臣下を迎えたり国政を司ったりする場所を指すが、中央政府や皇帝の同義語としても用いられる。 73. 明尚、明王:皇帝に対する敬称。 74. 后璋:後継君主。最後の皇帝の中には、慣習的に「后州」と呼ばれる者もいます。南朝の陳帝や五代の李帝など。 75. 郡政官:皇帝の愛称。古代には王都内の首都を郡と呼んでいたため、郡官は朝廷の同義語としても使われていました。 76. 管家:皇帝または朝廷の別名。胡三星:「前漢では皇帝は郡官と呼ばれ、後漢では皇帝は国と呼ばれていたので、どちらも皇帝と呼ばれていました。ある人は、五帝が天下を治め、三王が天下を治めたので、どちらも皇帝と呼ばれていたと言います。」白居易は「郡を解かれて喜ぶ」という詩の中で、「これからの時間は私のものであり、それ以前の時間は政府のものであった」と書いています。 77. 至高: 皇帝の愛称。賈懿の『秦の過去について』:「彼は最高の支配者であり、世界を支配し、鞭を使って世界を打つ。」 漢王朝以降、皇帝の後継者は皇太子、あるいは皇子と呼ばれるようになりました。彼らのほとんどは長男であり、これが通常の例です。しかし、金と元の時代には、皇帝の庶子も皇太子と呼ばれていました。 1. 元良:王子の別名。 「清朝史草稿」 『静帝紀』:「元良の跡継ぎ、 空位のまま長く放置しておくわけにはいきません。同氏の子である玄野は聡明で家系を継ぐ能力もあるので、皇太子に任命します。 ” 2. 王位継承者:皇太子の別名。 『新唐説』第9巻には、「則天は皇帝の位を主張し、睿宗を後継者にし、東宮に住んだ」と記されている。 3. 皇太子、親王:王子の別名。 「晋書」。 『天文記録』には、「五帝は皇太子と呼ばれる北の星に座し、王位継承者である」と記されている。 4. 楚皇、楚隠:皇太子の別名。 5. 皇太子と王妃 皇太子:皇太子の別名。 『後漢書』 『鄭忠伝』には「皇太子と皇位継承者は外交を行う権利はない」とある。楚:代理。 6. 皇太子、後継者任命:皇太子の別名。 『後漢書』 『安帝紀』:「彼は皇位継承者を剥奪し、悪を引き起こした。」 7. 楚二、楚福、楚良:皇太子の別名。 8. 元初と初元:皇太子の別名。 9. 東楚:皇太子の別名。皇太子が東宮殿に住んでいたことからこの名がつけられました。 10. 楚衛、楚公、東宮、青宮: 皇太子が住む宮殿なので、「楚衛」または「楚公」と呼ばれます。 11. 春宮と春維:王子が住む宮殿であり、王子の愛称でもある。 12. 副主、副王子: 皇太子の別名。 ハーレムの称号 1. 皇帝の正妻である女王。夏王朝の皇帝は、生前は「女王」と呼ばれ、死後は「皇帝」と呼ばれました。后記、后羿などの「后」はいずれも統治者を意味します。 商王朝の君主は、生前は「王」と呼ばれ、死後は「皇帝」と呼ばれました。商王朝では、「后」は君主の配偶者に対する特別な称号となり始めました。 「儀式の書」 「Qulixia」:「皇帝の配偶者は皇后と呼ばれます。」 2. 皇后:秦の時代に始まった皇帝の妻の称号。世代から世代へと受け継がれてきました。 3. 女王:王の妻。 4. 黄北:女王の別名。 『後漢書』 「皇后の記録と賛美」:「皇后よ、あなたの言葉は貞潔で高潔です。」 5. 元妃・元帝:君主または王子の最初の妻の称号。 『左伝』には、尹公元年について次のように記されている。「慧公の妻は孟子であった。孟子が亡くなった後、慧公は勝子と結婚し、勝子は尹公を産んだ。」 6. 元皇后、第一夫人:皇帝の正妻、第一夫人。 「明代の歴史」皇后と側室の伝記 II:「穆宗皇帝が即位したとき、祭祀大臣はこう言った。『先帝の最初の妻である孝潔皇后は、同じ寺院に一緒に埋葬されるべきだ』」 7. ヒロイン: 統治者である女性。通常は国を統治する皇太后を指します。 「偉大な歴史家の記録」 『呂太后紀』:「女君主である呂太后は呂氏を王にしようとした。」 8. 君后:君主の妻の称号。 9. 子同:皇帝が皇后につける名前。 10. 慈后と慈衛: 皇帝の母または皇后に対する敬称。宋代の范成大の詩『冰武東公寿』には、「朝夕、二つの優しい壺、詩と礼儀、賢い王」とある。 11. 中央宮殿: 女王の住居。女王としても知られています。 12. 郭容:側室の別名。古代では、男性は陽、女性は陰と呼ばれていたため、皇帝の側室は郭陰と呼ばれていました。 13. 皇帝の妻: 皇帝の妻は「皇帝の女性」または「女性の皇帝の側室」とも呼ばれ、一般の人々の妻よりも下位にランクされました。 「儀式の書」 「渾易」(渾の意味):「古代、皇帝は6つの宮殿、3人の妻、9人の側室、27人の側室、81人の皇帝の妻を持ち、国の内政を管理していました。」 14. 世界の母、天地の母:どちらも女王に対する敬意を表す称号です。 「漢書」。元皇后の伝記:「王莽が権力を握ると、孝元皇后は漢王朝の4代にわたって世界の母として君臨した。」 15. 娘娘: 女王または側室の称号。 16. クンジ:女王の別名。 『後漢書』 『梁皇后紀』:「梁小貴夫人は田作と結婚するのに適しており、彼女は君子の正しい地位にいます。」 17. 側室:皇帝の側室、皇太子、国王、侯爵の妻の称号。 18. 側室: 皇帝の側室。その地位は皇后に次ぐが、すべての側室の中ではより高い。 19. 側室:皇帝の側室の総称。唐代の杜牧の『阿房宮賦』には、「皇帝の側室、侍女、王子、孫たちが宮殿を出て、輿に乗って秦に来た」とある。どの王朝の皇帝にも多くの側室がいた。 「儀式の書」 『結婚の意義』には、「古代、皇帝は6つの宮殿、3人の妻、9人の側室、27人の嫁、81人の皇帝の妻を持ち、内政を管理していた」とある。秦の始皇帝は6つの国を征服し、その宮廷女官を後宮に迎え入れた。漢の武帝には昭夷や結妾など4階級の側室がいた。晋の武帝には1万人近くの側室がいた。康熙帝には51人の側室がいた。 20. 品・九品:皇宮の女性官吏、皇帝の側室の名前。側室、妾とも呼ばれる。 「周の書」天の役人。 「九人の側室」 「九人の側室は、九人の皇后に婦人学の方法を教える役割を担っている。」 九人の皇后は、九人の側室でもある。宮廷には女官9人につき側室が1人いると言われており、側室9人の合計は81人です。このシステムは多くの王朝で使用されてきましたが、名前は異なっていました。唐代には、昭夷、昭容、昭元、秀夷、秀容、秀元、崇義、崇栄、崇元の九人の側室がいた。『新唐書』 「皇后と側室の伝記」 21. 趙妃、于妃、趙妃:宮廷の女性官吏、皇帝や王子の側室。側室の地位は皇帝の側室よりも高い。 22. 貴婦人: 宮廷の女性や側室の称号。東漢の光武帝によって初めて設置され、皇后に次ぐ地位であった。それ以来、その名前は代々使われてきましたが、人々の地位は異なっていました。例えば、清朝では、貴族の女性は、皇帝の側室、貴族の側室、側室、皇帝の側室よりも下位にランクされていました。 23. 皇后:皇帝の側室の中で皇后に次ぐ最高の地位を持つ皇后の称号。南朝の宋武帝の時代に初めて設置されました。貴妃と貴婦人とともに三夫人と呼ばれ、宰相に匹敵する地位でした。隋代以降、歴代王朝に受け継がれてきました。 24. 桂嬪:宮殿の女性官吏、皇帝の側室の名前。魏の明帝の治世中、彼女の地位は皇后に次ぐものでした。その後、歴代の王朝で広く使われましたが、その地位は変化しました。 25. 徽妃と仙妃:宮廷の女性官吏の名前、また皇帝の側室の称号。唐代における第一位であった。 26. 宋妃:宮廷の女性官吏の名称。三国時代、魏の明帝の治世中に初めて制定された。当時、彼女の地位は高貴な側室と女官に次ぐ、比較的高いものでした。後の世代ではより頻繁に設置されるようになりました。 27. 皇太后:亡くなった皇帝の側室。清朝の制度によれば、皇帝の祖父または父の残した側室はそれぞれ皇帝貴妃または貴妃と呼ばれていました。 28. ペッパールーム: 「ペッパールーム」とも呼ばれます。漢の時代に皇后が住んでいた宮殿の壁には、温かさ、香り、豊穣を象徴する胡椒や泥などの香辛料が描かれ、幸運を表すために使われていました。後に、「交芳」という用語は女王を指すために使用されるようになりました。英邵の『韓観意』には「女王は胡椒室と呼ばれている…」とある。 29. 書院: 三国時代の魏の文帝の治世中に初めて確立された、宮廷の女性官吏の名称。叔妃の後任。 30. 徽妃、令妃、華妃:宮廷の女性官吏の名前、また皇帝の側室の称号。唐の玄宗皇帝の開元年間に建立されました。 「旧唐書」皇后と側室の伝記。序文:開元の時代、「皇后のもとに、慧妃、麗妃、華妃の三人の側室が設けられ、夫人に代わって第一位に就いた。」 31. 少妃:秦以前の時代の王子の側室の称号。 32. 皇太子妃:皇太子妃。 33. 董非:皇太子妃。 34. 美人:宮廷の女性官吏の名であり、皇帝の側室の称号でもある。西漢時代に設立されました。漢の宮殿には側室の階級が14あり、美人は5番目だったと言われています。それ以来、明代まで宮殿には美女たちがいた。 35. 良帝:皇太子の側室の称号。西漢時代に由来。その後、ハーレムは魏・晋の時代から隋・唐の時代まで維持されました。 36. 女性君主:君主の側室は、女性君主として敬意を込めて正妻と呼ばれます。 37. 側室、皇帝の側室、皇帝の側室: 皇帝に寵愛された側室。左伝、熙公17年:「斉公は側室を愛し、多くの側室がいたが、妻たちと同じくらい愛された側室が6人いた。」 38. 正姑、正室:正室、正妻の別名。 39. 側室、別室、別室:側室の別名。 40. 二番目の妻: 王子の二番目の側室の別名。 41. おばさんと小おばさん:女王と側室たちの愛称。清代の梁章居の題字 記録:「古代、皇帝の妻は大娘と呼ばれていました。」 42. 西君:元々は古代の王子の妻の称号であったが、後に妻の一般的な呼称となった。 43. 夫人: 周王朝の王子の正妻。 「儀式の書」 『屈麗夏』には「皇帝の妻は皇后と呼ばれ、王子の母は夫人と呼ばれる」とある。後に、王子の母も夫人と呼ばれるようになった。漢代の皇帝の側室は皆「夫人」と呼ばれていました。魏晋の時代以降、人々は夫人と呼ばれたり、別の称号を与えられたりすることがありました。 44. 「瓜小君」:古代の君主の妻が他の属国に対して自分自身を呼ぶときに使った謙虚な言葉。 「儀式の書」 「礼記」第 2 部: 「女性は皇帝に対しては「老女」と呼び、王子に対しては「未亡人の小さな君主」と呼びます。後に、臣下は他国と話すときに、自国の君主の妻を謙虚に「未亡人の小さな君主」と呼ぶようになりました。 45. 内官:先秦時代の王子や宮女の妻や側室の称号。それは後世でも今でも使われています。 46. 妾妃:秦以前の時代の王子の妻の称号。子孫は女王を指すこともあります。 「晋の武帝の皇后設置大赦の勅」:「すべての国を罰する者は、必ず自分の国の主人になる。」 47. 少君と小君:秦以前の時代、王子の妻は少君または小君と呼ばれていました。 48. 壬氏:古代皇帝の側室。 「漢書」。 「外国親族伝記」:「高祖伯記は文帝の母である。」 49. 帝帝:古代皇帝の側室の総称。年上の方は「娰」、年下の方は「娣」と呼ばれます。後世では、「娣娰」は義理の姉妹を指すこともある。 50. 側室: 持参金として来る側室。古代、王子の娘たちが結婚したとき、彼らはしばしば若い姉妹やnieを連結者と呼ばれる側室として連れて行きました。 51。concubine and maid:妻と結婚した側室。 Concubine and Maidとしても知られています。 52。CONCUBINEとMAID CONCUBINE:CONCUBINEの元の意味は女性の奴隷です。皇帝の側室の下のメイドは、一般的に側室またはメイドと呼ばれていました。 53。長老の側室と高貴な側室:息子がいた古代の王子の側室。 54。低い側室、副側室:王子の間の低い地位の側室。 55。Xiaoxing:古代の側室の別名。 56。Zhaoyi:宮殿の女性職員の名前、皇帝の側室も。ハンの元皇帝の治世中に最初に設立されました。漢王朝では、側室は皇后の下の14の階級に分割され、Zhaoyiが最初のランクでした。 「彼の立場は首相の立場に等しく、彼の位置は王子の位置と同等です。」このタイトルは後の世代でまだ広く使用されていますが、そのステータスは同じではありません。 57。Zhaorong:宮殿の女性職員の名前、皇帝の側室も。ハンのウー皇帝の治世中に最初に設立されました。ウェイとジンからスイ王朝とタン王朝に広く使用されていました。デュフーの「紫色の宮殿の宮廷から退却するためのスローガン」:「屋外で、帝国の側室の紫色の袖は垂れ下がっており、彼女は王位に目を向け、裁判所の儀式を率いています。」 58。Zhaohua:宮殿の女性職員の名前、皇帝の側室。それは最初にウェイの皇帝によって設立されました。このタイトルは、後の世代でも使用されました。 59。Xiuyi:宮殿の女性職員の名前、皇帝の側室も。それは最初にウェイの皇帝によって設立されました。このタイトルは後の世代でまだ広く使用されていますが、そのステータスは同じではありません。 60。Xiurong:宮殿の女性職員の名前、皇帝の側室。それは最初にウェイのウェン皇帝によって設立されました。このタイトルは後の世代でまだ広く使用されていますが、そのステータスは同じではありません。 61。Jieyu:Jieyuとしても書かれています。宮殿の女性職員、皇帝の側室もあります。ハンのウー皇帝によって最初に設立されました。当時、側室のZhao、concubine Yinなどがありました。ジユーシは、漢王朝の14の階級の側室で2番目にランクされました。このタイトルは後の世代(明王朝の前)でまだ広く使用されていましたが、そのステータスは同じではありませんでした。 |
<<: 重陽の節句は別名何と呼ばれていますか?重陽の節句の8つの別名は何ですか?
>>: 典韋と許褚の他に、曹操にはどんな強力な将軍がいましたか?
推薦する
「琴を聴く」の原文は何ですか?この詩をどのように評価すべきでしょうか?
【オリジナル】琴の金色の粟柱が演奏され、白い手が玉室の前にあります。周朗の注意を引くために、私はよく...
歴史上、大晦日に関する詩にはどんなものがありますか?詩人はどんな場面を描写しているのでしょうか?
大晦日の夜は、祭りの喜びと新年への期待が最高潮に達します。歴史上、大晦日に関する詩は数多くあります。...
任吾星の個人プロフィール:任吾星はどの小説に登場しますか?
任無興は金庸の武侠小説『微笑矜持放浪者』の登場人物である。日月宗の指導者であり、計り知れない武侠の技...
薛仁貴東征篇第一章:龍門郡の将軍が生まれ、唐の皇帝は夢の中で青龍に悩まされる
清代の在家仏教徒である如廉が書いた小説『薛家将軍』は、薛仁貴とその子孫の物語を主に語る小説と物語のシ...
『柯桂嶺・冰子年越昔想』の執筆背景は何ですか?どのように理解すればいいのでしょうか?
【オリジナル】蓬莱には古い木々があり、暗い雲があり、作物や雑穀は高く低く生い茂り、孤独なウサギが飛び...
李玉の周皇后追悼文:「新たな恩恵に感謝 秦楼に笛を吹く少女はいない」
以下、Interesting Historyの編集者が、Li Yuの「新恩恵に感謝:秦楼に笛の娘なし...
楊過はなぜ邱楚基を嫌うのか?彼らは何の恨みを持っているのでしょうか?
中国の武侠小説の世界では、楊過と秋楚麒の名前が最もよく知られていることは間違いありません。しかし、そ...
王夫人はいったい何を経験したのでしょうか?なぜ劉おばあちゃんは王夫人のソウルメイトだと言われているのでしょうか?
『紅楼夢』は、中国古代の章立て形式の長編小説で、中国四大古典小説の一つです。普及版は全部で120章か...
「事物之書」は張喬によって書かれたもので、非常に感動的で魅力に溢れています。
張喬(生没年不詳)は池州(現在の安徽省池州市貴池区)の人であり、懿宗の咸通中期の進士である。当時、徐...
趙狗は興味深い皇帝でした。彼が不妊だったというのは本当ですか?
趙狗皇帝といえば、やはり非常に興味深い皇帝です。彼に関する逸話はあまりにも多くあります。趙狗には生殖...
イタリアのカスティリオーネはどのようにして宣教師から宮廷画家になったのでしょうか?
宮廷画家の郎世寧はもともとイタリア人でしたが、1715年に布教のために清朝に来ました。その時、彼はす...
もしある日、王希峰が権力を失ったら、彼女は賈家でまだ繁栄できるだろうか?
『紅楼夢』は、中国古代の章立て形式の長編小説で、中国四大古典小説の一つです。普及版は全部で120章か...
『紅楼夢』の金川の死と宝玉との間にはどのような関係があるのでしょうか?
金川は『紅楼夢』の登場人物で、王夫人の部屋で働くメイドです。下記の興味深い歴史編集者が詳細な解釈をお...
蜀漢末期、魏延の他に蜀軍で張郃の敵となり得る人物は誰でしょうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
「Lotus River Ballad」が作られた背景は何ですか?どのように鑑賞すればよいでしょうか?
ロータスバラード文廷雲(唐代)清流に櫂の音が聞こえ、武園の東側には霧の中に緑が広がっています。水は澄...