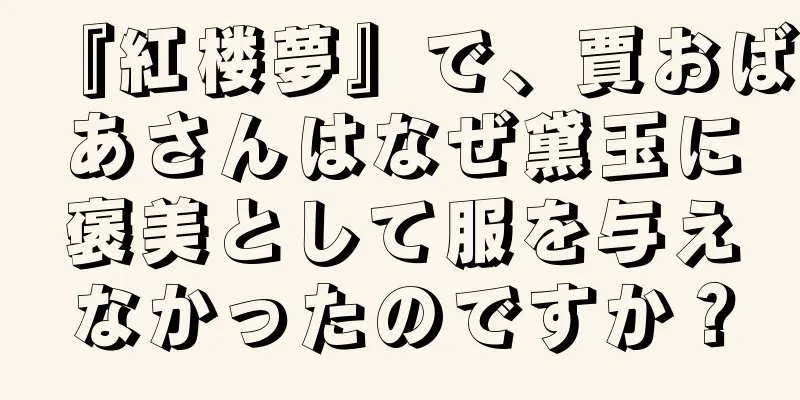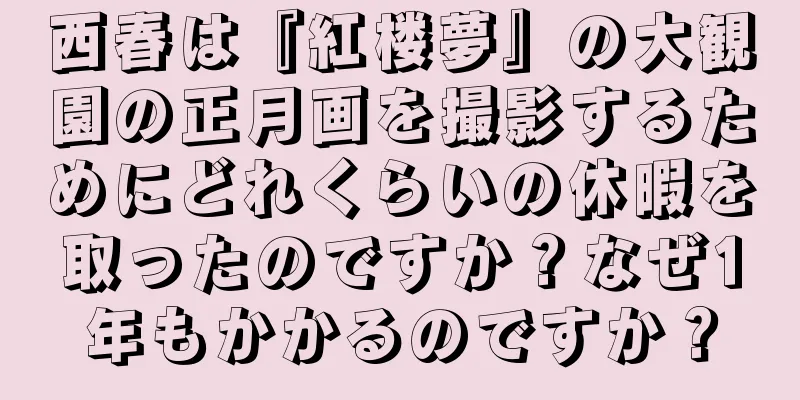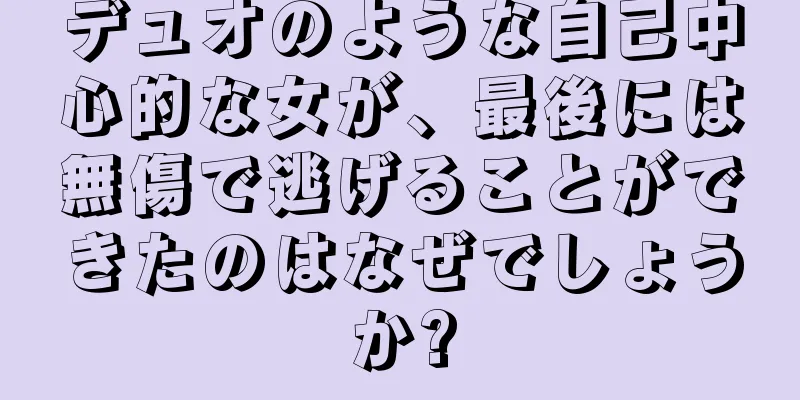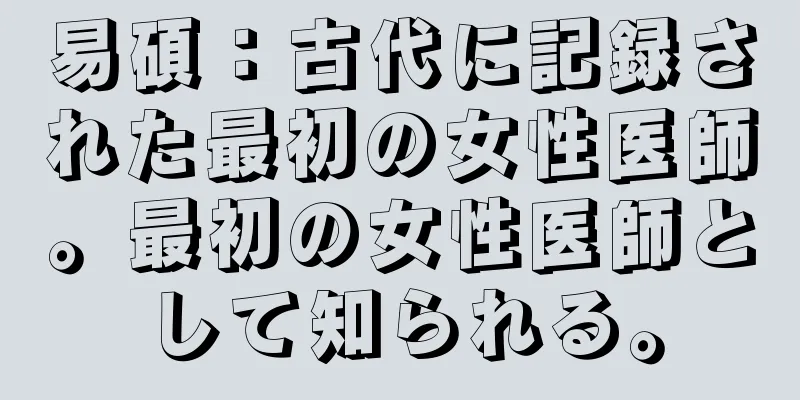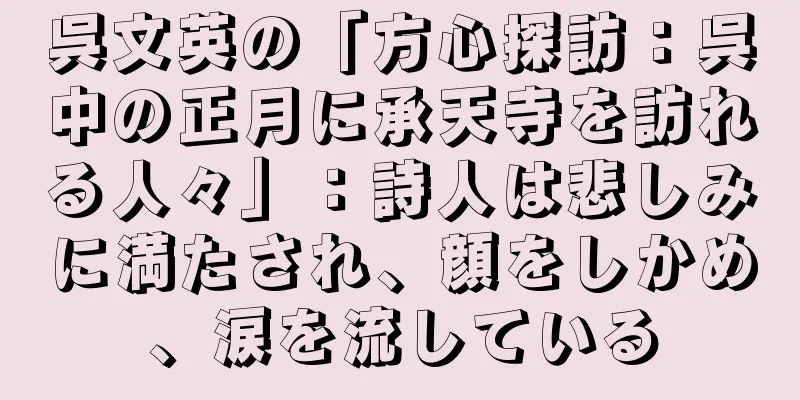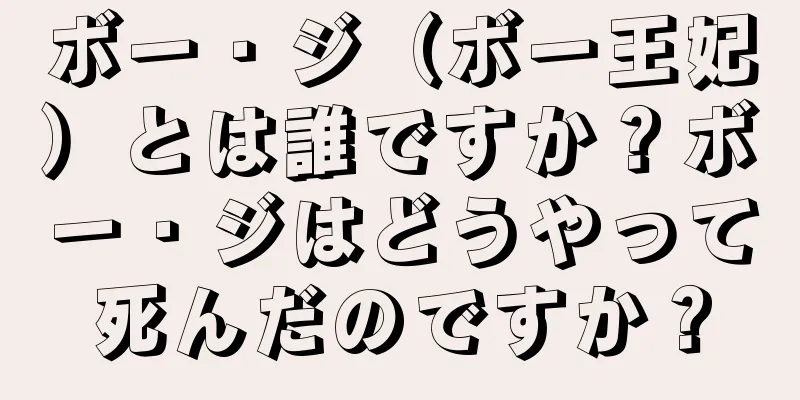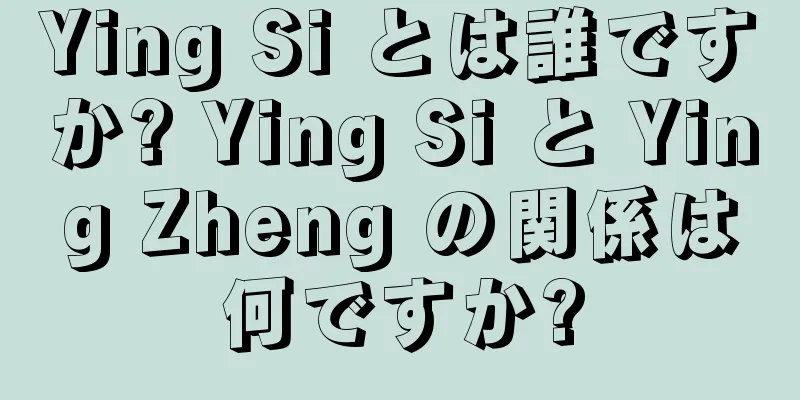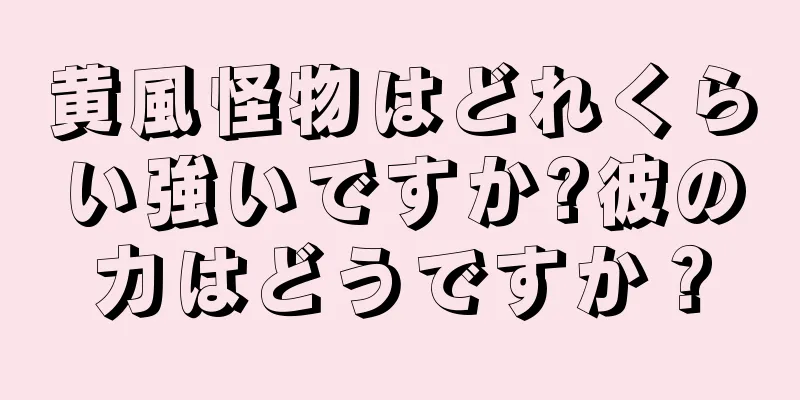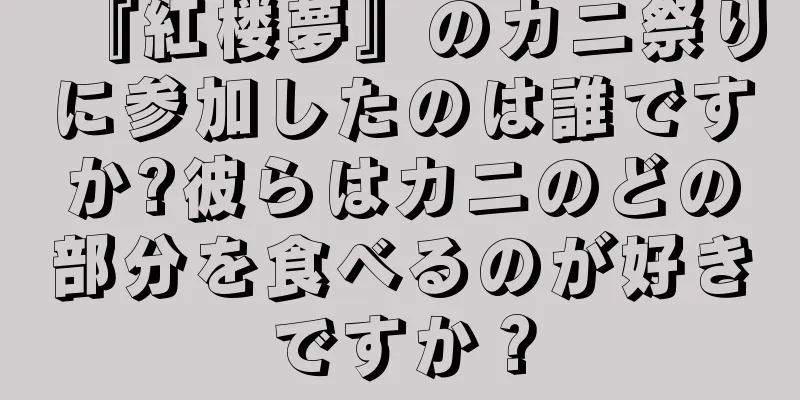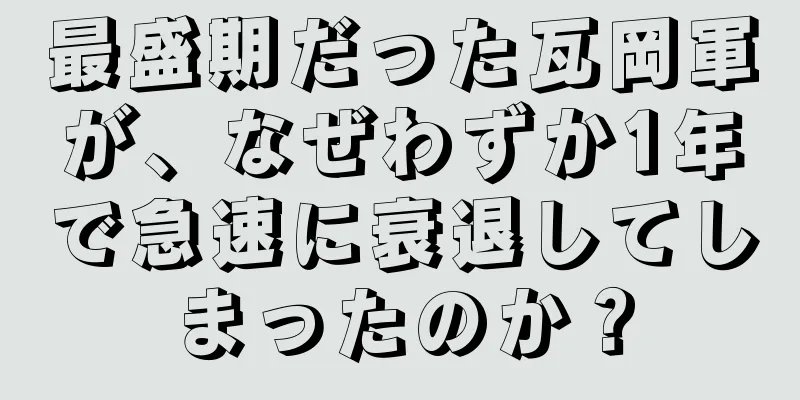水族の歴史 水族水書とはどのような歴史遺産でしょうか?
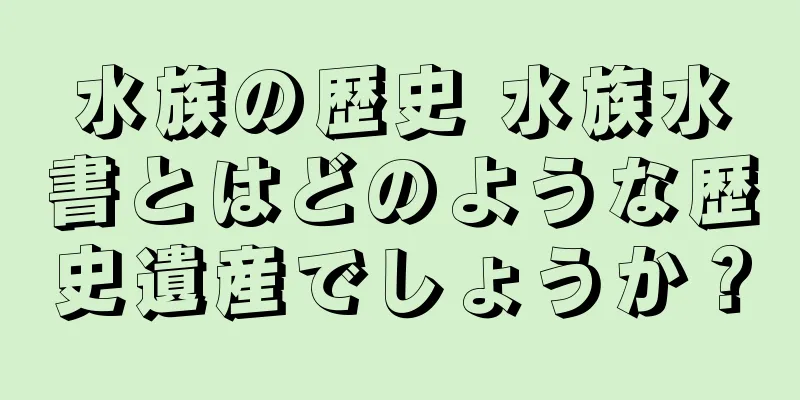
|
「水書」は水族の古代の文字体系です。水族はこれを「lesui」と呼んでいます。「le」は文字を意味し、「sui」は水(家)を意味します。「lesui」は水族の文字または本を意味します。私の国には 56 の民族がいますが、そのうち 17 の民族が独自の伝統的な文字体系を持っており、水書語もその 1 つです。甲骨文字や青銅文字に似た古代の文字で、古代水族の天文学、民俗、倫理、哲学、美学、法律などの文化情報が記録されており、象形文字の「生きた化石」として知られています。水書とは、わが国の56民族のうちの一つである水族の古代の文字と書籍の総称です。 『水書』には水族の『易経』や『百科事典』などの尊称があり、水族の長く波瀾万丈な歴史を解説した重要な書物です。同時に、水樹は「古代中国文化の宝庫にある貴重な生きた化石」であり、象形文字の最後の未開発地域としても知られています。 水書は、その神秘的な文章構造と特殊な用途により、数千年にわたり、一種の「抑圧され制限された」文字となり、人々の間で難なく継承されてきました。現在の研究結果から判断すると、「水の書」は魔術に使われた書物であると一般的に考えられています。水書の成立は非常に古く、一部の学者は水書の起源は夏王朝にまで遡り、「水書と古代殷人の甲骨文字の間には何らかの関係があるに違いない」と推測している。水酒が作られた場所はもともと北西部にあり、徐々に北部から江西省に伝わり、その後江西省から貴州省に移り、「すべてを持ち帰った」。水族の古代文字の構造は、大きく分けて以下の3種類に分けられます。1つは象形文字で、甲骨文字や青銅文字に似たものもあります。2つ目は擬漢文字で、漢字を逆に書いたり、逆さに書いたり、形を変えたりしたものです。3つ目は宗教文字で、水族の原始的な宗教を表すさまざまなコード化された記号です。 書き方は縦書きで、右から左へ、句読点は使いません。現在見られる水古代文字の主な伝達手段は、口伝、紙の手書き、刺繍、石碑彫刻、木彫、陶磁器の鍛造などです。 『拾遺書』は主に筆写と口伝によって今日まで伝承されてきました。その構造は主に象形文字で、主に花、鳥、昆虫、魚などの自然界の物や、龍などのトーテムで書かれ、描かれているため、古代文明の情報が残っており、現在でも水族地域で広く使用されています。わずか800字余りの文字からなる文字体系である水書は、数千年にわたり国家の文字史と文明史を支え、国家の精神的支柱となっている。 長年水書の研究に没頭してきた潘超林さんは、水書には独特の魅力があると考えています。まず、水書は水族固有の文化です。水書は独自の文字体系を持ち、古代中国文化の重要かつ切り離せない一部です。この文字体系は非常に「未熟」で脆弱に見えますが、時間と空間を超えて今日まで受け継がれており、それ自体が非常に神秘的です。 『水書』に収められた情報の量は、水族社会の範囲をはるかに超えています。「儀式が失われても、野に探し出すことができる」。『水書』に含まれる情報の一部は、中原の古代文化の含意を解明するのに役立ちます。 |
<<: 顔良は河北の四柱の一人の称号に値するでしょうか?彼は関羽によってどうやって殺されたのですか?
>>: 旧頤和園の北源山村の観光スポットは正確にはどこにあるのでしょうか?何の役に立つの?
推薦する
なぜ多くの人が呂布を最高だと考えるのでしょうか?なぜ呂布は第一の王座にしっかりと座ることができたのでしょうか?
『三国志演義』は四大古典の一つです。小説の中での軍事力の順位について、多くの人が「呂不韋が一、趙が二...
なぜ「彌」姓はすべての姓の祖先と言われているのでしょうか?吉姓の由来を詳しく解説
なぜ「彌」はすべての姓の祖先と言われているのでしょうか。これは、我が国の多くの姓が「彌」姓から進化し...
関羽の指揮下にある500人の「流派剣士」について人々が抱いている2つの推測とは何ですか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
失恋の痛みを表現した李尚銀の「無題」の簡単な分析
李尚銀の「無題」。次回はInteresting History編集長が関連コンテンツを詳しく紹介しま...
漢代の儒学者劉鑫の『西京雑記』:序文:古代の歴史ノートと小説のコレクション
『西京雑記』は古代の歴史ノートや小説を集めたものです。漢代に劉欣によって書かれ、東晋に葛洪によって編...
馬超の実力は張飛と同じくらい優れていたのに、なぜ劉備に評価されなかったのでしょうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
歴史上、扶桑公主はどのように亡くなったのでしょうか?彼女は不幸な結婚生活のせいでうつ病で亡くなった。
宋仁宗趙真は、自分を育ててくれた劉鄂皇太后が実の母親ではなく、皇太后の元侍女であった李蘭慧であったこ...
画家のゴッホは他人の嘲笑を聞かないように自分の耳を切り落としたのでしょうか?
ゴッホの父親はプロテスタントの牧師であり、ゴッホ一家は社会的に非常に高い地位にあったと言えます。ゴッ...
陸兆麟の「十五夜灯籠鑑賞」:元宵節はかつてないほどに賑やかで繁栄している
呂兆林(?-?)、雅号は盛之、号は有有子、渝州樊陽(現在の河北省涛州市)の人であり、唐代の詩人である...
『南軒歌』の原文は何ですか?どのように鑑賞すればよいでしょうか?
南軒松李白(唐)南亭には枝葉が茂った一本の松の木があります。そよ風は止むことなく、一日中優雅です。古...
「忠勇五人男の物語」の第 11 章ではどのような物語が語られていますか?
蒋氏は陸と陸の話を聞いて、今朝、鵲頭峰から投げ落とされた赤い絹で結ばれた印章を見たという。四代目師匠...
太平天国の洪玄奘の紹介 洪玄奘はどのように亡くなったのでしょうか?
太平天国 洪玄奘太平天国の洪玄奘は広東省花県富源水村(現在の花都区)の出身で、本名は楊雲奘であった。...
「秀雲閣」は道教の道を試し、村を建てて、虎の話を聞き、目覚める奇妙な男を待つ
農場を開設して、見知らぬ男が虎について話して目を覚ますのを待ちましょう言うまでもなく、三福、楽道、鳳...
「春風に吹かれて雪になっても、南の道で粉々に砕かれるよりはずっといい」という有名な言葉はどこから来たのでしょうか。
「春風に吹かれて雪になっても、南の道で粉々に砕かれるよりはずっといい」という有名な詩がどこから来たの...
李清昭は高層ビルに情熱と威圧感に満ちた傑作を書いた
今日は、Interesting Historyの編集者が李清昭についての記事をお届けします。ぜひお読...