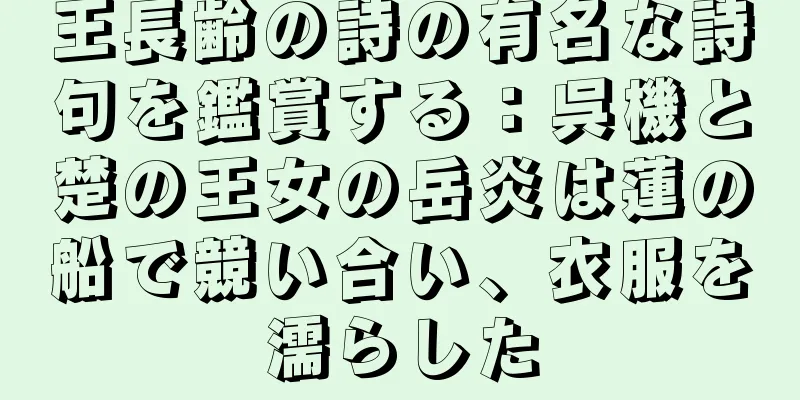劉長青著『ピアノを聴く』には2つの魅力がある

|
劉長清は、字を文芳といい、中唐の詩人である。五音詩を得意とし、自らを「五芒星の長城」と称した。降格後に書いた詩「雪の夜、芙蓉山の亭主の家に泊まる」は教科書に採用された。彼の詩には庶民への思いやりと運命への嘆きが込められています。『おもしろ歴史』編集者と一緒に、劉長青の『ピアノを聴く』について学びましょう。 人生は、絶え間ない別れやすれ違いの中で浮き沈みを繰り返し、不確かな出会いや別れの間をさまよい、数え切れないほどの打撃や利益を経験して初めて、徐々に成熟し始める。希望と挫折は半々ですが、絶望的な状況から脱出するという永遠の精神が人間の遺伝子に秘められているようです。たとえ最後には死であっても、人が自分の欲望を追求することを止めることはできません。 実際、私たちは人生の終わりがどうなるかははっきりとわかっていても、挫折感を感じます。しかし、たとえこの人生だけであったとしても、人間として生まれたことを誇りに思います。生きることは経験の人生です。たとえ最後には滅びても、何を恐れるのでしょう?人間として生まれたことに感謝すべきです!草木の季節、輪廻の四季、人生の無常のように、人生は短いです。私たちは味わい、泣き、笑い、愛し、憎んできました。それで十分です。なぜ欲張らなければならないのでしょうか?! ピアノを聴く 【唐代】劉長清 7本の弦で、 冷たい松風を静かに聞いてください。 私は古い曲が大好きですが、 最近はほとんどの人がプレイしません。 劉長清の詩は流暢で調和がとれており、調子が優雅で、七字律詩を書くのに優れているが、荘厳で力強い勢いに欠けている。彼は自らを「五字詩の長城」と称しており、現存する作品の7割を五字詩が占めている。当時、千琦、郎世源、劉長青、李嘉有を一緒に挙げる人もいたが、彼は「どうして李嘉有と郎世源を私と一緒に挙げることができようか」(『雲熙有意』)と言い、非常に誇り高く、並外れた人物であったことが分かる。彼は随州の知事としてその職を終えたため、友人たちは彼を「劉随州」と呼び、『劉随州全集』を著した。 「七つの弦を弾く私の冷たい松風を静かに聞いてください」と、詩人は冒頭から要点を述べ、ピアノを聴くときの気持ちを書くことに重点を置いています。この種のシーンの描写は比較的単純で、紆余曲折はありません。ピアノの澄んだ明るい音色は美しく優雅で、時折弦に響き渡り、いつまでも余韻が残ります。その瞬間、まるで静かな山の中にいるかのようで、耳元で松風が吹き抜け、全身が涼しく心地よく感じられます。 ここで繰り返し使われている「lingling」という言葉は、ピアノの澄んだ美しい音色を自然に表現しています。西晋の有名な詩人、陸季は『勧仙詩』の二番目に「渓流の清らかさ、飛泉の玉の洗い清さ」と書いている。彼も同じ考えを使っていた。七弦については、それは古代古琴を指し、「錦琴には五十本の弦があり、それぞれの弦と柱は私の青春を思い出させる」(李尚雁の『錦琴』)という詩に出てくる古代古琴の五十弦と同じです。 もちろん、詩人は要点を述べているように見えますが、実際にはそれは単なる場面の仮想的な描写に過ぎないということを、私たちは以前にも述べました。詩人がこれをしたのは、心の奥底に、後で書こうとしていた詩を表現したいという意図がまだ残っていたからである。したがって、ここでの「冷たい」とは、ピアノ曲「Wind in the Pines」の本来の意味だけでなく、ピアノの音そのものが人に伝える本能的な感覚的認識も指している。 「私は古い曲が好きですが、今ではそれを演奏する人はほとんどいません。」 前の部分がピアノを聴いたときの詩人の即時の感情を示しているだけだとすれば、ここでは詩人の本来の意図が自然に明らかになります。私は昔からあるクラシックピアノの楽譜を演奏する人の演奏を聴くのが本当に好きですが、今日、私と同じようにこれらの古い曲を心から好きな人は何人いるでしょうか? みんなずっと前から曲調を変えて、新しい現代のポピュラーソングを演奏する人の演奏を聴き始めています。 古代から現代まで、蔡鍾朗の交尾琴の喪失、山と水の音を聞きながらの博牙と子奇の出会い、「曲を探すのは簡単だが、心の伴侶に出会うのは難しい」という諺など、多くの逸話が伝承されている。人生がこのようなものであることは残念だ。そうでなければ、なぜ多くの人々は昔からいつもため息をつき、嘆いてきたのでしょうか。「私の前には昔の人は見えず、私の後ろには未来の世代は見えません。宇宙の広大さを考えると、私は一人で泣いています」(陳子の「幽州登楼歌」)。このような光景を見ると、人々は長い間顔を覆い、言い表せないほどの憂鬱な気分に陥らざるを得ません。 ここで詩人は音楽について嘆いているように見えますが、実はそこには二つの暗黙の訴えがあります。一つは詩人としての自分のアイデンティティに立ち、今日の詩の世界は繁栄した唐代の詩の世界とは比べものにならないと嘆いていることです。もう一つは自分の人生経験を悲しく思い、世の中には同じような考えを持つ人が少なく、自分の志を理解してくれる人が誰もいないので才能を発揮することが難しいと嘆いていることです。人生に対するこうした嘆きは、詩人自身のものだけではなく、何かを成し遂げたいと願う世界中のすべての人々に当てはまる。おそらく、後者の理由こそがこの詩を魅力的なものにしているのでしょう。 この詩の最後の2行、「私は昔の曲を愛しているが、今日ではそれを演奏する人はほとんどいない」は、おそらく格言の要素を含んでいるため、非常に目を引くものとなっている。平易な言葉の背後には、もう一つの深い意味が隠されています。一見すると、ピアノを弾くという日常の光景から導き出された結論に過ぎないように思えますが、実はすでにこの表面的なレベルを超え、人生の過程における避けられない多くの陰謀を指し示しています。したがって、この抽象化は表面的に見えるかもしれませんが、実際の意味合いは非常に広く、人々に際限なく考えさせ、一定の美的価値を持っています。 |
>>: 「地方考試 相霊琴を弾く」は唐代の銭其によって書かれたものですが、どのような場面を描いているのでしょうか?
推薦する
歴史上、「王子様の代わりに猫を登場させた」という事例は本当にあるのでしょうか?劉娜はこの事件の首謀者なのか?
『身代わり王子』は、王家の秘密を扱っており、鮑正が権力者を恐れずに事件を扱ったことから、古くから広く...
『紅楼夢』の薛叔母さんは本当に宝玉と黛玉を結びつけたかったのでしょうか?
『紅楼夢』は、中国古代の章立て小説であり、中国四大古典小説の一つで、黛玉と宝玉の悲恋物語が全編のメイ...
張仙はなぜ「張三英」と呼ばれるのですか?彼の歌詞の特徴は何ですか?
張仙は字を子夜といい、北宋時代の雅流詩人である。彼の詩の内容は、主に学者や官僚の詩と酒の生活、男女の...
『隋唐代記』第17章:漢家城における秦瓊対秋鋭
『隋唐代志』は、元代末期から明代初期にかけて羅貫中が書いた章立ての小説である。 『隋唐書紀』は瓦岡寨...
荊州を奪還できなかった場合、劉備は呉を攻撃するしかありませんでした。彼はどちらの道を選んだのでしょうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
水滸伝における胡三娘の肩書は何ですか? Yizhangqingとはどういう意味ですか?
胡三娘は古典小説『水滸伝』の登場人物で、「易張青」の異名を持ち、涼山の三人の女将軍の一人である。 I...
『左盛春夜』の作者は誰ですか?どのように鑑賞すればよいでしょうか?
チュンス・ズオシェン杜甫(唐代)夕暮れには花が壁の後ろに隠れ、鳥が飛びながらさえずります。どの家の上...
オズの魔法使い、第4章:宿屋で貧しい人々を助けるために白紙幣を切り、役所で私服に着替えて指導者を悼む
『オズの魔法使い』はファンタジー小説というよりは社会小説です。冷玉冰は仙人となる途中で弟子を受け入れ...
包公の事件簿 第39章 耳元で響く声
『鮑公案』は『龍土公案』とも呼ばれ、正式名称は『都本鮑龍土百公案全伝』で、『龍土神段公案』とも呼ばれ...
なぜ宮廷医師はリスクの高い職業だと考えられているのでしょうか?病気が治らなかった場合、本当に愛する人と一緒に埋葬されるのでしょうか?
時代劇を見ると、皇帝が他人の病気を治療するために宮廷の医師を招いたとき、宮廷の医師が治療が難しいと言...
「青春の旅・朝雲散薄絹」を鑑賞、詩人周邦艶が劉詩の欠点を補う
周邦厳(1057-1121)、号は梅成、号は清真居士、銭塘(現在の浙江省杭州市)の人。北宋時代の作家...
王安石はどのような経緯で「五江亭写本銘」を制作したのでしょうか?どうやって鑑賞すればいいのでしょうか?
王安石の『呉江閣の重複題目』、次の興味深い歴史編集者があなたに詳細な紹介をもたらします、見てみましょ...
二人とも牛魔王の妻なのに、鉄扇公主と玉面狐の間にはなぜこんなにも大きな違いがあるのでしょうか?
『西遊記』は、明代の呉承恩によって書かれた、古代中国における神と悪魔を扱った最初のロマンチックな小説...
「張」姓の男の子のためのシンプルで上品な名前のセレクション!
今日、Interesting History の編集者は、姓が張の男の子にふさわしいシンプルで上品な...
戦国時代には有名な七国以外に、全部でいくつの国があったのでしょうか?
春秋戦国時代も、多くの人がよく知っている時代です。この時代を代表する人物や国といえば、「春秋五覇」や...