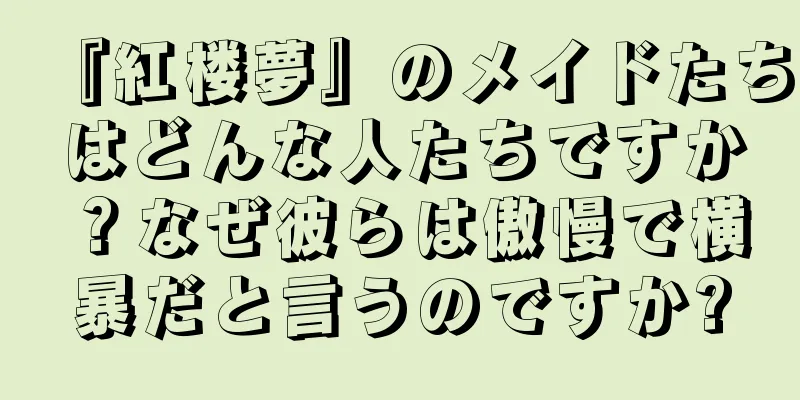崔俊の「草踏春宵」:女性の愛への憧れを、洗練され非現実的な絵で表現

|
孔鈞(961年 - 1023年10月24日)は、字を平中といい、華州下桂(現在の陝西省渭南市)の人である。北宋時代の政治家、詩人。 。白居易、張仁元とともに「渭南の三賢」の一人として知られている。崔仲敏は詩作に優れ、特に七字四行詩は魅力的で、三巻の『崔仲敏詩集』が現代まで伝わっている。それでは、次の興味深い歴史編集者が、Kou Zhun の「草踏・春夕」を紹介します。見てみましょう。 草の上を歩く - 春の夕暮れ 崑崙(宋代) 春はもうすぐ終わり、ムクドリの鳴き声は消え、赤い花びらは散り、緑の梅は小さくなっています。館内は静かで小雨が降り、山の衝立は半分隠れているが、香りは漂っている。 密約は重く、分離感は遠く、蓮の花はほこりに覆われ、輝くのが面倒です。私は建物に寄りかかり、言葉も出ず、悲嘆に暮れています。空は薄暗く、香りのよい草さえも暗くなっています。 これは、晩春の閨房で建物に寄りかかりながら恋人の帰りを願う少女の悲しい気持ちを表現した、閨房恨みの詩です。詩全体の言葉遣いは繊細で、深く、愛情にあふれています。情景の包括的な描写と、風景の緻密な描写の両方を備えています。情景に入り込み、感情と情景を融合させ、女性の恋の病を純粋かつ優雅に描き出しています。 前半は、春が過ぎ去ることへの悲しみと自己憐憫からくる主人公の孤独な心境を描写することに重点を置いています。 晩春となり、美しい春の景色も間もなく消え去ろうとしています。キイロコウライウグイスの鳴き声はますます成熟し、「コウライウグイスは恥ずかしそうに歌うことを覚えている」というように、優しく、さわやかで、耳に心地よいものではなくなっています。かつては華やかで色鮮やかだった赤い花は、すべて枝から離れて落ちてしまいました。緑の葉と木陰のある梅の木に、小さな緑の実が静かに実っていました。とても素晴らしい風景描写ですね。 「オリオールズの歌」、「赤い花」、「青い梅」は、たった3つですが、春の特徴が詰まっており、春の無限の美しさを具体的に示すのに十分です。 「色」と「音」、「青」と「赤」、「老い」と「若さ」の対比が鮮やかで明るく、言葉も巧みに洗練されており、考えさせられる。 「色あせる」「だんだん古くなる」「落ちた」「小さい」などの文字がはっきりと並んでおり、躍動感が強い。春の移り変わりは息を呑むほどだ。この詩の美しさは、言葉で表現されていなくても感情がはっきりと伝わってくるところにあります。春ははかないもので、私たちにはどうしようもない。こんなことなら、人々はどうやって耐えればいいのだろう。「草木が枯れるように、美しさも古びてしまうのではと心配だ!」(屈原『里索』)一度このような気持ちになると、「春の美しさがあまりにもうっとうしくて眠れない」(王安石『春の夜』)のも当然です。 屋外の光景はとても感動的ですが、壮麗なホールは静かで、私のそばには美しさはありません。混乱した春の雨だけが降り続け、春の時間が早く消え去るように促しています。美しい山水画の描かれた衝立が半分開いていたが、誰もそれに注意を向ける気はなかった。香炉は長い間燃え続け、今にも燃え尽きそうな残りの香りが、冷たく寂しい絵画館の中で、まるで果てしない遠い想いの流れのように、ゆらゆらと漂い、漂い、広がっていく。 「半開き」「ぼんやり」「湾曲」「静か」といった言葉は的確で詳細な描写で、華やかで精緻でありながらも寂しく空虚な絵画室の環境を生き生きと表現し、閨房で一人退屈している女性の憂鬱な気持ちと深い恨みを巧みに反映し、環境と心境の調和のとれた統一を完璧に形成している。 詩の後半では、主人公の愛する人との別れの深い悲しみと恋しさを表現することに焦点を当てています。 寝室で孤独になればなるほど、愛する人を恋しく思うようになります。思い出してみると、月明かりの下で私たちは誓いを立て、しぶしぶ別れを告げ、再び戻るための秘密の計画を立て、何千もの指示と警告を互いに与え合いました。私たちの愛はとても深かったのです。しかし、今まで彼女からの連絡が全くなく、彼女が戻ってくることもないなんて、誰が想像したでしょうか。 「沉沉」と「杳杳」という言葉を巧みに繰り返して使うことで、別れの感情の暗さ、深さ、広大さを強調しています。これでは鏡の前で化粧する気分は誰にもないだろう。「ダイヤモンド型の花がほこりまみれ」と細部までこだわり抜いた仕上がりだ。 「伯東の髪は飛ぶ草のよう。化粧水とシャンプーで体を洗わなければならないのに、誰が私の身だしなみを整えてくれるのか?」(詩経、魏風、伯熙)それで彼はダイヤモンド形の鏡にほこりを溜めたままにして、拭くのが面倒だった。愛する人のことがあまりにも恋しくて、そのことを考えずにはいられません。私はビルの最上階に行って見てみることにしました。もしかしたら、彼女が突然戻ってくるのを見ることができるかもしれません。しかし、現実は残酷です。私はまだ失望しています。私はイライラして言葉が出ません。しかし、私が見たのは、閨房の雰囲気と同じように、暗い広大な空でした。香りのよい草だけが空と地面をつなぎ、愛する人のいる遠い場所までずっと伸びていました。作者は風景を使って感情を表現し、自然な言語を作り出しています。香りのよい草は遠い場所を思い出させ、作者は巧みに暗示を使います。 「春草は毎年青々としている。王子は戻ってくるだろうか?」(王維『告別』) 「別れの悲しみは春草と同じで、どんどん離れていき、それでもまた生えてくる。」 (李游『清平月・中春の別れ』) 「人を悲しくさせるのは別れだけだ。」 (姜燕『告別』) 別れの悲しみが人をとても悲しくさせるとき、それは本当に魂が体から抜け出してしまったように感じます。悲しみと悲嘆は言葉では言い表せない。果てしない意味も言葉では言い表せない。 つまり、詩全体は風景の描写から始まり、その後、風景を使って感情を表現し、晩春に長い間会っていなかった恋人を恋しがる閨房の女性の孤独を巧みに感動的に表現しています。最初の部分は風景を描写し、風景から感情が生まれ、感情は風景の中にあります。2 番目の部分は感情を描写し、感情は風景に表現され、感情は風景で完結します。感情と情景が溶け合い、芸術的構想が完成し、感情と情景が織り合わされて天の神秘の錦織りを形成します。 |
<<: 歴代の王朝で秋の食べ物を描写した詩は何ですか?詩人はそれをどのように表現しているでしょうか?
>>: 張暁祥の『西江月・湖畔春景色問答』:詩人は俗世を軽蔑し憎む
推薦する
曹操の生涯において、曹操が最も望んだが、得られなかった三人の将軍は誰ですか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
古代中国では木造の建物が火災に遭わないようにどうやっていたのでしょうか?古代の防火具の発展の歴史
古代中国では木造建築物が火災に遭わないようにどうやっていたのでしょうか。古代の防火具の発展の歴史。 ...
後金の名将、王豫の伝記 後金の名将、王豫はどのようにして亡くなったのでしょうか?
王舜は後晋の有名な将軍でした。彼は生来残酷で狡猾でしたが、勇敢で戦闘に優れており、人々から賞賛されて...
桃園三勇士の物語はいつ広まったのでしょうか? 「神殿再建記録」には何が記録されていますか?
遅くとも宋代には、「桃園三英雄」の物語が民衆の間で広まり始めました。宋代末期から元代初期にかけて何景...
柴頭峰の『宋代の辞:赤くて柔らかい手』鑑賞。作者はどのような気持ちを表現しているのでしょうか?
簪の中の鳳凰:赤くて柔らかい手、宋代の陸游、次の興味深い歴史編集者があなたに詳細な紹介をもたらします...
なぜ昔の人は店主がお金を数えるのを待たずに、お釣りをテーブルに置いたのでしょうか?
時代劇を見たことがある友人なら、ドラマを追っているときに、このような場面を見たことがあるはずです。つ...
水滸伝で陸俊義と石文公が決闘したらどうなるでしょうか?
趙蓋はもともと涼山のトップの座に就いていたが、後に曽頭城で射殺され、それが宋江の権力奪取に直接つなが...
『梁書』に記されている徐勉とはどのような人物でしょうか?徐勉の伝記の詳細な説明
南北朝時代の梁朝の歴史を記した『梁書』には、6巻の史書と50巻の伝記が含まれているが、表や記録はない...
張松は劉璋の部下として、なぜ異例の優遇措置を放棄したのか? ?
今日の「興味深い歴史」で取り上げる戦略家は張松という人物です。私たちがお伝えするのは、張松と、劉璋を...
北魏の袁昊の略歴 北魏の袁昊はどのようにして亡くなったのでしょうか?
袁昊(485年 - 529年)は北魏の王族。号は子明。献文帝拓跋洪の孫、孝文帝袁洪の甥、北海王袁襄の...
『紅楼夢』のメイドたちは働くときどんな服装をしていたのでしょうか?
『紅楼夢』は、古代中国の章立て形式の長編小説であり、中国四大古典小説の一つである。普及版は全部で12...
四大古典の外国語訳の中で一番面白いのはどれでしょうか?
中国文学史上の「四大経」には、元代末期から明代初期の施乃安の『水滸伝』、明代初期の羅貫中の『三国志演...
「南への旅」の第 3 章ではどのような物語が語られますか?
凌瑶はドラゴン協会を明福に分割したしかし翌日、すべての真君は宮廷に集まり、玉帝に報告しました。「その...
フビライ・カーンは晩年、私生活でどのような挫折や不幸に遭遇したのでしょうか?
フビライ・カーンの晩年、彼の私生活も一連の挫折と不幸に見舞われた。次は興味深い歴史エディターが詳しく...
李端の『琴を聴く』:著者の洞察力と繊細な描写は非常に鮮明である
李端(737年頃 - 784年頃)、号は鄭義、唐代の詩人。昭君の李氏董祖支族の末裔。彼は、北斉の文宣...