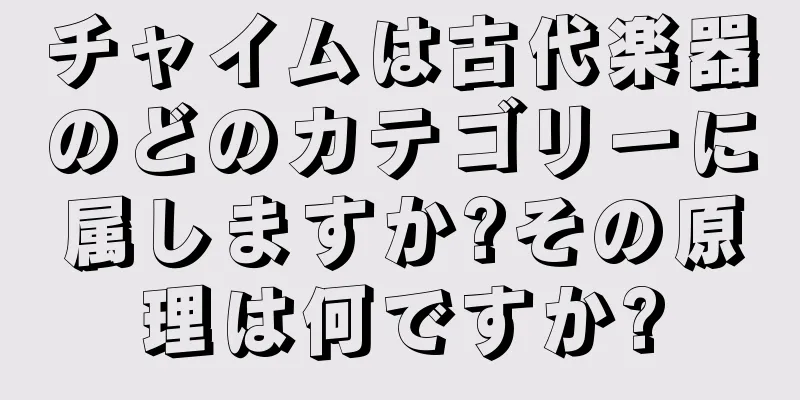「畑と庭に戻る、第 5 部」のオリジナル翻訳と評価

|
田舎に帰る、第5部 陶淵明(魏晋) 険しく曲がりくねった道を一人で通って帰ってくるのは悲しく、残念な気持ちです。 山の渓流は澄んでいて浅く、足を洗うのにちょうど良い肥沃な土地です。 新しく醸造したワインを濾して、鶏をゲームに招待します。 日が沈むと部屋は暗くなり、薪がろうそくの明かりの代わりとなります。 喜びは訪れますが、夜は短く、またすでに夜明けです。 翻訳 私はがっかりしながら杖をついて家に帰りました。険しい山道には草や木が生い茂っていました。 山の渓流は透き通っており、世間の汚れを洗い流すことができます。 新しく醸造したワインを自宅で濾過し、鶏を殺して近所の人々を楽しませます。 太陽が西に沈むと、部屋は暗く陰気になります。そこで、ろうそくの代わりに薪を灯します。 幸せなときはいつも夜が短すぎると文句を言いますが、いつの間にか昇る太陽が見えています。 注記 後悔: 失望の表情。策: 杖や松葉杖を指します。また、農作業を終えて家に帰ることも意味します。 Qu: 人里離れた道。この 2 つの文は、私がイライラしながら、杖に寄りかかりながら、草や木々に覆われた険しく人里離れた山道を一人で歩いて家に帰っていることを意味しています。 卓:洗う。足を洗う:世俗的な汚れを取り除くことを指します。 濾過する、しみ出す。新しく醸造されたワイン:新しく醸造されたワイン。近く:近所の人、隣人。これら 2 つの文は、ワインを濾過すること、鶏を殺すこと、近所の人を招いて一緒に飲むことを意味します。 暗い:薄暗い。この文と次の文は、太陽が沈むと家が暗くなり、ろうそくの代わりにとげのある木片に火が灯されるという意味です。 天旭:夜明け。この文と前の文は、楽しんでいる間に夜が明けてしまい、夜の短さを感じるという意味です。 感謝 これは詩集「庭園と野原への帰還」の 5 番目の詩です。一日の農作業を終えて帰宅途中や帰宅後の活動を描写し、「畑や庭に戻った」後の生活の別の側面を反映しています。 詩全体は2つの層に分けられます。最初の 4 つの文は最初の層を形成し、帰宅途中の情景の描写に重点を置いています。 「悲しみと後悔を感じながら、険しく曲がりくねった道を杖をついて一人で家に帰る」。仕事を終えて、杖をつき、悲しみと後悔を感じながら一人で家に帰る様子を描いています。しかし、家までの道は険しく、荒涼としていて、曲がりくねっています。表面的には、彼は一日中一生懸命働き、孤独で一人で家に帰らなければならなかったので、失望と憤りを感じずにはいられませんでした。より深い意味において、この詩は幸福で満ち足りた気持ちを表現しようとしており、「後悔」という言葉は、実際には、その後のテキストの明るさと喜びとを対比する役割を果たしています。「庭野に帰る」という詩全体を読むと、ここでの冒頭の「後悔」は、前の詩の荒涼とした丘と廃墟に対する嘆き、そして人生がやがて無に帰することに対する嘆きから来ていることが分かります。 「険しく曲がりくねった道」は、当時の社会不安によって生じた道の荒廃や困難さを描き、その時代背景の具体的なイメージを明らかにしています。 「渓流は澄んでいて浅く、足を洗うことができます。」途中、澄んだ山の泉を通り過ぎ、ほこりっぽい足を洗いました。一日中働いて疲れも洗い流され、全身が心地よくリラックスしました。この二つの文章は「悲しみや後悔」という感情をいとも簡単に吹き飛ばし、穏やかで満足した精神状態の自然な表現です。引退しても毅然とした態度を保つ決意を表します。 「足を洗える」という表現は、古代の『滄浪歌』に由来しており、「滄浪の水は澄んでいるので、房を洗うことができ、滄浪の水は濁っているので、足を洗うことができる」という一節がある。もともとこの詩は、滄浪水の透明度と濁度を比喩として使い、水が澄んでいるときには官に仕え、水が濁っているときには隠れるべきだという考えを鮮やかに表現していました。しかし、陶淵明は渓流の水を透き通ったままにして、その水で「足を洗う」という行為を続けており、これは著者の人生に対する関心と自然への献身と自然との調和を完璧に表している。 最後の 6 つの文は第 2 層を構成し、帰国後の活動について説明することに重点を置いています。 「新しく醸造したワインを濾過して、チキンをゲームに招待します。」自宅で新しく醸造したワインを濾過し、濁りを取り除き、飲用に適した透明なワインを保存します。彼はまた、近隣の農民たちを同じテーブルに座らせ、飲み物を飲み、鶏肉を食べるように誘い、それはとても楽しいことでした。この二行の詩は、隠遁詩人の祖先である陶淵明が田舎に戻った後の質素な農民生活を描いています。彼は畑を耕して生計を立てており、上等なワインや山海の幸など必要としていなかった。自家製のワインと鶏を飼い、近所の人や友人を招いて一緒に酒を飲めば、それで十分だった。このことからも、著者は近隣の農家と仲が良く、密接な関係にあることが伺える。 「日が沈むと部屋が暗くなるので、イバラをろうそく代わりに灯す。」 いつの間にか、「日が沈むと部屋が暗くなる。」 西に日が沈むと部屋が暗くなるので、イバラをろうそく代わりに灯すだけ。この文章はみすぼらしいように思えるかもしれないが、詩人の気楽で満足した自己を表現している。 「喜びは来るが、苦い夜は短く、夜明けがまた来る。」喜びが私の心を満たし、「喜び」という言葉の下にある「来る」という言葉が、喜びを自然で鮮明にしています。黄文煥氏は「『来』という字の配置が独特だ」と述べた。この状況と場面は、詩人たちに夜の短さと自分たちの興味を表現することの難しさについて不満を漏らすきっかけとなった。そして時間を無視して心ゆくまで飲んでください。 「もう夜明けを迎えた。」彼は、自分の高尚な野望と心の中にある超越的な感情を表現するために、太陽が徐々に昇り、空が明るくなるまで止まりませんでした。 この詩は、連作詩の中では主題の選択が独特です。田園風景や労働条件を描写しているのではなく、夕暮れから夜明けまでの活動、つまり今日のいわゆる「8時間外」の余暇を題材にして、田舎での幸せで充実した生活を表現しています。その視点は斬新で、新たな境地を拓いています。前の4つの詩と合わせて読むと、この詩群が、陶淵明の退官と引退の初期の人生場面と精神の歩みを、実に完全に、そして深く再現していることがわかります。 |
<<: 「夏の田舎情緒」をどう捉えるか?創作の背景は何ですか?
>>: 「初秋のガーデニング」の原文は何ですか?どのように鑑賞すればよいでしょうか?
推薦する
皇帝は龍のローブが汚れたときどうしましたか?本当に洗い流すだけでいいのでしょうか?
古代皇帝の汚れた龍のローブをきれいにする方法をご存知ですか?知らなくても大丈夫です。Interest...
赤壁の戦いの後、劉備はどのようにして荊州をしっかりと掌握したのでしょうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
古代軍事著作『江源』:第1巻『江北』全文と翻訳注
『江源』は、将軍の在り方を論じた中国古代の軍事書です。『諸葛亮将軍園』『武侯将軍園』『心中書』『武侯...
三国時代の呉の有名な将軍、甘寧の略歴
甘寧(?-220年)は、三国時代の呉の将軍で、芸名は興覇、愛称は金帆済。西陵の知事と浙州の将軍を務め...
李其は『古意』の中で兵士のイメージをどのように表現しているのでしょうか?
李斉の『古意』が兵士のイメージをどのように表現しているか知りたいですか?詩全体は前後の対照的な描写を...
旧暦1月13日の習慣は何ですか?旧暦1月13日の風習の紹介
中国の伝統文化は歴史が長く、奥が深いです!今日は、興味深い歴史の編集者が旧暦1月13日に新年を祝う習...
漢の元帝の後の皇帝は誰でしたか?漢の元帝が亡くなった後、誰が皇帝になりましたか?
漢の元帝の後の皇帝は誰でしたか?漢の元帝の死後、皇帝になったのは誰ですか?漢の元帝の次の皇帝は漢の成...
「季海雑詩・第5」の原文は何ですか?どのように理解すればよいのでしょうか?
季海の雑詩·第5号龔子真(清朝)別れの大きな悲しみに圧倒されながら日が沈む。鞭を東に向けると、地平線...
秦の始皇帝陵の2000年前の武器庫から数千点の石の鎧が発掘された
「秦の始皇帝陵」は、世界最大かつ最も独特な構造を持つ皇帝の墓の一つと考えられています。彼の王朝と野心...
『紅楼夢』における平児、宝仔、希人に対する評価はどうですか?
『紅楼夢』は、中国古代の章立ての長編小説で、中国古典四大傑作の一つです。今日は、Interestin...
『紅楼夢』の趙叔母さんと賈正の関係は何ですか?
みなさんこんにちは。趙おばさんといえば、みなさんも聞いたことがあると思います。賈正は本当に趙おばさん...
王希峰:古典小説『紅楼夢』の登場人物、金陵十二美女の一人
王希峰は、中国の古典小説『紅楼夢』の登場人物です。賈廉の妻で、王夫人の姪です。賈家では、一般的に鳳姐...
水滸伝の厄神である鮑胥はどのようにして死んだのでしょうか?死神、宝旭の簡単な紹介
水滸伝の死神、鮑胥はどのようにして死んだのでしょうか? 死神、鮑胥の紹介:鮑胥はもともと死樹山の盗賊...
隋王朝が最終的に滅亡した理由は何だったのでしょうか?実際の隋の煬帝はどんな人だったのでしょうか?
隋王朝といえば、私たちにとって馴染み深いものですね。さまざまな映画やテレビ番組、書籍に頻繁に登場しま...
昔と今の不思議 第34巻 女性学者の花と木の移植術(後編)
『今昔奇談』は、明代の鮑翁老人によって書かれた、中国語の俗語による短編小説集です。馮夢龍の『三語』と...