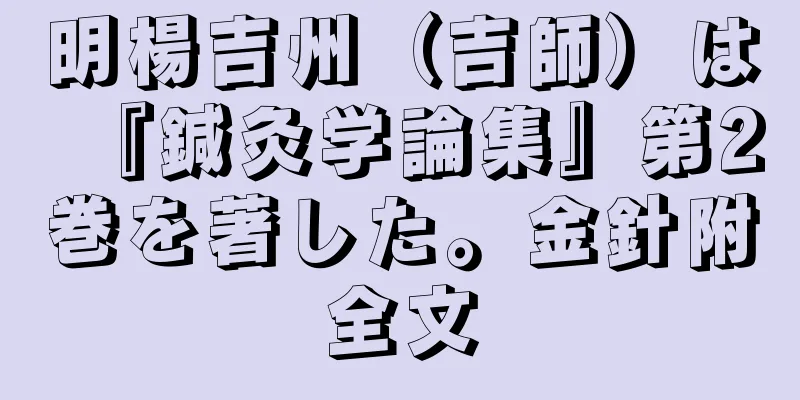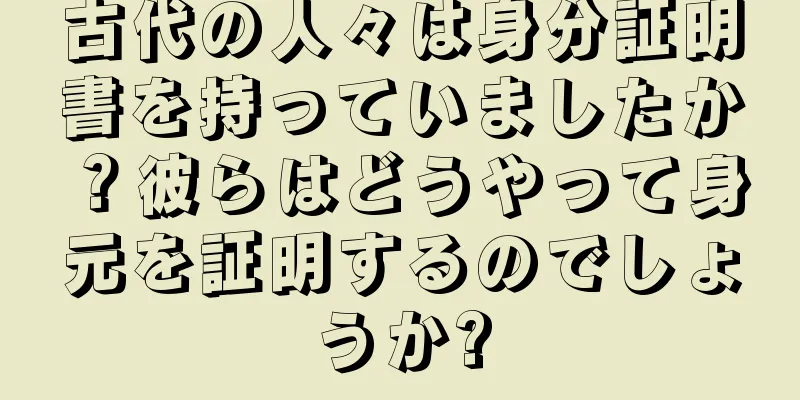本草綱目第3巻『諸病寒熱治療』の具体的な内容は何ですか?
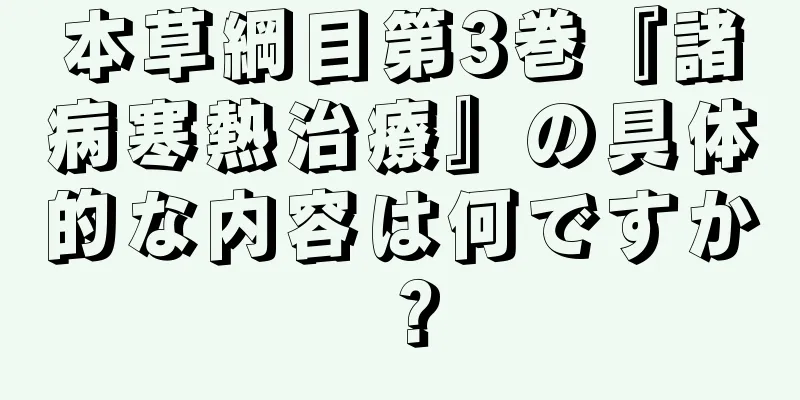
|
『本草綱目』は、明代の優れた医学者、李時珍によって著された全52巻からなる中国医学の古典書です。次の Interesting History 編集者は、皆さんと共有するために関連コンテンツを用意しました。 この本は「要綱に従って列挙する」という文体を採用しているため、「綱目」と名付けられました。 『正蕾本草』に基づいて改正された。この本には190万語以上が収録されており、1,892種類の医薬品が収録され、11,096の処方箋が収録され、1,160枚の精巧なイラストが掲載されています。16のパートと60のカテゴリに分かれています。本書は、著者が数十年にわたる実践と研究を重ね、これまでの生薬学の成果を継承・総括し、長期にわたる研究と聞き取り調査を通じて蓄積した広範な薬学知識を結集してまとめた傑作です。この本は、過去の生薬学におけるいくつかの誤りを訂正するだけでなく、大量の科学的データを統合し、より科学的な薬物分類方法を提案し、先進的な生物進化の考えを取り入れ、豊富な臨床実践を反映しています。この本は世界的な影響力を持つ自然史の本でもあります。 本草綱目 第3巻 あらゆる病気の治療 寒熱 【名前】 外部感染、内部損傷、火傷、無力症、マラリア、傷、瘡蓋炎などがあります。 【和解】 甘草:五臓六腑の寒熱邪を消し去る作用があり、虚弱体質や熱過多の人にも効果的です。ハナスゲ:腎不全、寒さや発熱に対する嫌悪感。サルビア・ミルティオリザ:無力症、風邪、発熱。オウレン:子供の風邪や発熱に。 Scutellaria baicalensis:悪寒と発熱が交互に起こり、骨に熱毒性が生じる。柴胡:寒熱の邪気、早朝のほてり、寒熱交代、女性の血室に入る熱を取り除く効果があります。ディクタムニ コルテックス: 高熱や悪寒を治療します。内臓:五臓のうちの寒と熱。秦郊、当帰、川芎、少薬:いずれも消耗性疾患、風邪、発熱の治療に用いられます。ナス、スベリヒユ、アマランサス、アリウム・マクロステモン、アプリコットの花:女性の風邪、熱、関節炎の治療に使用されます。桃色の髪:血の塊、寒さ、暑さ。マグノリア:風寒、寒さ、暑さを和らげます。 Vitex quinata と Vitex rotundifolia: 骨の間の冷たさと熱さを除去します。丹参を冷水で服用すると、患者は悪寒に襲われます。冬には、100 hu までの水でびしょ濡れになり、発汗すると回復します。貝子:温熱疾患の冷えや熱を治し、筋肉の緊張をほぐし、熱を発散させます。 【中臓を補い肺を清める】 黄耆:欠乏症における寒熱。アデノフォラ、イヌタデ、オウゴン:寒熱を除去し、気を補充し、胃の調子を整えます。キキョウ:寒さや暑さを取り除き、肺に良い。エボディア・ルタエカルパ、赤唐辛子、シナモン:肝臓と肺に効き、心臓と腹部の冷えと熱を和らげます。沈香:虚弱による各種の風邪、熱、寒痰に煎じてトリカブトと一緒に服用します。桑の葉には、冷えや熱を取り除き、発汗を促す働きがあります。豚の頭:冷たいものと熱いもの。 |
<<: 『本草綱目第 3 巻 あらゆる疾患および欠乏症の治療法』の元の内容は何ですか?
>>: 『本草綱目第3巻 血吐き及び鼻血等の諸疾患の治療』の本来の内容は何ですか?
推薦する
北魏は後期に衰退しました。その滅亡の直接的な原因は何でしたか?
中国の歴史における南北朝時代は、多くの王朝が共存し、国家間の戦争も頻繁に起こった、非常に混沌とした時...
古代バビロンは今どこの国ですか?古代バビロンはイラクですか?
古代バビロンはメソポタミア平原に位置しており、おおよそ現在のイラク共和国の領土内にあった。紀元前30...
『孫子』の著者は誰ですか?主な内容は何ですか?
『兵法』は、中国古代の軍事戦略に関する現存する最古の古典である。春秋時代に孫武によって書かれた。 「...
『新世界物語』第 23 章はどのような真実を表現していますか?
『十碩心于』は南宋時代の作家劉易清が書いた文学小説集です。では、『十碩心於・談話篇・第23章』に表現...
『江城子・澳州狩猟記』の執筆背景は何ですか?どのように理解すればいいのでしょうか?
【オリジナル】私は老人として、黄を左に、青を右に抱き、錦の帽子とクロテンのコートを着て、千頭の馬に乗...
なぜ古代では、権力は王族の親族ではなく、王族以外の親族によって主に握られていたのでしょうか。
なぜ古代では、王家の親族ではなく、皇帝の親族が権力を握ることが多かったのでしょうか。今日は、古代の封...
袁震は4つの恋愛物語があり、その物語は有名なドラマに翻案された。
唐代の大詩人袁真と、袁真より8歳年上の白居易は、共に生き、共に死んだ親友であった。二人は共に「新月符...
『紅楼夢』で、リン・ダオユはなぜ母親のジアに自分の気持ちを伝えなかったのですか?
『紅楼夢』は、古代中国の章立て形式の長編小説であり、中国四大古典小説の一つである。普及版は全部で12...
古代人が兄弟姉妹と結婚できた理由の秘密を明かす?奇妙な習慣を見てみよう
伏羲は、西皇や伏羲とも呼ばれ、中国神話における人類の祖先です。伝説によると、人類は伏羲と女媧の結婚に...
『太平広記』第369巻「鬼と妖怪2」の原文は何ですか?
蘇丙の娘江衛月華陰村鄭衛良東来客接待都市人岑順源の李楚斌が使用した雑器ス・ピヌ蘇丙は天宝年間に楚丘の...
顧振観が書いた「金糸の歌二首」は、呉昭謙への作者の丁寧な指示である。
顧振関は、本名は華文、雅号は元平、華鋒、雅号は梁汾で知られた清代の作家である。陳衛松、朱一尊とともに...
ブーラン族の宗教的信仰: ブーラン族の上座部仏教
上座部仏教は15世紀中頃に雲南省南西部と西部に伝わりました。当初は抵抗され、拒絶されましたが、数年を...
中秋節に潮を見るのはなぜでしょうか?中秋節に潮を見ることの起源と意味は何ですか?
中秋節になぜ潮を見るのでしょうか?中秋節に潮を見ることの起源と意義は何でしょうか?Interesti...
「年寄りの言うことを聞かない」の後半部分は何ですか?この文章全体をどう理解すればいいのでしょうか?
「年長者の忠告に耳を傾けるな」の後半部分とは何でしょうか?この文章全体をどう理解すればよいのでしょう...
「穀豊日標語」は明代の李昌麒が書いたもので、穀豊穣の季節の独特の魅力を捉えている。
明代の李昌奇が書いた「孝明節の標語」については、次の興味深い歴史編集者が詳しく紹介しますので、見てみ...