顔のほうれい線は何を表しているのでしょうか?ほうれい線とは
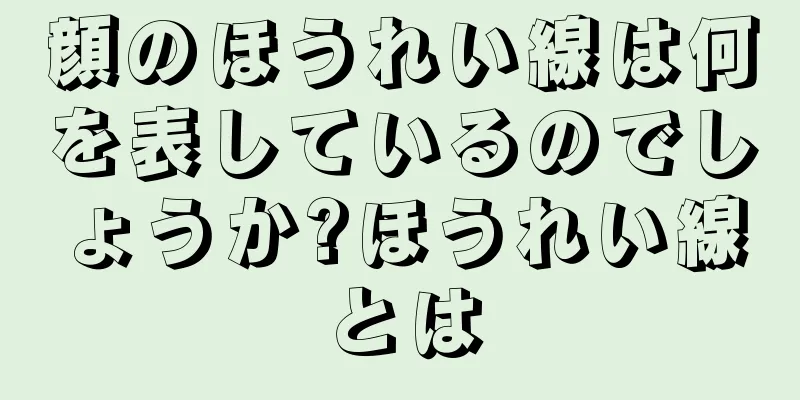
|
鼻のしわは口の両側にある線です。多くの人が持っています。鼻のしわは顔の特徴的な特徴であり、その人のさまざまなことを表します。ほうれい線について語るには、まず歴史上の出来事について語らなければなりません。漢の文帝は歴史に残る賢明な皇帝であり、彼が始めた「文靖帝」は漢王朝全体の絶頂期でした。文帝は勤勉で倹約家で、着古した衣服さえも捨てることをためらっていましたが、寵臣の鄧統を非常に可愛がり、彼のために費やしたお金の額は計り知れないほどでした。彼らは一緒に出かけるだけでなく、夜も同じベッドで寝ました。古代人は顔相を読むのが好きでした。かつて有名な占い師が鄧統の顔相を占い、鄧統のほうれい線の形がよくないと言いました。占い師は、鄧統は間違いなく餓死するだろうと結論付けました。これを聞いた漢の文帝は反対しました。文帝は占い師の判断を否定し、自分の洞察力と権力を証明するために、占い師の醜さを暴露して鄧通をさらに裕福にしようとした。こうして鄧統は富豪となり、文帝の援助のおかげで長い間世界一の富豪であったが、結局は飢えと寒さで亡くなってしまった。 現代の人相学では、ほうれい線を判断する基準は次のとおりです。 1. ほうれい線が左右非対称だと、性格が不安定になり、職場の上司や同僚とうまく付き合うことが難しくなります。 2. ほうれい線が口角に垂れ下がっている場合、人相書では「滕蛇の入り口」と呼ばれ、これは不利な人相です。古代の書物では飢餓の人相と呼ばれ、現代では胃腸疾患にかかりやすいことを表しています。 3. 女性が口角近くに深いほうれい線を持っている場合、これは恋愛生活に良くなく、結婚や異性との関係が円滑にならないでしょう。 4. 若い女性に深いほうれい線がある場合、それは両親との絆が弱いことを意味し、若い頃に苦労し、家族からのサポートを得るのが難しくなります。 5. ほうれい線は長くて広い方が良いです。そのような人は良いキャリアを持ち、指示を与えることができます。ほうれい線が広いほど、キャリアは良くなります。 6. ほうれい線が真ん中で折れている場合は、外界や他人の影響を受けやすく、意志が弱く、人生の方向が変わりやすいことを意味します。 ? 7. ほうれい線が短すぎたり、目立たなかったりする人は、途中で諦めてしまいがちで、人生に忍耐力がなくなり、常に誰かに励ましてもらう必要があります。 8. ほうれい線に傷や凹みがある人は、人生で裏切られる可能性が高いです。仕事ではもっと慎重になり、他人に任せず自分で行う必要があります。 9. ほうれい線が左右非対称な人は、仕事で障害に遭遇しやすく、多くの不平等な経験をすることになります。 上記は、一般的なほうれい線の基本的な見方です。幸いなことに、ほうれい線は後天的な修正によって改善することができます。しかし、顔だけから判断すると、これがより明白であり、判断がより正確です。 |
<<: 古代宋代の貨幣はなぜ清代の銀貨ほど価値がないのでしょうか?
>>: 「人間豚」とは何ですか?血まみれの「人間豚」の生産工程
推薦する
林冲はどのようにして涼山に入隊させられたのでしょうか?彼の性格的特徴は何ですか?
林冲は『水滸伝』の登場人物で、東京の80万人の近衛兵の教官を務めています。108人の英雄の中で、林冲...
『大連花宇寺蘭亭古今街道』の原文は何ですか?これをどう理解すべきでしょうか?
蝶の愛の花·豫寺蘭亭古今街道陸游(宋代)豫寺と蘭亭の古道と現代道。澄み切った霜の夜、湖畔の木々はすべ...
「肘の緊急処方箋」第1.5巻 突然の悪夢と不眠症を治療するための処方箋
『肘の応急処方』は古代中国の医学処方書です。これは中国初の臨床応急処置マニュアルです。漢方治療に関す...
開封県知事は何級の官吏ですか?開封県知事の責任は何ですか?
県知事の役職についての簡単な紹介:開封県知事とはどのような役人ですか?開封県とは何ですか?開封県知事...
薛剛の唐に対する反乱、第71章:父と息子はお互いを認識せずに戦い、夫婦は会って周の軍隊を打ち負かす
『薛剛の反唐』は、汝連居士によって書かれた中国の伝統的な物語です。主に、唐代の薛仁貴の息子である薛定...
古代に人気の宴会ゲーム:「壺投げ」は春秋時代に酒盛りに使われた
宴会は中国人にとって重要な精神的な舞台です。喜びも悲しみも、怒りも悲しみも、みんなで飲み干して楽しく...
司馬師の妻は誰ですか?司馬師には何人の妻がいましたか?その妻たちは誰でしたか?
司馬師の妻は誰ですか?司馬師には何人の妻がいましたか? 1. 夏侯慧(最初の妻)夏侯慧(211年 -...
なぜ曹充は曹丕に殺されたと言われるのでしょうか?この主張はどのような根拠に基づいているのでしょうか?
曹操は戦闘に優れていただけでなく、子孫を残すことにも長けていました。曹操には25人の息子と6人の娘が...
古典『管子国俊』の原文は何ですか?管子国鈔の詳しい説明
『管子』は秦以前の時代のさまざまな学派の演説をまとめたものです。法家、儒家、道家、陰陽家、名家、兵学...
清風図第9章:小吉は強氏を妻探しに誘うしかない
今日、興味深い歴史の編集者は、清代の溥麟が書いた小説「清風図」第九章の全文をお届けします。この本は、...
孟浩然の古詩「八人に入隊の通知を送る」の本来の意味を理解する
古代詩「第八軍に通達を送る」時代: 唐代著者: 孟浩然男は元気いっぱいなのに、なぜそんなにたくさんの...
古典文学の傑作『太平天国』:官部第66巻全文
『太平百科事典』は宋代の有名な百科事典で、北宋の李芳、李牧、徐玄などの学者が皇帝の命を受けて編纂した...
ヌルハチは女真族の子孫ですか?清朝王室の血統の秘密
歴史の記録によると、女真族の祖先は数千年前の夏、商、西周の時代にまで遡ることができるが、当時は「女真...
古代の十大魔女とは誰ですか?邪悪な女性トップ10はどんな人ですか?
古代の十大魔女とは誰でしょうか?以下、Interesting History編集部が関連内容を詳しく...
東林党争議とは何ですか?東林党闘争の起源、過程、結果
東林党争議とは、明代末期の東林党、宦官党などの派閥間の争いを指す。「声を上げる者はますます国を治める...









