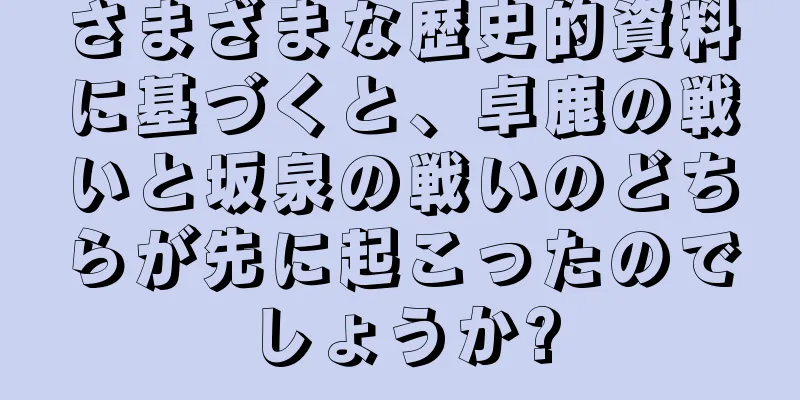心学派の創始者、王守人氏とは誰ですか?王守人の著作の有名な引用文は何ですか?
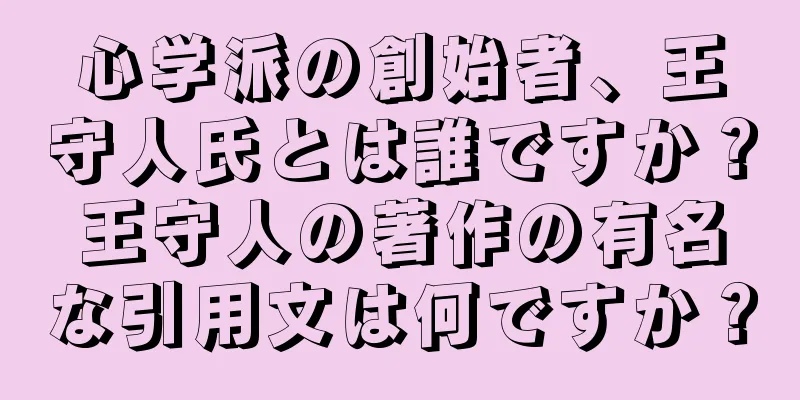
|
心学派の創始者、王守人氏とは誰ですか?王守人の著作や名言は何ですか? 王守仁とは誰ですか? 王守仁は王陽明とも呼ばれ、1472年に生まれました。彼の雅号は伯安で、陽明氏として知られていました。彼は生涯を通じて博識で多作であり、多くの本を著しました。彼は有名な思想家、作家、哲学者でした。彼の最も有名な業績は、陸と王の哲学を一人の人物に統合したことです。 王守仁は浙江省紹興県の出身で、名家の子として生まれ、幼いころから詩や書物に精通し、並外れた知恵を示しました。息子に良い学習環境を与えるために、両親は余姚から山と川のある美しい都市、紹興に引っ越しました。王守仁は両親の期待を裏切らなかった。12歳で初めて私立学校に入学したとき、彼は先生と世界情勢について議論し、国の政治について話し、人間の情勢について考えることができた。 彼は私立学校で一生懸命勉強し、一発で科挙に合格した。何度も首席を逃したが、27歳で科挙に合格して進士となった。彼は司法省長官に任命され、後に広東省と広西省の総督となり、まさに朝廷の柱となった。彼は広い心を持ち、野心的であったはずだったが、朝廷から度々降格された。彼は晩年に復活したが、朝廷に助言するには年老いすぎていた。 王守仁は官職に就くことが困難になったため、悟りの道に進み、儒教の心の哲学を理解し、多くの信者を集めて講義を行った。彼は「良心を養うこと」と「知行合一」を主張し、朱熹の「事物を調べて知を得ること」の理論に反対し、「事物を調べて知を得ること」は人間の本性を奪い、複雑すぎると信じていた。 陽明氏の生涯を振り返ると、国については朝廷に進言し、国と世界の興亡を自らの責任としてとらえ、学問については、明朝の主流の学説の一つとして、さらには海外にまで広まった心学を継承し、生涯にわたって著述を行い、その著作は数多く輝かしく、心学の秘訣を書に取り入れ、そのことに後悔はなかった。 王守仁は浙江省紹興県の出身で、名家の子として生まれ、幼いころから詩や書物に精通し、並外れた知恵を示しました。息子に良い学習環境を与えるために、両親は余姚から山と川のある美しい都市、紹興に引っ越しました。王守仁は両親の期待を裏切らなかった。12歳で初めて私立学校に入学したとき、彼は先生と世界情勢について議論し、国の政治について話し、人間の情勢について考えることができた。 彼は私立学校で一生懸命勉強し、一発で科挙に合格した。何度も首席を逃したが、27歳で科挙に合格して進士となった。彼は司法省長官に任命され、後に広東省と広西省の総督となり、まさに朝廷の柱となった。彼は広い心を持ち、野心的であったはずだったが、朝廷から度々降格された。彼は晩年に復活したが、朝廷に助言するには年老いすぎていた。 王守仁は官職に就くことが困難になったため、悟りの道に進み、儒教の心の哲学を理解し、多くの信者を集めて講義を行った。彼は「良心を養うこと」と「知行合一」を主張し、朱熹の「事物を調べて知を得ること」の理論に反対し、「事物を調べて知を得ること」は人間の本性を奪い、複雑すぎると信じていた。 陽明氏の生涯を振り返ると、国については朝廷に進言し、国と世界の興亡を自らの責任としてとらえ、学問については、明朝の主流の学説の一つとして、さらには海外にまで広まった心学を継承し、生涯にわたって著述を行い、その著作は数多く輝かしく、心学の秘訣を書に取り入れ、そのことに後悔はなかった。 王守仁の心の哲学の中心となる考えは、「良心の涵養」と「知行合一」である。 「良心に従う」とは、自分の内なる道徳基準に従うことができれば、外的な事柄を気にする必要がないことを意味します。 「良心」とは、自分の内面的な考えや道徳を指すだけでなく、自然の原理も指します。 王守仁は、すべての人に良心があり、すべての人の心の中に理性が存在すると信じていました。 「知識と行動の統一」とは、知識と行動が相互に依存しており、両者が切り離せないことを意味します。 「知る」とは認識すること、善悪、あらゆることを知ることを意味します。 「行為」とは、人が「知識」に基づいて善を保持し、悪を排除することです。 簡単に言えば、人が何かの善悪について内なる理解を持っている場合、その人は内なる理解に従ってそれを実践するでしょう。人間が自分の内なる認識を行動に移さなければ、簡単に言えば、王守仁が言う「認識と行動の統一」を達成していないことになります。この側面から、知識は実践の中にあり、実践は知識の中にあることが示されます。 「良心の実現」は「知行合一」の前提であり、「知行合一」は「良心の実現」の基準である。両者は独立して存在し得ない。 王守仁の思想のユニークさは、知識と行為の関係を切り離さなかったことにあります。彼は、知識と行為が結びついて初めて完全な存在になると信じていました。これは、彼の思想が明代の主流思想の一つとなった重要な要因でもあります。今日の社会においても、心理学は自己理解のための一定の参考価値を持っています。 王守仁の作品 王守仁は陽明先生とも呼ばれ、明代の心学の師であり、偉大な学者であった。彼の死後、後世の人々から王文成先生として称えられた。彼は公職のほかに、立法院で講義も行い、多くの文学作品を残しました。では、彼の作品とはどのようなものなのでしょうか。 王守仁の作品は流暢かつ雄大な文体で書かれており、行間から彼の野心が読み取れます。現在広く流布している彼の哲学的著作には、『実生指南』、『陽明全集』、『大学論』などがある。 『実生指南』の主な内容は、王守仁と友人や弟子たちとの間で交わされた学問上の事柄に関する書簡と王守仁自身の言葉の引用を集めたものであり、客観的な観点から王守仁の心の哲学の主要な思想を要約しており、後世の学者が王守仁の思想と心の哲学理論を研究するための重要な基礎を提供している。 また、陽明先生の『陽明全集』は『王文成公全集』とも呼ばれ、我が国の明代主流思想学派の研究において重要な位置を占めています。 『大学』は、心の哲学の真髄を記録した重要な経典であり、心の哲学の主要な真髄を問答方式で簡潔かつ明確に説明しています。 王守仁は、心の学派の研究と発展に関する著作のほかに、詩においても大きな業績を残しました。詩は彼にとって感情を表現し、世界の変化を嘆く主な手段であり、なくてはならないものである。この詩は、絶妙でシンプルな言葉が使われており、厳密な構成を持ち、印象に残ります。詩の内容は日常生活に基づいていますが、小さなことから大きなこと、微妙なことから深遠なことを見ています。 王守仁の著作を見ると、生涯を通じて博識で博識な人物であり、興味の対象は幅広く、主題に制限がなかったことがわかります。上記の書籍や詩のほかに、「毛先夫に」「旅人の埋葬」などの随筆や、「退却」という歌もあります。 王守仁の名言 明代の偉大な儒学者で、後に王文成公と称えられた王守仁も、後世に多くの名言を残しました。彼の名言には深い意味があり、後世の人々に深く考えさせます。 彼らの中で最も人気のある格言は、「山の敵を倒すのは簡単だが、心の敵を倒すのは難しい」です。これは、明徳13年に当時の検閲総監であった王守仁が江西省に匪賊を討伐しに行った際に、弟子に宛てた手紙の中で書いた文章です。彼は弟子たちに、地方の匪賊を鎮圧するのは簡単だが、匪賊と地方民衆の思想認識を根本的に修正するのは非常に難しいと語った。彼らの認識はすでに形成されており、社会不安の根本原因を根絶するのは依然として困難である。 この一文から、人を変えるには、その人の心から始めなければならないことが分かります。この方法でのみ、本当の変化を達成することができます。明代という偉大な歴史の舞台において、王守仁の深い理解は時代の最先端にあった。 「心は理なり」という言葉は皆さんもよくご存知だと思います。それは、自分と対象は同一であり、また独立した存在であるという意味です。外界の事物を認識するのは人間の本能であり、心は世界を判断する存在である。心の役割を極め、人間と自然の統一を実現できれば、その人はすべてを見通すことができる。現代社会においても、これは重要な意味を持っています。人は自分の感性だけで物事を判断するだけでは不十分で、合理性と感性の両方が求められます。 前述の 2 つの有名な引用に加えて、博識で知識も豊富だった王守人は、私たちがさらに探求する必要がある他の多くの有名な格言や格言も残しました。王守仁の有名な言葉からは、彼の気質や野心、そして政治への執着が垣間見えます。 |
<<: 王守仁の子孫は、王守仁のどの子孫が有名かを紹介します
推薦する
本草綱目第8巻乾苔の本来の内容は何ですか?
『本草綱目』は、明代の優れた医学者、李時珍によって著された全52巻からなる中国医学の古典書です。次の...
鄴皇と女英の夫は誰でしたか?姉妹が一人の夫を共有する前例を作る
メロドラマやインターネット上の古い小説の中には、姉妹が同じ人に恋をしたり、妹が姉の恋人を誘惑したりす...
『太平広記』第331巻の「鬼十六」の原文は何ですか?
薛進、朱其娘、李光元、李巴、洛陽鬼兵、李道徳学者、安芳学者、裴勝、楊普、薛志、劉紅薛進薛進は開元時代...
土地占拠制度とは何ですか?土地占有制度の概要
曹魏が実施した大規模な軍事農耕制度は、魏の末期までに徐々に破壊されていった。西暦264年、魏の元帝は...
「ゴブリ」蒸しパンの起源 ゴブリ蒸しパンの起源と伝説
伝説によると、清朝時代、天津近郊の武清県楊村に高貴有という若者が住んでいた。彼は子供の頃から頑固な性...
『紅楼夢』で宝玉はなぜ黛玉に銀杏を食べさせたのですか?それはどういう意味ですか?
『紅楼夢』では、賈牧の最も愛された子孫が宝玉と黛玉であることは誰もが知っています。以下の記事はInt...
『文心语龍』第34章の原文の鑑賞
感情を設定するには家があり、言葉を配置するには位置があります。感情の家は章と呼ばれ、言葉の位置は文と...
『紅楼夢』で黛玉が北京に行ったとき、なぜ幼い雪艶を連れて行ったのですか?
林黛玉の母親が亡くなった後、林如海は賈宇村に林黛玉を北京に連れて行くよう託した。次回はInteres...
水滸伝には李逵に関するどんな話がありますか?彼はどのようにして宋江と知り合ったのですか?
水滸伝で李逵が涼山に行った理由の紹介水滸伝の李逵は、元代末期から明代初期の有名な小説家、施乃安が書い...
七剣士と十三英雄第150章:呉天雄とその家族が戻り、玄真子が祭壇に登り命令を下す
『七剣士十三勇士』は、『七子十三命』とも呼ばれ、清代の作家唐雲州が書いた侠道小説である。清代末期の侠...
唐代の転換点を語るとき、なぜ李林甫が言及されなければならないのでしょうか?
『長安の一番長い日』の人気により、唐の玄宗皇帝に注目する人が増えています。玄宗皇帝は前半生では賢く、...
鏡の中の花 第33章:白い顔の男は縛られた足に閉じ込められ、長いひげの女は彼女のお尻を弄んで愛情を示す
『鏡花』は清代の学者、李如真が書いた長編小説で、全100章からなり、『西遊記』『冊封』『唐人奇譚』な...
蘇東坡はどのようにして健康を維持したのでしょうか? 『東坡志林』にはどのように記録されているのでしょうか?
現代では蘇東坡の健康法に感心する人が少なくありません。では、この文豪であり大食漢だった人物は、どのよ...
「The Road is Hard, Part One」の執筆背景を教えてください。これをどう理解すべきでしょうか?
【オリジナル】金の杯に入った一杯のワインは一万枚の貨幣の値段がし、翡翠の皿に盛られた珍味も一万枚の貨...
陸游の『西村』:この詩の特徴は、物事に縛られず、物事の外観から自由であることです。
陸游(1125年11月13日 - 1210年1月26日)は、字は武官、字は方翁、越州山陰(現在の浙江...