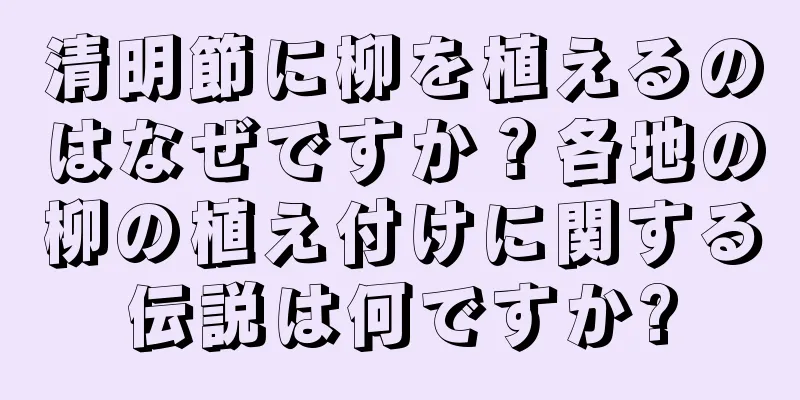明代の神宗皇帝朱義君の生涯

|
明代の神宗皇帝の本名は朱懿君であり、明代の第13代皇帝であった。彼が10歳のとき、父親が亡くなり、少年ながら王位に就かなければなりませんでした。朱義君は即位後、副大臣の間で争いが起こり、最終的に内閣顧問として残ったのは張居正のみとなり、張居正と朱義君の間には10年以上も続く抑圧と抑圧される関係が始まった。 朱義君は若くして帝位に就いたが、権力を握る前は常に張居正の影の下に生きていたと言える。権力を握った後もその影は完全には消えず、張居正の死後まで状況は改善されなかった。もちろん、これは張居正の死後、朱一軍の統治姿勢が劇的に変化した理由も説明しています。 明代の皇帝朱義君の生涯 朱懿君は1562年に生まれた。彼は父の3番目の子だった。彼には2人の兄がいたが、彼らは若くして亡くなった。そのため、彼は皇帝になる運命にあったと言える。彼は6歳のとき、父である明朝の穆宗皇帝によって皇太子に立てられた。 朱義君が皇太子に立てられてから4年後、父王の死により朱義君が即位した。彼が即位した後の彼の治世は万暦と呼ばれた。当時、若くして帝位に就いた朱義君は、父の命令に従い、熱心に統治し、大臣の言うことを聞き入れ、発展に資する多くの改革政策を実施し、非常に有名な出来事である「万暦の三大遠征」を主導しました。当時の社会観は一新され、人々は豊かで快適な暮らしを送ったと言われており、後世の人々からも「万暦の新政」として称賛されています。 しかし、この繁栄は長くは続かなかった。張居正の死後4年目、つまり朱義君の治世14年目に、朱義君は酒と色に溺れるようになり、その後、誰が皇太子になるべきかを巡って内閣と口論し、ついには国事を無視して30年間宮殿を離れなかった。 国事を無視していればよかったのですが、朱怡君は金銭欲が強かったため、世界中の富をすべて自分のものにしようとし、民衆から鉱山税まで徴収しました。彼は宦官を派遣して税金の徴収を監督させ、民衆から金銭を巻き上げさせた。彼の治世の後半、人々は悲惨な暮らしを送っていた。 朱一軍と張居正の闘争 張居政は明代の「時代を救った宰相」や「有名な改革大臣」として称賛された。しかし、この世代の名士たちは権力に非常に熱心でした。当時、朱義軍の父が死去する前に取り決めたことによると、もう一人の副大臣である高公が最高位の、最も権力のある大臣であった。しかし、張居正の取り決めにより、高公は宮廷から追放された。高公が去った後、もう一人の副大臣も張居正に怯え、血を吐いて亡くなった。 それ以来、張居正は朱怡軍の父が残した3人の内閣副大臣のうち唯一残った人物となった。張居正は若くして帝位に就いた朱懿君に厳しい要求をし、非常に厳しい学習スケジュールを定めた。そのスケジュールは1分1秒まで詳細に定められていたと言われている。朱一軍には抵抗するすべがなかったため、張居正の支配の影の下で成長した。このように育った朱一軍は張居正に非常に依存していたが、張居正の独裁的な統治を受け入れることは非常に困難だった。 張居正は10年間権力を握っていたが、彼が行使した権力は朱義軍が持つべきものであった。張居正にとって、これは政権にとって必要不可欠なものであったが、朱義軍にとっては権力の喪失の象徴であった。朱一君の目には、張居政の国家への忠誠心は皇帝の権力に対する軽蔑として映った。 張居正が生きている間、朱怡君には抵抗するすべがなかった。張居正の死後、朱怡君の秘められた怒りが爆発したようだった。張居正の死後4日目、当時の皇帝の検閲官たちは朱義軍の意図をよく知っていたため、張居正の残りの側近たちを弾劾し始め、後に張居正に直接非難の矛先を向けた。朱怡軍はこれを機に張居正の自宅を捜索するよう命じ、朱怡軍の怒りを鎮めるために張居正の棺が開けられそうになった。朱一軍が世論の圧力に耐えられなくなったとき、彼はようやく張居正の親族や友人に対する迫害をやめた。 朱一軍は死後物議を醸した 張居正は生前は栄華を誇っていたが、死後財産を没収され、名声も失墜した。朱一軍の生前と死後の張居正に対する態度は、当時の多くの名官の心を凍らせた。しかし、これは君主の権力と大臣の権力の矛盾なのかもしれません。張居正は世間では有名な大臣ですが、朱一君にとっては裏切り者の大臣です。 朱義軍の48年間の統治期間中、彼は勤勉であると同時に無謀で、人々は安楽と幸福を経験したが、同時に苦痛と貧困も経験した。そのため、後世の人々の彼に対する評価は、愛憎入り混じったものとなっている。著者の評価は複雑である。ただ言えることは、朱一君が初期の統治に熱心に取り組んだのは張居正の教えによるところが大きいが、教えが厳しすぎることも逆効果を招いたということである。 張居正の存命中は朱一君は名君であったが、張居正の死後まもなく暴君となった。これは極度の抑圧からの解放によって生じた人間性の歪みであった。この歪曲は、実は多くの大学入試受験生が大学入試を受けた後に薬物使用や中絶に手を染める事件と似ている。人間はバネのようなものです。あまり強く圧縮したり、あまりに引き伸ばしたりすることはできません。そうしないと、バネが壊れ、人間性が崩壊してしまいます。 |
推薦する
「成都曲」の原文は何ですか?どのように鑑賞すればよいでしょうか?
成都ソン張季(唐代)錦江の水は西側では緑に霧がかかっており、雨上がりの山ではライチが実っています。万...
元王朝の領土はどれくらい広かったのでしょうか?元朝の領土の最北端はどこですか?
今日は、興味深い歴史の編集者が元朝の領土についての記事をお届けします。ぜひお読みください〜周知のよう...
唐代の詩人杜申艶の『蘭州往来』をどう鑑賞するか?
杜神艶の『蘭州紀行』では、次の興味深い歴史編集者が詳しい紹介をお届けしますので、ぜひご覧ください。蘭...
有名な哲学書『荘子』:外篇:天地篇(1)原文鑑賞と方言訳
『荘子』は『南華経』とも呼ばれ、戦国時代後期に荘子とその弟子たちが著した道教の教義をまとめた書物です...
世界から忘れ去られつつある二十四節気は、中国の39番目の世界級無形文化遺産である。
2016年11月30日、「二十四節気」が正式に世界無形文化遺産リストに登録されました。中国で39番目...
「南朝四百八十の寺、霧雨の中の多くの楼閣」:『長江南の春』鑑賞
以下、Interesting History の編集者が杜牧の「長江南の春」の原文と評価をお届けしま...
易経の卦とは「元夫と会って、互いに信頼し合う」という意味ですか?
『易経』の奎卦にある「袁夫、交夫に会う」とはどういう意味でしょうか? これは多くの読者が知りたい質問...
白居易の詩「正月三日徒然」の本来の意味を鑑賞する
古詩「正月三日の徒然なる歩み」時代: 唐代著者: 白居易オリオールの並木道の入り口ではオリオールが歌...
李毅の「暁の角笛を聞く」:この詩は鏡に映った自分の姿を写し取るという手法を用いている
李懿(746-829)、号は君有、隴西省古蔵(現在の甘粛省武威市)の出身。後に河南省洛陽に移住。唐代...
「涼州二歌一」を鑑賞するには?創作の背景は何ですか?
涼州慈詩集その1王志桓(唐代)黄河は白い雲の間を遠く流れ、孤立した都市とそびえ立つ山々が見えます。春...
諸葛亮はなぜ張宝の死の知らせを聞いて気を失ったのでしょうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
唐僧の紫金の鉢はどのようにしてできたのでしょうか?彼が経典を手に入れるために旅に出たとき、なぜ紫の金の鉢を残していったのでしょうか。
今日、『Interesting History』の編集者は、経典を探すときに紫の金の鉢を残して行かな...
宋江が毒殺された後、なぜ呉容と華容は同時に宋江の墓の前で首を吊ったのですか?
みなさんこんにちは、「水滸伝」といえば、みなさんも聞いたことがあると思います。 『水滸伝』の終盤では...
西涼政権の君主、李勲とはどのような人物だったのでしょうか?歴史は李勲をどのように評価しているのでしょうか?
李勲(?-421)は、隴西省城邑(現在の甘粛省秦安市)の出身で、西涼の武昭王李昊の息子であり、西涼最...
曹操はすでに葬儀の準備を済ませているのに、なぜため息をつく必要があるのか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...