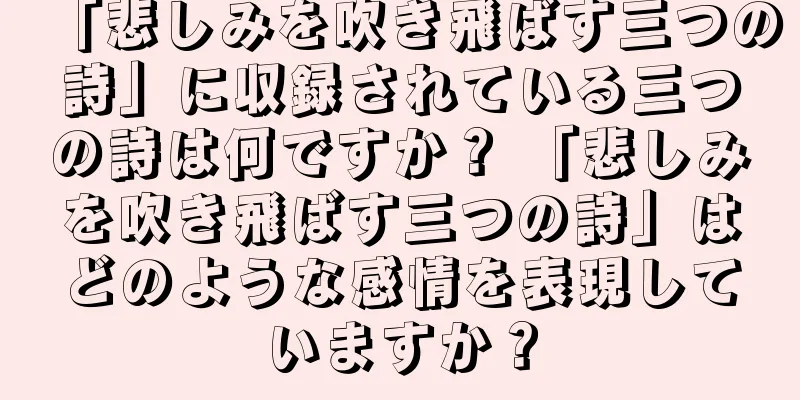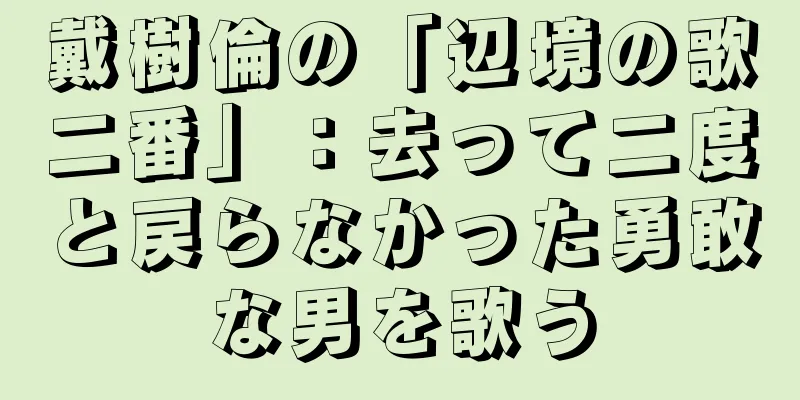清朝皇帝の中国語能力はどの程度でしたか?満州語より良いですか?

|
満州語は結構ですが、皇帝の中国語レベルはどうでしょうか? 唐代の詩よりも多くの詩を書いた乾隆帝以前の皇帝は、中国語に精通していたのでしょうか? 一般的に、言語の習得度は 2 つの段階に分けられます。1 つは流暢な口頭コミュニケーション、もう 1 つは現代の知識人の平均レベルに達する言語能力です。清朝初期のヌルハチと黄太極は、まだ基礎的な言語能力を身につけていなかった。日本の学者平田正治は、藤本幸雄の『清朝紅楼寺の正しい発音の研究』の研究を引用し、ヌルハチは中国語を話せる朝鮮人捕虜と会話する際には中国語の翻訳に全面的に頼っていたと指摘している。 太宗皇帝黄太極の治世中、満州人は漢人の役人を雇い始めました。しかし、漢人の大臣が太宗皇帝と日常的に連絡を取る際、中国語で表現すると、太宗皇帝にとって理解するのは非常に困難でした。寧婉瑜の「明朝の行法を改め、六通詞を立てよという請願書」は、次のように明確に述べている。「私はまた、六省の中国官吏は黄金語を知らないと言うだろうと思う… ハーンは常に二人の優秀な通訳をそばに置いておくべきである。そうすれば、中国官吏がハーンに会いに来たときに、質問して才能を試すことができる。そうでなければ、彼らは木と石のようであり、どうして彼が善人か悪人かを知ることができようか…」 これは、当時の黄太極の中国語能力が極めて限られており、「金華」(つまり満州語)を理解しない漢人の役人と意思疎通を図るために通訳(通詞)に頼る必要があったことを示しています。 清朝の順治帝の治世になって初めて、皇帝は徐々に漢の習慣に慣れ、漢の大臣たちと基本的に円滑な口頭によるコミュニケーションを実現できるようになりました。順治は中国語を使えるだけでなく、中国語自体にもある程度の理解力を持っていました。『洪覚印禅師北遊集』という本には、禅師と順治の会話が載っています。「ある日、禅師は韻書を師に見せてこう言いました。『作詞家や作曲家が使う韻は、沈月詩の韻とは全く違います。』…師はこう言いました。『北京語には入韻がないだけです。入韻語に出会ったら、必ず平調、上昇調、下降調に翻訳しなければなりません。』…」 順治帝は詩の韻と音楽の韻の違いがわかるだけでなく、当時の北京語の入韻が消え去っていることも知っていたことがわかります。彼の中国語能力は、もはやヌルハチや黄太極のそれに匹敵するものではありませんでした。 実際、順治帝は優れた語学力を持っていました。当時、多くの大臣は母国語しか理解できませんでした。順治帝が大臣を召集する際は、状況に応じて行動する必要がありました。満州人の大臣には満州語、漢人の大臣には中国語、モンゴル人の大臣にはモンゴル語で話しました。 残念ながら、順治の漢文の読解力はまだ十分ではなかった。『順治実録』には「皇帝は広く読書し、内廷の大臣は翻訳しなかった」と記録されている。彼は翻訳についていけないほど読書が好きだった。満州語の助けがなければ皇帝はスムーズに読むことができなかったことが分かる。翻訳業務を担当する「七心朗(むじれんばはぶく)」という肩書は長く存続した。 康熙帝の時代になると、王室教育モデルは徐々に成熟し、すでに移民二世であった康熙帝は中国語能力が急速に向上し始めました。 『宮廷訓練の格言』には、康熙帝が「8歳で即位し、勉学に励むことを心得ていた。当時、張宦官と林宦官という二人の宦官がいて、私に読書と暗唱を求めた。二人とも明代に非常に博識な人物だった。彼らの教えは古典のみに集中し、詩や散文は後回しにされた」と記されている。彼は確かに父や祖父と同じではない。 康熙帝の治世初期の満州族の大臣のほとんどは、公務と日常生活の両方で満州語を主要言語として使用していました。たとえば、上に示した康熙帝時代の肖像画では、左側に満州語の文字だけが書かれています。 皇帝と旗人の中国語能力が向上するにつれて。職業翻訳者の七心郎も歴史的使命を終えた。順治15年に各省庁の七心郎が廃止され、康熙12年には宗仁府の七心郎が廃止された。康熙以降、清朝の皇帝の中国語能力はいずれもかなり優れていた。 |
<<: 後漢末期の名将、夏侯淵が戦死した場所はどこでしょうか?夏侯淵の墓はどこにありますか?
推薦する
古代では姓は高貴な姓と卑しい姓に分かれていました。答えるときに「ミアンギ」と呼べない姓はどれですか?
中国人は初めて会うとき、たいてい「あなたの苗字は何ですか?」と尋ねたがります。古代では、苗字は確かに...
『合皇老兵』をどう理解すべきか?創作の背景は何ですか?
合皇の老兵張喬(唐代)私は若い頃、将軍に従って合皇を征服し、年老いて故郷に戻りました。 10万人の漢...
『紅楼夢』では、リン・デイユは賈一家を永遠に繁栄させることができるのでしょうか?それはどういう意味ですか?
林黛玉は中国の古典小説『紅楼夢』のヒロインです。以下の記事はInteresting Historyの...
「紅楼夢」では、薛宝才が大観園から出て行きたいと偽善的に言っていました。皆さんはどう反応しましたか?
『紅楼夢』では、薛宝才は大観園から出て行きたいと偽善的に言ったが、いつ戻ってくるかについては言及しな...
『隋唐代記』第 57 章: キングコングの敗北と北突厥への逃亡
『隋唐代志』は、元代末期から明代初期にかけて羅貫中が書いた章立ての小説である。 『隋唐書紀』は瓦岡寨...
ピ・リシウの「樫の母の嘆き」:この詩は思想的にも芸術的にも非常に特徴的です。
皮日秀(838年頃 - 883年頃)、号は希美、号は易紹、かつて襄陽の鹿門山に住み、鹿門子とも呼ばれ...
なぜライチは長い歴史の中で悪い評判を持たれてきたのでしょうか?
唐代の有名な詩人、杜牧はかつて「華清宮を過ぎゆく四行詩」という詩を書いた。「振り返って長安を見ると、...
鮑嗣の生涯についてはどのような神話や伝説がありますか?
鮑嗣は西周時代の鮑の出身で、周の有王の二番目の王妃であり、深く愛されていました。歴史記録によると、包...
賈宝玉はいつ宝斎のために詩を書いたのですか?テーマは何ですか
賈宝宇と聞くといつもテレビに出ていたあの人を思い出すので、彼について詳しく話さなければなりません。賈...
李清禄とは誰ですか?斉宇峰の姪の李清禄のプロフィール
孟姑は金庸の武侠小説『半神半魔』の登場人物。西夏の王女で、李秋水の孫娘、徐竹子の配偶者である。彼女は...
楊万里の「霊鷲寺に泊まる」:この詩は芸術的にも非常に特徴的である
楊万里(1127年10月29日 - 1206年6月15日)は、字を廷秀、号を程斎、程斎野客と号した。...
『紅楼夢』で最も陰謀を企む人物は誰ですか?それはザイレンですか?
本日、Interesting Historyの編集者が、紅楼夢の小紅についての記事を皆様にご用意しま...
『紅楼夢』の男性陣はなぜ皆側室と結婚できるのでしょうか?
『紅楼夢』、特に『大観園』には女性がたくさん登場し、基本的に女性の国です。これらの女性は、主人、すな...
明らかに:古代の舜帝はなぜ家族から繰り返し迫害を受けたのか?
はじめに:堯と舜は古代の五帝であり、実は部族連合のリーダーでした。当時は退位制度が実施され、リーダー...
宋代の四行詩の鑑賞:呉涛は詩の中でどのような場面を描写したのでしょうか?
宋代の呉涛の四行詩、次の興味深い歴史編集者があなたに詳細な紹介をもたらします、見てみましょう!旅人は...