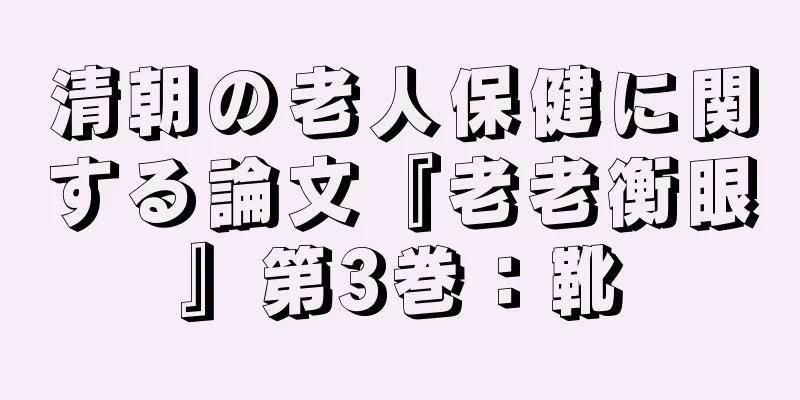前漢時代の儒学者、光衡に関する物語は何ですか?

|
匡衡は、字を智桂といい、後漢末期の人物である。生没年は不明である。前漢の儒学者で、宰相を務めた。「壁に穴をあけて光を盗む」ほどの勉学に励んだことで有名である。祖先の故郷は東海県城邑(現在の山東省臨沂市蘭陵県鹿城鎮匡望村)である。「幼少期に鄒邑陽霞村(現在の鄒城市)に移り、勉学に励んだ」(朱成明編『鄒県志』による)。 「父は農民でした。光衡は勉強が好きでしたが、家族は貧しく、生計を立てるために働きました。」 「光衡は勉強に熱心でしたが、ろうそくがありませんでした。隣人はろうそくを持っていましたが、彼のものほど明るくありませんでした。そこで光衡は壁に穴を開けて光を取り入れ、その光を反射する本を使って読書をしました」(西都雑記)。これは、光衡が光を盗むために壁に穴を開けたという物語で、2000年にわたって広く伝えられてきました。若い頃、光衡は生計を立てるために働き、その賃金で本やペン、その他の学習用品を買っただけでなく、歴史的記録によれば、彼はしばしば書籍収集家のために報酬を求めず、代わりに本を貸すだけの仕事もしていたことが分かっています。光衡が儒教の古典の達人になれたのは、彼の熱心な勉強のおかげでした。 元帝の治世後期、宦官の石仙は中書の大臣を務めていた。彼は私利私欲のために徒党を組んで政府を掌握し、元帝に増税と民衆の搾取を唆した。しかし、彼は皇帝の寵愛を受けていたため、誰も彼を怒らせようとはしなかった。成帝が即位した後、光衡は石仙を弾劾する書状を提出し、石仙の過去の罪を列挙し、その追随者を非難した。これは、光衡が反逆的な役人を排除し、漢朝への忠誠を示すために行った最後の行為であった。やがて、光衡は同僚たちと不和になり、弾劾され平民に降格された。故郷に戻ったが、数年後に故郷で病死した。 光衡に関する逸話や物語は何ですか? クアン・ヘンは優秀な生徒であり、非常に勤勉です。西漢の時代に、光衡という名の農民の子供がいました。彼は子供の頃とても勉強したかったのですが、家族が貧しかったので学校に行くお金がありませんでした。その後、彼は親戚から読み方を教わり、読む能力を身につけました。 クアン・ヘンさんは本を買う余裕がなかったので、本を借りて読まなければなりませんでした。当時、本は非常に貴重なものであり、本を持っている人はそれを他人に貸すことを躊躇していました。農繁期には、クアン・ヘンさんは裕福な家庭でパートタイム労働者として働いていた。賃金は一切求めず、読むための本を貸してほしいと人々に頼むだけだった。 数年後、クアン・ヘンは成長し、家族の主な労働力となった。彼は一日中畑で働き、昼休みにしか読書する時間がなかったので、一冊の本を読み終えるのに10日か半月かかることもよくありました。クアン・ヘンはとても不安になり、心の中で思いました。「農作物を植えているので、昼間は読書する時間がない。夜にもっと時間をかけて読書できる。」しかし、クアン・ヘンの家族は非常に貧しく、照明用の石油を買う余裕がありませんでした。彼はどうしたらよいのでしょうか? ある夜、クアン・ヘンはベッドに横たわり、その日読んだ本を暗唱していました。それを背負っていると、突然、東の壁から一筋の光が差し込んでくるのが見えました。彼は立ち上がって壁まで歩いて行って見ました。ああ! 差し込む光は隣家からの光です。そこで、クアン・ヘンはある方法を思いつきました。小さなナイフを使って、壁の割れ目を少し大きく掘りました。こうすることで、差し込む光がより明るくなり、彼は光の中で本を読むために身を乗り出した。 光衡は一生懸命勉強し、質素な暮らしをし、後に非常に学識のある人物になりました。この話は「壁に穴を開けて光を盗む」または「壁に穴を開けて光を借りる」としても知られています。 |
<<: 前漢時代の儒学者・光衡とはどのような人物だったのでしょうか?歴史は光衡をどのように評価しているのでしょうか?
>>: 前漢時代の儒学者、光衡の物語の分析と光衡の墓はどこにあるか?
推薦する
三国志演義では「馬祖敗街亭」のあらすじはどのように描かれているのでしょうか?
三国志演義では、諸葛亮は賢明で勝利を収めた英雄ですが、神ではないため挫折も経験します。「街亭の敗北」...
馮青阳は霊湖崇の師匠ですか?馮青阳の個人プロフィール
馮青阳は金庸の武侠小説『微笑矜持放浪者』の登場人物である。彼はもともと華山剣派に属しており、金庸の小...
古典文学の傑作「劉公安」第95話:熊さんは美しい少女に恋をする
『劉公庵』は清代末期の劉雍の原型に基づく民間説話作品で、全106章から成っている。原作者は不明ですが...
巡回警部補の地位は9級に過ぎないのに、郡内での彼の地位がなぜそれほど特別なのでしょうか?
明清時代の官制によれば、官吏は一級から九級までの九等級十八階に分けられ、各階は主階と従階に分かれてい...
七剣士と十三英雄の第33章:徐明高が五虎将軍を殺し、飛龍嶺が五雷峰を爆破する
『七剣士十三勇士』は、『七子十三命』とも呼ばれ、清代の作家唐雲州が書いた侠道小説である。清代末期の侠...
唐王朝の歴史はどれくらい長かったのでしょうか?唐王朝はどのようにして成立したのでしょうか?
唐王朝は何年間続いたかご存知ですか? 知らなくても大丈夫です。Interesting History...
アチャン族は水かけ祭りをどのように祝うのでしょうか?
地元のダイ族と同様に、アチャン族も水かけ祭りを祝います。水かけ祭りは若者にとって配偶者を見つける良い...
『紅楼夢』における青文の最後の悲劇は王夫人によって引き起こされたのでしょうか?
賈宝玉の周りの四人の侍女の一人である青文は、美しいだけでなく、賢くて器用です。清文は、その個性的な魅...
関羽に関しては、孫権が結婚を申し込んだにもかかわらず拒否されたのはなぜでしょうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
韓愈が書いた「湖南の里李政子を送る」は、シンプルでありながら奥深く、率直でありながらも不思議な詩である。
韓愈は、字を徒子といい、自らを「昌里の人」と称し、通称は「韓昌里」または「昌里氏」であった。唐代の著...
『紅楼夢』の春仙はなぜ夜遅くにハンカチを洗って干したのでしょうか?それはどういう意味ですか?
第33章では、夏休みの昼休みの後、賈正の書斎で宝玉が殴打された。皆さんも聞いたことがあると思います。...
本草綱目第7巻青銅石碑文蛇黄の原文の内容は何ですか?
『本草綱目』は、明代の優れた医学者、李時珍によって著された全52巻からなる中国医学の古典書です。次の...
『紅楼夢』の薛宝才の誕生日パーティーはどのように企画されましたか?
宝仔は『紅楼夢』のヒロインの一人です。林黛玉とともに金陵十二美女の第一位に数えられています。『おもし...
「水龍陰:ツバメは忙しく、コウライウグイスは怠惰で香りは薄れつつある」をどう理解すればよいでしょうか?創作の背景は何ですか?
水龍音:ツバメは忙しく、コウライウグイスは怠け者だが、香りは薄れつつある張愈(宋代)ツバメは忙しく、...
李白の有名な詩の一節を鑑賞する:私は15歳を超えた自分を哀れに思う、私の顔色は桃やプラムのように赤い
李白(701年 - 762年12月)は、太白、清廉居士、流罪仙とも呼ばれ、唐代の偉大な浪漫詩人です。...