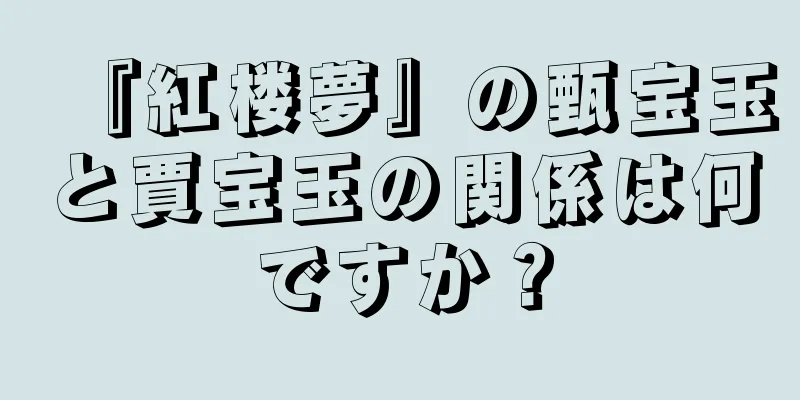「譲位受諾記念碑」は曹丕が漢王朝を簒奪したことを記念するものですか?

|
禅テーブル この石碑は「寿禅石」としても知られています。三国時代、黄初元年(220年)に創建された。長さ270cm、幅140cm、22行、1行あたり49文字。 東漢献帝の延康元年(220年)10月10日、彼は魏王曹丕に譲位し、曹丕はすぐに即位して皇帝を称し、年号を大魏黄楚と改めた。 10月27日、漢王朝の「退位」を受け入れたことを記念してこの石碑が彫られました。許昌南部の曹魏古城(現在の古城村)にある漢献帝廟には、「譲位受諾標」と有名な「皇帝位授与碑」が並んで立っているが、この廟は長い間放置されていた。 『譲位碑』と『賜皇帝碑』はどちらも魏初期の傑作であり、重要な歴史的価値を持っているだけでなく、その書法も長い間世界から高く評価されており、そのため唐や宋の時代から繰り返し記録されてきました。構造は正統で厳格、筆致は力強く果断、精神は雄大で奔放、また『西平石経』『張騫』『李斉』など後漢末期の名碑の風格も保持しており、洞察力があり、奥深く、優雅である。明代の郭宗昌の『青銅石銘史』には、「書体は『奨励進』と同じで、漢人のものとは少し違うが、優雅で優美で、衣服や靴の装飾も風格があり、しかも直立している」と評されている。趙剛も、この石碑は「主に『奨励進』と同じ官書体に基づいている」と述べた。王時珍は言った。「……。」 もともと明皇帝の「泰山銘」が好きだったのですが、これを見て急に迷ってしまったのです。漢風は四角くて細く、力強くてすっきりしており、感情は少なく骨格が多い。一方、唐風は広くて太く、愛嬌がありゆったりしており、骨格は少ないが姿勢が多い。漢の建安や晋の三謝などの時代は時代によって抑圧され、超えることができませんでした。この発言は物語りの三昧を達成しました。 (下傳傳傳)漢字の進化から見ると、漢末から魏初にかけては官字から楷書への過渡期であった。魏初期の彫刻は、漢末期の『西平石経』『先于皇』『張騫』などの碑文の遺産を受け継ぎ、筆遣いにおいて新たな突破口を開いた。具体的には、筆画を逆に減らし、一刀両断にし、一息入れた後に素早く筆画を持ち上げて四角い波を形成し、これはすでに初期段階の楷書の特殊な筆遣いであり、先人たちはこれについて多くの議論を重ねてきた。 例えば、清代の孫光は「首禅表」と「上尊好碑」について次のように評している。「この二つの碑はみな同じものだ。ひどく磨耗し、傷んでいるが、字はまだ半分は判読できる。まさに決定的な筆致だ。……危険な折れ字を直す方法は、主にここから生まれた」。楊守敬の『書を学ぶ小論』でも、「孔仙」「梵字」「上尊好」「首禅表」は「刀の先のように書かれ、字は鋭く、六朝の楷書の祖である」と述べている。少し遅れて登場した魏の「王記碑」と呉の「鼓浪碑」は、この「折れ刀」の書体をさらに発展させ、字形は後代の楷書に近くなっている。 |
<<: 羅貫中の『三国志演義』には架空の要素が含まれていますか?
>>: 歴史とフィクションの違い:三国志演義のフィクション99選
推薦する
古典文学の傑作『太平天国』:仏教篇第1巻全文
『太平百科事典』は宋代の有名な百科事典で、北宋の李芳、李牧、徐玄などの学者が皇帝の命を受けて編纂した...
「朗涛沙4号」が誕生した背景は何ですか?どのように鑑賞すればよいでしょうか?
朗涛沙第4号劉玉熙(唐代)パロット島の砂浜には波が打ち寄せ、売春宿から外を眺めると太陽が沈んでいく。...
前漢時代の有名な官僚である公孫洪の貢献は何ですか?
公孫洪(紀元前200年 - 紀元前121年)は、本名は洪、字は季、別名は慈青(『西京雑録』に記録)で...
三国志演義:三国志の領土はどのように分割されたか
1. 曹魏 曹魏の領土は曹操の時代に大幅に拡大し、曹丕が皇帝を称して建国した後に確定し、華北地域のほ...
宋代の詩「相会」金陵城西塔鑑賞では作者はどのような表現形式を用いているのでしょうか?
宋代の朱敦如による『歓喜の出会い:金陵城西楼』。以下、Interesting Historyの編集者...
明朝抗日戦争で最初の名将となった李如松:3,000人の兵士は3万人より優れている
明朝抗日戦争で最初の名将となった李如松:3,000人の兵士は3万人より優れている明の万暦年間に、特に...
周波は後世でどのような地位にあるのでしょうか?周波の墓はどこにありますか?
周渤(紀元前169年?-)は、秦末期から漢初期にかけての軍事戦略家、政治家であり、前漢の創始者の...
王維はなぜ『新清天荒野』を書いたのか?詩人は自然、田舎、そして人生を愛しているから
王維(701-761)、字は墨傑、字は墨傑居士。彼は河東省蒲州市(現在の山西省永済市)に生まれ、祖先...
晋の懐帝、司馬懿の略歴 司馬懿はどのようにして亡くなったのでしょうか?
司馬遷(284年 - 313年3月14日)は、雅号は馮都、晋の武帝司馬炎の25番目の息子であり、晋の...
『塔から王清への手紙』が制作された背景は何ですか?どのように鑑賞すればよいでしょうか?
王清に手紙を送るために塔に登る魏英武(唐代)楼閣に登ることと林に登ることの憎悪は異なるが、楚雲と広大...
「北に送る夜の雨」の原文は何ですか?どのように鑑賞すればよいでしょうか?
夜の雨が北へ李尚閔(唐代)いつ戻ってくるのかと聞かれるが、日付はない。バシャンの夜の雨が秋の池を潤す...
孟浩然の別れの詩「江南の杜世思に別れを告げる」への感謝
「夕暮れ時に帆船を停泊できる場所はどこでしょう?水平線を見ると心が痛みます。」この詩を読んだことがあ...
『破陣詩 柳の下の庭で歌い奏でる』の創作背景は何ですか?どのように鑑賞すればよいでしょうか?
ポジェンツィ:柳の下の歌と踊りの庭顔継道(宋代)中庭の柳の木の下では音楽と歌が流れ、姉妹たちは花の間...
左冷然の個人プロフィール 左冷々はどの小説の登場人物ですか?
左冷然は金庸の小説『微笑矜持放浪者』の登場人物。彼は宋山流の宗主であり、五山剣派の指導者である。彼ら...
二科派安静記第39巻:泥棒は梅の花で自分の気持ちを表現し、義賊は立体的な遊びに慣れている
『二科派経記』は、明代末期に凌孟初が編纂した俗語小説集である。 1632年(崇禎5年)に書籍として出...