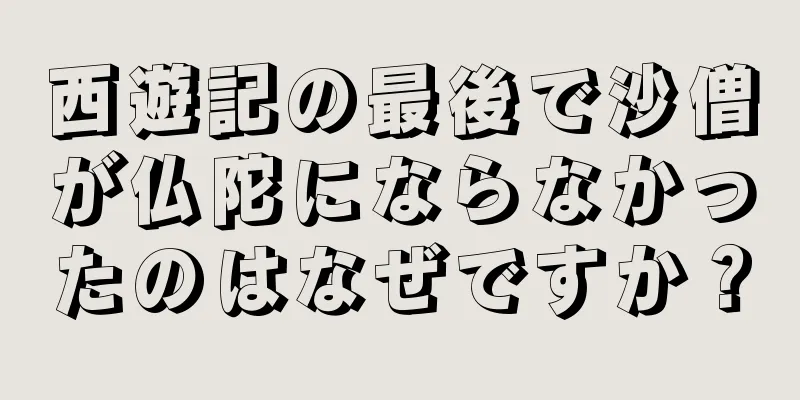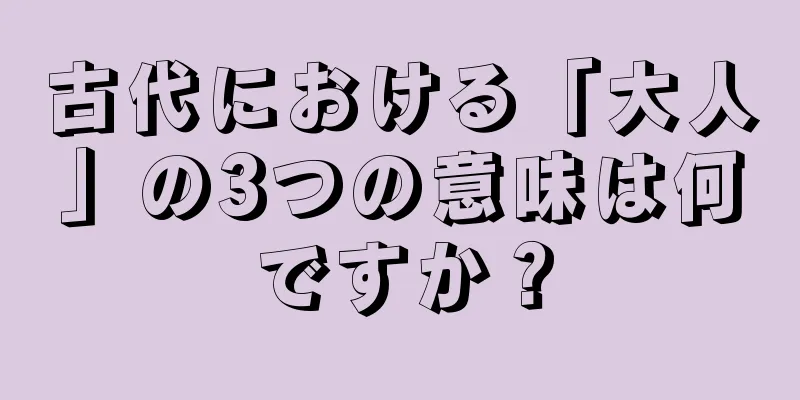天皇が「至高の統治者」と呼ばれる理由の謎を探る

|
中国最後の二つの封建王朝の宮殿である北京の紫禁城は、皇帝の至高性をあらゆる場所で体現しています。 「天下一統」という言葉は多くの人に知られていますが、故宮の建築はまさに「9」と「5」という数字に関係しています。例えば、世界的に有名な天安門塔の基壇には5つの出入り口があり、幅は9、奥行きは5です。故宮の多くの建物は 9 間または 5 間の構造になっていますが、太和殿は 11 間の構造になっており、これは故宮全体でも珍しいものです。それはなぜでしょうか。和殿の幅がなぜ 11 間なのかを分析する前に、古代中国の数字の概念、特に「9」と「5」という数字について簡単に説明する必要があります。 「9」と「5」という数字は、建築を含む封建宮廷生活のあらゆる側面と密接に結びついており、封建時代の皇帝だけが享受できる最高の象徴的意味を持っています。その理由は何でしょうか? 簡単に言うと、古代中国では数字は陽数と陰数に分けられ、奇数は陽、偶数は陰でした。陽数の中で九が最も高く、五が真ん中にあることから、「九」と「五」は皇帝の権威を象徴し、「九五の覇王」と呼ばれています。 秦の始皇帝 別の説では、「九武」という言葉は『易経』に由来していると言われています。現在まで伝わる易経は、周の文王が著したとされ、周易とも呼ばれています。 『易経』の六十四卦のうち最初の卦は天を象徴する「乾」であり、皇帝を表す卦となった。乾坤六十四卦は6本の陽線で構成され、極度の陽と繁栄を表します。下から数えて5番目の線を九五といいます。9は、この線が陽線であることを表し、5は5番目の線を意味します。九五は乾坤六十四卦の一番良い卦で、六十四卦の一番目です。そのため、九五は六十四卦の384卦の一番目であり、皇帝の象徴となっています。 ここでの「9」は特定の数字ではなく、数字の陰陽の性質を区別するための記号です。その後、人々は「九」と「五」を特定の数字として使うようになりました。これは皇帝を表す「九五」の卦に合わせるためだったと思います。また、建築における「九」と「五」の数字の使用は、美的原理とも非常に一致しています。 『易経』の説明文には、「千道の変化は、それぞれの本質と運命を正し、調和と平和を維持することであり、有益で堅実である」という一節がある。大和殿の名前の由来はこれに由来すると言われています。 『易経』は中国最古の経典の一つであり、六経の第一として常に尊ばれており、中華民族のあらゆる分野に深い影響を与えています。そのため、「九五」という用語が『易経』に由来するという説の方が信憑性が高いと言えます。 「九」と「五」は封建皇帝の象徴なのに、なぜ和殿の幅は11間なのでしょうか?関連情報によると、和殿は明代には奉天殿と呼ばれ、幅は9間、奥行きは5間でしたが、李自成が北京に入った後に破壊されました。清代の康熙8年(1669年)に再建されたときに11間に変更されました。なぜ11間としたのか?それは、当時は長さの十分な良質な黄金南樵が手に入らなかったためだと言われています。9間にすると木材のスパンが足りなくなるため、スパンを短くするために11間に変更しなければなりませんでした。 この発言が真実かどうかは別として、紫禁城の最初の建物である太和殿は、独特な11の区画の形式を採用しており、建築群の中でも際立っており、その最高かつ高貴な地位を際立たせています。 9 区画の形式は紫禁城で何度も使用されています。9 に数字を加えても 11 にしかなりません。建物の中央にあるドアの特性を維持するために、ベイの数は奇数でなければなりません。美観の観点からは、11 のベイはまだ許容範囲です。長い廊下でない限り、13 以上のベイは建物としては多すぎます。 紫禁城 故宮の建築には多くのデジタル現象があり、それらはしばしば異なる解釈をされます。しかし、私たちが今、その本来の意味を本当に理解しているかどうかに関係なく、その創造者、つまり私たちの祖先が気まぐれや衝動で行動したわけではないと信じる理由があります。そして、すべてに統一された目的、つまりエチケット、秩序、美しさの完璧な組み合わせがあります。 簡単に言うと、古代中国では数字は陽数と陰数に分けられ、奇数は陽、偶数は陰でした。陽数の中で九が最も高く、五が真ん中にあることから、「九」と「五」は皇帝の権威を象徴し、「九五の覇王」と呼ばれています。 別の説では、「九武」という言葉は『易経』に由来していると言われています。現在まで伝わる易経は、周の文王が著したとされ、周易とも呼ばれています。 『易経』の六十四卦のうち最初の卦は天を象徴する「乾」であり、皇帝を表す卦となった。乾坤六十四卦は6本の陽線で構成され、極度の陽と繁栄を表します。下から数えて5番目の線を九五といいます。9は、この線が陽線であることを表し、5は5番目の線を意味します。九五は乾坤六十四卦の一番良い卦で、六十四卦の一番目です。そのため、九五は六十四卦の384卦の一番目であり、皇帝の象徴となっています。 ここでの「9」は特定の数字ではなく、数字の陰陽の性質を区別するための記号です。その後、人々は「九」と「五」を特定の数字として使うようになりました。これは皇帝を表す「九五」の卦に合わせるためだったと思います。また、建築における「九」と「五」の数字の使用は、美的原理とも非常に一致しています。 『易経』の説明文には、「易の道の変化は、それぞれの本質と運命を正し、調和と平和を維持することであり、有益で堅実である」という一節がある。大和殿の名前の由来はこれに由来すると言われています。 天皇 『易経』は中国最古の経典の一つであり、六経の第一として常に尊ばれており、中華民族のあらゆる分野に深い影響を与えています。そのため、「九五」という用語が『易経』に由来するという説の方が信憑性が高いと言えます。 |
<<: 都市部の人々の90%は田舎の子供たちの宝物を理解していない
>>: 千年の歴史を持つ海渾古代都市消失の謎:南昌で六朝の古墳が発掘される
推薦する
中国古典文学の原典の鑑賞:易経・第五十五卦・風水卦
風水六十四卦は豊かさと大きさを象徴します。離は稲妻と火を表し、震は雷を表します。雷と稲妻が同時に現れ...
『新唐語』第5巻の公志の原文は何ですか?
唐方清は武徳時代の茶妃の官吏であり、太宗皇帝は彼を高く評価し、劉月のもとで働くよう招いた。方青は「母...
なぜ死後の称号は古代の牧師たちの究極の追求と考えられたのでしょうか?
なぜ諡号は古代の大臣にとって究極の追求だったのでしょうか。それは、古代から古代の大臣が諡号を非常に重...
「大明宮の賈思仁の早朝の謁見に応えて書いた詩」をどのように理解すればよいでしょうか?創作の背景は何ですか?
朝、大明宮で賈世仁と詩を書いた王維(唐代)真紅の帽子をかぶった雄鶏が夜明けを告げ、尚儀は緑の雲毛皮の...
軍事著作『百戦百策』第5巻 安戦全文と翻訳注
『百戦奇略』(原題『百戦奇法』)は、主に戦闘の原理と方法について論じた古代の軍事理論書であり、宋代以...
鳩を捧げて放つという中国の寓話。この寓話はどのような教訓を明らかにしているのでしょうか。
こんにちは、またお会いしました。今日は、Interesting History の編集者が、鳩を捧げ...
『紅楼夢』で黛玉はどんな秘密を抱えているのでしょうか?
『紅楼夢』のヒロインである黛玉は、金陵十二美人本編の最初の二人の登場人物の一人です。今日は『おもしろ...
太平広記·巻41·仙人·劉武明をどのように翻訳しますか?原文の内容は何ですか?
『太平広記』は、漢文で書かれた中国古代の記録小説集で、全500巻、目録10巻から成り、漢代から宋代初...
賈志『春思(上)』の創作背景とは?
まだ分からないこと:賈詡の「春思(上)」が創作された背景は何だったのでしょうか?この詩はおそらく...
『紅楼夢』で賈元春が死んだ本当の原因は何だったのでしょうか?それはトネリコと何の関係があるのでしょうか?
賈元春は『紅楼夢』の登場人物。金陵十二美女の一人であり、賈家の四美女の長女である。本日は、Inter...
曹爽がすでに天下の権力を掌握していたのは明らかだったが、なぜ司馬懿に負けたのだろうか?
後漢末期、魏王曹操の息子曹丕は漢の献帝に退位を強制し、曹魏政権を樹立して漢王朝の終焉を公式に宣言した...
李婉はなぜ賈邸に入ったのか?彼女の夫は誰ですか?
タイトル: 紅楼夢の李婉は誰の嫁?歴史的背景の解釈段落1: はじめに『紅楼夢』では、李婉は注目を集め...
イェルヤンのプロフィール イェルヤンは小説の登場人物である
耶律燕は金庸の武侠小説『射雁英雄の帰還』の登場人物である。彼女はモンゴルの役人イェル・チュツァイの娘...
唐詩閣の夜をどのように鑑賞するか?杜甫はこの詩をどのような意図で書いたのか?
唐代の葛野、杜甫については、次の興味深い歴史編集者が詳しく紹介しますので、見てみましょう!年の瀬には...
伏羲秦とはどんな人ですか?伏羲はなぜ八卦を発明したのでしょうか?機能は何ですか?
秦の伏羲に非常に興味がある人のために、Interesting Historyの編集者が詳細な記事を参...