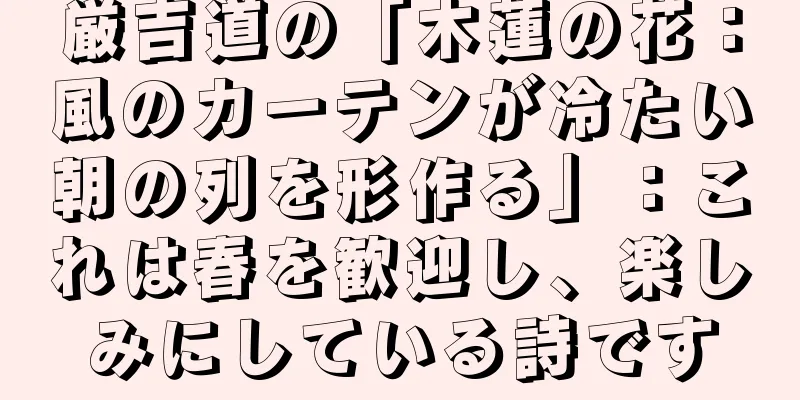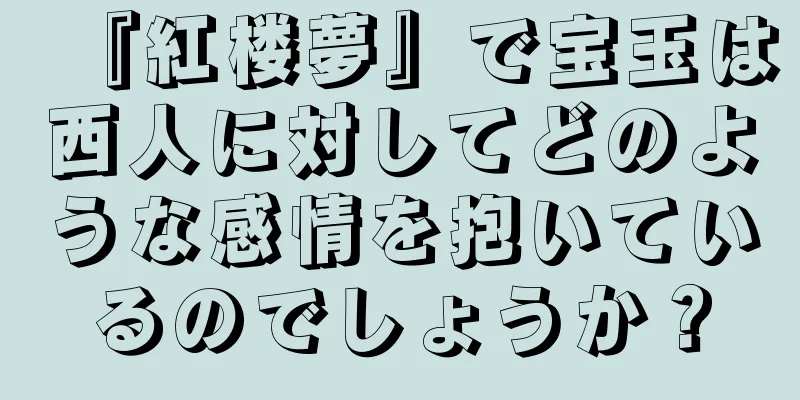なぜ宋代には「楊家の将軍」や「胡家の将軍」という用語があったのに、「越家の将軍」という用語がなかったのでしょうか?

|
なぜ宋代には「楊家将軍」や「胡家将軍」という用語があったのに、「越家将軍」という用語がなかったのでしょうか。次の「興味深い歴史」編集者が詳しい答えを教えてくれます。 歴史ロマンス小説に詳しい、あるいは好きな人にとって、『楊家の将軍』、『胡家の将軍』、『薛家の将軍』などの本は、昔から人々の間で大人気です。本の主人公は、いずれも歴史上、勇猛果敢で名声のある一流の将軍です。しかし、『岳家の将軍』のように、楊柳浪、胡延卿、薛仁貴よりわずかに優れた偉大な英雄、岳飛の物語はありません。その代わりに、人々は岳家の軍隊のほうがよく知っています。この一字一句の違いは単なる癖なのでしょうか?宋代の胡氏と楊氏は同じ一族の末裔であり、唐代の薛仁貴は薛奎の子孫に家系を伝えたので、岳飛の一族よりも繁栄しているのではないかという人もいるかもしれません。 しかし、岳飛の物語では、岳飛から岳雲、岳雷、そして岳雲の息子である岳福に至るまで、これはまた、先祖と孫の世代の終わりのない循環でもあります。もちろん、これを言う前提は、それが歴史小説に限られ、正史ではないということです。正史だけを言えば、岳飛と岳雲の父子は、楊業と楊延郎よりも、「一族の将軍」の称号にふさわしいですし、薛立家や胡延瓊家もそうです。 「岳族将軍」という用語が正史や小説ではあまり見られないことがわかります。なぜこのようなことが起こるのでしょうか? 実は、厳密に言えば、「岳家の将軍」は「岳家の将軍」よりも荘厳な用語であり、言い換えれば、「岳家の軍隊」にはもともと「岳家の将軍」が含まれており、「楊家の将軍」や「薛家の将軍」は才能のある将軍の家系であるだけで、個人名を持つ軍隊を持つことは困難です。つまり、「楊家の将軍」は存在するかもしれませんが、「楊家の軍隊」は絶対に存在しません。理由は簡単だ。趙匡胤が乾杯して軍事権を放棄した時から、北宋朝の朝廷は将軍の権力掌握を阻止することに注力してきた。宋太祖が苦労して確立した「将軍が自らの軍隊を独占できない」状況は、数十万の近衛兵が宋皇帝の手中だけに集中する結果となった。宋代の最高位の官僚集団もこの制度を高く評価していた。彼らは何といっても「天下は150年平和である」という善の原則を信じていた。そのため、軍事的に優れた功績を挙げた狄青でさえ、欧陽秀らの「強い助言」により、功績に見合った高い地位を得ることができず、心の中に憎しみを抱えたまま死んでいった。したがって、その環境では「楊家軍」が存在することは不可能であろう。 南宋の時代になって金との戦争が激化するにつれて、この状況は徐々に変化しました。康昭狗王が「泥馬に乗って川を渡る」ことを余儀なくされ、南宋で平和に暮らすようになった後、当時の朝廷では正規軍を組織して金の騎兵と戦うことは不可能でした。そのため、女真族に抵抗する重荷は将軍たちに託され、将軍たちは状況を利用して勢力を拡大し、盗賊や難民を吸収し、徐々に大きな規模を築き上げていった。南宋の諸制度が一定の規模に達し、対金戦線の重要な軍事拠点に駐留する主力部隊に統一した人数を与えるだけの力と条件が整ったのは、宋の高宗皇帝の治世の建延3年になってからであった。 この部隊の命名にも紆余曲折があり、当初は「五皇軍」、2年目には「五神武軍」と改名された。しばらくして、「神武」は北斉軍の名称であり、道義的にも不適切であることが発覚したため、「野営守備軍」に変更された。このような紛らわしく不確かな名前は、人々が公式の番号を使用して各部隊を指すことにさらに嫌悪感と不慣れ感を抱かせていることがわかります。したがって、張軍の軍隊は張家軍と呼ばれ、韓時忠の軍隊は漢家軍と呼ばれます。それで、「岳家軍」はどのようにして誕生したのでしょうか? この物語は岳飛が宗沢の軍に加わったときから始まります。宗沢は東京に残った老将軍として、「盗賊でも兵士にできる」という信念を常に持ち、多くの難民や盗賊を受け入れました。しかし、このような義兵集団は将軍の能力に大きく依存しなければなりません。宗沢の死後、軍は杜充に引き渡され、「兵士全員が盗賊」という困った状況になりました。岳飛が率いる部隊は、かつて強大だった東京駐屯軍の唯一の残存部隊となった。杜充が晋に降伏した後、軍は完全に敗北した。当時江淮玄武師団右軍の指揮官であった岳飛は、部隊の再編成を開始し、次々と散在していた兵士を組み入れた。そこから彼は自分の軍隊を編成し、岳家軍の伝説的な章を書き上げた。したがって、宋朝だからこそ、岳家軍は存在できるが、楊家軍と胡家軍は存在できない。したがって、楊家軍と胡家軍と比較すると、岳家軍が欠けているわけではないが、より強力な岳家軍の中では、岳家軍は少し手薄に思えることも理解できます。 |
<<: 古代の大臣はなぜ朝廷に出席するときに「胡」を握っていたのでしょうか?小さな木片の機能は何ですか?
>>: なぜ古代中国では、政治権力を指すのに古代から現代まで「王朝」という用語を使い続け、「国」という用語を使わなかったのでしょうか。
推薦する
曹雪芹の『紅楼夢』は「明珠の家族問題」についてですか?
『紅楼夢』第一章のシーン:「元宵節に各家庭が提灯を灯すと、小潔英蓮が姿を消す。」 『紅楼夢』では、こ...
『新説天下一篇・方正篇』第20話の原文は何ですか?どのように翻訳しますか?
有名な古代書物『新世界物語』は、主に後漢末期から魏晋までの有名な学者の言葉、行為、逸話を記録していま...
「孫権は関羽を殺してはならないと繰り返し強調した」という主張は妥当だろうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
劉邦と斉奎の息子である劉如意はどのようにして亡くなったのでしょうか?
劉邦が死ぬとすぐに、権力を握っていた呂太后は復讐の準備を整えた。特に、斉妃と趙の王太子如意とその母親...
「私は川辺の塔の上に一人で立って考え事をしている。月の光は水のようで、水は空のようだ」という有名な一節はどこから来たのでしょうか?
「ひとり河楼に登り、月明かりに思いを馳せる、水のよう、水は空のよう」という有名な詩句はどこから来たの...
もし張飛が夾孟関の戦いで趙雲に取って代わられたら、彼は馬超を倒すことができただろうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
孫悟空は地獄の王の生死の書で自分の名前を消したのに、なぜ結局死んだのでしょうか?
『西遊記』の地獄王生死記は有名です。李世民は、その本に書き加えた内容のおかげで、12年間長生きしまし...
ドルゴンの妻シャオユエ はじめに シャオユエはどうやって死んだのか?
多くの映画やテレビ作品では、ドルゴンの妻はシャオ・ユエです。このシャオ・ユエとは誰ですか?彼女は歴史...
水滸伝の梁山泊の英雄108人の中で、役に立たないのは誰ですか?
『水滸伝』に描かれたいわゆる涼山百八英雄は、昔から英雄的道徳の体現者として人々にみなされてきた。今日...
水滸伝の河龍李軍の結末は?渾江龍里の紹介
水滸伝の渾江龍李君の最後は?渾江龍の異名を持つ李君は、涼山の26番目の英雄です。彼はもともと蘆州(現...
曹爽が処刑されたとき、なぜ誰も助けに来なかったのですか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
『太平広記』第423巻の龍流の原文は何ですか?
陸俊昌、袁易、方平、長景虎頭蓋、法溪寺龍寺、龍使い孔維華、銀丘崔道樹ゴールデンドラゴンソン 黄洵林漢...
郭宇:金宇・献公が何月に郭を攻撃するかを布延に尋ねた(全文と翻訳注釈)
『国語』は中国最古の国書である。周王朝の王族と魯、斉、晋、鄭、楚、呉、越などの属国の歴史が記録されて...
宋代の詩「歓喜沙」- 莫莫清寒上小楼の鑑賞。作者はこの詩の中でどのような比喩を用いているのでしょうか。
環西沙・桃色清漢上小楼、宋代秦官、次の興味深い歴史編集者があなたに詳細な紹介を持ってきます、見てみま...
張九玲の『夫徳子君子初易』:この詩は新鮮で愛らしく、強い生命感に満ちている
張九齢(673-740)は、雅号は子首、通称は伯武で、韶州曲江(現在の広東省韶関市)の出身である。唐...