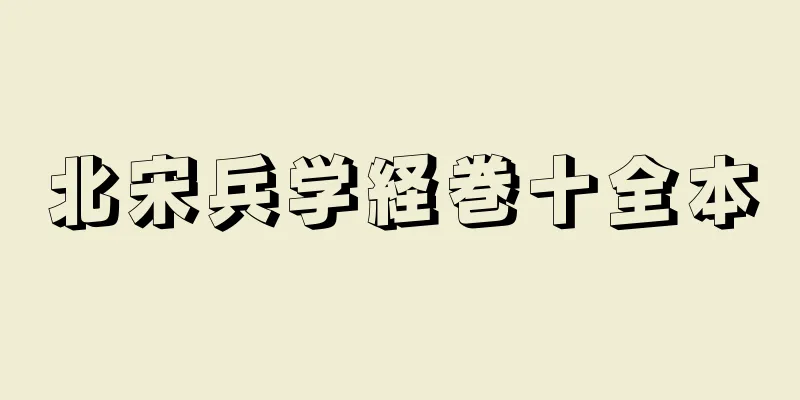曹操に対して賢く振舞おうとしていた楊修が、どうして曹操を怒らせて殺されてしまったのでしょうか?

|
曹魏の歴史に詳しい人なら誰でも、曹操が才能を非常に愛した君主であったことを知っています。しかし、曹操は殺人者でもありました。彼の手によって、敵軍の多くの人々が殺されただけでなく、彼自身の顧問たちも殺されました。その中でも最もよく知られているのは楊秀の死です。次は興味深い歴史エディターが詳しく紹介しますので、見てみましょう! 周知のように、楊秀は非常に才能があり、筆を執るとすぐに文章を書くことができました。曹操でさえ、楊秀ほど機転が利かないと公言していました。さらに、楊秀は家柄も良く、曹操よりもはるかに強かった。しかし、結局楊秀は曹操によって処刑されてしまいました。曹操が有能な人材を嫉妬していたからでしょうか、それとも別の隠された理由があったのでしょうか? 曹操が才能ある人々に嫉妬していたという主張は真実ではないと言うべきである。それは曹操が一流の才能を持っていたからです。曹操が台頭し、北方を平定した時代に、彼の知恵と洞察力は当時の頂点に達しました。劉備や孫権らも英雄だと思っていましたが、曹操に追いつくことはできませんでした。 曹操のグループを見てみると、最高の顧問は荀攸や程攸のような才能のある人たちで、彼らは皆曹操をとても尊敬していました。したがって、曹操の階級は当然楊秀よりもはるかに高い。したがって、曹操は楊秀に対して全く嫉妬しないであろう。それに、楊秀自身には嫉妬するようなことは何もなかった。彼の技術レベルは、ちょっとしたアクロバティックな巧妙さ程度で、上流階級に受け入れられるほどのものではありません。 よく知られている「一人一口の菓子」事件自体が曹操に対する侮辱であった。ただ曹操は心が広かったので、その件については追及しなかった。そうでなければ、楊秀はとっくの昔に斬首されており、漢中の戦いまで殺されるのを待つ必要もなかっただろう。 楊秀が庭園を造った時の巧妙さについて語る人もいたが、実はこれは楊秀のレベルがそれだけだったことを示しているに過ぎず、彼は注目を集めるために小細工に頼っていたが、それは曹魏グループにとって何の利益もなく、茶番劇に過ぎなかった。 もちろん、楊秀が自分の賢さを誇示し、曹操にちょっとしたいたずらをし続けていれば、最終的に命を失うことはなかったでしょう。しかし問題は、楊修は曹操から一度も批判されたことがなく、これは自分に対する感謝の表れであると感じていたかもしれないということだ。その結果、自殺行為が頻繁に行われるようになる。漢中の戦いの際、楊秀は曹操が軍を撤退させるだろうという主観的な推測を実際に行い、当時劉備と対峙していた曹操軍をパニックに陥れた。 楊秀は曹操に近い人物だと誰もが思っている。楊秀がそう言ったのだから、それは曹操の考えだったに違いない。そこで、曹操が噂を払拭するために出てきた時、兵士たちはもうそれを信じませんでした。これは、当時すでに戦略的に消極的な立場にあった曹操軍にとっては非常に不利なことでした。そのため、軍規を厳格にし、兵士たちの戦闘精神を強化するために、曹操は楊秀を処刑しなければならなかった。 さらに、楊秀も大臣として一線を越えた。彼は曹丕と曹植の争いに盲目的に介入し、曹植を擁護した。いつも疑い深い曹操は、このことで非常に不安になった。曹植がすでに側近たちに手を差し伸べていると思い、曹植に対する印象も悪くなった。 では楊秀はどうでしょうか?彼は自己反省をしなかっただけでなく、曹植が曹丕に勝つために不正行為をするのを手伝いました。曹操は楊秀の無謀で自殺的な行動を見て、もしこれを処理しなければ、大臣たちは必ず徒党を組み、曹魏グループの力を大きく消耗してしまうだろうと感じた。したがって、楊秀の死は避けられなかった。 |
<<: 当時の隋の皇太子は楊雍でした。晋の太子である楊広はどのようにして隋の煬帝になったのでしょうか?
>>: 臥龍と鳳凰だけが天下を征服できると言われているのに、その両方を手に入れた劉備がなぜ蜀漢だけを手に入れたのでしょうか?
推薦する
于謙は明朝を救ったが迫害された。彼を迫害した裏切り者の役人たちはどうなったのか?
明の正統14年、土木の戦いの後、オイラトの騎兵隊は北京の街に直行しました。危機に直面して、陸軍大臣の...
検閲官として、韓奇はどのようにして一挙に4人の首相を倒すことができたのでしょうか?
韓起は、字を智桂といい、湘州安陽の出身で、1008年に官僚の家に生まれ、祖父たちは皆官僚を務めていた...
黄庭堅が書いた水仙に関する 4 つの詩を見ると、彼は水仙をどのように表現したのでしょうか。
黄庭堅はかつて水仙に関する詩を 4 つ書きました。次の Interesting History 編集...
「木の下の木ではなく、他人の下にいる人間になりなさい」をどう理解しますか?このことわざの意味は何ですか?
「人の下に人、木の下に木」をどう理解するか?このことわざの意味は何ですか?次の興味深い歴史編集者があ...
古典文学の傑作『前漢演義』第85章:漢王が韓信の称号を楚に改めた
『西漢志演義』と『東漢志演義』は、もともと『江暁閣批判東西漢通志演義』というタイトルで、明代の中山の...
司馬光の「異国の初夏」:危険な言葉も美しい言葉もない、素朴な小詩
司馬光(1019年11月17日 - 1086年10月11日)、号は君子、号は幽素、山州夏県蘇水郷(現...
宋代における「秀」という言葉はどういう意味ですか?武大浪が金持ちになったら、「武大秀」と呼ばれるようになるかも!
宋代における「秀」という言葉は何を意味するのでしょうか? 武大浪の富は「武大秀」と呼ばれるかもしれま...
『後漢書 蔡瑁伝』の原文と翻訳、『蔡瑁伝』より抜粋
『後漢書』は、南宋代の歴史家・范業が編纂した年代記形式の歴史書である。『二十四史』の一つで、『史記』...
米芳と傅士人は関羽のせいで東呉に降伏した。これは本当に真実か?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
なぜ高太公は朱八戒を追い払ったのですか?理由は何でしょう
この質問を見た読者は、外見が全てであるこの時代に、どうしてガオさんは豚に恋をすることができたのかと言...
富の神、鍾馗と劉海の伝説
鍾馗の故郷、陝西省湖県には、鍾馗王が編纂した伝説がある。「劉海は仙根を持って生まれ、湖県曲宝村で生ま...
馬超と張飛の戦闘能力は似ていますが、趙雲と関羽が一対一で戦ったらどちらが勝つでしょうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
蘇軾の妻を恋しがる詩:「迪蓮花:蝶は怠け者、コウライウグイスも怠け者、春は半分終わった」
以下、Interesting History の編集者が蘇軾の「當連花・蝶と鴉は春に怠け者」の原文と...
明代の楚王宮は高官山の南麓にあります。どの宮殿をモデルに建てられたのでしょうか。
明楚宮は高官山の南麓に位置し、南京故宮を模して建てられたが、規模は小さく、南向きで、高官山を背にして...
南唐最後の君主、李郁:「伯正子:四十年家と国」の原文と鑑賞
本日、『興味深い歴史』編集者は、李宇の『形成を破る詩:家族と国家の40年』の原文と評価をお届けします...