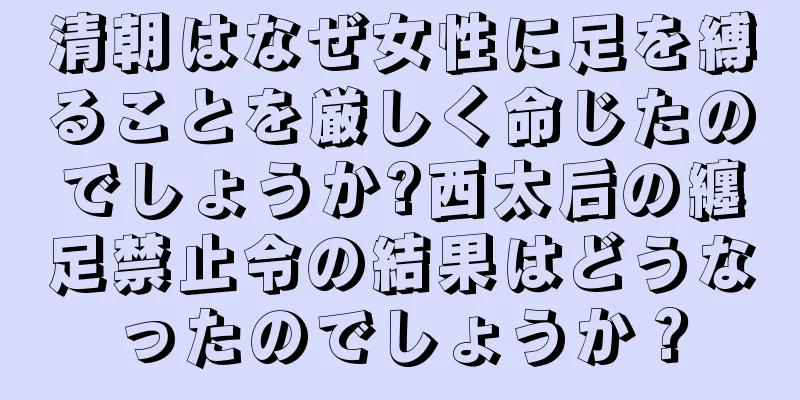李時珍は本草書に多くの誤りを発見しましたが、彼が編纂した医学書はどれですか?

|
数十年にわたる医療活動と古典医学書の読書の中で、李時珍は古代の本草書に多くの誤りがあることを発見し、新しい本草書を編集することを決意しました。嘉靖31年(1552年)、李時珍は『正蕾本草』をもとに本草綱目を編集し始め、800冊以上の本を参考にしました。この間、嘉靖44年(1565年)から、李時珍は何度も家を出て現地調査を行い、湖広、江西、直隷などの有名な山や川を数多く訪れ、多くの難問を解明しました。次は興味深い歴史エディターが詳しく紹介しますので、見てみましょう! 『本草綱目』を編纂する過程で、李時珍にとって最も頭を悩ませたのは、薬物名の混乱により、薬物の形状や生育条件が分からないことが多かったことだった。過去の本草書には繰り返し説明が書かれていましたが、一部の著者は深い調査や研究を行わず、本からそのままコピーしただけでした。その結果、説明はますます混乱し、矛盾が多くなり、人々が合意に達することが難しくなりました。例えば、薬草のヒメハコベ。南北朝時代の有名な医学者、陶洪景は、これは麻黄のような小さな草だが、色は緑色で、花は白いと言いました。しかし、宋代の馬志は、この草が藍の植物に似ていると信じ、陶洪景がヒメハコベを全く知らなかったと責めました。例えば、ゴウジという生薬については、地黄丸に似ていると言う人もいれば、八双に似ていると言う人もいれば、関中に似ていると言う人もいます。意見は非常に矛盾しています。李時珍は父親から刺激を受け、「何千冊もの本を読むこと」は必要だが、「何千マイルも旅すること」はさらに不可欠だと悟った。そのため、彼は「数百の話を集めた」だけでなく、「あらゆる方面の人々にインタビュー」して徹底的な調査を行った。 彼は27年間の長期にわたる努力を経て、明の万暦6年(1578年)、61歳の時に『本草綱目』の初稿を完成させた。その後10年間に3回改訂され、合計40年が経過しました。彼は万暦21年(1593年)に亡くなった。万暦25年(1596年)、李時珍の死後3年目に、『本草綱目』が金陵(現在の南京)で正式に出版されました。 本草綱目 「本草綱目」は、52 巻からなる薬草書です。明代の嘉靖31年(1552年)から万暦6年(1578年)にかけて李時珍(董弼)によって書かれ、原稿は3回改訂されました。この本は「要綱に従って列挙する」という文体を採用しているため、「綱目」と名付けられました。 『正蕾本草』に基づいて改正された。序文(第 1 巻と第 2 巻)は、一般的な序文に相当し、重要な本草書と薬効の理論について説明しています。 第1巻『歴代本草綱目』では、明代以前の主要な本草綱目41編を紹介しています。この本は、明代以前の薬の匂いの陰陽、五味の良し悪し、標本の陰陽、昇降、補瀉、経絡の誘導と報因、薬の諸禁忌などに関する議論を集めたもので、その中でも金元代の議論が最も多い。第3巻と第4巻は「万病主薬」で、『正蕾本草』の「万病総薬」の古い例に倣い、病気の原因に基づいて主な薬の名前とその主な効果を列挙しており、臨床投薬マニュアルに相当します。第5巻から第52巻までは単行本で、1,892種類の薬品と1,109種類の図版が掲載されている。 一般的なルールは、「3つに分けるのではなく、異なる部分に分け、物事はそのカテゴリに従って分類され、項目は主要な原則に従って列挙されます。」 このうち、部分が「主要な原則」、カテゴリが「項目」であり、16の部分(水、火、土、金石、草、穀物、野菜、果物、木、衣服と器具、昆虫、鱗、貝、鳥、獣、人)と60のカテゴリに分かれています。各セクションは小さいものから大きいもの、安価なものから高価なものへと並べられており、検索に便利で、生物の進化と発展の考え方を反映しています。各部門の下には 60 のカテゴリがあり、各カテゴリ内では同じ科と属の多くの生物が一緒に配置されていることがよくあります。それぞれの薬には、概要として薬名、詳細として内容が記載されており、1つの薬名の下に8つの項目(つまり「もの」)が記載されています。その中で、「名医」は別名を列挙し、名前の意味を解説しています。「集医」は薬物の製造、形状、採取などを紹介します。「偏依」(または「訂正」)は各流派の意見を集め、薬物の疑問や誤りを分析して訂正します。「補治」は焙煎の方法を説明しています。「香」「主適応」「発明」は薬効の理論を解説し、投薬の要点を提案し、多くの場合、著者の個人的な意見が添えられています。「附方」は病気を題名とし、関連する処方を列挙しています。 |
<<: 宋徽宗は道君帝として知られています。彼のどのような能力が陸羽や蔡襄の能力に匹敵するでしょうか?
>>: 李時珍が帝室医局を辞職して故郷に戻った後、自らの書で作った堂名は何ですか?
推薦する
劉果の『唐多齢 葦葉汀州』:この詩は微妙で暗示的な方法で書かれており、熟考する価値があります。
劉果(1154-1206)は南宋時代の作家であり、雅号は蓋之、別名は龍州道士としても知られている。彼...
古典文学の傑作『太平天国』:人材資源編第35巻全文
『太平百科事典』は宋代の有名な百科事典で、北宋の李芳、李牧、徐玄などの学者が皇帝の命を受けて編纂した...
本草綱目第8巻生薬編抗ひまわりの具体的な内容は何ですか?
『本草綱目』は、明代の優れた医学者、李時珍によって著された全52巻からなる中国医学の古典書です。次の...
「バシャンへの道における大晦日の思い」の原文は何ですか?どのように鑑賞すればよいでしょうか?
バシャンの道中での大晦日の思い崔図(唐代)三波までの道は長く、私の体は何千マイルも危険にさらされてい...
皇帝の物語: 李淵はなぜ隋に対する反乱を起こすために晋陽を選んだのでしょうか?
中国の歴史では、秦の始皇帝が皇帝制度を創設し、「始皇帝」として知られる最初の皇帝となった。それ以来、...
岳飛の死後、彼の子供たちはどうなったのでしょうか?
岳飛は南宋時代に金と戦った有名な将軍です。中国の歴史上、有名な軍事戦略家であり国民的英雄でした。結局...
易経の六十四卦の62行目「何も成し遂げられず、ただ食物が与えられるのみ」とはどういう意味ですか?
『易経』の六十四卦の62行目「何も成すことはできず、ただ食べ物だけが真ん中にある」とはどういう意味で...
那藍星徳の「草を踏む・月の光は水のよう」:詩全体が悲しく、曲がりくねっていて、多くの紆余曲折があります。
納藍興徳(1655年1月19日 - 1685年7月1日)は、葉河納藍氏族の一員で、号は容若、号は冷家...
宋代の詩「建門路小雨に遭遇」を鑑賞します。陸游は詩の中でどのような場面を描写しましたか?
宋代の陸游が建門路で小雨に遭遇した事件について、次の興味深い歴史編集者が詳しく紹介しますので、見てみ...
元劇の言語的特徴は何ですか?元劇の言語的特徴の紹介
ご存知の通り、元曲は元代に栄えた文学様式で、元雑曲と三曲の総称です。 では、元劇の言語的特徴とは何で...
かつては勢いがあった王安石の改革が、なぜ腐敗した官僚の温床となってしまったのか。
王安石の改革は、当時の「貧困と弱体化」という社会実態に対応して、富国強兵を目的に北宋時代に開始された...
太平広記・第92巻・奇和尚・玄奘三蔵をどう翻訳しますか?具体的な内容はどのようなものですか?
『太平広記』は、漢文で書かれた中国古代の記録小説集で、全500巻、目録10巻から成り、漢代から宋代初...
紅楼夢第93話:ジェンの召使がジアの家族に避難、水月寺がロマンチックな事件を発見
『紅楼夢』は、中国の四大古典小説の一つで、清代の章立て形式の長編小説です。通俗版は全部で120章から...
Bian Queをご存知ですか?ビアン・クエはどこで医療技術を学んだのですか?
皆さんは、扁鵲をご存知ですか? 次に、『Interesting History』の編集者が扁鵲につい...
韓愈の『張吉に聞け』:著者は李白と杜甫の詩と随筆を熱烈に賞賛している
韓愈(768年 - 824年12月25日)は、字を随之といい、河南省河陽(現在の河南省孟州市)の人で...