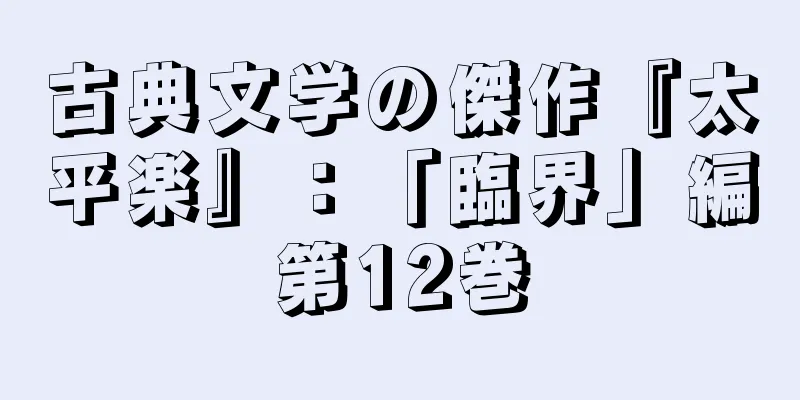『史記・李斯伝』の記録によると、古代の皇帝はなぜ自らを「朕」と呼んだのでしょうか?
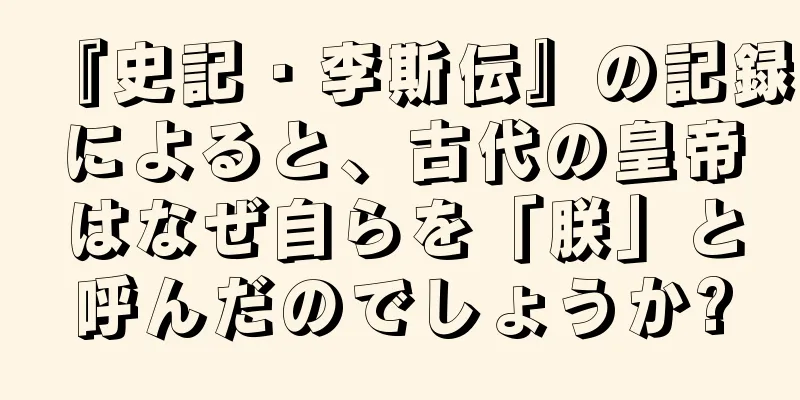
|
「皇帝が高貴なのは、声だけが聞こえ、臣下は誰もその顔を見ることができないため、彼を「朕」と呼ぶ。」これは『史記・李斯伝』に記録されている一文です。多くの友人がこの質問に興味を持っていると思います。古代の皇帝の中には、なぜ「朕」と名乗った人がいるのでしょうか。「朕」の意味は何ですか。秦の始皇帝が統一の大業を成し遂げた後、「帝」と「王」を「皇」に置き換え、最初の皇帝になりました。李斯は後に皇帝の一人称代名詞は「朕」であるべきだと提案しました。これは「皇帝の権力の優位性」を意味します。そして、当時の「朕」という字の書き方から、いくつかの手がかりも見えてきます。次の興味深い歴史編集者が、詳しい紹介をお届けします。見てみましょう! 中国の2000年以上の封建制の歴史の中で、秦王朝は紀元前221年に始皇帝嬰誠が「六王を滅ぼし天下を統一」して建国してから、2代目に滅亡するまで、わずか十数年しか続かなかった。歴史の深遠さから見れば、ほんの一瞬の出来事だった。しかし、中国史上初の統一封建王朝として、嬰誠と秦王朝は後世に数え切れないほどの政治的遺産を残した。 「皇帝制」は嬴政から始まりました。紀元前221年に六国を統一した後、嬴政は「功績は三君を超え、徳は五帝を超える」と考え、李斯の提案により「三君五帝」の称号を組み合わせて皇帝の称号を作りました。帝国の権力の優位性に加えて、「私」という称号の排他性もあります。それ以来、1912年に清朝が崩壊するまで、皇帝は自らを「朕」と称した。 皇帝の専制政治が封建社会と封建制度の必然的な結果であることは、私たちにとっては理解しにくいことではありません。さらに、この結果は封建制度のさらなる発展と改善とともに継続し、明と清の時代にピークに達しました。 しかし、春秋戦国時代、つまり「余」「朕」「我」「吾」「台」「卬」などの一人称代名詞が流行していた時代に、なぜ秦の始皇帝嬰誠は最終的に皇帝の独占名詞として「朕」を選んだのか、という疑問を抱かずにはいられません。偶然だったのでしょうか。 「朕」という用語は秦以前の時代には珍しくなかった。 「朕」は一人称代名詞として「私」を意味し、高官、文人、国王から一般人まで幅広く使われます。 屈原には「私の父は伯雍という」「私は時が来ないことを嘆く」「私が道に迷ってしまう前に、私の馬車を道に戻してください」という一節があり、『堯経』には「あなたは私の後を継ぐことができます」という一節もあります。 「朕」は『二亜世古』に出てきます。後漢の作家蔡邕は率直にこう言っています。「朕は私を意味します。昔は、貴人と卑人を区別せず、富者と貧者を同じように扱っていました。」意味は非常に明確です。一人称代名詞「朕」は、まさに貴人と貧者の両方が使う言葉です。 では、「朕」が際立つ魅力とは何でしょうか。実は、「朕」は甲骨文字に初めて登場した人称代名詞で、「余」「吾」「我」に比べ、その起源と使用はもっと早いのです。さらに、時代の発展とともに、戦国時代後期には「朕」の使い方にかなりの変化が見られました。もともと日常の話し言葉でよく使われていた「朕」は、書き言葉でしか見られなくなりました。逆に、より口語的で、より流通していて、大衆に近い「我」と「吾」が主流になっています。 このように、秦の始皇帝は「朕」を自分の代名詞として選びました。これは、民衆のタブーによる殺人を避けることができただけでなく、天下の統治者としての皇帝の「荘厳さ」と「威厳」を反映するものでもありました。顧潔剛氏と劉啓宇氏が『尚書唐詩』の注釈と翻訳の研究で指摘したもう一つの点は、「朕」という一人称代名詞は、秦以前の時代の「我」や「余」に相当しないということです。 「朕」は「私の」を意味し、「我」や「余」などの単語とは異なり、所有格と主格があります。すべての甲骨文字において、「朕」は「私の」を意味する単数一人称属格としてのみ使用されています。 『上書順典』には「汝は我が山湖の司令官となれ」という一文がある。『大于定』(銅銘)には「我の命令を廃止してはならない」という一文がある。 「私の命令を放棄するな」と説明する方が簡単です。この意味から、李斯の「世界は私のものであり、皇帝の権力は最高である」という言葉も説明しやすいです。 しかし、この説明に対して、有名な歴史学者で言語学者の戴震は、船の継ぎ目を「朕」と呼ぶという見解を提唱しました。 --戴震、「高公記図・寒仁注」。 『朕文街子』によれば、「朕」という字は「舟」と「灷」という字から成り、本来の意味は「船の中の火」を指す。戴震は、「朕」という字が「舟」と「灷」の間の隙間を繋ぐ役割を果たしていると信じていた。 「周」と「灷」は古代の水上民族の発展、繁栄、成長に欠かせないものであり、アイデンティティ、権力、地位、富の象徴であり、「朕」は間違いなくそれらをつなぐ最も重要なもの、要点でした。 この発言は、一人称代名詞の登場が早いか遅いか、明らかな所有格の解釈よりも説得力があり、始皇帝嬰誠が築き上げた統一状況は前例のない偉業だったため、このような自信から、始皇帝嬰誠が自らを国家の最優先課題に位置付けたのは必然の結果であると考えられています。 |
<<: 古代人は高いベッドや柔らかい枕を好まなかったのに、なぜ古代の人々はそのような高い枕を使ったのでしょうか?
>>: 喬潔は『紅楼夢』にはあまり登場しないのに、なぜ十二美女の一人なのでしょうか?
推薦する
ロバ族は現代においてどのように発展したのでしょうか?
19世紀末、イギリスの侵略者はアッサムの辺境地域に住むロバ族の古い徴税制度を無差別に破壊し、ロバ地域...
白峰と高建礼の関係は?どちらが強いのか?
白峰と高建立白鋒と高建礼はどちらも武侠アニメ『秦の始皇帝』の登場人物です。二人とも武侠の達人であり、...
『紅楼夢』で宝仔はどうやって蟹の宴会を企画したのでしょうか?
大観園で催された蟹宴会は石向雲が主催したが、費用を支払い、尽力したのは薛宝才だった。今日は、Inte...
楊秀の死因は何でしたか?楊修の死を通して漢から魏への変遷を見つめる!
今日、『Interesting History』の編集者は楊秀の死についての真実をお伝えし、皆様のお...
ラフ族にはいくつの種類の踊りがありますか?このダンスの伝説は何ですか?
ラフ族の民俗舞踊には多くの種類があり、生産や日常生活に関係し、生活の味わいに満ちています。動物の動き...
「博社梅花図」を書いた詩人は誰ですか?この詩の本来の意味は何ですか?
【オリジナル】咲くとまるで雪のようです。消えていくと雪のように見えます。ユニークな花。香りは雌しべや...
古典文学の傑作「太平天国」:白骨部第4巻全文
『太平百科事典』は宋代の有名な百科事典で、北宋の李芳、李牧、徐玄などの学者が皇帝の命を受けて編纂した...
『紅楼夢』で宝玉と青文が最後に会ったとき何が起こりましたか?
青文は賈宝玉の部屋の四人の侍女の一人だったが、結局は王夫人によって賈邸から追い出された。次に、Int...
『紅楼夢』で妙玉が誰かを招いてプライベートなお茶を飲む時に取り出した茶器の意味は何ですか?
『紅楼夢』第41話では、妙玉が宝仔、岱玉、宝玉を耳の部屋に招待し、「プライベートティー」を楽しみまし...
諺にあるように、皇帝に仕えることは虎に仕えるようなものだ。年庚瑶が反乱を起こしたら、彼に王位に就くチャンスはあるだろうか?
雍正帝は非常に柔軟で、高い政治教養を持ち、疑い深く懐疑的であったため、兄弟たちとの王位争いに勝利する...
古典名作『太平天国』:四夷篇第14巻 西栄II 全文
『太平百科事典』は宋代の有名な百科事典で、北宋の李芳、李牧、徐玄などの学者が皇帝の命を受けて編纂した...
宋代の才女であった李清昭は、なぜ晩年は孤独で寂しい思いをしたのでしょうか。
李清昭は誰もが有名な詩人、作詞家といった印象を持っています。彼女の作品の多くは、後世の私たちに精神的...
仏教経典にある「十四無意識」とは何ですか?なぜ孔子も釈迦牟尼もそのような質問に答えなかったのでしょうか?
本日、Interesting Historyの編集者が、仏教経典にある「十四無意識」とは何かについて...
水滸伝で黒旋風の李逵はどのように死んだのですか?黒旋風李逵の紹介
水滸伝で黒旋風の李逵はどのように死んだのか? 黒旋風の李逵の紹介 李逵は中国の古典小説「水滸伝」の重...
名字の由来は何ですか?同じ姓を持つ女の子のための素敵な名前の完全なリスト!
今日、Interesting History の編集者が、姓が Zheng の女の子にふさわしい素敵...