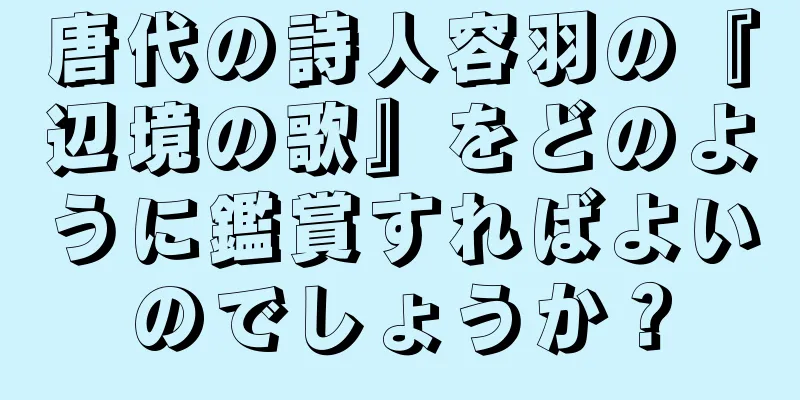盛雍は荊南の戦いで朱棣の軍を何度も破ったのに、なぜあのように惨めな死を遂げたのでしょうか?

|
盛雍は明代の有名な将軍で、荊南の戦いで朱棣の軍を何度も破り、戦争の流れを変えそうになったほどです。残念なことに、朱雲文は気づくのが遅すぎたため、早い段階で聖勇を利用せず、朱棣の軍隊に息抜きのチャンスを与えてしまいました。朱棣は都を征服した後、聖雍の能力を非常に高く評価したため、彼を殺さずに使い続けました。しかし、盛勇には裏の目的があると何度も指摘され、ついには絶望的な状況に追い込まれ、自殺に至った。聖勇の人生は実に苦しいものでした。彼は誠実に職務を遂行しましたが、決して良い結末を迎えることができませんでした。次は興味深い歴史エディターが詳しく紹介しますので、見てみましょう! 朱雲文が即位しようとしていたとき、朱元璋は朱雲文に、叔父たちが明朝の国境を守ってくれるので、自分は皇帝として安心していられると語った。しかし、朱雲文は朱元璋にこう尋ねた。「もし叔父たちが反乱を起こしたらどうしますか?」 朱元璋は曖昧な口調で「どうするつもりですか?」と尋ねた。朱雲文は「まず徳で説得し、それがうまくいかなければ武力で鎮圧します」と答えた。朱元璋は黙ってうなずいた。その時から、朱雲文とこれらの家臣王たちの間に戦争が起こるだろうと彼は知っていた。 朱雲文は朱元璋の最も愛された孫であった。朱元璋は息子を皇太子に立てる伝統を無視し、自分の長男を皇太子にした。当然、朱雲文が王位にしっかりと座ることを望んでいた。そのため、朱元璋は朱雲文に最大の切り札、数少ない現存する建国の英雄の一人である聖勇を残した。 聖雍は朱元璋が反乱を起こして以来、朱元璋に従っていた。その時代、聖雍は名将としての風格を示し、朱元璋に忠誠を誓っていたため、朱元璋は彼を殺そうとはしなかった。 当時、朱元璋は明朝の将軍のほとんどを殺害していました。朱元璋は朱雲文に使える将軍がいなくなることを恐れ、聖雍を残しました。しかし、朱雲文は朱元璋よりも疑い深く、聖雍をまったく使わず、中将にまで昇格させました。 その結果、耿炳文と李景龍は敗れ、朱雲文は正気を取り戻し、盛鏞を将軍に任命した。しかし、朱棣も長年名将たちの間で活躍しており、盛鏞と互角であった。朱棣は朱雲文の弱点(叔父を殺したという汚名を着せられるのを恐れる)につけ込み、盛鏞を倒した。 聖雍は朱元璋が期待する部下として相応しかった。不利な状況でも朱棣を苦しめ、何度も生け捕りにしかけた。朱棣も聖雍を非常に尊敬していたため、朱棣は皇帝になった後も、聖雍を将軍として軍を指揮させた。 しかし、聖雍は結局朱雲文のチームの一員でした。この関係を利用して、聖雍は反乱を望んでいると言う人もいました。朱棣も聖雍に疑いを抱きました。聖雍は自殺するしかありませんでした。このような有名な将軍がこのような結末を迎えるのは残念です。 |
<<: もし馬皇后がまだ生きていたなら、朱棣が始めた荊南の役は起こらなかったでしょうか?
>>: 魏皇后は武則天の完全な複製でしたが、なぜ李龍基はクーデターを成功させることができたのでしょうか?
推薦する
古代の恋愛物語の一つ:後羿と嫦娥の恋が悲劇となったのはなぜでしょうか?
后羿が太陽を射抜き、嫦娥が月へ飛ぶ。これは誰もが知っている神話です。では、后羿と嫦娥のラブストーリー...
『紅楼夢』の妙玉は本当に未亡人なのでしょうか?なぜそんなことを言うのですか?
『紅楼夢』に登場する金陵十二美女の一人、妙玉は髪を切らずに仏教を実践する尼僧である。 Interes...
『太平広記』第275巻:童子召使の登場人物は誰ですか?
魏道夫、李景武、公干、呉興禄、李虎、硯と剣を持って秦に帰る、段璋、尚青、李斉、侍女李福の奴隷少女募集...
二胡は中国の伝統的な弦楽器です。何年の歴史があるのでしょうか?
二胡(ピンイン:Erhu)は唐代に起源を持ち、「西琴」と呼ばれていました。1000年以上の歴史があり...
『紅楼夢』の胡医師はどんな人物ですか?彼は何回登場しましたか?
みなさんこんにちは。胡医師については、皆さんも聞いたことがあると思います。 『紅楼夢』は曹公が10年...
『紅楼夢』の三女タンチュンってどんな人ですか?
賈丹春は『紅楼夢』の登場人物。金陵十二美女の一人であり、側室の趙叔母の娘である。よく分からない読者は...
『紅楼夢』の雪屋敷の使用人たちはどんな人たちですか?
『紅楼夢』は中国古典小説思想と芸術の最高傑作の代表作であり、中華民族の文化の宝庫の至宝でもあります。...
太平広記・巻43・仙人・真人陰をどのように理解すべきでしょうか?具体的な内容はどのようなものですか?
『太平広記』は、漢文で書かれた中国古代の記録小説集で、全500巻、目録10巻から成り、漢代から宋代初...
禅逸話第17章:蕭峠の孤児趙守村と張老荘の正道への改宗
『禅正史』の筋は非常に複雑で、南北朝時代の南梁と東魏の対立を背景に、義侠心あふれる林丹然とその弟子た...
水滸伝で魯智深の命を救った人物は誰ですか?
『水滸伝』の魯智深のイメージは、凡庸な古典小説の登場人物の類型の束縛から抜け出し、多面的な性格特性を...
劉晨翁の考えさせられる歌詞:「西江月・新秋」
以下、Interesting Historyの編集者が劉晨翁の『西江月・新秋説行』の原文と評価をお届...
古代中原王朝の男性はなぜ匈奴の女性との結婚を望まなかったのでしょうか?理由は何ですか?
古代中国では、漢民族は他の民族を見下し、野蛮人と呼んでいました。さらに、これらの民族が中原に到着した...
軽い風邪の「3つの兆候」とは何を指しますか?小寒期の各地の食習慣にはどのようなものがあるでしょうか?
2023年1月5日23時04分に、2023年の最初の節気である小寒が始まります。小寒は二十四節気の第...
古典文学の傑作『太平楽』:統治部第11巻全文
『太平百科事典』は宋代の有名な百科事典で、北宋の李芳、李牧、徐玄などの学者が皇帝の命を受けて編纂した...
『沼地の無法者』第138章:皇帝とその大臣たちに捕虜を捧げて平和な宴を開く。彼の誕生と雷鳴の時代まで遡って彼の神格化を示す。
『水滸伝』は清代の作家于完春が口語で書いた長編英雄小説である。道光帝の治世6年(1826年)に起草さ...