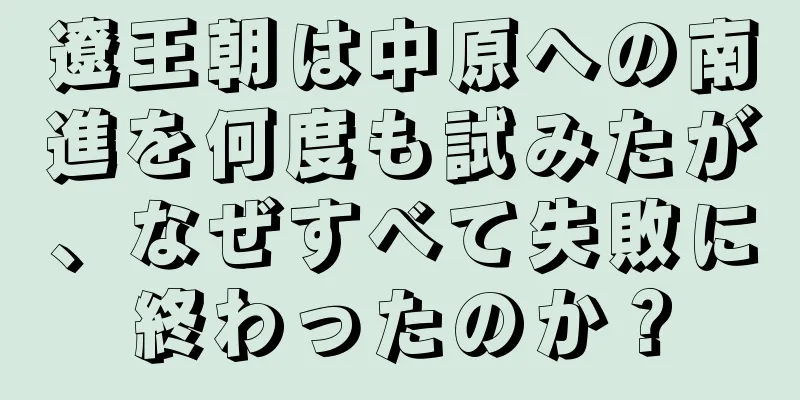孟子:梁恵王章句集(上) - 第1節、原文、翻訳および注釈

|
『孟子』は儒教の古典で、戦国時代中期に孟子とその弟子の万璋、公孫周らによって著された。『大学』『中庸』『論語』とともに「四書」と呼ばれ、四書の中で最も長く、最後の書である。清代末期まで科挙の必修科目であった。 『孟子』は全部で7章から成り、孟子と他の学派との論争、弟子への教え、君主への働きかけなどが記録されている。彼の教義の要点は、性善説と老人の保護と道徳的統治である。 孟子、梁慧王第一章 【オリジナル】 孟子は梁の恵王と会った。王は言いました。「あなたは遠くから来ましたが、我が国に利益をもたらすことができますか?」 孟子は答えた。「王はなぜ利を語るのか。仁義もある。王は『どうしたら国を利するか』と言い、大臣は『どうしたら一族を利するか』と言い、学者や庶民は『どうしたら自分の利を得られるか』と言い、上下が利を争えば国は危うくなる。一万の戦車を持つ国で王を殺すのは必ず千の戦車を持つ一族であり、千の戦車を持つ国で王を殺すのは必ず百の戦車を持つ一族である。一万から千を取り、千から百を取る。少なすぎることはない。利を義より優先すれば、決して満足しない。親族をないがしろにする仁者はいないし、王を後回しにする義人もいない。王は仁義を語るべきだ。なぜ利を語るのか」 【翻訳】 孟子は梁の恵王に会いに行きました。恵王は言った。「殿様、遠くからここまで来られましたが、我が国に利益をもたらすでしょうか?」 孟子は答えた。「なぜ王は利益を語らなければならないのか? 王は仁と義を持たなければならない。王が『我が国にとって何が良いのか』と問うだけで、大臣たちも『我が領地にとって何が良いのか』と問うならば、学者や庶民も『我にとって何が良いのか』と問うだろう。このようにして、上から下まで皆が自分の利益を追求することになり、国は危険にさらされるだろう! 1万台の戦車を持つ国では、王を殺すのは1,000台の戦車を持つ大臣に違いない。1,000台の戦車を持つ国では、王を殺すのは1,000台の戦車を持つ大臣に違いない。百台の戦車を持つ者は、百台の戦車を持つ大臣でなければなりません。彼は一万台の戦車のうち千台を持ち、千台の戦車のうち百台を持っています。これらの大臣の財産はかなり多いに違いありません。もし彼が義を忘れ、すべてのことにおいて利益を第一に考えるなら、君主からすべてを奪わない限り満足しないでしょう。仁を心に抱く者は誰も親を捨てず、義を心に抱く者は誰も君主を無視しません。王は仁と義について話すだけでよいのに、なぜ利益について話さなければならないのですか? 【注意事項】 (1)梁恵王:魏恵王とも呼ばれ、「恵」は彼の諡号である。紀元前339年、魏の首都が安義から大梁(現在の河南省開封市)に移されたため、彼は梁恵王とも呼ばれました。彼は治世の最初の20年間に、魏を戦国の中で最も強力な国にしました。この章の題名は「梁恵王章句集 第一部」である。これは、『孟子』の章の題名が『論語』の章の題名と同じであり、各章の冒頭にある重要な単語や句を抜粋しただけであるからである。 「章居」とは漢代の儒学者がよく使う言葉で、古書の章や文章を分析することを意味します。ここでは古代の書物のタイトルとして使われています。ここでの『梁慧王張居尚』は、東漢の趙斉が著した『孟子張居尚』の古い題名です。彼は『孟子』の七章を二巻に分けたので、ここでの題名は『張居尚』です。 (2)叟:「sǒu」と発音し、「老人」を意味する。 (3)亦: 意味はより抽象的で、「ただ」という意味です。この意味は「のみ」とも翻訳できますが、2つの間には依然として違いがあります。 (4)庶民:庶民、shùと発音する。 (5)上層と下層が協力して利益を得る:征、取る。コミュニケーション、相互作用、相互。この単語は「交差する」という意味から派生して、相互作用や相互関係という意味になり、副詞として使われることが多いです。 「互」の意味は、両者(または複数)が同時に一緒に何かをすることなので、「都」とほぼ同じ「俱」と解釈できます。 「上と下が自分の利益を競っている」という文章では、「上と下が自分の利益を追求している」と訳す方が間違いなく正確ですが、ある本では「上と下が自分の利益を追求している」と「訂正」しており、一貫性がありません。詳細は楊鳳斌著『孟子新注訳』(北京大学出版局)を参照。 (6)殺す:目上の者を下の者で殺す、身分の低い者で高貴な者を殺す。 (7)一万台の戦車を持つ国、または千台の戦車を持つ国:一台の戦車を戦車と呼び、戦車はshèngと発音する。春秋戦国時代、国の規模と強さは戦車の数で測られました。戦国時代の七国は戦車一万台、宋、魏、中山、東周、西周は戦車千台を所有していました。 (8)千台の戦車の家、または百台の戦車の家:古代では、統治する大臣は一定の領地を持っており、そのような領地を所有する大臣は家と呼ばれていました。 (9)号:仮定する、想定する、もし。 (10) 餍:「yàn」と発音し、満ちた、満足したという意味です。 |
<<: 夏の夜風のような詩30編。読むと心が落ち着き幸せな気分になります
>>: 恋煩いに満ちた宋代の古典詩トップ10の中で、どれが1位にランクされるでしょうか?
推薦する
「名付け親を養子に迎える」というのは清朝が滅亡する前も流行っていたのでしょうか?
「役人になるには時間は必要ない、すべては太いアンテナを持っているかどうかにかかっている」という格言が...
分析:孝仙春皇后の葬儀はどうなったのか?
乾隆帝の最初の妻である孝仙春皇后(1712年3月28日 - 1748年3月12日)は、満州族の縁取り...
蒋子牙の軍事書『六策・豹策・小集団』の原文と評価
【オリジナル】武王は太公に尋ねました。「少数の者で多数を、弱者の者で強者を倒したいのですが、どうした...
『済公全伝』第9章:趙文慧が西湖の済公を訪ね、酔った禅師が西湖から魔除けを盗む
『済公全伝』は清代の学者郭暁廷が書いた神と悪魔についての長編小説である。主に済公僧侶が世界中を旅しな...
趙雲という人物は小説の中でどのように描かれていますか?彼にはどんな物語があるのでしょうか?
趙雲は、全120話からなる三国志演義では、第7話で若き将軍として登場し、第97話で戦場で亡くなるまで...
劉克荘は世界に涼しい風を吹き込みたいと願い、「清平楽:五月十五夜月見」を著した。
劉克荘(1187年9月3日 - 1269年3月3日)は、原名は卓、字は千福、号は后村で、福建省莆田県...
『紅楼夢』で妙玉は宝玉の誕生日にどんな贈り物をあげましたか?何がポイントですか?
『紅楼夢』に登場する金陵十二美人の一人、妙玉は髪を切らずに仏教を実践する在家の仏教徒である。本日は、...
『微笑みの放浪者』のイー・リンはどんな人物ですか?イリンを評価する方法
イー・リンは、金庸の武侠小説『微笑の放浪者』の登場人物です。彼女は衡山流の女性弟子で、彼女の師匠は丁...
鄭州はどの王朝の首都でしたか?鄭州の歴史入門
Interesting History の編集者は、読者が商王朝の古代の首都に非常に興味を持っている...
顧勇のお墓はどこですか?三国時代の呉の宰相、顧雍の墓
顧勇のお墓はどこですか?顧勇の墓は小王山の南斜面に位置している。小王山の名前の由来については、次のよ...
廖道宗の皇后蕭観音は「わいせつな詩」を書いたとして有罪判決を受けた
遼の道宗皇帝野呂弘基の皇后、蕭観音は、死後、玄奘と名付けられました。彼女は音楽を愛し、琵琶の演奏が上...
『新世界物語』第 49 章の教訓は何ですか?
『世确心豫』は南宋時代の作家劉易清が書いた文学小説集です。では、『世确心豫・方正篇・49』に表現され...
『紅楼夢』の薛宝琴と薛宝柴の関係は何ですか?
『紅楼夢』の薛宝琴と薛宝柴の関係は何ですか?薛宝琴は薛宝柴のいとこです。彼の母親は薛叔母さんの妹です...
淮安水軍が明代末期に重要な地位を占めたのはなぜでしょうか?淮安海軍の生き残りの道!
今日は、Interesting Historyの編集者が淮安海軍の生存術をご紹介します!興味のある読...
『紅楼夢』の石丁とは誰ですか?彼は誰ですか?
『紅楼夢』に登場する四大家は、賈家、石家、王家、薛家であり、強大な権力を持つ封建官僚集団である。これ...