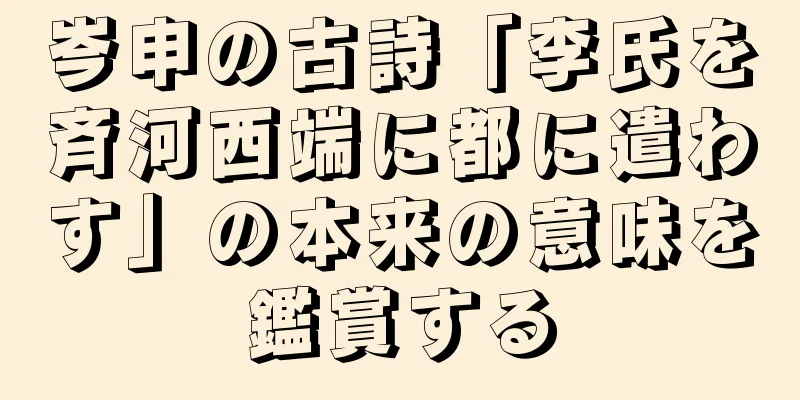「七段詩」の原文は何ですか?どのように理解すればよいのでしょうか?

|
七段詩 曹植(漢代) 豆を煮ると豆の鞘が焦げて鍋の中で豆が泣きます。 私たちは同じ起源であるのに、なぜ互いに戦うことに熱心なのでしょうか? (バージョン 1) 豆を煮てスープを作り、豆を濾してジュースを作ります。 (菽は豉とも呼ばれます) 鍋の下では薪が燃えていて、鍋の中では豆がしずくを垂らしています。 私たちは皆同じ根源から来ているのに、なぜ互いに戦うことに熱心なのでしょうか? (バージョン 2) 翻訳 鍋の中で豆が煮え、鍋の下で豆の茎が燃え、鍋の中で豆が泣いています。 豆と豆の茎はもともと同じ根から生えているのに、どうして豆の茎が豆をそんなにも苦しめることができたのでしょうか。(バージョン 1) 豆は鍋で煮られ、残留物を濾し取って豆汁だけを残してスープを作ります。 鍋の下で豆の茎が燃え、鍋の中で豆が泣いています。 豆と豆の茎はもともと同じ根から生えているのに、どうして豆の茎が豆をこんなにも苦しめることができるのでしょうか? (バージョン2) 注記 保留: 使用されます。 スープ:肉や野菜から作られたペースト状の食べ物。 フィルター: フィルター。 豉(シュウ): 豆。この文は、豆の残渣を濾し取って豆汁だけをスープ用に残すという意味です。 ヤマノイモ:マメ科植物を脱穀した後に残る茎。 大釜:鍋。 燃やす:燃やす 泣く:静かに泣く ベン:もともと、もともと。 建:苦痛、ここでは迫害を指します。 彼:なぜですか? 背景 黄初元年(220年)、曹丕は即位し、魏の文帝と名付けられました。曹丕は皇太子の座を争った経験から立ち直れず、皇帝になった後も曹植に対する恨みを持ち続け、あらゆる手段を使って曹植を排除しようとした。曹植は兄が故意に自分を陥れようとしていることを知っていたが、自分を免罪する方法がなかったため、極度の悲しみと怒りの中で七歩以内に詩を詠まなければならなかった。 感謝 この詩は、同じ根から生える葦と豆を使って、父と母が同じ兄弟を象徴し、葦で豆を揚げるという手法を使って、兄弟である兄の曹丕が弟を傷つけることを象徴しています。詩人の曹丕に対する強い不満を表現し、封建支配集団内の残酷な闘争、詩人自身の困難な状況、そして憂鬱で憤慨した考えや気持ちを生々しく鮮明に映し出しています。 最初の4行は、薪を燃やして豆を煮るという日常生活の現象を描写しています。曹植は自分自身を「豆」に例えており、「泣く」という言葉は被害者の悲しみと痛みを十分に表現しています。 2番目の文の「噜豉」は、煮て発酵させた豆を濾して調味液を作ることを指します。 「気」とは豆の茎のことで、乾燥させて薪として使います。気と同じ根から生えた豆を煮ます。兄弟が無理をして傷つけ合うことのたとえで、自然の法則に反し、常識では許されないことです。詩人が瞬時に発した比喩や言葉遣いの巧みな使い方は、実に驚くべきものだ。最後の 2 つの文は一転して曹植の内なる悲しみと憤りを表現しており、明らかに曹丕への質問です。「あなたと私は兄弟ですか。」なぜ彼らは互いにそれほど強く強制し合う必要があるのでしょうか。「私たちは同じ根を持っているのに、なぜ私たちは互いに傷つけ合うことにそれほど熱心になるのですか?」何千年もの間、これは人々が互いに戦ったり殺したりしないように忠告する一般的なフレーズになっており、この詩が人々の間で広く流布されていることを示しています。 詩全体は「揚げ豆が互いに揚げ合う」という比喩を使って、曹丕が自分や他の兄弟を残酷に迫害したことを非難しています。その調子は婉曲的で奥深く、皮肉の中には注意と勧告があります。一方では曹植の聡明さと才能を反映し、他方では曹丕が兄弟を迫害した残酷さも反映しています。もちろん、この詩のスタイルは曹植の他の詩とは一致していません。急いで書かれたため、洗練された言葉や精緻なイメージはありません。適切で鮮やかな比喩と明確で深い意味があるからこそ、何千年もの間読者の評価を獲得してきたのです。 |
<<: 「七つの雑詩第4番」の作者は誰ですか?どのように鑑賞すればよいでしょうか?
推薦する
乞食チキンを発明したのは誰ですか?ベガーズチキンはどのように調理されるのですか?
伝説によると、清朝時代、江蘇省常熟市の玉山地区で、物乞いが路上で物乞いをしていて、裕福な家庭に生きた...
なぜ中国の一国一民族の政治体制はこれほど早熟なのでしょうか?弓とクロスボウが大きな役割を果たしました!
今日、『Interesting History』の編集者は、中国の国家統合の政治システムがなぜこれほ...
『紅楼夢』の主人公たちの名前に込められた深い意味とは?
「紅楼夢」は曹雪芹の丹精込めた作品で、その中の一語一句が丁寧に考えられています。では、主人公の名前の...
黄巾の乱の背景は何だったのでしょうか?当時の統治者はどの皇帝でしたか?
劉邦が天下を統一した後、その王朝は西洋のローマ帝国に匹敵するほどの大帝国となった。しかし、漢の宣帝は...
岑申の詩「崔山池太妃、于文明邸に再送」の本来の意味を鑑賞
古代詩「崔山池太后、于文明を再び邸宅に送る」時代: 唐代著者: セン・シェン竹林の赤い橋を渡り、花々...
漢書第60巻にある杜周伝の原文
杜周は南陽市杜岩の出身であった。易宗は南陽の太守であった。彼は周を子分として使い、張唐に最高裁判所の...
清朝時代の文学審問はどれほど厳しかったのでしょうか?清朝はなぜこのような大規模な文学審問を行ったのでしょうか?
多くの人は文学異端審問がどのようなものかを理解していません。Interesting History ...
白龍衛府の意味は何ですか?それはどんな歴史的な物語があるのでしょうか?
「白龙微服」という慣用句は、貴族が身元を隠してお忍びで旅をすることの比喩です。また、このように身元を...
張中蘇の詩「秋の夜の歌」秋が近づき、虫は夜通し鳴き、軍服は送られず、霜が飛ばないように
『秋夜歌』は唐代の詩人、張仲粛が書いた七字四行詩である。この詩は、月明かりの夜に徹夜で、水の滴る音や...
巨神の本当の名前は何ですか?西遊記では語られない
小説『西遊記』でも映画やドラマでも、孫悟空が最初に天宮に反逆し、花果山で「天に匹敵する大聖人」を名乗...
三国志演義で、劉備、関羽、張飛が呂布に対して全く異なる態度をとるのはなぜですか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
『紅楼夢』の秦克清の葬儀で何が起こったのですか?それはどういう意味ですか?
『紅楼夢』では、秦克清の葬儀の描写にほぼ2章が費やされている。 Interesting Histor...
『紅楼夢』で西仁はいつ江玉漢と結婚したのですか?
希仁は『紅楼夢』の登場人物で、宝玉の部屋のメイド長です。下記の興味深い歴史編集者が詳細な解釈をお届け...
星堂伝第50章:張成進が金地関を占領し、徐茂公が瓦岡寨を説得した
小説『大唐興隆』は『大隋唐』『大唐興隆全物語』とも呼ばれています。関連する古典小説には、清代乾隆年間...
南宋の御営局は何をしたのでしょうか?皇室駐屯地事務所はなぜ設立されたのですか?
御営部は御営使部とも呼ばれ、南宋の建延元年(1127年)に設置された南宋の軍事機関です。高宗皇帝が即...