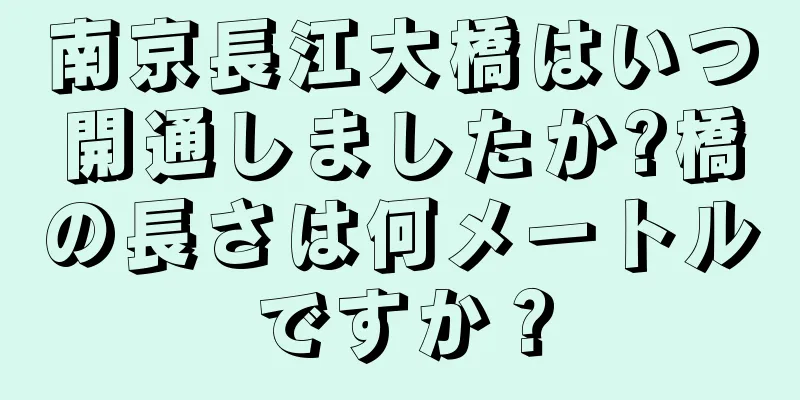中国最古の古典『黄帝内経』は黄帝によって書かれたのですか?

|
中国最古の古典『黄帝内経』は黄帝によって書かれたのでしょうか?実は違います。後世の人々に広く認識されているように、この本は西漢時代にようやく成立し、著者は一人ではなく、中国の各王朝の黄老医学者によって継承、補足、発展、創造されました。次の興味深い歴史の編集者が詳しく紹介します。 『黄帝内経』は、古代中国の唯物哲学である気一元論を受け入れ、人間を物質世界全体の一部とみなし、宇宙のすべてのものは元の物質「気」によって形成されると考えました。 「人は天地と調和する」と「太陽と月に対応する」という概念の指導の下、人間と自然は密接に結びついています。 『黄帝内経』は霊書と素文の2部に分かれており、中国最古の医学古典であり、伝統医学の四大古典の1つです(他の3つは『南京経』、『傷寒論』、『神農本草経』です)。 『黄帝内経』は総合的な医学書であり、黄老道教の理論に基づいて、伝統的な中国医学における「陰陽五行説」「脈説」「臓腑説」「経絡説」「病因説」「病態説」「症状」「診断」「治療」「養生」「運勢説」を確立し、ホリスティックな視点から医学を論じ、自然、生物学、心理学、社会の「ホリスティックな医学モデル」を提示している(現代の学者も、現在の黄老道教の痕跡は隋唐時代の道士王兵によって浸透されたことを確認している)。その基本的な材料は、古代中国の人々の生命現象に対する長期にわたる観察、大量の臨床実践、そして単純な解剖学的知識から来ています。 『黄帝内経』は人体の生理、病理、診断、治療の理解の基礎を築き、中国で非常に影響力のある医学書であり、医学の祖として知られています。 名前の由来 『漢書・易文志・方極略』には『医経』『経方』『仙人』『床子』の四種の漢方医学経典が収録されており、『黄帝内経』は『医経』に収録されています。 いわゆる「医学古典」とは、人体の生理、病理、診断、治療、予防などの医学理論を解説した著作です。その重要性から「クラシック」と呼ばれています。古代人は、儒教の「六経」、老子の「道徳経」、シンプルな「三字経」など、特定の規則を含み、一般的に勉強しなければならない重要な書物を「経典」と呼んでいました。 「内経」と呼ばれるのは、呉坤の『蘇文殊』や王九達の『内経合雷』にあるように「五臓の陰陽を内という」からでも、張潔斌の『雷経』にあるように「内は命の道なり」からでもなく、単に「外」に対する対比として使われているだけです。これは『韓氏内伝』と『韓氏外伝』、『春秋内伝』と『春秋外伝』、『荘子の内弁』と『外弁』、『韓非子の内註』と『外註』と同じ意味ですが、『黄帝外経』と扁鵲と白石の経典は失われ、伝承されていません。 メインコンテンツ 『黄帝内経』は「蘇文」と「霊鷲」の2部に分かれています。 「蘇文」は、内臓、経絡、病気の原因、病態、症状、診断方法、治療原則、鍼治療に重点を置いています。 『霊書』は『素文』と切っても切れない姉妹作であり、内容も基本的に同じである。内臓の機能、病気の原因、病態について論じるほか、経絡やツボ、鍼、鍼治療の方法、治療原理についても重点的に解説します。 |
>>: 太平広記・巻35・仙人・魏単の具体的な内容は何ですか?それをどう理解すればいいのでしょうか?
推薦する
火焔山は本当に孫悟空のせいでできたのでしょうか?この背後にいる首謀者は誰なのか見てみましょう。
今日、Interesting History の編集者は、皆さんに次の疑問を提起します。火焔山は本当...
南宋文芸奇談集第一巻『易軒志全文』
『易軒志』は、南宋時代の洪邁が漢文で書いた奇談集である。本のタイトルは『列子唐文』から来ている。『山...
『紅楼夢』で青文が賈宝玉に見た夢の内容は何でしたか?
『紅楼夢』では、秦克清は死ぬ前に王希峰の夢に現れ、青文は死ぬ前に賈宝玉の夢に現れた。では、この 2 ...
孫尚香は当時絶頂期にあった。彼女は劉備と結婚する気があっただろうか?
古代では、男性は多くの妻や妾を持つことができました。権力と影響力があれば、年配の男性でも18歳の少女...
『秀雲閣』第116章ではどんな物語が語られていますか?
仙女を見て、彼女は自分の死すべき体に嫌悪感を抱き、ハオ・シャンと出会い、再び死すべき欲望に誘惑された...
唐代の懿宗皇帝の寵愛を受けた郭叔妃の紹介。郭叔妃の最後はどうなったのでしょうか?
郭叔妃(?——?)は唐の懿宗李毅の側室の一人で、娘の同昌公主を産んだ。郭は若い頃、当時雲王であった唐...
古典文学の傑作『太平天国』:居館編第1巻全文
『太平百科事典』は宋代の有名な百科事典で、北宋の李芳、李牧、徐玄などの学者が皇帝の命を受けて編纂した...
『紅楼夢』で賈歓はなぜ賈邸校に行かなかったのですか?
紅楼夢で賈歓はなぜ賈邸校に通わなかったのか?次は、興味深い歴史の編集者が関連記事をお届けします。賈歓...
蘇軾は結婚式の日に妻への愛を表現するために『南湘子詩集』を書いた。
蘇軾が属した蘇家は文学史上重要な地位を占めており、彼の父である蘇軾と弟だけで「唐宋八大家」のほぼ半数...
王万の発音は?王万の生涯の簡単な紹介。王万はどのようにして亡くなったのか?
王万は秦の宰相であった。彼の生誕と死亡の日付は歴史上正確に記録されていない。秦の始皇帝が天下を統一し...
電気がなかった古代、人々は暗くなってから何をしていたのでしょうか?
現代人は電気を使って照明を点灯したり、テレビを見たり、インターネットをサーフィンしたり、夜に映画館に...
『三朝北孟慧編』第167巻には何が記録されていますか?
延行第二巻は67巻です。それは紹興5年閏2月1日に始まり、5月に終わりました。閏年の二月一日、皇帝は...
墨子・第49章 陸からの質問(1)原文は何ですか?どうやって翻訳するのでしょうか?
『墨子』は戦国時代の哲学書で、墨子の弟子や後世の弟子たちによって記録、整理、編纂されたと一般に考えら...
なぜ馬岱は楊毅の命令に従い、魏延を追いかけて殺害することを選んだのでしょうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
漢代の技術:張衡が最初の地震計を製作
製紙西漢時代には絹と麻を使って紙が作られ、これが紙の起源です。東漢の蔡倫が製紙技術を改良し、現代の意...