「本当の自分を見せる」というフレーズはどのようにして生まれたのでしょうか? 「人間の足を見せろ」とか「豚の足を見せろ」ってどうしてダメなの?
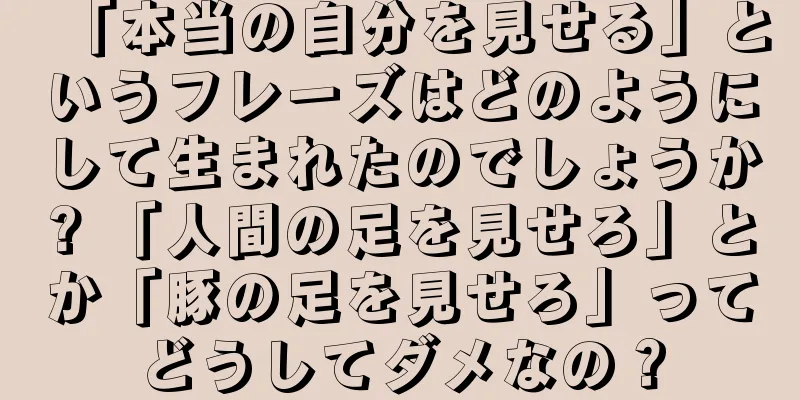
|
今日は、Interesting Historyの編集者が「自分の本性をさらけ出す」というお話をお届けします。気に入っていただければ幸いです。 通常、何かの真実が暴露されたことを表現したいときは、「本性を現す」と言います。しかし、「本性を現す」という言葉の起源は何でしょうか? 伝説によると、「本性を現す」は朱元璋と馬皇后に関係しています。当時、女性は足を包む必要がありましたが、馬皇后は子供の頃からそれを拒否したため、他の女性に比べて足が大きいのです。かつて馬皇后の足が外部の人から見えたことから、「馬の足が見える」ということわざが生まれました。しかし、歴史の記録によると、「露馬脚」という言葉は唐代にはすでに登場していましたが、馬皇后の物語の方が有名です。 1. 本性を現す。 なぜ「人間の足」ではなく「馬の足」を使うのでしょうか? 人はよく「露马脚」という言葉を誰かの嘘を表すときに使いますが、なぜ「露人脚」ではなく「露马脚」を使うのでしょうか? 伝説によると、朱元璋は足を縛られていない馬という少女と結婚した。 ある日、馬さんは金陵の街で車に乗っていました。突風が車体のカーテンをめくり、馬さんの大きな足が露わになりました。 噂は一人から十人へ、十人から百人へと広まり、たちまち金陵中に大騒ぎとなった。 「馬嬌」という言葉は後世に受け継がれました。 2. 不注意。 宋代、都の画家が虎の頭を描き終えたところ、馬を描いてほしいと頼まれました。画家は虎の頭の後ろにある馬の体を何気なく描きました。 誰かが彼に、馬を描いているのか、それとも虎を描いているのかと尋ねると、彼は「まあまあ、まあまあ」と答えた。 訪問者がそれを欲しがらなかったので、彼はその絵をホールに掛けた。 長男は絵を見て、何が描かれているか尋ねました。長男は、虎だと答えました。次男が尋ねると、馬だと答えました。 その後間もなく、長男が狩りに出かけ、トラと間違えて馬を射殺してしまいました。画家は馬の所有者に賠償金を支払わなければなりませんでした。 末の息子は外に出て、トラに出会いました。彼はそれを馬だと思って乗りたいと思いましたが、結局トラに噛まれて死んでしまいました。 それ以来、「不注意」という言葉が広まりました。 3. 老人。 街では、年老いたおばあちゃんが配偶者を「おじいさん」と呼んでいるのをよく耳にします。これは人の老齢を表すために使われているとは思わないでください。実際、「おじいさん」の意味はそれよりもずっと深いのです。 記録によると、真夏のある日、季小蘭が胸と背中を露出した状態で原稿を校正していたとき、乾隆帝が彼に向かって歩いてきた。季小蘭は服を着るには遅すぎたので、机の下に潜り込んだ。 しばらくして、乾隆帝が去ったと思い、ホールの人々に尋ねました。「老人は去りましたか?」 彼が話を終えるとすぐに、乾隆帝が彼の隣に座っていることに気づいた。 乾隆帝は怒って季小蘭に尋ねた。「『老人』という三つの単語をどう説明するんだ?」 意外にも、季小蘭は落ち着いて答えた。「長寿を老といい、背丈が高いことを頭といい、天地の父母を天子といい、要するに『老人』というのです。」 4. 恐喝。 近年、運転中に「車にぶつかる」というニュースが多く報道されています。「車にぶつかる」は「恐喝」とも言えます。 「恐喝」の起源は実は密輸と深く関係しています。 清朝時代、朝廷はアヘンを厳しく禁止し、各地の水上要塞や陸上要塞に検問所を設置した。 水運商人が、成長し始めたばかりの若い竹を切り開き、その中にアヘンを隠して検査を逃れた。 かつて、商船が紹興埠頭に到着したとき、関所の弁護士が船に乗り込み、パイプで竹竿をたたき、「カチカチ」という音を立てました。商人は弁護士が欠陥を見抜いたと思い、数両の銀貨を取り出して弁護士のポケットに詰め込み、竹竿を「カチカチ」と鳴らさないように頼みました。 それ以来、「恐喝」という言葉が人々の間で広まった。 5. ケチ。 「Stingy」は2人であることが判明しました。 「stingy」はけちな人を表すのに使われることは誰もが知っているはずですが、それが実際には 2 人の人の名前であることは知らないかもしれません。 昔、王林という男がいました。中秋節の前夜、彼は古い友人の李世を訪ねました。しかし、月餅を買うのをためらっていたので、月餅を描いて李世の家に持って行きました。 結局、李世は家にいなかったので、息子は「王おじさんが月餅を持って家に来たので、お返しに贈り物をしよう」と言いました。そこで、大きなカボチャを描いて王林に渡しました。 その後、李世は息子の王林に何か贈り物をしたかどうか尋ねた。 息子は答えました。「月餅を一箱あげたよ。」 「贈り物は返しましたか?」 息子は答えました。「僕はこんなに大きなカボチャを手に入れたよ。」 後に、人々はこの物語の二人を、意地悪でけちな人々を表すために「けち」と名付けました。 6. 愚かなふりをする。 水仙は咲いていない ― 咲いているふりをしているだけ。 「バカなふりをしないで」というのは、誰かと決着をつけたいときに相手がバカなふりをしているときによく使われる表現です。では、「バカなふりをする」というのはどこから来たのでしょうか? 伝説によると、乾隆帝はある春に南方へ視察に行き、青々としたニンニク畑を見て賞賛したそうです。 翌年の冬にもう一度確認しに行きましたが、残念ながらその季節には青ニンニクはまだ育っていませんでした。 皇帝を喜ばせるために、地方の役人は人を遣わしてたくさんの水仙を植えさせました。遠くから見ると、その葉は青ニンニクのように見えました。乾隆帝はそれを見て大いに賞賛し、役人はこれによって昇進しました。 それ以来、人々は不正行為をしたり、何も知らないのに知っているふりをすることを「愚か者を演じる」と嘲笑するようになりました。 |
<<: なぜ陸俊義は水滸伝の十大槍の名人の中で第一位にランクされているのですか?
>>: なぜ燕青は『水滸伝』の秘武器名人トップ10の中で4位にしかランクされていないのでしょうか?
推薦する
中国最大の玉仏はどこにありますか?中国最大の玉仏の大きさはどれくらいですか?
こんにちは、またお会いしました。今日は、Interesting History の編集者が中国最大の...
『紅楼夢』の賈宝玉の霊玉にはどんな言葉が書かれていましたか?それはどういう意味ですか?
賈宝玉は中国の古典小説『紅楼夢』の主人公です。これは、Interesting History の編集...
古龍の武侠小説『英雄の双子』に登場する蒋別河の簡単な紹介
江別河は、本名を江秦といい、古龍の武侠小説『紅蓮の双』の重要な悪役である。彼は「于朗」江鋒の召使/秦...
天界の最上層三層に住むことができる神は誰ですか?
神話小説に詳しい人なら、中国の神話小説では神々の住処を総称して三十六天と呼んでいることを知っているは...
三角クルミの弁はどのように見えますか?本物の三角クルミと偽物の三角クルミを見分けるにはどうすればいいですか?
本物の三角クルミと偽物の三角クルミの見分け方は?次のInteresting History編集者が関...
「山天全芳雷」の発音は? 「山天全芳雷」は何に使われますか?
「山天全芳籃」はどのように発音しますか?「山天全芳籃」は何に使われますか?Interesting H...
秦は晋の文公と同盟を結んでいたが、なぜ鄭国への攻撃を諦めたのか?
春秋時代:晋国は楚国と戦い、最終的に晋国が勝利し、他の王子たちと力を合わせました。しかし、晋国が予想...
隋代の仏教法帯『七つの詩一』:人々は橋を渡るが、橋の下の水は流れない
古代の詩人の多くは禅を探求することを好んだ。王維は半官半隠遁者で、彼の詩には「水の果てに着くと、座っ...
遼・金・元の衣装:遼の鎧と軍服
遼王朝は契丹族によって建国され、主に中原の先進的な文化、生産技術、社会制度を吸収・採用することで、短...
白居易の古詩「兄弟甥に見せるために新しく建てた楼閣と台地」の本来の意味を理解する
古代の詩「兄弟と甥のために新しく建てられたパビリオンとテラス」時代: 唐代著者: 白居易プラットフォ...
周邦厳の詩「雨は止んだが花びらはまだ濡れていて飛ばない」にはどのような感情が表現されているのでしょうか?
以下、興味深い歴史の編集者が、周邦厳の『桓溪沙:雨上がりに濡れて飛ばない紅花』の原文と評価をお届けし...
小説『紅楼夢』に出てくる秦克清の部屋のレイアウトはどのようなものですか?
秦克清は『紅楼夢』の主人公です。金陵十二美女の一人。 ご存知ですか、次の興味深い歴史編集者が説明しま...
呉維野は『淮陰通過二詩一』を著し、その中で詩人は明朝に失敗したことを深く恥じている。
呉衛野は、号を君公、号を梅村といい、陸喬生、観音師、大雲道士とも呼ばれ、明代末期から清代初期の著名な...
『清代名人故事』第3巻原文の誠実さの項目には何が記録されていますか?
◎関世玉の不正に対する抵抗武進県知事の于世明は政府に対する抵抗で知られていた。ある日、彼は友人たちと...
『紅楼夢』で賈おばあさんはなぜ西仁を二度批判したのですか?
賈祖母は、石夫人とも呼ばれ、賈家の誰もが敬意を込めて「老夫人」と呼んでいます。次の興味深い歴史の編集...









