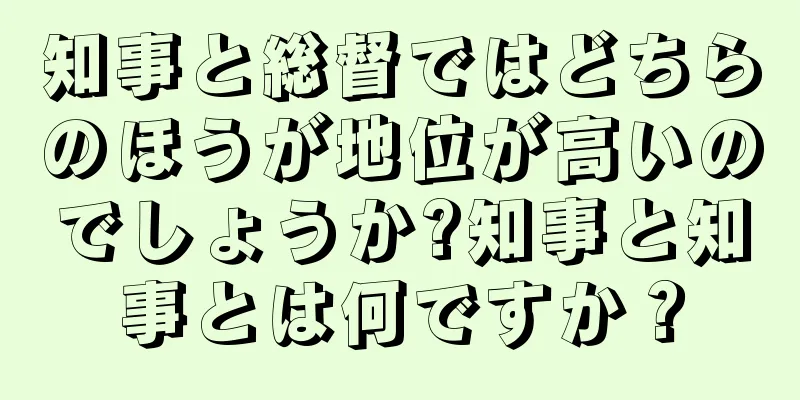なぜ男性は「サー」と呼ばれるのでしょうか? 「ミスター」という言葉の由来

|
男性はなぜ「ミスター」と呼ばれるのか?「ミスター」という言葉の由来 「サー」という称号には長い歴史があります。しかし、歴史のさまざまな時代において、「Sir」という称号はさまざまな人を指すために使われてきました。 『論語』には「酒と料理があれば、師は料理を司る」とあり、注釈には「師とは父と兄のこと」とある。つまり、酒と料理があるときは、父と兄を敬っているということだ。 「孟子」:「先生、なぜそうおっしゃるのですか?」ここでの「先生」とは、年長者で知識豊富な人を指します。 戦国時代には、「国策」は「殿、どうぞお座りください。なぜこんなことをしなければならないのですか」という意味で、目上の人に対して徳を積んで呼びかけるときに使われました。 先生を呼ぶときに「仙生」が最初に使われたのは『古歴』で、「先生に従うときは、他の人と話すときにルールを超えてはならない」というものです。注:「仙生は教える老人です。」現在、先生を「仙生」と呼ぶのはこれに基づいています。 漢代には「氏」の前に「老」という字が付け加えられました。 清朝初期、首相は「老君」と呼ばれていた。乾隆帝以降、「老君」という称号は官界ではほとんど使われなくなった。 辛亥革命後、「老君子」という称号が再び人気を博した。社交の場で人々が出会うと、年上の人をいつも「老紳士」と呼びます。 最近では、ほとんどの妻が夫を「サー」と呼びます。他の女性の夫も「Sir」と呼ばれます。 「ミスター」は必ずしも男性を指すとは限りません。高い道徳心と名声を持つ女性も「ミスター」と呼ばれます。たとえば、「宋清玲さん」などです。 |
>>: 三国時代の孫権の王妃、潘王妃の紹介 潘王妃はどのように亡くなったのか
推薦する
『小崇山:緑のカーテンと雲の中の一筋の赤い糸』の執筆背景は何ですか?これをどう理解すべきでしょうか?
小中山·緑の雲に映える赤い光陳良緑の暗闇の中にほんのり赤が見える。イナゴの枝の上で鳥が鳴き、冷たい煙...
「中秋月図」は唐代の李嬌によって制作され、月の中のキンモクセイの鮮やかな絵が描かれています。
李嬌は、字を玉山といい、唐代の宰相であった。文才に優れ、蘇魏道と並ぶ名声を博した。二人は合わせて「蘇...
魏王曹丕はなぜ漢の献帝が王位を簒奪した直後に彼を殺さなかったのですか?
三国時代は中国史上最も有名な激動の時代の一つです。特に魏王曹操の死後、曹魏の後継者である曹丕は漢王朝...
『西遊記』の黄風怪物がなぜ最初に孫悟空を倒すことができたのか?
『西遊記』では、第19話で唐僧が八戒を受け入れ、第22話で西遊記の全員が集合した。この 2 つの章の...
奇談集第二巻第15巻:韓世朗の女中が妻になり、顧天堅が事務所に住む
『二科派経記』は、明代末期に凌孟初が編纂した俗語小説集である。 1632年(崇禎5年)に書籍として出...
『紅楼夢』で、邢夫人と幽夫人はなぜ裕福な家庭に嫁いだ後も地位を保つことができたのでしょうか?
『紅楼夢』は、古代中国の章立て形式の長編小説であり、中国四大古典小説の一つである。普及版は全部で12...
神話:宣公が帝位を継承。五帝の一人、宣公の物語
荘厳帝が帝位を継承した神話の物語。黄帝の晩年、彼は広城子と容成公という仙人を師とし、自然の成り行きに...
翡翠は中国文明の担い手の一つです。翡翠文化の特徴は何ですか?
玉は中国文明の担い手の一つであり、その役割は道具に集中し、文化と芸術を融合させ、中国民族が今日世界に...
ムーラン、奇妙な女の伝説、第20章:カンヘは金牛峠で将軍を変え、ムーランは五狼町で神のふりをする
『木蘭奇譚』は清代の長編小説です。正式名称は『忠孝勇敢木蘭物語』で、『忠孝勇敢女物語』とも呼ばれてい...
漢民族のドラゴンボート祭りは何を記念するものですか?
端午節の起源の伝説端午の節句は、中国の春秋戦国時代に始まり、2000年以上の歴史を持つ古代の伝統的な...
薛宝柴が林黛玉を尋問のためにひざまずかせると、林黛玉はどのようにして状況を簡単に解決したのでしょうか?
『紅楼夢』は、中国古代の章立て形式の長編小説で、中国四大古典小説の一つです。普及版は全部で120章か...
魏子夫は平陽公主に対して一体何を負っていたのでしょうか?
平陽公主は魏子夫を探しに宮殿へ行き、皇帝に自分の結婚の手配を頼むのを手伝ってくれるよう頼みました。魏...
辛其記の『水龍歌 建康上心亭に登る』はどのような背景で制作されたのでしょうか?どのように鑑賞しますか?
辛其記の『水龍歌:建康尚心亭に登る』、興味のある読者は『Interesting History』編集...
占いと甲骨文字にはどのような関係があるのでしょうか?
商王朝の人々は占いに対して迷信深く、ほとんどすべてのことを占うほどでした。殷虚で発見された甲骨文字か...
薛定山の西征 第44章:麗花は定山で死んだふりをし、薛世子は生きたまま麗花を崇拝する
清代の在家仏教徒である如廉が書いた小説『薛家将軍』は、薛仁貴とその子孫の物語を主に語る小説と物語のシ...