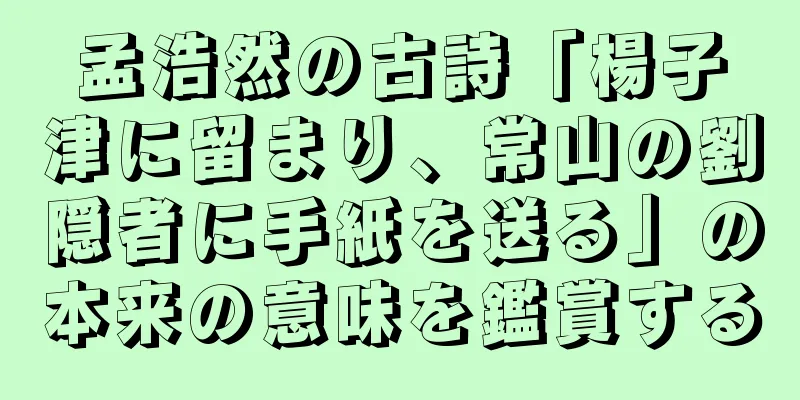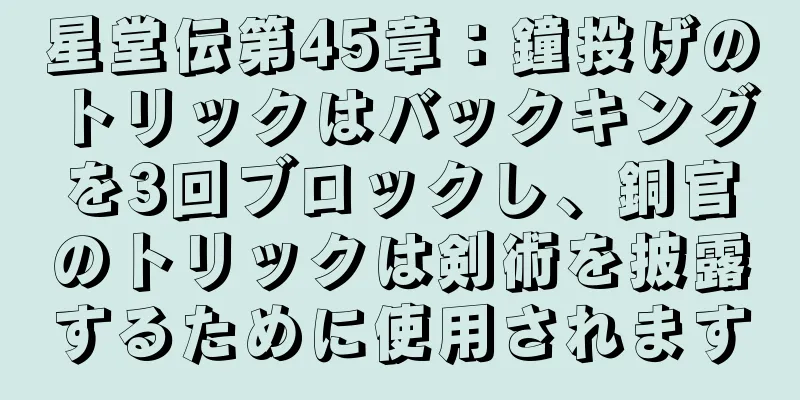隋・唐・五代の服装:唐代の女性の髪型

|
髷は古代女性の最も一般的な髪型で、夏、商、周の時代に始まり、周の時代に完成し、隋と唐の時代に芸術的頂点に達しました。おだんごは、髪の毛を頭の上または後ろで集めて巻き付けるヘアスタイルです。結び方の違いにより、生み出される効果も異なります。 唐代の女性がよく使っていた髪型は、高髪、花髪、日本髪、馬落髪、化粧掃髪、逆髪、E字髪、低髪、小髪、黒髪、囚人髪、宝家髪、ウイグル髪、鳳凰髪、百葉髪、逆髪、双髪、木髪、団子、もみあげなど、30種類以上ありました。スタイルは多かったものの、一般的には頭頂部で梳くタイプと後頭部で梳くタイプの2種類に分かれていました。ここでは、ハイバン、フラワーバン、日本バン、フォーリングホースバン、ノイジーメイクバン、バンなどの典型的なヘアスタイルに焦点を当てます。 唐代初期には、高位の女性の髪型は、隋代の平たい雲のような髪型から、さまざまなスタイルでただ高くそびえ立つ髪型へと変化しました。 「唐の武徳時代、宮廷の女性たちは髪を半分結い上げたおだんご、逆おだんご、楽優おだんごにしていた。」人々がそれに倣い、これが流行となった。大臣たちはかつて太宗皇帝にそれを禁止する命令を出すよう要請した。太宗皇帝は彼らを叱責したが、後に側近の霊虎徳に、なぜ女性はもっと高い位置にお団子を結んでいるのかと尋ねた。霊虎徳は、頭は体の上部にある重要な部分なので、もっと高い位置に結ぶのが理にかなっていると考えていた。したがって、アップスタイルは制限されなくなり、より多様化します。フライングバンとスカイハイバンはどちらもハイバンです。唐代初期には、一般的にはお団子はきつく結われ、頭のてっぺんの高い位置にありました。袁維之は『礼話』の中で、「城中の人は皆、高さ 1 フィートのお団子を結っていますが、妾は例外です」と述べています。もう一つの例は、李和の「高饅頭、夕雲のように悲しい」で、当時の高饅頭の高さを表現しています。もちろん、ほとんどの女性の髪はこの高さまで伸びないので、かつらがとても人気がありました。木製の付け冠とヘアパッドが髪に追加され、おだんごを上げました。楊貴妃は、当時は人工おだんごと呼ばれていたかつらを愛用していました。 その後、いわゆるセミの羽が登場しました。これは、こめかみの髪を外側にとかして非常に薄く開いた層を作り、それを頭のてっぺんの高いところで束ねるというものです。この頃は、頭頂部に二重のボール型のお団子と平らなサイドのお団子があり、左右にとかしてから耳の横に二つの涙型のお団子にとかした髪もありました。 パン 五美娘伝説の垂れ髪 お団子は、髪の毛を頭の後ろで集めて、その端を小さなお団子に結んで作られます。 花饅頭とは、お団子の中に様々な花を挿した髪飾りの一種です。李白の『宮廷楽』には「高饅頭に山花を挿す」という一節があり、万楚の『水墨画』には「高饅頭に花を挿す」という一節がある。唐代の人々は牡丹を花の王であり、富と繁栄の花であると信じていたため、牡丹を髪の束に挿しました。特に裕福な家庭の娘たちは、魅力と華やかさを示すために、牡丹の簪を髪の束に挿すことを好みました。 『箱史:女人世序』には、「張衡は牡丹の花を飾った宴会を催した。何十人もの有名な側室がいて、皆頭に牡丹の花を飾っていた」と記録されている。周芳の「花を飾った女性たち」には、この種の髪飾りが反映されている。牡丹のほかに、さまざまな小花を挿すこともできます。「牡丹の花は髷の中の雪のようです」(羅丘『毗鴻児』)牡丹の花は小さな白いジャスミンの花で、髷の中に挿すことで、黒い髪と白い花のコントラストがさらに際立ちます。この装飾方法は人々の間で受け継がれ、中国女性の主な髪飾りの手段となっています。 日本の吊り饅頭 唐代の全盛期に最も人気があった髪型は、こめかみから後頭部にかけて髪をとかし、上に向かってかき上げ、頭のてっぺんで1つまたは2つのお団子に結び、額の前まで下げる日本式のお団子ヘアでした。繁栄した唐代に出土した陶器の女性像の多くは、日本式の饅頭で作られています。現在でも、日本の女性が着物を着るときに結う髪型は、唐代の日本風のお団子ヘアです。 唐代中期から後期にかけて、女性のおだんごヘアの新しいスタイルが数多く登場しました。唐の徳宗皇帝の鎮元年間末期、首都長安で落馬髷が流行した。頭頂部の髪を大きな髷にまとめ、片側に傾けるという、偶然にできたような、生き生きとした自然な髪型である。この髪型は、画家張玄の「国果夫人春遠出図」に登場している。また、当時流行していたのが、髪を上に乱した「直梔荘記」という髪型でした。白行堅の『三夢』には、「唐末期の宮廷の髪型は直梔荘記と呼ばれ、その形は炎の風のようであった」と記されています。また、無造作に梔子を結った髪型も直梔荘記と呼ばれ、梔子とも呼ばれたという人もいます。別の説では、若いメイドたちは髪を左右に分け、頭の上に何列ものお団子を並べるという、非常に複雑な髪型をしていたという。 ウー・メイ・ニャンの馬の尾の髪型 「夜頭」と「舞丹」は女性の髪型に由来しています。未成年の女性は、髪を頭の上でまとめ、2つの小さなお団子に結ぶのが一般的でした。左右に一つずつあり、形が木の枝に似ていることから「夜刀」と呼ばれています。後に、「夜刀」は若い女性の愛称となった。李佳有の『古星』には「小さな家の15歳の少女、誰も知らない二つの三つ編み」という一節があり、これは若い女の子の三つ編みの様子を描写している。 ヤジ メイドのおだんごとお団子には、主に 2 つの違いがあります。1 つ目は、おだんごは中が詰まったおだんごであるのに対し、メイドのおだんごは中が空洞になっていることです。2 つ目は、メイドのおだんごは頭のてっぺんの高い位置にあることが多いのに対し、メイドのおだんごは耳まで垂れていることが多いことです。女性の年齢によっても髪のとかし方には違いがあります。一般的に、女性は若いときは髪を束ね、成長するとメイドのお団子にします。結婚の日に、若い女性のお団子にします。結婚適齢期を超えているが未婚の場合は、髷を結うのではなく、おだんごヘアにすることしかできません。このことから、当時、お団子ヘアやおだんごヘアは、女性が結婚しているかどうかの象徴であったことがわかります。杜甫の詩「薪を運ぶ」には、「桂州の処女は髪が半分白く、40、50歳になっても未婚である。年を取ると髪はうさぎのように垂れ下がり、野の花や山の葉をあしらった銀のかんざしをつける」とある。これは、長年の戦争と男性人口の減少により、40、50歳になるまで結婚しない四川省桂州地域の女性たちを描写している。彼女たちの髪はすでに白髪になっているが、結婚の準備ができている髪を束ねている。 髪をねじって巻くように梳かして編み込み、安定させて落ちないように頭のてっぺんに重ねます。この髪型はかつて長安で非常に流行していました。ドラマと同じように、おだんごの前に櫛を入れ、おだんごの上に花飾り、金色のヘアピン、もみあげ、ヘアピンを添えて、呉昭懿の威厳、優雅さ、優雅さを表現しています。 潘環寺 扇形のアップヘア 高めのお団子スタイルです。コーミングの際、上の方の髪をまとめて、ウィッグを扇形にコームでとかして固定し、お団子の前にコームを入れると、堂々とした印象になります。貴族や庶民の中高年女性の間で人気がありました。 花のヘアピン この髪型は唐代の貴族女性の間で流行した髪型です。髪を梳くときは、本物の髪と人工の髪を組み合わせて、頭頂部に向かって層状に梳きます。おだんごの横に翡翠のヘアピンを挿し、おだんごの前にビーズのヘアピンを挿し、頭頂部に牡丹の花を挿します。 フー・ジ 高めのお団子スタイルです。髪を梳くときは、髪を4本に分け、かつらで作ったお団子を頭のてっぺんに置き、ヘアピンで固定し、それを本物の髪と組み合わせます。お団子には真珠、絹の花、装飾用の櫛などで飾り付け、高貴で優雅で威厳のある外観にします。この髪型は、皇帝の側室や官族の貴族の女性に好まれました。 ダブルタッセルのお団子 ダブルハイパンの一種です。髪を真ん中で結び、頭のてっぺんにタッセル型のお団子を二つ作ります。それぞれのお団子の前に銀色の花を一つずつ付けます。唐代末期には宮廷や官僚の女性の間で人気を博し、宋代にはさらに人気が高まりました。 翡翠の指輪 飛仙紀 高めのお団子です。髪を6つに分け、1本を垂らしてから上に折り曲げて輪を作り、残りの5本を上に巻き上げて5つの輪を作ります。真ん中の輪が一番大きく、両側の輪はだんだん小さくなります。お団子の両側に翡翠のビーズが付いた鳳凰のヘアピンを挿し、お団子の真ん中に鳳凰を飾ります。鳳凰は真珠、翡翠、羽で孔雀の冠を形成します。唐代の玄宗皇帝の寵姫であった楊貴妃もこの髷を結っていたと言われており、宮廷の身分の高い歌姫たちも好んでいたそうです。 |
<<: 額黄色とは何ですか?唐代の女性はなぜ額に染料を使ったのでしょうか?
推薦する
皇帝の物語:隋楊堅の文帝は歴史上どのような人物だったのでしょうか?
中国の歴史では、秦の始皇帝が皇帝制度を創設し、「始皇帝」として知られる最初の皇帝となった。それ以来、...
南宋代の『電前寺』にはどのような歴史的変化が起こったのでしょうか?海軍との関係は?
南宋建延年間の初め、近衛総司令官と近衛騎兵・歩兵総司令官の職が次第に空席となったが、紹興5年から7年...
『紅楼夢』の薛宝琴はなぜ嘘をついたのか?
第52話では、薛宝琴は大きくも小さくもない嘘をついたが、残念ながら林黛玉にバレてしまった。なぜでしょ...
周王朝はなぜ後宮の側室の数を規定したのでしょうか? 121 という数字を決定する根拠は何ですか?
周の時代はなぜ後宮の側室の数を定めたのか?121人という設定の根拠は何だったのか?興味のある方はぜひ...
鍾郁の紹介:春秋時代の孝行息子で、百里の距離まで米を運ぶ二十四孝子の一人です。
『二十四孝典』の正式名称は『二十四孝典詩全集』で、元代の郭居静が編纂したものです。一説には、郭居静の...
昔の役人は年末ボーナスをもらっていたのでしょうか?年末ボーナスはどのように分配されるのでしょうか?
年末になると、多くの人は、新年を迎えるために帰省するときに「威厳」を保つために、1年間一生懸命働いた...
劉宗元は柳州に左遷され、突然悟りを開いた詩を書いた。
『Interesting History』の編集者は、読者が劉宗元の物語に非常に興味を持っていること...
中国人はなぜお湯が好きなのでしょうか?中国人が白湯を飲む3つの理由とは?
中国人はなぜ白湯が好きなのか?中国人が白湯を飲む3つの主な理由とは?以下、Interesting H...
朱元璋はどのような政策を公布しましたか?これらの政策は高齢者にどのようなケアを提供するのでしょうか?
朱元璋は世界中の高齢者に敬意を表し、「養老令」を発布した。洪武20年、朱元璋は関係部門がこの政策を効...
『西遊記』における仙界問題:真元子と高麗人参の果樹の救済
中国の古典『西遊記』の中で、高麗人参の果樹の物語は非常に興味深い筋書きです。高麗人参の樹の守護者であ...
唐代の李和の詩を鑑賞します。この詩は劉雲の詩に応えて書かれたものです。この詩の本来の内容は何ですか?
劉雲[唐代]李和に続いて、次の興味深い歴史編集者が詳細な紹介をお届けしますので、見てみましょう!汀州...
張小祥詩人が張軍元帥のために書いた「六州歌頭:淮河長景」鑑賞
張孝祥(1132-1170)は、名を安国、通称を玉虎居士といい、溧陽呉江(現在の安徽省河県呉江鎮)の...
唐三伝第28章:漢江関の戦いと范洪水、范麗華の魔丸が弟を救う
『唐代全物語』は清代の長編英雄伝小説で、『唐物語』と略され、『唐代前編』、『唐代物語』、『唐代全物語...
歴史物語:荊軻が秦王を暗殺した
「風は吹き、沂河は冷たく、英雄は一度去ったら二度と戻らない。」『史記・刺客伝』のこの詩の一節は、荊軻...
孟浩然の詩の有名な一節を鑑賞する:父は桑畑で農作業をしており、私は鍬を持った羊飼いの少年の後を追っている
孟浩然(689-740)は、浩然、孟山人としても知られ、襄州襄陽(現在の湖北省襄陽市)の出身です。唐...