宦官と公務員の違い:異なる貪欲さ
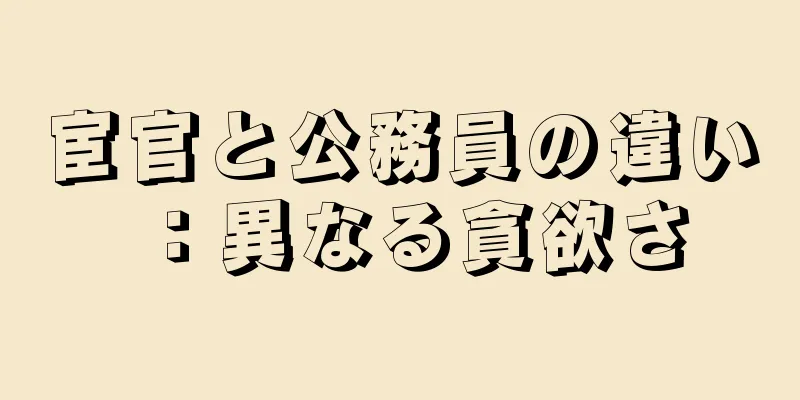
|
明朝の宦官による税務行政が政府を混乱させた 明代の宦官は一般的に質素な背景を持つ小さな家庭の出身であり、後継者がいなければ、その影響力と背景は官僚のそれとは比べものにならないほどでした。彼らの腐敗の手法は、往々にして単純かつ粗雑である。一般的には、賄賂など簡単に見破れるものばかりです。事件後、国(皇帝)は財産を没収し、指導者を処刑することで、多くの損失を回復することができました。 公務員は制度的腐敗に関与しており、海上禁止の推進はその最たる例である。宦官は海関を支配し、賄賂を受け取っていたため、国の税収が半分失われることも珍しくなかった。しかし、少なくとも収入の半分はまだ残っています。公務員はどうやってやるのでしょうか?海禁! まず第一に、公務員のほとんどは大地主であり、自らも製品の生産者です。次に、貿易を行う海上商人を支援します。しかし、これには 2 つの問題があります。 一つは海上税関が課す税金です。 第二に、他の民間商人との競争により利益が減少しました。 当時の文人の記録によれば、双嶼と月岡の人々の間では海外貿易がまだ非常に盛んであった。中小企業は、鉄の針などの商品を輸入し、港に到着すると、特別な船が輸送を提供していました。金額は、人数と商品の重量に基づいて計算されました(計算方法は、重量、種類、容積を考慮する非常に複雑なものでした)。日本への往復で、中小企業の利益は少なくとも2倍になりました。 公務員はどうやってそれをやったのでしょうか?海上禁止。 一つ目は脱税です。海上を禁じれば理論上は海外貿易はなくなり、海上関税局も廃止できます。公務員の船舶は税金を支払う必要がなくなる。 2つ目は、競合する個人投資家を取り締まることです。海上禁止令により個人投資家の取引が禁止されるため、大口投資家のキャラバンは自由に移動でき、ほぼ独占的な取引の利益は自然に倍増します。 実際、日本の海賊のその後の台頭も、文官や文人によって課された海上禁制と直接関係していた。大まかに言えば、海商が次第に大きくなり団結し始めたため、文官による統制が難しくなり、衝突の末に両者が戦うようになったと理解できます。倭寇の本当の始まりは、倭寇のリーダーである王志(安徽省出身の漢民族の男性)が数人の大海商(ほとんどが漢民族の男性)とグループを結成し、学者官僚の支配から脱却しようとしたときでした。その後、江南の朱という愚かな知事が月岡を占領して平定し、数人の日本海賊のリーダーを捕らえて殺害し、両者の対立は激化した。 彼が愚か者と呼ばれる理由は、学者官僚でさえ金の卵を産む鶏を飼い慣らそうとしただけなのに、愚か者は鶏を殺してしまったからです。自殺に追い込まれる結末も普通です。ちなみに、歴史上、日本の海賊のリーダーは数十人記録されています。名前だけから判断すると、彼らは全員中国人です。山田一郎なんて存在しない。したがって、日本の侵略者との戦いは、基本的に反侵略とは関係がありません。 このことから、宦官と公務員の違いが分かります。宦官がどんなに貪欲であっても、最大の分け前は皇帝のものとなります。宦官が職務をきちんと果たせず、皇帝が不満を抱くと、宦官は必ず死ぬでしょう。官僚たちは良心の呵責を全く感じず、皇帝はほとんど一銭も受け取らなかった。崇禎年間、北部では大災害が起こり人々が餓死する中、南部では農地を破壊して桑や茶を植え、ある年には茶税が一桁になったこともあった。これは制約のない公務員制度の必然的な結果です。 歴史書は官僚によって書かれ、国家の問題や政策の誤りは宦官のせいにされることが多かったが、時には皇帝のせいにされた。したがって、明朝の皇帝のほとんどは当然ながら良い皇帝ではなく、もちろん宦官はさらに悪かった。 追伸:明朝の皇帝の権力について話しましょう。重大な勅令には皇帝の印璽と内閣の承認が不可欠でした。内閣の承認なしに皇帝自らが発布した勅令は「中治」と呼ばれた。理論上は、明朝の役人はそれを違法な命令とみなして(例えば、宦官や皇帝の妻の親戚、その他の裏切り者によって発布されたと信じて)、執行を拒否する権利があった。歴史的に、明朝の役人たちはかつて皇帝の勅令を拒否することを良いことだと考えていた。逆に言えば、皇帝の印がなければ、内閣が発した命令に抵抗する者はほとんどいなかった。わかりやすい例は、内閣の命令により首都の守備隊が国王の防衛を拒否した宮殿移転のケースである。文官は「江斌の話には気をつけろ」という一言で軍将軍を完全に黙らせた。 |
<<: 食料は人民の第一の必需品である。中国の歴史は穀倉を守るための3000年の戦いである。
推薦する
白族文化の紹介 白洱海文化の特徴は何でしょうか?
3,500年以上も昔、白族の祖先は中華民族の輝かしい文化の不可欠な一部である「洱海文化」を創り出しま...
『漢宮の春 - 南鄭から成都に初めて到着したときに書いたもの』の原文は何ですか?これをどう理解すべきでしょうか?
漢宮の春 - 成都到着初日に南鄭から書いたもの陸游(宋代)羽根の付いた矢と彫刻が施された弓は、鷲を呼...
「左盛春夜」を鑑賞するには?創設の背景は何ですか?
チュンス・ズオシェン杜甫(唐代)夕暮れには花が壁の後ろに隠れ、鳥が飛びながらさえずります。どの家の上...
『紅楼夢』で西春はどんな秘密を抱えているのでしょうか?彼女は誰ですか?
『紅楼夢』の西春は、金陵十二美女の第7位にランクされているにもかかわらず、あまり語られることのない女...
李和の「髪を梳く美人の歌」:詩人は詩全体を純粋に筆で表現している
李和(790-816)、雅号は昌吉とも呼ばれる。彼は河南省富昌県長谷郷(現在の河南省益陽県)に生まれ...
清王朝はなぜ国名を金から清に変更したのですか?黄太極が国名を清に改めた謎
清朝が関に入る前は、金と呼ばれていました。なぜ後に清に改名したのでしょうか?黄太極はなぜ国名を金から...
王毓の「季春」:この詩の中の感情と風景は絡み合い、混ざり合っている
王毓(650-676)、号は子安、江州龍門県(現在の山西省河津市)の出身。唐代の作家で、文仲子王通の...
唐代の詩「春恨」を鑑賞します。劉芳平はこの詩の中でどのような感情を表現しているのでしょうか?
唐代の劉芳平の『春嘆』については、次の興味深い歴史編集者が詳細な紹介をお届けしますので、見てみましょ...
李世民が皇帝になった後、秦瓊はなぜ病気で引退したのですか?
李世民は夢の中で邪悪な幽霊を見たため、眠るのが怖かった。その後、安らかに眠れるよう、秦瓊と于池公を呼...
欧陽秀の女性の不満を詠んだ詩「百種の憧れと千種の憎しみ」
以下、興味深い歴史の編集者が欧陽秀の『滴蓮花・百恋千憎』の原文と評価をお届けします。興味のある読者と...
太平広記・第84巻・奇人・伊寧坊の狂人の原作の内容は何ですか?どう理解すればいいですか?
『太平広記』は、漢文で書かれた中国古代の記録小説集で、全500巻、目録10巻から成り、漢代から宋代初...
中国の統一王朝の中で、外国の民族と婚姻関係を結ばなかった王朝はどれですか?
紀元前200年、漢の皇帝高祖劉邦は白登山でフン族に包囲され、7日7晩かけてようやく脱出することができ...
中国初の大学、洛陽皇大学校の紹介
大学といえば、今では誰もが知っていると思います。大学は最近になって我が国に導入された外国のものだと言...
『首陽区・山城清霧』の創作背景は何ですか?どのように鑑賞すればよいでしょうか?
首陽区·山城清霧馬志遠(元代)曹甸の西側にある華村の外では、日没とともに雨が止み、空が晴れ渡っていま...
『紅楼夢』におけるシレンの結婚は幸せですか?彼女の結末はどうなったのでしょうか?
『紅楼夢』は、古代中国の章立て形式の長編小説であり、中国四大古典小説の一つである。普及版は全部で12...









