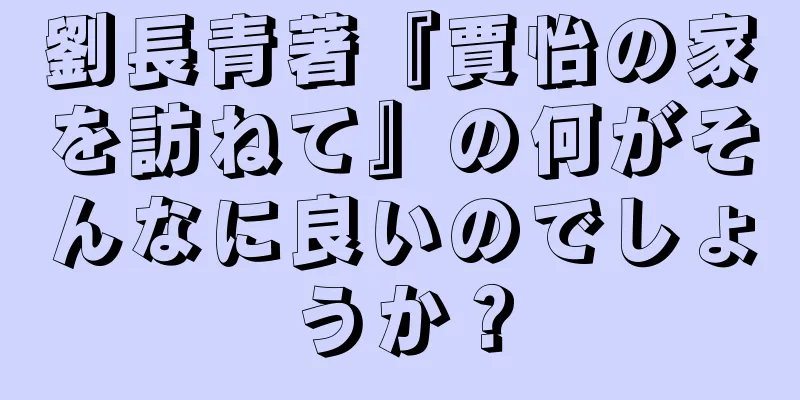漢服は長年存在してきましたが、どのような発展や変化を遂げてきましたか?

|
漢民族の衣服の変遷をご存知ですか?今日は、Interesting History編集長が詳しく紹介します。 「食は民の第一の必需品」という言葉があるように、食べ物の重要性が強調されています。また、「衣食住交通は民の第一の必需品」とも言われ、衣服は食べ物よりも優先されます。これは、古代から人々の生活において衣服が重要であったことを示しています。漢文化は数千年にわたって受け継がれ、漢服もそれとともに発展を続けてきました。今日は漢服について簡単に紹介します。 古代人は上着を「イー」、下着を「シャン(第2音はチャンと発音)」と呼んでいました。ちなみに、古代中国のシャンは、今日私たちが着用しているズボンのようなものではなく、むしろスカートのようなもので、男女ともに着用されていました。 武侠小説には「仁経と杜経」という言葉がよく出てきます。では、人体の仁経と杜経はどこにあるのでしょうか?簡単にまとめると、顎からおへそまで線を引くと「仁経」の位置になります。逆に背中の真ん中あたりで背骨に沿って線を引くと「杜経」の位置になります。簡単に言えば、仁経と杜経は人体の前面と背面の間にある2本の中央の線です。そのため、古代人は衣服のデザインにもそのような用語を適用し、衣服の前面の中心線を「衽(レンと同じ発音)」、背面の中心線を「裻(ドゥと同じ発音)」と呼びました。古代漢服の特徴の一つはクロスカラー、つまり服の左右が胸の前で重なり合って交差し、襟の形が小文字のアルファベットのようになっていることです。重なり合っているので左右の方向に差があります。襟が右下に傾いている場合は「右襟」、そうでない場合は「左襟」と呼ばれます。 右襟 周代以来の礼儀作法では、衣服は必ず右襟で着なければなりません。他の民族の中には中原の服装を真似した人もいますが、漢民族の文化を十分に理解していなかったため、左襟で着ていました。同時に、外国の民族は漢人のように髪を結わず、髪を下ろしていることが多いため、「髪を下ろして左襟」は古代の蛮族の象徴となりました。また、「陰陽の分離」や「人間と幽霊の異なる道」を反映するため、古代の死者が着ていた帷子には左襟が付いているのが一般的でした。そのため、漢民族が左襟の衣服を着ることはタブーとされています。日本は中国文化の影響を強く受けています。日本の「着物」は漢服から発展したものです。今日に至るまで、日本人は着物を着る際、右襟を着用することにこだわります。左襟は今でも不吉と不吉の象徴です。 衣服の左半分が右側を覆った後、胸元の端を「ラペル」、右腰に近い端を「ヘム」と呼びます。漢服の発展の初期段階では、裾は切られておらず、布地の角そのもので、体に巻き付けて固定されていました。このスタイルは「曲尺」と呼ばれています。ここでの「曲」は「曲げる」と発音され、裾が体に巻き付いていることを指します。衣服の前面はラペル、背面はヘムです。これが「フロントラペル、バックヘム」という慣用句の由来です。 カーブスカート その後、服装デザインの発展とともに、人々は曲線の裾が少し冗長だと感じ、端が上下にまっすぐになるようにカットしたほうが美しく、布地の節約にもなると考えました。このスタイルは「直線裾」と呼ばれ、後期にさらに一般的になりました。 ストレート裾 また、漢服の袖の体に近い部分、つまり二の腕は「袂」、前腕の部分は「袖」、袖口は「袪」と呼ばれます(視力の弱い学生は注意してください。「衣补」の横は「袪」であり、「示补」の横は「归」ではありません)。 トップスについて話した後は、ボトムスであるスカートについて話しましょう。構造ははるかにシンプルで、布2枚だけから始まります。漢服の発展初期、春秋戦国時代は、スカートの前後の布が別々になっていて、左右に隙間があり、チャイナドレスの下部に少し似ていました。漢代には、美しさとプライバシーのために、前後の布を横から縫い合わせて筒状にするようになりました。これは、現代の女性が着用するスカートに似ていますが、古代では、このスカートのようなスカートが男女ともに主流の衣服でした。しかし、現代の女性がスカートをはいて走ったり乗馬したりするのは不便であるのと同様に、このようなスカートは馬に乗る兵士や農作業を行う農民には不向きであったため、真ん中から二つに分かれた「袴」に改良されました。現在私たちが履いている「ズボン」と同じ発音ですが、スタイルは異なります。袴は、脚を包み、腰でベルトで結ぶ2本のズボンの脚のみで、2本のズボンの脚は真ん中でつながっておらず、つまり股下がありません。股下のある別のタイプの下着は「裈」と呼ばれ、より短いです。 明代の赤いローブ 袴は室内で履くことが多いため、見た目にこだわる必要はなく、一般家庭では粗めの生地で作ることが多いです。しかし、裕福な家庭ではコストの問題は考えません。衣服に絹や繻子を使用するだけでなく、見えない部分にも絹を使用します。そのため、裕福な家庭を「椀く」と呼ぶことがあります。椀は上質な絹、くは絹の袴を指します。 漢服の上着と下着の組み合わせは一般的に2種類あり、初期の頃は上着と下着は別々で、そのデザインと製造プロセスは比較的単純でした。通常、衣服の色は比較的単純で厳粛ですが、スカートはさまざまな模様や色で飾られており、「空は晴れ、地は濁っている」という意味を暗示しています。 その後、衣服の着やすさや職人の技術の向上により、上着とスカートを直接縫い合わせて完全な構造を形成するようになり、このような漢服は「神衣」と呼ばれました。このような深みのある衣服は着やすいので、男性も女性も、老若男女も、貴族も庶民も、みんな日常的に着ることを好みます。しかし、犠牲の儀式などの非常に正式な場面では、人々は依然として、よりエチケットに沿ったトップスとスカートを使用します。 各時代の深襟の服には細部に多くの違いがあります。宋代には朱熹が古代の礼儀作法を理解した上で「朱子神易」というスタイルを考案しました(訂正:コメントで指摘されたように、この王朝には誤りがあり、訂正しました。コメントありがとうございます)。非常に代表的で、韓国や日本など中国周辺のアジア諸国の服装の発展に大きな影響を与えました。 |
<<: 『銀真快楽帖』によると、銀真は普段どのような快楽を楽しんでいたのでしょうか?
>>: 竇夷が不当に殺される前に立てた3つの誓いとは何ですか?なぜ一般の人々をこれに巻き込まなければならないのでしょうか?
推薦する
閻吉道の『桑の実摘み:西楼の月の下で君に会う』:作者は歌う少女の運命を気にしている
顔継道(1038年5月29日 - 1110年)は北宋時代の有名な詩人である。名は書源、号は蕭山。福州...
『紅楼夢』で、南安妃が賈家を刺した後、応春はなぜ弔問に出なかったのですか?
『紅楼夢』に登場する賈祖母は、実に高貴な身分であり、非常に高い権威を持っています。 Interest...
魏荘の詩「長安清明」の鑑賞
【オリジナル】早春は雨の日の夢ですが、香り高い草はさらに青々としています。清明の火はまず内務官僚が許...
古代にもおやつはあったのでしょうか?昔の人のおやつはどんなものだったのでしょうか?
古代におやつはあったのか?古代人のおやつはどんなものだったのか?Interesting Histor...
『紅楼夢』では、西仁は薛宝柴よりも賈宝玉をうまくコントロールできます。なぜそう言うのでしょうか?
『紅楼夢』は、中国古代の章立て形式の長編小説で、中国四大古典小説の一つであり、一般に使われているバー...
「長庭元満・次第に吹く」を鑑賞する。詩人蒋魁は単に柳を詠んでいるのではない。
蒋逵(1155-1221)は、字を堯章、号を白石道人、鄱陽(現在の江西省)に生まれた南宋時代の作家、...
なぜ後宮の侍女たちは嘉靖帝を暗殺しようとしたのでしょうか?その理由は何でしょうか?
周知のとおり、歴史上の封建王朝において、皇帝は最も名誉ある地位を有していましたが、同時に最も羨望の的...
宋江の死後、華容に何が起こったのでしょうか?彼もなぜ自殺したのでしょうか?
『水滸伝』の英雄108人は最後には散り散りになったが、読者を困惑させる点が一つある。次回は、Inte...
燕雲十六県の歴史的意義:中原の自然の障壁
燕雲十六県は戦略的に重要な位置にあり、防御は容易だが攻撃は困難である。北方の関門である延雲十六県の喪...
『紅楼夢』で石向雲はなぜ賈祖母に養子として引き取られ、賈屋敷に住んでいたのですか?理由は何ですか?
石向雲は『紅楼夢』の主要登場人物であり、金陵十二美女の一人です。今日は『Interesting Hi...
明代史第247巻第135伝記原文の鑑賞
劉静(チャオ・イーチー)、李英祥(トン・ユアンジェン)、陳林(ウー・グアン)、鄧子龍、馬孔英劉敬は、...
シンバルは中国の打楽器です。演奏方法は何ですか?
シンバルは「chǎ」と発音します。中国の打楽器で、小型のシンバルのことであり、シンバル、シンバルなど...
古代の女性にとって「離婚すべき7つの理由と離婚すべきでない3つの理由」とは何だったのでしょうか?
「離婚する七つの理由と離婚しない三つの理由」とは、古代中国における女性の離婚問題について言及している...
北瓊の「吉有年端午節」:詩人が仙人の人格と精神に憧れていることを表現している
北瓊(1314-1379)は、もともとは鵲(け)、雅号は丁鎮(ていちん)、またの名を丁居、中居、丁鎮...
古代と現代の驚異 第33巻:唐潔源の奇妙な遊び心
『今昔奇談』は、明代の鮑翁老人によって書かれた、中国語の俗語による短編小説集です。馮夢龍の『三語』と...