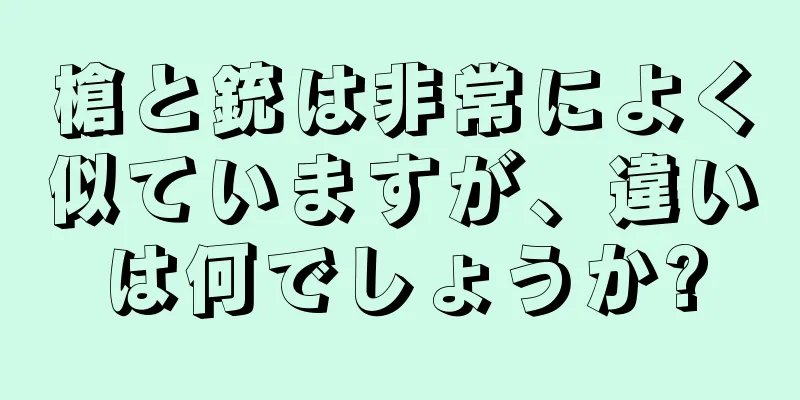和宗と連衡の戦いは何回起こったのでしょうか?秦の始皇帝はどのようにして国家統一の戦略を打ち破ったのでしょうか?

|
今日は、興味深い歴史の編集者が、秦の始皇帝が縦横の同盟戦略をいかにして打ち破ったかをお伝えします。皆さんのお役に立てれば幸いです。 戦国時代も中期に入り、世界の情勢は大きく変化しました。西秦と東斉という二つの強国が共存していました。各国は自国を守るために同盟を結び、秦と斉の脅威に対抗する連合を組まなければなりませんでした。楚、趙、魏、韓、燕の国土が南北に繋がっていたため、この国は河宗と呼ばれていました。連合軍は秦と5回戦いました。連合軍はさまざまな理由で秦軍に敗れ、6つの国は土地を割譲して和平を求め、勝利し、占領した土地を秦に返還させましたが、最終的に6つの国を征服したのは「連衡」政策を提唱した秦でした。なぜでしょうか? 1.最初の戦いで、連衡は小さな勝利を収めました 戦国時代の中期、山東省の六つの国は、はるか西方の秦国が変貌し、その力が一国では対抗できないほど強くなっていることを知りました。蘇秦は強大な秦に抵抗するために六国を巡り、山河の利や血縁関係を利用して六国が団結して秦に抵抗するよう説得した。その結果、地理的につながり、共通の利益を持つ六国は団結した力を頼りに強大な秦に100年間耐え抜くことができた。魏の張儀は秦に行き、恵文王に会いました。張儀は「暴君は強者に仕え、弱者を攻撃する」という持論を唱え、高い地位を獲得しました。張毅は人間の本質をよく理解していた。いわゆる六国同盟は、異なる考えを持つ人々の集まりに過ぎないことを知っていた。各国はそれぞれ異なる利益を持ち、当然優先順位も異なる。したがって、各国に働きかけることができれば、同盟を解体できるだろう。 張儀が最初に狙った国は魏であった。張儀は「衡廉」の戦略を用いて、まず倪桑で斉と楚の大臣と会談し、秦の東進の憂慮を取り除くために同盟を結んだ。そして、秦の恵文王と同じ歌を歌った。恵文王は故意に張儀を廃位し、秦から魏に行かせた。張儀は名目上は魏の宰相を務めたが、実際は秦の軍事力を利用して魏を降伏させ、秦の家臣となった。しかし、犀の頭を持つ公孫燕の妨害により、魏、趙、韓、燕、楚の五国は同盟を組み、秦を攻撃した。さらに、公孫燕は秦の後方にある易丘王国とも同盟を組み、二正面作戦という不利な状況に秦を陥れようとした。連合軍は非常に強力でしたが、張儀は連合軍の不利を一目で見抜きました。彼はまず、当分秦の脅威にさらされていない楚と燕に軍を撤退させるよう説得しました。連合軍のリーダーである楚の淮王も撤退を命じました。残った連合軍の士気は急落し、秦軍は魏、趙、韓を破りました。連合軍による秦への最初の攻撃は失敗しました。 2. 秦国は敗北した 秦に対する最初の連合軍の攻撃が失敗した後、双方は勝敗の理由を分析した。一方、秦の恵文王は易曲が引き起こした災難を深く認識していた。後方を安定させるために、周の申景王5年(紀元前316年)、巴と蜀の反乱に乗じて張儀と司馬崋に軍を率いさせ、巴、蜀、朱などの国を攻撃して滅ぼした。その結果、秦は「国土を広げるのに十分な土地を獲得し」、「富を得て民を豊かにし、軍隊を訓練するのに十分な財産を獲得した」のは100年もの間であった。その後、彼らは大軍を率いて北進し、易丘の25の城を占領した。これにより易丘の勢力は大きく弱まり、秦への攻撃から一時的に撤退を余儀なくされた。この時点で、秦は「富国」「領土の拡大」「軍の強化」という目標を基本的に達成していました。その後、秦は再び中原に軍を向け、魏、韓、趙などの国を攻撃し続けました。魏の2つの都市を占領するか、韓の3つの都市を攻撃し、三晋の国土を徐々に侵食しました。 秦の無節操な拡張は他国の不満を引き起こし、斉、韓、魏は同盟を組み、秦への二度目の攻撃を開始した。 3年間の戦いの後、秦は敗北しました。有名な斉の将軍である匡璋が率いる連合軍は、秦の漢谷関を攻撃しました。秦の昭襄王は、漢の武煕と魏の鳳霊を返還し、領土を譲って和平を求めざるを得ませんでした。この勝利は連合軍の勢いを加速させた。第二次連合軍による秦への攻撃の勝利は、秦軍が長い楚への遠征で疲弊し、連合軍の精鋭部隊に太刀打ちできなかったことによるものであった。さらに、秦国内には後継者が不足していた。名臣の甘茂は去り、“ブレーン集団”の朱礼は重病にかかっており、秦の昭襄王は権力を握ったばかりで民心は安定しておらず、名将の白起や衛然もまだ権力を握っていなかった。一方、斉・魏・韓と強固な同盟を結んでおり、内部的に不安定な秦とは対照的であった。同盟諸国が過去の遺恨を捨てて一つにまとまれば、当然秦が勝つことは困難であったことがわかる。 3. 両者は第3次戦闘では戦わなかったが、第4次戦闘では共に勝利した。 秦が敗れた後、秦は連合軍の崩壊と復興を図るため、一時的に攻撃を中止し、率先して楚と斉の二大国と和平を結び、一時的に天下は平和を取り戻した。このような平和は長くは続かなかった。周の南王21年(紀元前294年)、秦と楚が無力で斉が中原に介入する暇もなかったため、秦は軍を派遣して魏と漢を侵略した。易闕の戦いで、白起は秦軍を率いて魏と漢の連合軍24万人を全滅させ、魏と漢の精鋭部隊をすべて殺害した。その後、秦の昭襄王は斉国と同盟を結び、自らを「西帝」と称した。また斉の閔王を「東帝」として尊敬した。この時、世界は大いに恐れ、各国は大いに動いた。その中で、魏と趙は共謀し、李允を派遣して各国と連絡を取り、共同で秦と戦わせた。有名な連合主義者である蘇秦もまた、燕国の利益のためにロビー活動を行うために斉に行き、閔王に皇帝の称号を放棄して秦と共同で戦うよう説得した。斉、趙、魏、韓、燕の五国も秦を攻撃するために同盟を組んだ。しかし、五国はそれぞれ目的や計画が異なり、互いに警戒し合い、率先して攻撃しようとはしなかった。秦の昭襄王は五国の同盟を破壊するために皇帝の位を取り消し、以前に占領していた土地を返還する行動に出ました。連合軍は撤退し、同盟は攻撃を受けることなく崩壊しました。 秦の昭襄王は権力を握ると、樊於の「遠国を友とし、近国を攻める」という戦略に従い、遠くの斉、楚と友好関係を築き、同時に、最も近い韓、魏、趙を攻撃の焦点に置き、名将白起を任命して三晋に対する攻勢で何度も勝利を収めました。長平の戦いでは、戦国時代後期の斉と楚の弱体化後、秦と唯一対抗できた趙が敗れた。白起は趙軍45万を壊滅させ、西周、東周、宜曲も征服し、広大な土地を侵食した。これにより、各国は再び秦を攻撃するために同盟を組まざるを得なくなりました。これは生死に関わる問題であったため、各国は全力を尽くしました。連合軍は秦軍を打ち破り、4度目の連合軍による秦への攻撃に勝利しました。 4. 始皇帝が権力を握り、国は滅亡した 四度目の連合軍による秦への攻撃の勝利は、他の国々が生き残るための時間を稼いだに過ぎなかった。この戦争は秦の戦闘力を弱めることはなく、他の国々の壊滅という結果を覆すこともできなかった。秦の政王が即位した後、秦の宰相呂不韋は依然として遠国を友好に結び、近国を攻撃する政策を採用し、斉と楚を安定させた後、三晋を攻撃し、有利な地形を占領し、燕、趙、魏、韓のつながりを断ち切り、戦略的に趙、魏、韓の側面包囲網を構築した。山東省は自らを守るために再び第五次連合を結成し、秦を攻撃したが、結局失敗した。やがて秦の政王が権力を握り、李斯の「諸侯を滅ぼし、皇道を確立する」と「数年以内に天下を統一する」という提言に従い、他の国々を次々と打ち破るペースを速め、再び協力する機会を与えなかった。こうして縦横の同盟戦略は崩壊した。 結果から判断すると、縦同盟戦略は横同盟戦略に負けたが、本当にそうだろうか?もし山東省の6つの国が常に団結し、縦同盟戦略を実行し続けていたら、秦と横同盟戦略は依然として勝利していただろうか?結局のところ、戦略がどれだけ優れていても、それは補助的な手段にすぎません。失われたのは縦同盟戦略ではなく、人々の心でした。中原諸国が団結して秦を攻撃できなかった重要な理由は、一時的な利益だけを気にし、強固な同盟を築けなかったことです。一見攻撃的な連合は、一突きで壊れる張り子の虎に過ぎませんでした。そして英徳は敵と同盟を結ぶ戦略ではなかった。それを支えていたのは秦の強力な軍事力だったからだ。「弱国に外交なし」であり、真の強さだけが戦争に勝利をもたらすことができる。 |
<<: 清朝はいつ衰退し始めたのですか?なぜわずか40年でいじめられるほどに落ちぶれてしまったのか?
>>: 清朝では総督と総督のどちらの地位が高かったのでしょうか?同様の権限を持つ知事は知事をどのように指導するのでしょうか?
推薦する
蘇定芳は唐代初期の猛将でした。なぜ皆の印象では彼は悪役とみなされているのでしょうか?
蘇定方は唐代初期の猛将で、軍事上の功績が大きく、自分に厳しい人物であった。しかし、そのような将軍は、...
『紅楼夢』で賈牧は衡武院についてどのようにコメントしましたか?
『紅楼夢』の大観園にある「恒智清分」と刻まれた額のある建物は、薛宝才の邸宅です。 「歴史の流れを遠く...
「川の孤島を登る」の原文は何ですか?どのように理解すればよいのでしょうか?
川の中の孤島を登る謝霊雲(南北朝)揚子江の南を旅するのは疲れたし、揚子江の北を探検するのも疲れました...
「木々の果ての探検船の帆はどこへ行くのだろう? 野鳥が砂浜に降り立つこともある」という有名な一節はどこから来たのでしょうか?
「遠征の帆はどこへ行くのか?野鳥は砂の上に止まることもある」という有名な一節がどこから来たのか知りた...
王鶴清の「大魚」:作品全体に独特な想像力があり、素晴らしいアイデアに満ちています。
三句の作家、王和清。彼は大明(現在の河北省)の出身で、生没年や雅号は不明である。彼は関寒青と親しく、...
太平天国の宝の謎:誰が真実と偽りを見分けられるのか?
かつては強大な勢力を誇った太平天国でしたが、後世に腐敗し、徐々に衰退し、ついには自らの死を告げました...
太平広記第422巻の龍五の登場人物は誰ですか?
徐漢陽、劉玉熙、周漢、子州龍、魏思公、陸元宇、陸漢、李秀、魏有、茅木、石時子徐漢陽徐漢陽はもともと汝...
『中国のスタジオからの奇妙な物語 - 鳥の言葉』はどんな物語を語っていますか?原文はどのように説明されていますか?
「中国のスタジオからの奇妙な物語」からの「鳥の言葉」の原文中州[1]には村人から食糧を集める道教の僧...
徐州を失った後、劉備はなぜ張飛をあまり責めなかったのでしょうか?
三国志演義では、劉備が関羽と袁術の将軍・季霊を率いて徐邑で戦ったとき、張飛は徐州に留まるよう命じられ...
唐代の作家・随筆家、劉宗元:「小石池記」の原文と作品の鑑賞
劉宗元の『小石池記』は、絶妙な文体と感情と情景の融合による山河紀行である。全文は193語で、場面転換...
孫悟空は朱子国の王をどのように扱いましたか?彼は医学を理解していますか?
多くの人は理解していません。孫悟空は医学部に行ったこともなければ、観察、聴診、問診、触診という4つの...
南極の仙人は道教の神ですか?南極仙翁は誰の息子ですか?
南極仙人は道教の神ですか?南極仙人は誰の息子ですか?興味深い歴史の編集者と一緒に鑑賞してみましょう。...
中国神話の二十八星座のうち、北星座の紹介です。西方七星座のうち、どの星座でしょうか?
碧月は月に属し、カラスを象徴し、二十八星座の一つであり、西方七白虎星座の五番目である。 12月の夜ま...
古典文学の傑作『太平天国』:帝部巻第17巻全文
『太平百科事典』は宋代の有名な百科事典で、北宋の李芳、李牧、徐玄などの学者が皇帝の命を受けて編纂した...
『紅楼夢』の宝仔のような完璧な女性が、なぜ林黛玉とは比べものにならないのでしょうか?
本日は、Interesting Historyの編集者が、皆様のお役に立てればと願って、薛宝才につい...