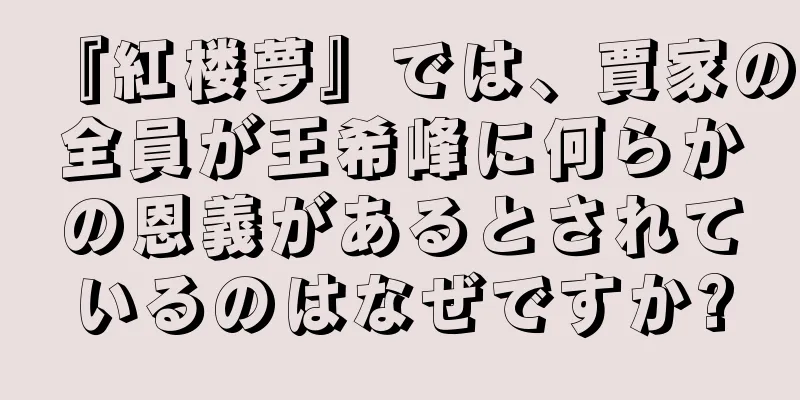王妃と王女の称号はどのようにして生まれたのでしょうか?それはどの王朝で始まったのですか?

|
現代のオペラ、映画、テレビ番組では、皇帝の娘を「王女」、皇帝の婿を「皇子妃」と呼ぶのが一般的である。しかし、この名前はどのようにして生まれたのでしょうか。また、どの王朝で始まったのでしょうか。次の興味深い歴史編集者が詳しく紹介しますので、見てみましょう。 「プリンセス」という称号の由来と由来 「皇女」は皇帝の娘の称号です。その起源は西周の時代にまで遡ります。最も古い歴史記録は『史記・孫子・呉起伝』にあり、「公叔は宰相であり、魏の王女と結婚した」と記されている。 古代では、娘の結婚を司るのは通常父親でした。周王朝初期、周の皇帝の娘は王冀と呼ばれていました。西周の第11代皇帝、周の宣王冀靖の治世中、彼の娘が属国と結婚することになり、結婚式を司る人も必要でした。しかし、周の宣王は、娘の結婚式を自ら司るのは、国の統治者としての自分の地位を落とすことになると感じました。 では、このような一大行事を司会するのにふさわしいのは誰でしょうか? 最終的に、大臣たちの提案により、国王に次ぐ地位にある「公爵」が娘の結婚式を司会することを許可されましたが、普通の「侯」にはまったく資格がありませんでした。 「朱」は結婚式の主人を意味し、その名の通り、「公主」は「公」によって結婚します。 秦・漢の時代以降、政府は朝廷の「三公」が皇帝に代わって結婚式を執り行うことを明確に規定した。いわゆる「三公」とは、「一人の男に次ぎ、一万人以上の男に次ぐ」最高位の軍事・政治官僚のことである。西漢の時代は宰相(司徒)、将軍(司馬)、監察総(司空)であり、東漢の時代は将軍、司徒、司空であった。 「三公爵」が皇帝の結婚を司ったため、皇帝の娘は王女と呼ばれました。漢王朝の制度によれば、皇帝の娘は「公主」と呼ばれ、皇帝の妹は「公主」と呼ばれ、皇帝の叔母は「太公主」と呼ばれていました。 「チャン」と「ダ」はどちらも敬意を意味します。 その後、歴代の封建王朝でもこの称号が使用され続けました。 漢の時代以降、皇帝の娘だけが皇女と呼ばれ、王子の娘は女官と呼ばれました。顔時固は『漢書高地記下』の「女公主」の項で、「皇帝は自ら結婚を主宰しないので、公主と呼ばれる。王は自ら結婚できるので、その娘は翁主と呼ばれる。翁は父を意味し、つまり、父親が結婚を主宰することを意味する。また、王主とも呼ばれ、つまり、王が結婚を主宰することを意味する」と説明している。 「福媽」の本来の意味と変化 「Fu Ma」という用語は「Fu Ma Du Wei」から派生したものです。 『漢書表』には「扶馬度衛は扶馬馬を管理する官職で、漢の武帝の時代に初めて設置された」とあり、顔時孤の注釈には「扶馬とは副馬使いのことである。主馬使いでない者はすべて副馬使いである」とある。名前の通り、扶馬度衛(副馬司令官とも呼ばれる)は副馬使いを管理する官吏である。 「セカンドカー」誕生の伝説。秦の始皇帝は頻繁に巡業に出かけたと言われており、巡業のたびに大勢の随行員に囲まれ、盛大な祝賀会が開かれた。張良は博浪沙(現在の河南省元陽市)で、屈強な兵士とともに秦の始皇帝の進軍を阻止し、副戦車に命中しただけだった。これには秦の始皇帝もかなり驚いた。 そのため、その後のパレードでは乗る車両が頻繁に変更され、予備車両も多数用意された。彼はまた、人々を騙して皇帝が「2台目の車」に乗っているように見せるために、特別に代役を立てた。それ以来、すべての王朝の皇帝は巡業の際に秦の始皇帝の例に倣った。 漢の武帝の時代には、鳳車、伏馬、斉の3人の独衛がいて、それぞれ主車、副車、近衛を担当していました。 |
<<: 故宮の床タイルはなぜ金レンガと呼ばれているのでしょうか?複雑なプロセスはいくつありますか?
>>: 嘉靖帝は何十年も朝廷に出席しませんでした。なぜ明王朝に大きな混乱が起こらなかったのでしょうか?
推薦する
鮑昭の「夕焼けに川を眺める荀成の詩」:詩全体は修辞が精巧で複雑であり、文体は力強く鋭い。
鮑昭(416?-466)は、号を明遠といい、唐の人々が武帝の禁忌を避けるため「鮑昭」と書いたと思われ...
『後漢書』第39巻「劉趙淳于蒋劉周趙伝」の原文は何ですか?
孔子は言った。「父の孝行ほど偉大な孝はない。父の孝行ほど偉大な孝はない。周公はまさにその人物である。...
アイシン・ジョーロ・ハウゲの紹介:黄泰極の長男ハウゲはどのようにして亡くなったのか?
アイシン・ジョロ・ハウゲ(1609-1648)は、清朝の皇帝太宗黄太極の長男である。母は黄太極の2番...
「紅楼夢」の邢夫人は道徳心がなく、迎春を全く教育できない
『紅楼夢』の邢夫人は応春の継母であり、嫡母でもある。応春は嫡子ではないが、彼女を教育するのは邢夫人の...
岑申の詩「夜、潘石を渡り、永楽を眺め、斉梁の風に我が閨房に手紙を送る」の本来の意味を鑑賞
古代詩「斉梁風に夜河を渡る盤石を通り過ぎ、永楽を眺めて我が閨房に送る」時代: 唐代著者: セン・シェ...
清朝詩の鑑賞:桓錫沙 - 庚申の大晦日。この詩にはどのような比喩が含まれていますか?
環西沙・庚申大晦日[清代] 那蘭興徳、次の興味深い歴史編集者が詳細な紹介を持ってきますので、見てみま...
銃器製造者戴子:世界で初めて機関銃を発明した人物
銃器の発展について語るとき、銃器メーカーの戴子を必ず思い浮かべるでしょう。戴子は清朝の順治年間に生ま...
『紅楼夢』の少女、香玲はなぜ宝玉の前でスカートを着替えたのでしょうか?
翔玲の悲劇的な人生は、彼女が両親のもとを去った後に始まった。興味のある読者とInteresting ...
呂布はどの程度の包囲に直面して撤退を賢明に選択したのでしょうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
道教の書物『管子地源』の原文は何ですか?管子地源の紹介
『管子』は秦以前の時代のさまざまな学派の演説をまとめたものです。法家、儒家、道家、陰陽家、名家、兵学...
秀雲閣第90章:陰朔閣が陣形を整え、古仏寺が徐武に出会う
『秀雲歌』は清代の魏文忠が書いた神と悪魔を扱った長編民俗小説である。 「秀雲仙閣」とも呼ばれる。この...
古典文学の傑作『太平楽』:伏儀部巻第15巻全文
『太平百科事典』は宋代の有名な百科事典で、北宋の李芳、李牧、徐玄などの学者が皇帝の命を受けて編纂した...
彭石、愛称は春道、安府出身。『明史 彭石伝』の原文と翻訳
彭石は、名を春道といい、安府の出身であった。正統13年、科挙で首席となり、編纂官に任命された。来年、...
初夏の農業生産において、どのような点に注意すべきでしょうか?作物を育てるには?
各地方は好天を十分に利用して、できるだけ早く稲の苗を植えるべきです。私たちの県には「初夏に田んぼの半...
「荊門の秋」を鑑賞するには?創設の背景は何ですか?
荊門の秋李白(唐)霜が降り、荊門川沿いの木々は葉を落としていますが、布の帆はまだ秋風にたなびいていま...