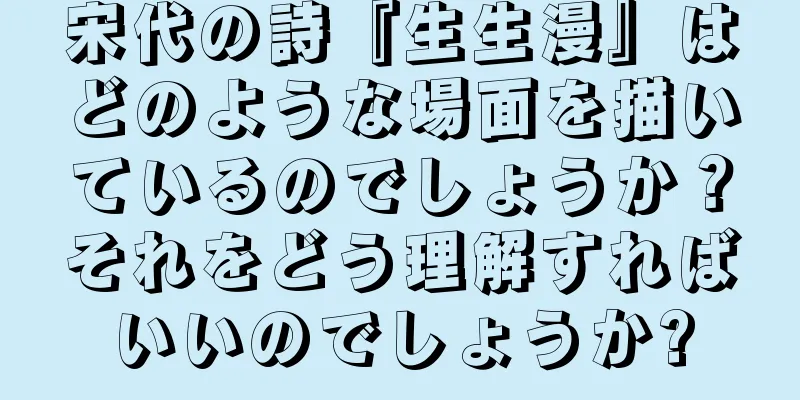西漢時代の軍事制度によれば、漢代軍の各レベルの指揮官はどのような訓練を受けなければならないのでしょうか?

|
軍事面では、三公に相当する中央の高級官僚として大元帥、騎兵将軍、車騎将軍、近衛将軍がおり、九大臣に相当する官僚として前将軍、後将軍、左将軍、右将軍がおり、いずれも常任の役職ではない。上記の将軍たちはそれぞれ独自の役職を持ち、その下に1人の大書記、1人の宮廷書記、29人の補佐、31人の書記、2人の副書記がおり、彼らはすべて朝廷によって任命され、助言を与える責任を負っていました。将軍が直接軍隊を率いる場合は、師団、部隊などに大佐、司馬、軍侯、駐屯軍長などの軍司令官を配置します。次は興味深い歴史エディターが詳しく紹介しますので、見てみましょう! 後漢中期以降、皇太后が権力を握って国を治め、外戚が将軍として国を治め、太夫、三公とともに五部と呼ばれた。何かあったときに任命され、任務が完了すれば退任する、いわゆる雑将もいる。南匈奴の内部抗争のため、永平8年(西暦65年)に杜遼将軍の地位が恒久的に確立されました。漢の霊帝は、首都洛陽の駐屯軍を指揮するために西園の将を8人置き、宦官にその指揮を任せました。これが後世の宦官が軍隊を率いる始まりでした。 常備軍は中央軍と地方軍(郡軍と州軍)から構成されていた。中央軍では、首都守備隊は城門隊長が指揮し、野戦部隊(北軍)は北軍中尉が指揮した。北軍には、屯騎(騎兵)、月騎(特殊部隊)、歩兵、長水(海軍)、射勝(弓矢)の5つの部隊が管轄下にあった。最高責任者は大佐、副責任者は司馬です。 軍隊の総数は5,000人未満でした。北軍は通常、君主の護衛を監督し、首都の治安維持を支援するために首都に駐留していました。戦争が勃発すると、北軍は遠征軍を形成する中核となりました。東漢初期には地方の郡軍と州軍が何度も解散・縮小され、国境の郡と内陸の峠に少数の駐屯軍だけが残った。戦争が起こるたびに、一時的に兵士を募集したり、首都から北軍を呼び出し戦わせたりした。 漢王朝は秦の制度を継承し、皇帝は依然として最高軍事指揮官であり、皇帝は直接管理する2つの主要な朝廷軍事指導組織を通じて全軍を統制しました。この二つの主要な機関は、一つは閔中令、衛衛、中衛から構成される近衛軍の指導機関であり、もう一つは太衛、将軍、将官、中尉から構成される全軍の最高軍事行政指導機関である。 皇室衛兵の指揮系統は、大まかに宮廷衛兵と首都衛兵に分けられます。宮廷の衛兵は南軍と呼ばれ、主に閔中令の指揮下にあり、その配下には宜郎、中郎、士郎、閔中などがいた。漢の武帝の治世中、南軍は衛衛によって率いられ、宮殿の警備を担当していました。衛衛の配下の官吏には、公舒司馬凌と衛氏凌がいた。 首都を守る軍隊は北軍と呼ばれ、首都の精鋭部隊でした。緊急事態がなければその場に留まり、緊急事態が発生したときに皇帝の勅命に応じました。彼らは未阮宮の北に駐屯し、宮殿内の南軍と向かい合っていたため、この名前が付けられました。 北軍は主に中尉によって率いられ、漢の武帝の治世中に近衛軍と改名された。プラエフェクトゥス・ウルビは宮殿と首都の日常的な警備を担当していたほか、皇帝が旅行する際には皇帝の護衛と儀式の護衛も務めていました。総督府の従属官吏には、中雷、四虎、武庫、都川などの軍事職が含まれる。 皇帝は軍全体を効果的に統制するために、将軍、中尉、その他の役職を含む大元帥を長とする軍事指導組織を宮廷内に設置した。 太衛は名目上は最高軍事指揮官であったが、実際には軍事行政の責任のみを負い、軍隊を派遣したり指揮したりする権限はなかった。軍隊を動員する権限は完全に皇帝の手中にあった。皇帝の印章がなければ、たとえ将軍であっても軍隊を率いたり派遣したりすることはできなかった。 将軍という称号は先秦時代にも存在したが、漢代になって初めて正式な称号として確立され、大将軍と中将軍の区別があった。皇帝の護衛兵は将軍と呼ばれ、その長は大将軍でした。 彼は皇帝に近く、臣下のほとんどが皇帝の側近であったため、官房の記録官に任命され、宮殿に住み、政務に参加し、次第に宮廷の重要な役人となっていった。西漢時代の将軍の地位は、基本的に三公の地位に相当した。 将軍と同等の地位には騎兵将軍、戦車騎兵将軍などがあり、その少し下に近衛将軍がいます。国境問題の場合は前後左右の4人の将軍もいます。 将軍より少し地位の低い将校は将軍、または次席将軍と呼ばれます。その下には大佐や大尉を含む中級軍将校がいます。一般的に言えば、小衛の階級は杜衛の階級より上です。彼らは戦時には軍隊を率いて戦い、平時には皇帝の直接の指揮下で将軍たちとともに宮廷に住んでいました。 漢王朝の軍隊の各階級の指揮官は、戦時中に戦闘で部隊を率いただけでなく、平時における軍事訓練も担当していました。前漢時代の軍事制度によれば、訓練を受けていない、または技術のない兵士は呼び出しに応じることができなかった。同時に、軍事訓練の内容は軍の部門によって異なります。 |
<<: 牛耕技術は東漢時代に広く評価されていましたが、『四民月令』にはどのような記録がありますか?
>>: 東漢時代の官選制度では、推薦された人はどのような試験に合格しなければならなかったのでしょうか?
推薦する
水滸伝で梁山泊に強制された人物は誰ですか?
水滸伝で涼山に入城させられたのは誰だったのか?これは多くの読者が知りたい疑問です。次の『おもしろ歴史...
『紅楼夢』の賈徴の書斎はどこにありますか? Mengpozhaiの意味は何ですか?
『紅楼夢』の賈正の書斎はどこにあるのか?孟伯斎の意味とは?今日は『おもしろ歴史』編集者が詳しく解説し...
野呂景は政治的に何をしましたか?野呂景の政治的措置は何でしたか?
耶律経(931-969)は、別名舒禄とも呼ばれ、後周の時代には祖先郭靖の禁忌を避けるために耶律明と呼...
『紅楼夢』では、王夫人は長年責任者を務めていたにもかかわらず、なぜ誕生日プレゼントのお金さえ用意できなかったのでしょうか。
「紅楼夢」の王夫人は長年家計を担ってきたのに、賈の母の誕生日プレゼントのお金さえ出せないのはなぜでし...
馮延思の『如夢霊・陳夫于台論経』:作者の憂鬱が行間から伝わってくる
馮延嗣(903-960)は、正忠、仲潔とも呼ばれ、南唐の丞相馮霊懿の長男であった。彼の先祖は彭城出身...
関羽の傷を癒すために骨を削ったのは本当に華佗だったのだろうか?関羽の傷を治すために実際に骨を削ったのは誰ですか?
華佗が「関羽の傷を治すために骨を削った」という魔法の伝説が広く人々に伝わっています。しかし、関羽は西...
秦瓊は玄武門の変に参加したのか?公式の歴史上の記録は何ですか?
唐王朝(618-907)は、隋王朝に続く中原の統一王朝であり、289年間続き、21人の皇帝がいました...
周邦厳の詩「迪蓮花・托星」鑑賞
オリジナル明るい月はカラスを驚かせ、落ち着かなくさせました。夜警はもうすぐ終わり、巻き上げ機が金の井...
南宋時代の散文はどのように分類されるのでしょうか?散文の特徴は何ですか?
南宋の散文は時代によって特徴が異なり、前期は主に政治に関する文章が中心であった。中期には依然として政...
『紅楼夢』で王夫人は賈夫人に対して何をしたのですか?
王夫人は『紅楼夢』の賈宝玉の母親で、優しそうな女性像です。『おもしろ歴史』の編集者がまとめ、詳しく解...
王維の古詩「勅令に従い、護国総督、礼相の不孟を安渓に送り返し、勅令に応えさせる」の本来の意味を鑑賞する
古代詩「勅令に応えて、護国総督、礼務大臣の布孟を安渓に派遣し、勅令に応えさせる」時代: 唐代著者 王...
「それぞれ自分のやりたいことをやる」という慣用句はどういう意味ですか?その裏にある物語は何ですか?
「各自が自分のやりたいことをやる」という慣用句をどう説明すればいいのでしょうか?その裏にはどんな物語...
古代中国ではマクロ経済規制をどのように行っていたのでしょうか?
マクロ経済規制とは、政府が特定の政策措置を実施して、市場と国民経済の運営を規制することを指します。こ...
古代の戦争免除は本当に役に立つのでしょうか?それを吊るした後は双方とも戦闘を停止しなければならないのでしょうか?
免罪符については、『岳飛全伝』にこう書かれています。「『免罪符』は城に掛けられる。いくら叫んでも、私...
三国志の有名な将軍、張飛はどのようにして亡くなったのでしょうか?張飛が死んだ後、劉備が言った4つの言葉は何ですか?
周知のように、後漢末期から三国時代にかけては、世界各地で英雄が出現し、呂布、趙雲、関羽、張飛など、非...