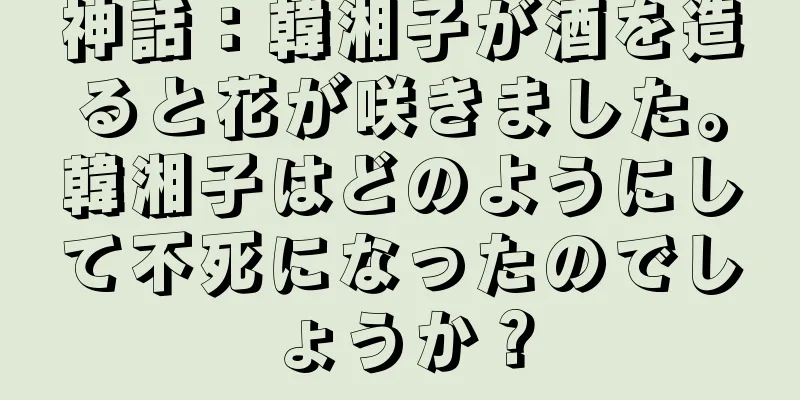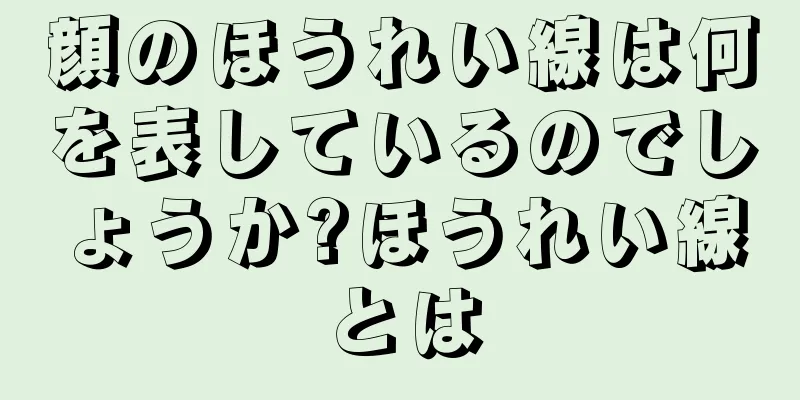曹植の『野に黄鳥の歌』:鍾蓉の『詩評』は「表現が非常に気品があり、優雅である」と賞賛した。

|
曹植は三国時代の著名な文人であり、建安文学の代表者および巨匠の一人として、晋や南北朝時代の文芸の模範として尊敬されていました。代表作に『洛河の女神』『白馬』『七悲歌』などがある。後世の人々は、曹操と曹丕の文学的才能から、彼らを「三曹」と呼んだ。彼の詩は力強い文体と美しい言葉遣いで知られ、30巻の詩集を残したが、現在は失われている。現存する「曹子堅集」は宋代の人々が編纂したものである。曹植の散文も「優雅で恨み深い感情、優雅で洗練された文体」という特徴を持ち、その多様性の豊かさと多様性と相まって、この点で傑出した業績を収めた。南宋時代の作家、謝霊雲はかつてこう言った。「世の中に才能の石は一つしかなく、曹子堅だけが八斗を持っている。」それでは、次の興味深い歴史編集者が曹植の「野原黄鳥歌」をお届けしますので、見てみましょう! 野田イエローバード 曹植(漢代) 背の高い木々は悲しいことに風に吹かれて倒れたり、海水が波を立てたりすることが多々あります。 剣があなたの手にないなら、なぜ多くの友人が必要なのですか? 柵の上にいるスズメは見えませんが、凧が罠に落ちていくのが見えます。 羅一家はスズメをもらって嬉しかったが、若者はスズメを見て悲しかった。 剣を抜いて網を取り去れば、オリオールは飛び去るでしょう。 空高く飛び上がり、青年に感謝するために降りてきました。 詩全体は2つのセクションに分けられます。最初の 4 つの文が段落を構成します。 「高い木々には悲しい風が吹き、海水は波を立てる」という2つの文章は比喩で始まっており、衝撃的です。 『易経』には「風ほど万物を乱すものはない」(朔卦)とあります。また、「高い木は風を引き寄せる」ということわざもあります。高い木に吹く風の力は想像に難くありません。 「風」の前の「悲しい」という言葉が、この自然の風景の主観的な感情的な色彩をさらに強めています。海は果てしなく、波は山のように高く、風が吹けば波がうねり、櫂は折れ、マストは傾く。冒頭の文章で描写された厳しい自然環境と海は、実は現実の政治情勢の象徴であり、官僚機構の荒波と政治の挫折によって生じた作者の内なる悲しみと恐怖を、歪んだ形で反映している。このような政治的環境と雰囲気の影響下で、著者は苦い経験から学び、紆余曲折を経て、悲しみと憤りをもって「剣も手にしていないのに、なぜそんなに多くの友人を作るのか」と叫んだ。これは著者自身の苦い経験から導き出された結論だった。 「権力がなければ、友達を作る必要はない」これは本当に画期的な発言です。このような結論は、従来の概念からも、一般の人々の実際の生活からも導き出されるものではありません。儒教では、「遠くから友人が来るのは大きな喜びである」(『論語』「学問」)、「世界中の人々は皆兄弟である」(『論語』「顔元」)ということが常に強調されてきました。 『雅歌集 薪をくべて』の「蝉は鳴きながら友の声をたずねる」という一節から、現代の有名な「家では親を頼り、外出時には友を頼りにせよ」という諺まで、いずれも友人が多ければ多いほど良いということを強調しています。しかし、常識や理性に反するからこそ、より強い衝撃力を持ち、作者の内面の悲しみや憤りをより深く反映している。曹詩集の「徐干に献上」「親しい友の忠誠はその誠意にある」「丁易に献上」「親しい友の忠誠はその誠意にある」「英石に別れを告げる」「生涯の親族を思う」「孔后序」の「親族や友人が私の旅路についてくる」などの詩節から判断すると、作者は友だちを作るのが好きで、友情を大切にする人である。こんなにも上品で優雅な青年が、自分の本性とはまったく相容れない言葉を叫んでいる。彼はその言葉を自分自身に警告するためだけでなく、世界に対しても警告している。彼の心の悲しみと痛みがいかに激しいかは明らかだ。 詩の2番目の段落は「生垣の間にはスズメは見当たらない」の後に始まる。権力や影響力がないなら、友達を作る必要はない。これは決して著者の本心ではなく、むしろ特殊な状況下での非常に悲しく怒りに満ちた不満である。この見解は読者に受け入れられておらず、著者も古典からの引用で支持していません。そこで彼は寓話的な技法を採用し、「見えない」という言葉を使って、剣を持った少年が雀を救う物語を紹介した。この話は一見すると、「剣を手にしていないのなら、多くの友人を作る必要はない」という反対論のようで、受け入れがたい点である。しかし、実際には、前の段落の続きであり、作者の内面の悲しみと憤りをさらに表現している。 黄色いスズメはおとなしい小鳥です。「生け垣の間」という言葉は、空に舞い上がる野心はなく、生け垣の間で遊んで日々を過ごしているだけであることを示しています。しかし、人や動物に無害なこのような小さな鳥でも、世間では許されるものではなく、人々はできるだけ早く捕まえようと網を張ったりタカを放ったりするのです。網のために雀を追い払うトンビはなんと凶暴なことか。網に落ちるトンビを見たコウライウグイスはなんと哀れなことか。雀を見て喜ぶ羅一家はなんと卑劣なことか。著者は賞賛も批判も一言も述べていないが、彼の感情が物語の中に深く織り込まれている。著者の権力者に対する憎悪と、無実の罪で被害を受けた弱者に対する同情は、彼の言葉から容易に読み取れます。 著者はさらに、鋭い剣を持った若者が網を破ってムクドリを逃がす場面を想像している。黄色い鳥は死を免れて空高く飛び上がり、その後空から急降下し、若者の周りを旋回しながら歌い、命を救ってくれたことに感謝した。明らかに、「剣を抜いて網を取り去る」ハンサムな若者は、実は作者の想像上の自己イメージの具現化であり、「青空を飛ぶ」黄色い鳥が表現する軽やかさと喜びは、実は作者が想像の中で友人を窮地から救った後に感じる軽やかさと喜びである。確かに、これは著者の単なる空想です。現実では無力なので、精神的な救いをファンタジーという仮想世界に求めることしかできないというのは、本当に悲しいことです。しかし、この幻想的な想像力の中には、ウェブスリンガーに対する著者の怒りと抵抗が隠されています。 鍾蓉の『詩』の中で曹植の詩の特徴を最もよく表している8つの言葉は「精神が非常に高尚で、言葉と言葉の選択が豊かである」であり、最も頻繁に引用されている言葉でもある。しかし、この詩「野に黄色い鳥の歌」に関しては、確かに「精神」(思想的内容)は高いが、言語は「華やか」とは言えない。全体的に、この詩は漢代の民謡の素朴な趣をより強く感じます。まず、剣を抜いて網を取り、黄色い鳥が感謝を表すという筋書きは、漢代の民謡にある多くの寓話作品の影響を受けていることは明らかです。前漢時代の『鼎歌』十八首のうち、『艾如章』という曲には「山に黄色い鳥が現れ、網もあるが、鳥はもう高く飛んでしまった。どうしようもない」という一節があり、この曲の着想からインスピレーションを得たものであることは明らかである。第二に、この詩の言葉や文章はほとんどが単純で飾り気がありません。 「羅家は雀をもらって嬉しいが、若者は雀を見て悲しむ」という文章構造は、純粋に話し言葉である。「黄色い雀が飛び、空高く飛ぶ」という文章における言葉の繰り返しや平行法の修辞技法も、月府の民謡によく見られる。これらの単純な言葉やフレーズは詩の内容と一致しています。意図的に装飾されていたら、その感動的な力は弱まっていたかもしれません。これは、優れた文人であった曹植が民謡から学んだ功績を示すものである。 |
<<: 曹植『七雑詩第四』:この詩は清新で自然な美しさを持っている
>>: 曹植の『七雑詩その1』:この詩は文体は単純だが、意味は奥深く、複雑である。
推薦する
明代末期の将軍、毛文龍の簡単な紹介。毛文龍はどのようにして亡くなったのでしょうか?
毛文龍(1576年2月10日 - 1629年7月24日)、号は鎮南、別名は毛伯倫。浙江省杭州府銭塘県...
張宏帆とは誰ですか?張宏帆はどうやって死んだのですか?
張鴻帆は、元代の有名な将軍である張柔の9番目の息子でした。張柔(1190-1268)、号は徳綱、河北...
高延宗には何人の兄弟姉妹がいますか?高延宗の兄弟姉妹は誰ですか?
高延宗(544-577)は北斉王族の一員であった。北斉の文祥帝高成の5番目の息子であり、北斉の文宣帝...
清昭陵の三大謎の真相とは?
黄太極の墓は、彼の功績を後世に伝えるために昭陵と名付けられました。しかし、清昭陵には常に3つの大きな...
南宋の詩人呉謙の傑作「毓章の滕王閣」鑑賞
以下に、興味深い歴史の編集者が呉謙の「満江紅・玉章滕王閣」の原文と評価をお届けします。興味のある読者...
辛其の『臨江仙:黄金谷は煙がなく、宮殿は緑である』の原文は何ですか?どう理解すればいいですか?
辛其記の『臨江仙・金谷武彦公書録』の原文は何ですか? どのように理解しますか? これは多くの読者が関...
「ヤマウズラの空:冷たい太陽が小さな窓に鳴く」の鑑賞。当時、詩人の李青昭は故郷を離れようとしていた。
李清昭(1084年3月13日 - 1155年)は、易安居士とも呼ばれ、宋代の斉州章丘(現在の山東省章...
水滸伝で翼虎雷亨はどのように死んだのか?翼虎雷亨の紹介
水滸伝で翼虎雷亨はどのように死んだのか? 翼虎雷亨の紹介:雷亨は梁山泊の25番目の英雄であり、歩兵隊...
朱棣はなぜ即位後、首都を北京に移したのですか?主な理由は何ですか?
明朝の建国後、朱元璋は風水の宝地である南京を首都に選びました。これは良い選択です。南京は江南の豊かな...
『紅楼夢』で袁春が仙徳妃の称号を授かったことを知ったとき、賈宝玉はどのように反応しましたか?
中国の古典小説『紅楼夢』の主人公である賈宝玉は、比較的高い地位を持っています。本日は、Interes...
曹操は諸葛亮を軽蔑していたのでしょうか?諸葛亮に関する彼のコメントがレビューされていないのはなぜですか?
これは非常に興味深い質問です。ほとんどの人は三国志演義から三国の歴史を知っています。しかし、三国志演...
石碩新宇の歴史的意義:石碩新宇が後世に与えた影響
『新世界物語』は、魏晋の優雅さを研究する上で優れた歴史資料である。その中には、魏晋時代の著名な学者に...
明史第195巻伝記83原文の鑑賞
王守仁(ジ・ユアンヘン)王守仁は、名を博安といい、余姚の出身であった。父の華は、雅号を徳恵といい、成...
『徐霞客旅行記』原文鑑賞 - 広東省西部旅行記12
10日目は早朝にポーターを探し、朝食後に出発します。真武門を出て柳州路を進みます。 〕西に五マイル行...
『易堅志』第9巻の主人公は誰ですか?
ゾウ・イーメン鄒毅は饒州楽平の出身で、壬氏であった。三家の始まりの頃、城隍廟の夢の中で物乞いをしてい...