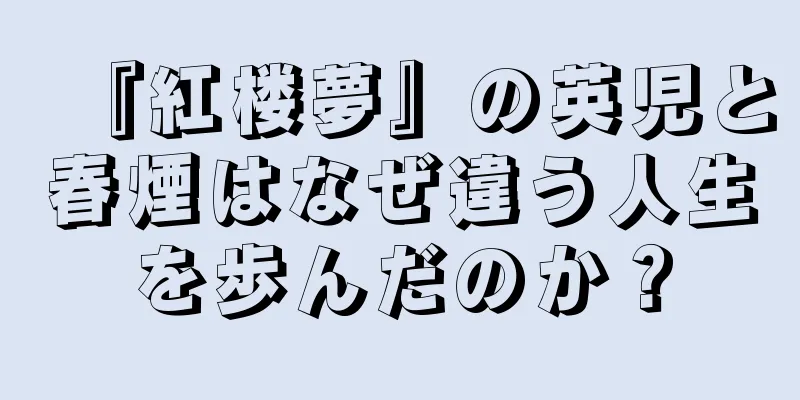王朗はどうやって死んだのですか?彼は本当に諸葛亮に叱られて死んだのでしょうか?

|
『三国志演義』には数多くの名場面がありますが、「諸葛亮が王朗を叱り殺す」もその一つです。 『三国志演義』によると、諸葛亮が北伐に出ていたとき、王朗は高齢にもかかわらず、太守の曹真らとともに諸葛亮と戦いに行きました。戦いの前に諸葛亮と口論になりましたが、諸葛亮の鋭い言葉で論破され、怒りのあまり落馬して亡くなりました。しかし、この部分は素晴らしいのですが、「三国志演義」の中での架空の物語であり、歴史上では決して起こったことではなく、歴史上にもそのような部分は存在しません。 この口論は刺激的だが、あくまでもフィクションである。史実では王思徒はこの戦いに参加していないので、当然諸葛亮と口論することはできなかった。また、王朗は諸葛亮の北伐と同じ年に亡くなったが、実際にはこの戦いが終わってから半年が経過していた。叱られて死んだわけではないことは明らかである。 王朗は諸葛亮に叱られて死ぬことはなかった 諸葛亮の北伐について、『三国志・魏書・明帝志』には「太和二年(228年)春正月、蜀の将軍諸葛亮が国境を侵略したが、天水・南竿・安定の三県の官民が梁に反抗した。曹真将軍が軍を率いて関羽に進軍した。右将軍張攸が街亭で梁を攻撃し、これを破った。梁は逃亡し、三県は平定された」と記されている。つまり、諸葛亮の北伐は228年の春に起こった。街亭の戦いの後、諸葛亮は撤退し、曹魏側には王朗が軍事顧問として北伐に同行することはなかった。 王朗の死については、『三国魏書 明帝紀』にも「11月に司徒王朗が亡くなった」と記されている。このことから、王朗が亡くなったとき、諸葛亮の北伐はすでに半年以上も終わっていたことが分かります。戦場で諸葛亮に叱られて死んだということは、明らかにあり得ないことです。 王朗は実際、典型的な学者でした。 実際、王朗は三国時代の代表的な名学者でした。『三国志』巻13魏書13鍾瑤・華信・王朗伝』には、王朗の著作には『易経』『春秋』『孝経』『周官』などの書物や『説話』があり、「すべて世に伝わっている」と記されています。後世の人々は、王朗の注釈にある思想を「王学」と呼び、王朗の息子の王素は「王学」の代表的人物でした。 裴松之の『三国志注』も『衛略』を引用し、彼を大いに賞賛している。「郎は才能が高く、知識も豊富だったが、性格は厳格で寛大で、威厳があり、礼儀正しく、質素で、結婚の際、贈り物や贈答品を一切受け取らなかった。彼は、世俗の人々が慈善活動はしているが、貧しい人や卑しい人のことを気にかけないことで知られているとよく嘲笑し、まず自分のお金を使って困っている人を助けた。」 このことから、王朗は高潔で才能があり、名声のために世間に媚びることを好まない正直な官僚であったことがわかります。人々は彼を非常に高く評価していました。彼は明らかに『三国志演義』で描かれたイメージではありませんでした。 |
<<: 郭嘉の最後の言葉はなぜ曹操に司馬懿を殺すよう勧めたのでしょうか?
>>: 「綿州八歌」をどう理解するか?創作の背景は何ですか?
推薦する
狄公事件第49話:薛敖草が途中で捕らえられ、狄良公は泥棒を排除することを決意する
『狄公安』は、『武則天四奇』、『狄良公全伝』とも呼ばれ、清代末期の長編探偵小説である。作者名は不明で...
文廷雲の最も有名な詩『菩薩人』を読んだことがありますか?
以下、Interesting Historyの編集者が、文庭雲の『菩薩人・水景幕李伯李枕』の原文と評...
清朝皇帝の龍のローブはどのようなものだったのでしょうか?清朝時代の龍のローブは保存されていますか?
古代において、皇帝は世界の最高統治者であり、極めて高貴な地位を有していました。古代において、皇帝の威...
涼山の麓で林冲と楊志の戦いが続くと、どちらが勝つでしょうか?
『水滸伝』は中国史上初の農民反乱をテーマとした章立ての小説である。作者は元代末期から明代初期の史乃安...
陸游の『環西沙・何無窮雲』:作者は別れを惜しむ気持ちを表明している
陸游(1125年11月13日 - 1210年1月26日)は、字は武官、字は方翁、越州山陰(現在の浙江...
『紅楼夢』で小翠堂はどこにいますか?どんな秘密が隠されているのでしょうか?
小翠堂は曹雪芹の『紅楼夢』に登場する大観園にある建物です。今日は、Interesting Histo...
『紅楼夢』でタンチュンが遠く離れた地へ嫁いだ後、何が起こったのでしょうか?どうしたの?
高鄂の『紅楼夢』の最後の四十章で、丹春が遠く離れた地へ嫁ぎ、趙おばさんと抱き合って泣く場面は私たちに...
清朝はなぜ剃髪命令を出したのでしょうか? 「断髪命令」の結果はどうなったのでしょうか?
清朝はなぜ「剃髪令」を出したのか?「剃髪令」の結果は何だったのか?「Interesting Hist...
文公11年の儒教経典『古梁伝』の原文は何ですか?
顧良池が著した儒教の著作『春秋古梁伝』は、君主の権威は尊重しなければならないが、王権を制限してはなら...
古代では銀紙幣はどのように作られていたのでしょうか?なぜ誰も偽造しないのでしょうか?
古代の銀貨がどのように作られたかを見てみましょう。古代中国の貨幣制度は主に銅貨、金貨、銀貨に基づいて...
宋史第298巻第186巻伝記原文
◎隔離韓愈は言った。「『簡』の第六行には『王の臣下は不器用である』とあり、『顧』の第九行には『行いは...
『江南を思い出す:泥を運ぶツバメ』の著者は誰ですか?どのように鑑賞すればよいでしょうか?
江南の思い出:泥を運ぶツバメ牛喬(唐代)泥を運んだツバメが絵画館の前に飛んできました。杏の木の梁の上...
なぜ後世の人々は西漢の馮堂と李広をいつも哀れに思うのでしょうか?
唐代の王毓の『秋紅府滕王閣告別序』に「ああ、運命はそれぞれ違う、人生は紆余曲折に満ちている、馮堂は老...
秋を表現した詩にはどんなものがありますか?秋の風景を描いた有名な詩
秋の風景を描いた有名な詩は何ですか?秋風は荒々しく、波はうねる。「海を眺める」 3ヶ月目に葉が落ち、...
東周紀伝第95章:四国について語る:岳夷が斉を滅ぼし、天山が火牛で燕を倒した
『戦国志』は、明代末期の小説家馮夢龍が執筆し、清代に蔡元芳が脚色した長編歴史恋愛小説で、清代の乾隆年...