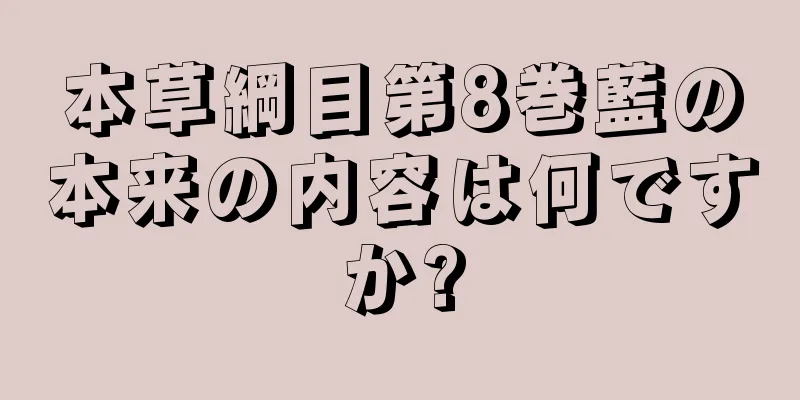曹植の『幽思譜』はどのような感情を表現しているのでしょうか?

|
曹植は若い頃は機転が利き才能に恵まれていたことはよく知られています。では、曹植の『独思賦』は後年どのような感情を表現したのでしょうか。実は、この賦は曹植が才能を認められず、野望も叶わなかったために落ち込んでいたときの憂鬱で憤慨した心理状態を表現するために書かれたものです。 【オリジナル】: 人里離れた離れた場所にある、高いプラットフォームの曲がりくねった丘の斜面に寄りかかっています。浮かぶ雲を眺めると、朝は晴れ、夕方は曇り空です。秋の花が枯れていくのを見ると、年の終わりが寂しく感じます。南の池で飛び跳ねる魚を眺め、北の森で鳴く鶴の鳴き声を聞いてください。彼は非常に寛大に筆をとり、平易で優雅な文体で書いた。そよ風にため息をつき、悲しい弦楽器を通して自分の思いを表現します。心が遠く離れていると思うので、高い所に登って川を眺めます。なぜ自分の心の中の間違いを心配しなければならないのでしょうか。むしろ自分の書いたものを後世に伝えていきたいのです。 【翻訳】: 私はプラットホームの曲がり角に寄りかかりながら、静かで優雅な谷間にいるような気分になった。青い空に浮かぶ白い雲を見上げてみると、朝は晴れていても夕方になるとまた曇ってきます。秋に枯れた花々を眺めていると、時が終わってしまうのが寂しく感じます。南の沼地に行って魚が跳ねる様子を眺め、北の森の奥深くに行って赤い鶴の鳴き声を聞きましょう。私はペンを手に取り、その時の悲しみを言い表しながらため息をついた。そよ風に直面しながら、私はため息をつき、これからの道のりに悲しみを表明することしかできません。たとえ国のために尽くすという崇高な志を抱いていても、高い山に登り、大河のほとりに立つ勇気を奮い起こすのは難しい。なぜこんなにも落胆するのか。それを言葉でどう表現すればいいのか。 【レビュー】: 太祖曹操はかつて「私は人生で三男が一番好きだ」と言った。曹植を皇太子にしたいと思っていたほどだ。曹操は多くの「評価」を行った後、曹植が後継者に選ばれなかったのは「独断で行動し、自分を律せず、酒を飲み過ぎていた」ためだと判断した。曹操は曹植が「虚栄心が強く不誠実」であると考え、彼を候補から外した。曹丕は即位後、兄弟たちを解任し、権力を剥奪し、追放し、遠方に送った上、殺害さえしました。また、自分の統治の地位を固めるために、反対派(丁兄弟など)を排除する口実も作りました。曹植はまず父の寵愛を失い、次に兄の妬みを受け、彼を取り巻く適切な人材を見つけることができませんでした。彼は何度も官職に就くことを要請したが、そのたびに拒否された。孤独で、落胆しています。この記事はこのような背景で書かれました。 遠くを見るために高く登り、物についての詩を通して感情を表現することは、封建社会のあらゆる王朝の文人や詩人が好んだ(あるいは主観的な努力によって作られた)執筆環境です。こうした環境自体が、客観的に見て、指揮力と統制力のある勢いを生み出します。ビジョンは広く無限で、想像力は自由です。自分の野望を文章で表現し、自分の情熱を言葉で表現することができます。 「独思の譜」は全部で16の文章から構成されています。最初の 8 つの文は風景の描写と感情の表現に重点が置かれ、最後の 8 つの文は感情の表現と解説に重点が置かれています。最初の 2 つの文は環境について説明しています。著者は高い台に登った後、すぐに遠くを見るのではなく、まず「曲がった斜面」に寄りかかり、世間の喧騒を避けて「隔離」と「静寂」を求めようとしました。詩の冒頭では、詩人が暮らす「静かな」環境が強調されており、これは記事のタイトルに忠実であるだけでなく、その後のテキストの「考え」の基礎にもなっています。しかし、曹植はこの時、憂鬱な気持ちを隠すことができなかった。次の 4 つの文は、詩人が見たものや感じたものを描写し、風景を描写し、感情を表現しています。空を見上げて、青空に悠々と浮かぶ白い雲と、地面に咲く枯れた秋の花(「悠々と飛ぶ雲を眺める」と「枯れた秋の花を眺める」)を見ると、才能が評価されず、野望が叶わず、落ち込んでいて、気持ちを吐き出せないという潜在意識がすぐに呼び起こされた。彼はすぐに「朝は晴れ、夕方は曇り」、曇りと晴れの交代、太陽と月の交代、星の動きなど、自然界の客観的な変化を思い浮かべました。春に花が咲き、秋に枯れるという避けられない過程を思い浮かべ、真に「年末の憂鬱」の寂しさを感じました。ここで作者は、正対比の書き方を採用し、奇妙な峰が点在し、錦織りのスクリーンが互いに向き合っているような感覚を読者に与えています。次の2つの文は、南の池で魚が自由に跳ね回り、北の森で鶴が心ゆくまで鳴く楽しい光景を描いています。文字通り、魚が跳ねるのを見たり、鶴の鳴き声を聞いたりする様子を描写しており、物語を語り、風景を描写しているようです。実際、詩人は自分の「考え」を「南の沼地」や「北の森」といった遠い場所に置き、その「考え」をより「静かに」し、自分の深い内面の感情をよりよく表現できるようにしています。魚も鶴も、ちょうど良い場所にちょうど良いタイミングでいたので、目標を達成し、偉業を成し遂げたともいえます。では、著者自身はどうでしょうか? 無限の感情と言葉にできない「思い」だけです。これら 2 つの文はタイトルと密接に関連しており、次のような歌詞の議論につながります。 記事の最後の8つの文は第二層であり、感情と議論をさらに表現し、才能と野望を実現できない詩人の憂鬱な気分を表現しています。これが記事の核心です。 「白筆を持ち、惜しげもなく書き綴る」の4行には、「寛大さ」「哀愁の詠唱」「溜息」という言葉が使われ、感情が直接的に表現されています。詩人の憂鬱で言い表せない苦しみは、当時は吐き出すことができなかった。彼には「上京」する機会さえ与えられなかった。彼は自分の苦しみを誰に話せばいいのだろうか?彼にできることは、「素朴な筆」で自分の気持ちを吐き出し、「悲しい弦」で自分の気持ちを表現することだけだった。 「搦」「扬」「仰」「寄」の4つの動詞は、以下の対象と適切に対応しており、その意味を正確に表現しています。 「寛大さ」「嘆き」「ため息」「悲しい弦」で表現される考えや感情はさらに適切です。 「而」「之」「以」「于」などの異なる機能語が文を繋ぐのに使用され、文が整然とするだけでなく、多様で独創的なものにもなります。この詩人が非常に独創的で、言葉をコントロールする能力が並外れていることは容易に分かる。最後の 4 行は、物語 (「高く登る」と「川を眺める」) と議論 (「なぜ...」と「むしろ...」) を通じて詩人の憂鬱と憤りをさらに表現しており、これがテキスト全体のクライマックスとなっています。曹植は冷静になってみると、「信念を持ち、志を遠くに持つ」という志がまだ完全に消えていなかったことに気づいた。彼は常に自分の才能を発揮するために一生懸命働き、「国のために努力し、民のために尽くし、永続的な業績を築き、遺産を残す」ことを望んでいた。(楊徳作への手紙)しかし、彼の理想はもはや実現できなかった。この瞬間、詩人の悲しみと壮大さ、愛と憎しみが絡み合う複雑な気分は、どれだけ言葉を使っても表現できません。「なぜ私の心は悩むのか、むしろ文章で伝えたい」は、疑問文を使用して作者の「憂鬱」という無限の感情を表現し、詩人の感情の波が勢いよく押し寄せ、際限なく押し寄せ、頂点に達し、最高で最強の音を歌います。 この賦は簡潔な言葉を使いながらも芸術的概念が深く、文章は整然としており、平行線で押韻されている。言葉遣いは明快で優雅でありながら、正確さと適切さを失わず、読みやすく、後味が長く残り、著者の優れた芸術的才能が十分に発揮されています。文章は巧妙に考えられており、細部が明確で、肯定と否定の対比がはっきりしており、構成が自然で整然としており、短編小説の中でも傑作と言える。 |
推薦する
『魯班書』には何が記録されているのか?その内容の何が特別なのでしょうか?
「魯班書」と聞いて、あなたは何を思い浮かべますか?次のInteresting History編集者が...
袁美の「私が見たもの」鑑賞
オリジナル羊飼いの少年は黄色い牛に乗って、その歌声で森が揺れます。彼は鳴いているセミを捕まえたかった...
皇帝の墓はなぜ「霊廟」と呼ばれるのでしょうか?十の皇陵
古代皇帝の墓はなぜ「霊廟」と呼ばれるのでしょうか? 「笛の音は悲しく、秦娥の夢は秦楼の月に破れる。秦...
リス族の服装 リス族の女性服の発展と変化は何ですか?
どの民族にも独自の民族衣装や特徴があり、雲南省に住むリス族にも独自の衣装の特徴があります。彼らの服は...
趙蓋は誕生日プレゼントを盗んだ後、なぜ劉唐に宋江に手紙を届けるように頼んだのですか?
私たちはずっと、趙蓋が誕生日プレゼントを盗んだ後、劉唐に手紙を宋江に届けるように頼んだのは、密告して...
もし陳宮が曹操と袂を分かつことがなかったら、曹操は大きな敗北を避けることができたでしょうか?
もし陳宮が曹操に降伏していたら、曹操は戦役中に董卓を倒すことができたでしょうか?今日は、Intere...
唐の太宗皇帝の六番目の息子で蜀王の李寅はどのようにして亡くなったのでしょうか?李寅の墓はどこにありますか?
唐の太宗皇帝の六番目の息子で蜀王の李隠はどのようにして亡くなったのでしょうか?李隠の最後はどうなった...
ピーチカーネルブレスレットの選び方は?新しいクルミが手に刺さってしまったらどうすればいいですか?
今日は、Interesting Historyの編集者が、皆様のお役に立てればと、桃のブレスレットの...
関羽が顔良を殺したのに、なぜ曹陣営の将軍たちは関羽を恐れなかったのでしょうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
中国革命の最初の山はどこにあるのでしょうか?第一革命山はなぜそのように名付けられたのでしょうか?
中国最初の革命の山である井岡山は、古代には「陳、横、湖南、江西の合流点、洛霄山の腹」として知られてい...
古典文学の傑作「劉公安」第73章:遊女が禅寺で馴染みの客に出会う
『劉公庵』は清代末期の劉雍の原型に基づく民間説話作品で、全106章から成っている。原作者は不明ですが...
なぜ幽潭之は阿子のためにすべてを捧げようとしているのか?悠潭志さんはどんな人ですか?
なぜ幽潭之は阿子のためにすべてを捧げる覚悟ができたのか?幽潭之とはどんな人物なのか?『興味深い歴史』...
「紅楼夢」では、宝玉が殴られました。希仁は賈おばあちゃんを怒らせるために何をしたのですか?
皆さんご存知の通り、「紅楼夢」では、金伝児と斉観の二人のせいで宝玉が殴られました。では、宝玉が殴られ...
『天剣とドラゴンセイバー』のキャラクター紹介のテーマにはどのような点が含まれていますか?
「天剣龍剣」は、安徽の農民朱元璋の反乱と明朝の成立を背景に、張無忌の成長を手がかりに、武術界のさまざ...
巨人の精霊は誰ですか?彼の出身地は何ですか?
『西遊記』に登場する神々の多くは仙人になった経験がある。『神々の演義』でも民間の伝説でも、彼らはみな...