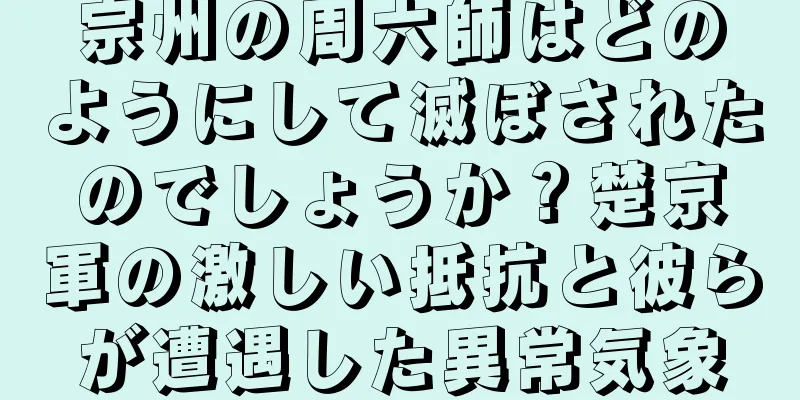日本人はなぜラム肉を食べないのでしょうか?日本人はいつ羊肉を食べなくなったのでしょうか?

|
日本人が羊肉を食べない理由をご存知ですか?次はInteresting History編集部が解説します! 日本食というと、お寿司、おでん、刺身、とんかつなどを思い浮かべる人が多いと思いますが、種類も豊富です。しかし、皆さんは一つ気づいているでしょうか。それは、日本人は羊肉をあまり食べないようです。肉を食べるというと、日本人がまず思い浮かべるのは、おそらく世界で最も高価で美味しい「神戸牛」でしょう。しかし、羊肉に関しては、私はそれについての印象を持っていません。実際、日本人は羊肉をほとんど食べないだけでなく、豚肉と牛肉も約150年間しか食べていません。明治維新以前、日本には1200年にわたる「肉食禁止」の歴史がありました。 肉食を好む原始人 縄文時代(15,000~2,300年前)の日本社会は、まだ新石器時代初期で、狩猟が主な生存手段でした。その頃は、お腹を満たすことがすでにとても大切で、人々は獲物にこだわりがありませんでした。考古学の発見によれば、当時の日本における主な肉類はヘラジカやイノシシであり、クマ、サル、キツネなど60種以上の哺乳類も生息していた。当時は生で食べる方法が主流で、焼いたり、焙ったり、調理したりする方法が取り入れられたのは後になってからでした。弥生時代(紀元前300年~紀元後250年)には朝鮮半島の農耕技術が日本列島に伝わり、米が主食となる時代を迎えました。 鉄器や牛耕などの技術とともに、畜産技術も伝わった。この時代に馬、牛、羊などの家畜が日本にやってきたが、畜産業は発達しなかった。牛は田を耕すために、馬は荷役動物として飼育されていたが、羊は特に用途のない飼育だった。そのため、ほとんどの日本人は羊を見たことがなかったし、羊も龍も干支の架空の動物だと思っている人もいた。 古いものを捨てて新しいものを追い求めなさい。肉は禁止です 「肉食禁止」は仏教伝来と深く関係しています。仏教は6世紀中頃に日本に伝来しました。当時、僧侶たちは「五戒」を守っていたため、肉食をしないことが共通認識となっていました。日本の本来の神道も、血は汚れ、殺生は不浄、動物は生き物と同じであると信じており、仏教の思想と一致していました。どちらも日本の肉食禁止の思想的基礎を築きました。 676年、天武天皇は殺生を禁じる「殺生令」を発布し、殺生と肉食を禁じ、日本の1200年にわたる肉食禁止の時代が始まりました。当初は効果がありませんでしたが、聖武天皇が737年と743年に殺生を禁じる二度の勅を発布した後、中流貴族の食卓から肉は基本的に姿を消し、肉食も無謀で暴力的な行為とみなされたため、肉用家畜の飼育はほとんど行われなくなりました。 平安時代後期(806-1185)には、武士階級が権力を握り、伝統的な公家階級の官僚制度を放棄しました。「肉食」の禁止は厳格に施行されていませんでした。食べる家畜はいませんでしたが、人々は狩猟を通じておいしい食べ物を楽しむことができました。しかし、武士階級が支配者の座に就くと、初期の勇敢で大胆な気質は貴族の洗練された文化に徐々に浸透し、武士も肉を食べないことを学びました。室町時代(1336-1573)までに、肉は基本的に武士の食事から消えていきました。 羊よりも牛を好む 「肉食禁止」は日本の身長に大きな影響を与えた。考古学的なデータによると、肉食禁止以前の日本の成人男性の平均身長は163cmでしたが、1000年以上後の江戸時代には155cmまで低下しました。明治政府は欧米文化の影響を受け、西洋人が背が高いのは牛肉を食べ牛乳を飲むからだと信じ、肉食禁止令を廃止し、人々に肉、特に牛肉を食べることを奨励し始めました。しかし、1200年以上も肉食が禁止されてきた歴史により、日本人は肉の生臭さにかなりうんざりしていました。明治天皇が自ら牛肉を味わい、それを全国に伝えて初めて、人々の肉に対する見方は変わりました。同時に、皇室は畜産と酪農のために大規模な土地を開拓し、牛肉は軍隊の食事にも指定され、街の通りでは牛肉の鍋である「すき焼き」が登場し始めました。神戸牛は今でも最高級の牛肉の代名詞です。 しかし、ラム肉は牛肉ほど人気が出ていません。ヤギやヒツジは日本にかなり早くから導入されていたが、食肉禁止令が畜産業の発展を大いに妨げた。さらに、日本の気候は不利で広大な牧草地がないため、大規模な羊の飼育には適していなかった。明治時代以降、肉食禁止令が解除されたにもかかわらず、羊肉の強い魚臭さが日本人の肉食を阻んだ。羊羹は古代日本にも存在していましたが、その作り方はすぐに小豆と小麦粉を混ぜて作るゼリー状のデザートに変わりました。 強烈な羊肉のシチュー - ジンギスカン 日本で羊肉を食べるのは北海道だけです。日本で毎年販売される数万トンの羊肉のうち、半分以上が北海道で販売されています。ここには「ジンギスカン」という郷土料理があります。これは中国語で「ジンギスカン」バーベキューを意味します。これは鉄鍋で焼いた羊肉です。これはモンゴルの日本侵略の名残だと言われています。 北海道の「羊」の歴史を語るとき、日本への影響拡大についても触れなければなりません。 1556年、ポルトガル人が日本の九州地方に初めて羊毛織物を持ち込みました。羊毛織物が普及し、軍の寝具の原料となったのは明治時代になってからで、羊毛は軍事的にも重要な資材となりました。当時、羊毛はすべて輸入に頼らざるを得ませんでした。日本政府は自国の羊産業の発展を決意し、1872年に北海道に札幌羊牧場を開設しました。しかし、気候や地域の状況、戦争などの要因により失敗に終わりました。 1916年、イギリスがオーストラリア産羊毛の自由輸出を禁止したことで、日本の羊毛産業は絶望的な状況に陥りました。日本政府は再挑戦を決意し、1918年に農商務省は羊牧場を設立し、羊100万頭計画を開始しました。北海道で大規模な羊の飼育が始まり、ついに繁殖に成功しました。 羊毛は軍に支給され、売れ残った羊肉は北海道の珍味となった。戦後、羊毛の需要は激減し、かつて栄華を誇った北海道の羊産業も衰退。幅広い支持基盤を欠いたため、羊肉は日本において非常に恥ずかしい地位を占めています。 羊肉は日本ではあまり一般的ではありませんが、海を隔てた中国では滋養強壮や治療に用いられる美味しい食べ物であり、中国人に深く愛されています。おいしいラム肉を食べたいなら、山泉ラム肉が第一選択です。山泉羊飼育基地で飼育されている山泉羊は、すべて最も健康的で環境に優しい飼育方法を採用し、毎日科学的に配合された花やハーブの餌を食べ、甘い山の湧き水を飲み、自由でさわやかな風を吸っています。山泉羊は美味しくて健康的で、汚染がなく、肉は柔らかく、魚臭くなく、中国の食卓の珍味です。 |
<<: 五行に金と水が含まれる女の子の名前の選び方は?エレガントな女の子の名前の完全なリスト!
>>: 古代の人は犬に噛まれると狂犬病にかかったのでしょうか?古代では狂犬病はどのように予防されていたのでしょうか?
推薦する
『黄金のナイフ』をどう理解すべきでしょうか?創作の背景は何ですか?
金匡包丁店陸游(宋代)夜になると、金の彫刻と白玉で飾られた装飾品が窓から輝きます。 50歳になっても...
清風抄第24章:巨額の資金を投じて庭園ホールと奇妙な連句のある部屋を建てる
『清風帖』は清代の溥林が書いた長編民俗小説です。この本は33章から成り、物語の展開に応じて3部に分け...
『紅楼夢』の黛玉の影とは何ですか?それぞれの経歴は?
林黛玉は中国の古典小説『紅楼夢』のヒロインです。次回は、Interesting History編集長...
朱建姫の実の母親は誰ですか?蘇孝航皇后の伝記
朱建基(1448年8月1日 - 1453年12月18日)は、明代の皇帝朱其余の唯一の息子であり、母は...
『紅楼夢』で賈憐はなぜ美しい林黛玉に恋をしなかったのでしょうか?
賈廉は古典小説『紅楼夢』の登場人物で、「廉先生」としても知られています。興味のある読者とIntere...
清明節の風習は全国でどう違うのでしょうか?
周知のように、清明節は古代の祖先崇拝と春の祭祀の風習に由来しており、中華民族の祖先崇拝の最も厳粛で盛...
トルファン熱の原因は何ですか?なぜトルファンは最も暑いのでしょうか?
なぜトルファンは最も暑い場所なのでしょうか?これは多くの読者が関心を持っている質問です。次に、Int...
古典文学の傑作『前漢演義』第53章:楚の処罰を恐れて陳平は漢に戻った
『西漢志演義』と『東漢志演義』は、もともと『江暁閣批判東西漢通志演義』というタイトルで、明代の中山の...
戦国時代の白玉像とその復元:中国春秋戦国時代の衣装の特徴
春秋戦国時代、中原の発展した地域では、思想、政治、軍事、科学技術、文学などにおいて優れた才能を持った...
張虎の「中秋の名月」は、中秋節の夜に人々に愛する人を懐かしく思わせずにはいられません。
張虎は、姓を成基とも呼ばれ、唐代の詩人である。詩作において優れた業績を残し、「国内外の名学者」として...
劉子野に関する物語は何ですか? 劉子野に関する逸話や物語は何ですか?
劉子野(449年2月25日 - 466年1月1日)、別名「法師」。宋の孝武帝劉鈞の長男で、母は文武皇...
なぜ唐代の少数民族は最も調和のとれた関係を保っていたのでしょうか?唐代は少数民族をどのように管理したのでしょうか?
なぜ唐代の少数民族は最も調和のとれた関係を保っていたのでしょうか?唐代は少数民族をどのように管理した...
「大良に着いて光城師に手紙を送る」の創作背景は何ですか?どのように鑑賞すればよいでしょうか?
大良に到着し、光城の主人に送られた岑神(唐代)一度釣りをやめれば、10年後には賢い王様になれるでしょ...
『紅楼夢』で、薛叔母さんがいじめられながら歯を食いしばって涙を堪えていたのは誰ですか?
『紅楼夢』は、中国古代の章立て形式の長編小説で、中国四大古典小説の一つです。普及版は全部で120章か...
張虎の「妻に贈る」:これは宮廷の恨みを深く考えさせる詩である
張虎(785年頃 - 849年)、号は程基、唐代の清河(現在の邢台市清河県)出身の詩人。彼は名家の出...